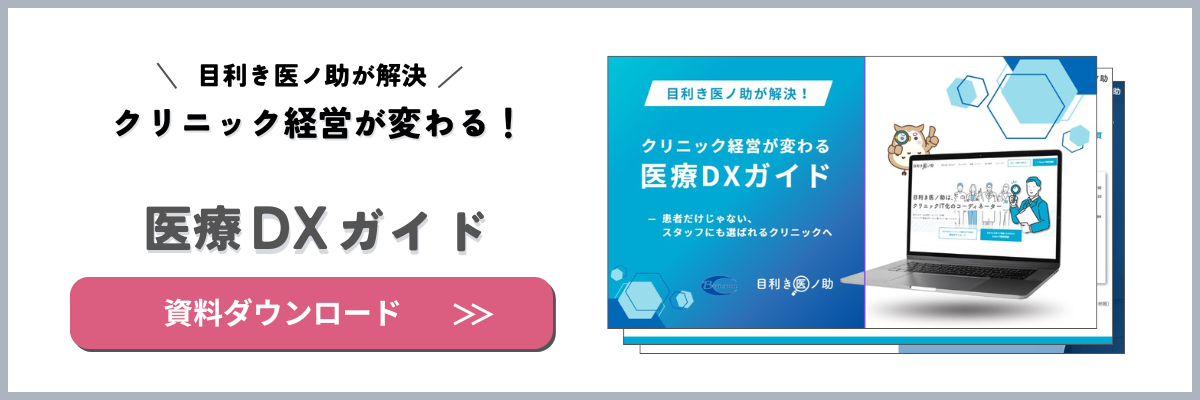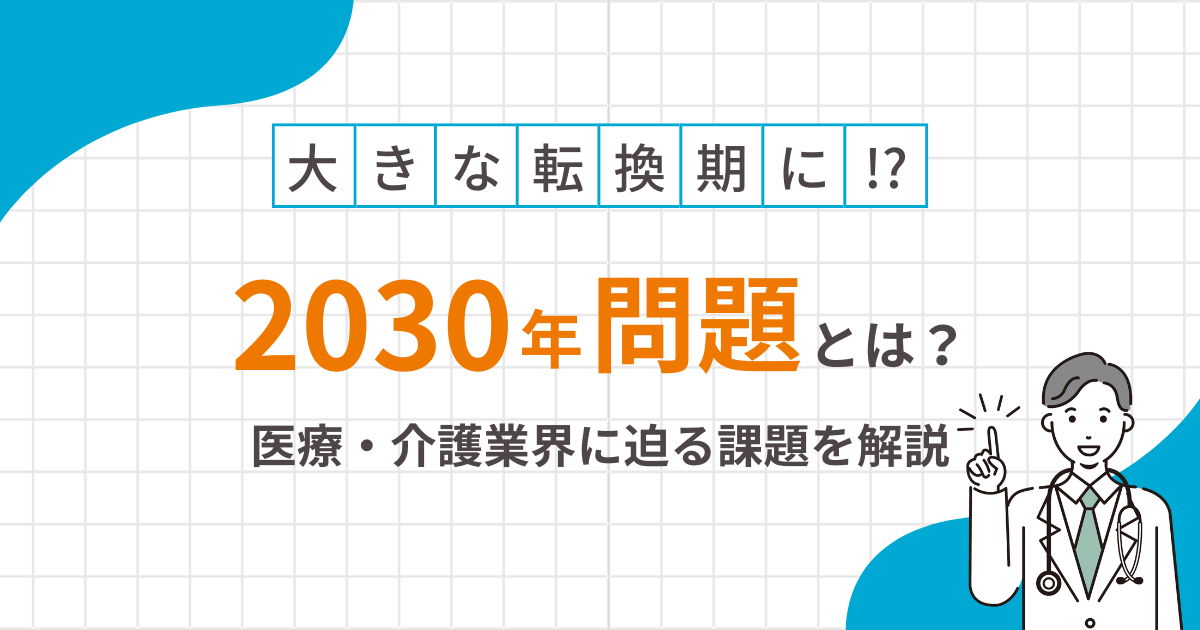
2025.11.03
2030年問題とは?医療・介護業界に迫る課題を解説【目利き医ノ助】
「2030年問題」とは何か?医療・介護業界への影響と背景
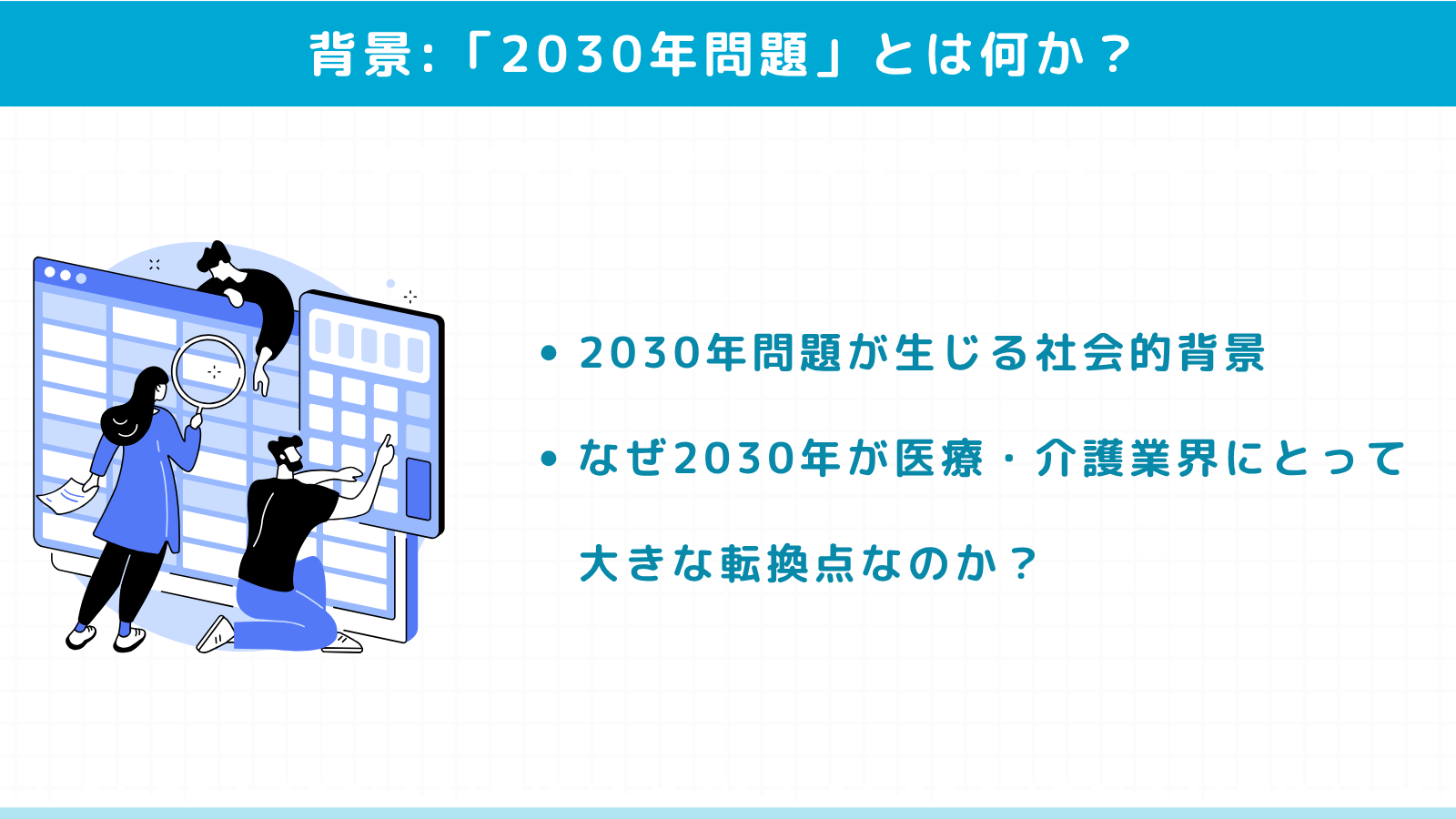
2030年問題が生じる社会的背景とその意味
「2030年問題」とは、主に団塊の世代(1947年〜1949年生まれの約800万人)が全員75歳以上の後期高齢者となる2030年頃に起こるとされる、医療・介護を中心とした社会保障に関する諸課題の総称です。
団塊の世代は、日本の戦後復興期に大量に生まれた世代であり、その人口規模は非常に大きく、日本の人口ピラミッドの中で特に存在感があります。この巨大な人口集団が一斉に高齢化し、後期高齢者の段階に突入すると、医療や介護サービスの需要が急激に増加します。そのため、社会保障費用の急増や人材不足、施設不足など、さまざまな問題が発生することが懸念されています。
さらに、日本社会全体として少子化が進んでおり、高齢者を支える現役世代が減少していくことも、この問題を一層深刻化させています。現役世代1人あたりが支える高齢者数が増加し、医療・介護サービス提供の質が低下するリスクや、経済的な負担が重くなる可能性もあります。
このような社会的背景から、2030年問題は医療・介護業界だけではなく、日本全体の社会保障制度にとって極めて重要な問題として注目されているのです。
なぜ2030年が医療・介護業界にとって大きな転換点なのか?
2030年が医療・介護業界にとって大きな転換点となる理由は、これまで経験したことがない規模で後期高齢者が急増し、医療・介護サービスの需給バランスが一気に崩れる恐れがあるからです。
具体的に考えると、現在の医療・介護提供体制は、ある程度想定された高齢者数に対して整備されてきましたが、団塊の世代の一斉高齢化という特殊な状況が発生する2030年には、従来の体制では全く対応しきれないほどの負担が医療・介護現場に降りかかります。
さらに、人口構造が急速に変化するため、病院や介護施設の増設、人材確保や養成、ICT活用による業務効率化など、抜本的な改革が求められるでしょう。つまり、単なる量的な問題だけでなく、医療・介護サービスそのものの質や提供方法、業務プロセスにおいても、大きなパラダイムシフトが必要になるのです。
2030年という時点を一つの節目として、業界のあり方そのものが問われ、対応力のない医療機関や介護施設は経営存続すら難しくなる可能性があります。このように、2030年は医療・介護業界にとって極めて重要な転換点であり、現在から継続的な対策が必要な理由がここにあります。
団塊の世代の後期高齢者化がもたらす具体的な課題
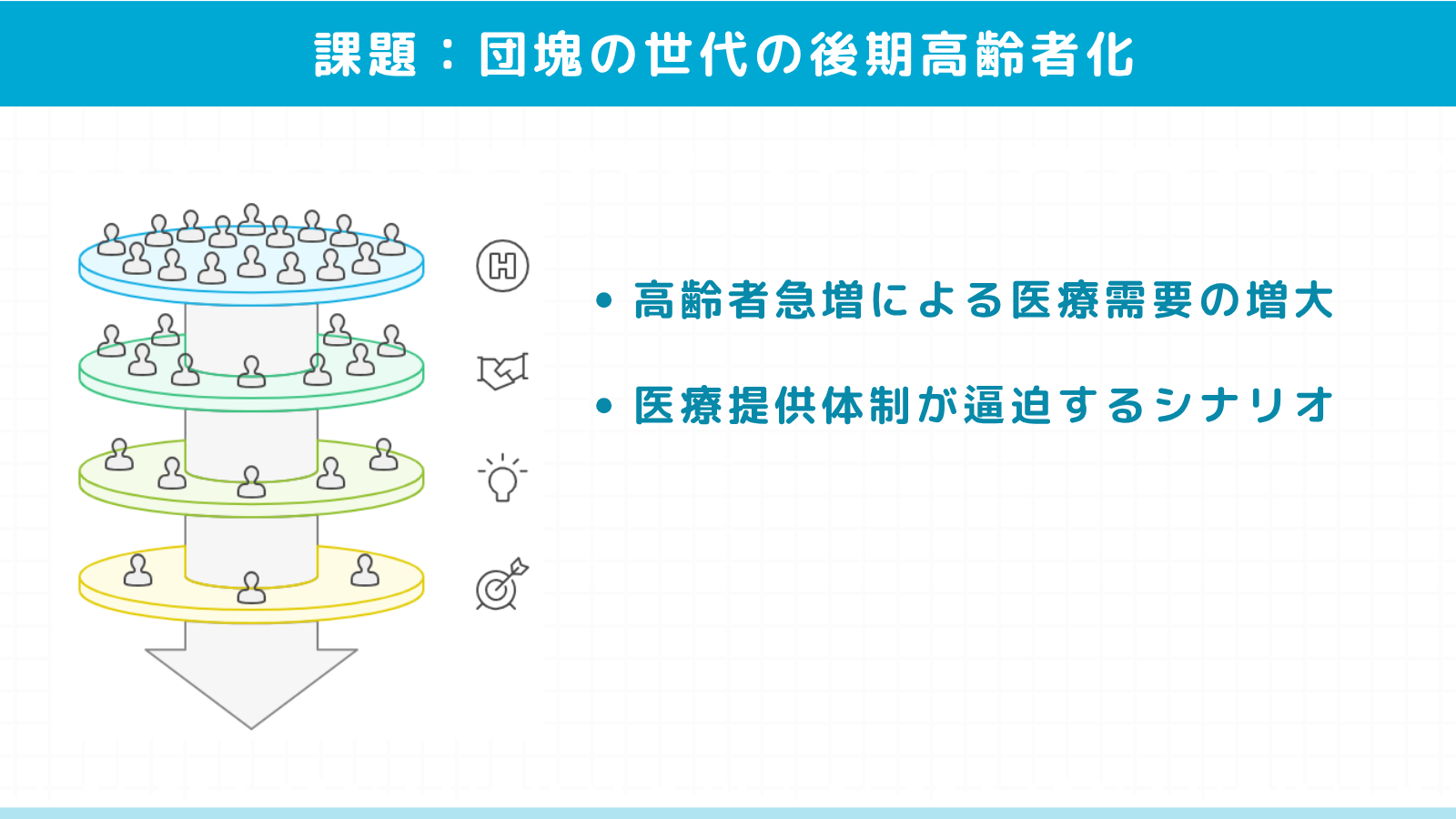
後期高齢者急増による医療・介護需要の増大
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2030年頃には、医療・介護を必要とする高齢者の数が一気に増えることになります。特に、後期高齢者は要介護状態になるリスクや慢性疾患の割合が急激に高まるため、病院や介護施設、在宅医療・介護サービスの需要が飛躍的に増加します。
これに伴い、外来診療や入院施設、在宅医療、訪問介護などのサービスにおいては、受け皿となる病院や介護施設が圧倒的に不足する可能性があります。従来の施設やサービス体系だけでは増え続ける高齢者をカバーすることは難しくなり、サービスの待機期間やサービスを受けられない高齢者が増えることが懸念されます。
また、後期高齢者が増加すると、認知症をはじめ慢性疾患や合併症を抱える患者が増えるため、複雑かつ多様なケアニーズに応える必要があり、医療・介護サービスの質的な負担も増加します。
こうした需要の急増に対し、供給体制が追いつかない場合、医療・介護の現場に大きな混乱をもたらし、ひいては医療安全性や介護サービスの質低下につながる可能性もあります。
医療提供体制が逼迫する具体的なシナリオ
団塊の世代の後期高齢者化に伴い、医療提供体制には以下のような具体的課題が生じます。
入院病床の絶対的不足
・病院の病床数が高齢者の入院需要を満たせず、入院待機期間が長期化する可能性がある。
外来診療の混雑
・慢性疾患患者が急増し、診療予約が取りづらく、待ち時間が長くなる状況が予想される。
医師・看護師の負担増大
・患者増加により一人あたりの負担が増え、業務量が大幅に増加し、医療従事者の離職リスクも高まる。
在宅医療サービスの不足
・入院が難しくなった高齢者が増加する一方で、在宅医療を支える人材や訪問看護の体制が追いつかず、在宅医療の提供体制が逼迫する。
救急医療の機能低下
・緊急時の病院受け入れが困難になるケースが増え、地域の救急医療が危機的状況に陥る。
このような具体的シナリオは、医療の現場のみならず地域社会全体にも大きな影響を与え、医療の質やサービスの低下を招く恐れがあります。
施設不足と在宅医療・介護サービスへの影響
後期高齢者の急増は、介護施設や在宅医療・介護サービスにも深刻な影響を及ぼします。施設介護のニーズは高まるものの、施設の供給が需要増に追いつかないため、多くの高齢者が施設入居の待機状態となり、家庭での介護負担がさらに深刻化する可能性があります。
特に都市部においては土地不足や人材不足により新たな施設開設が困難であり、介護サービスの不足が顕著になるでしょう。一方、地方部では施設はある程度整備されていても、介護従事者の不足によりサービス提供がままならず、稼働率が落ちるという事態も想定されます。
この結果として、在宅医療や訪問介護サービスの需要が高まりますが、在宅サービスを提供する人材もまた不足しており、十分なサービス提供が難しくなります。結果として、家族介護の負担が増し、家庭内の介護疲れや介護離職など、社会的な問題が一層深刻化する恐れがあります。
また、施設不足により在宅で生活せざるを得ない高齢者が増えるため、住宅改修や介護用品の整備、地域での見守り体制の構築など、新たな地域ケアの仕組みづくりが急務となります。
このように、後期高齢者化は施設介護と在宅介護の両面において深刻な影響をもたらし、従来の仕組みを根本から見直すことが求められています。
深刻化する医療・介護業界の人材不足問題
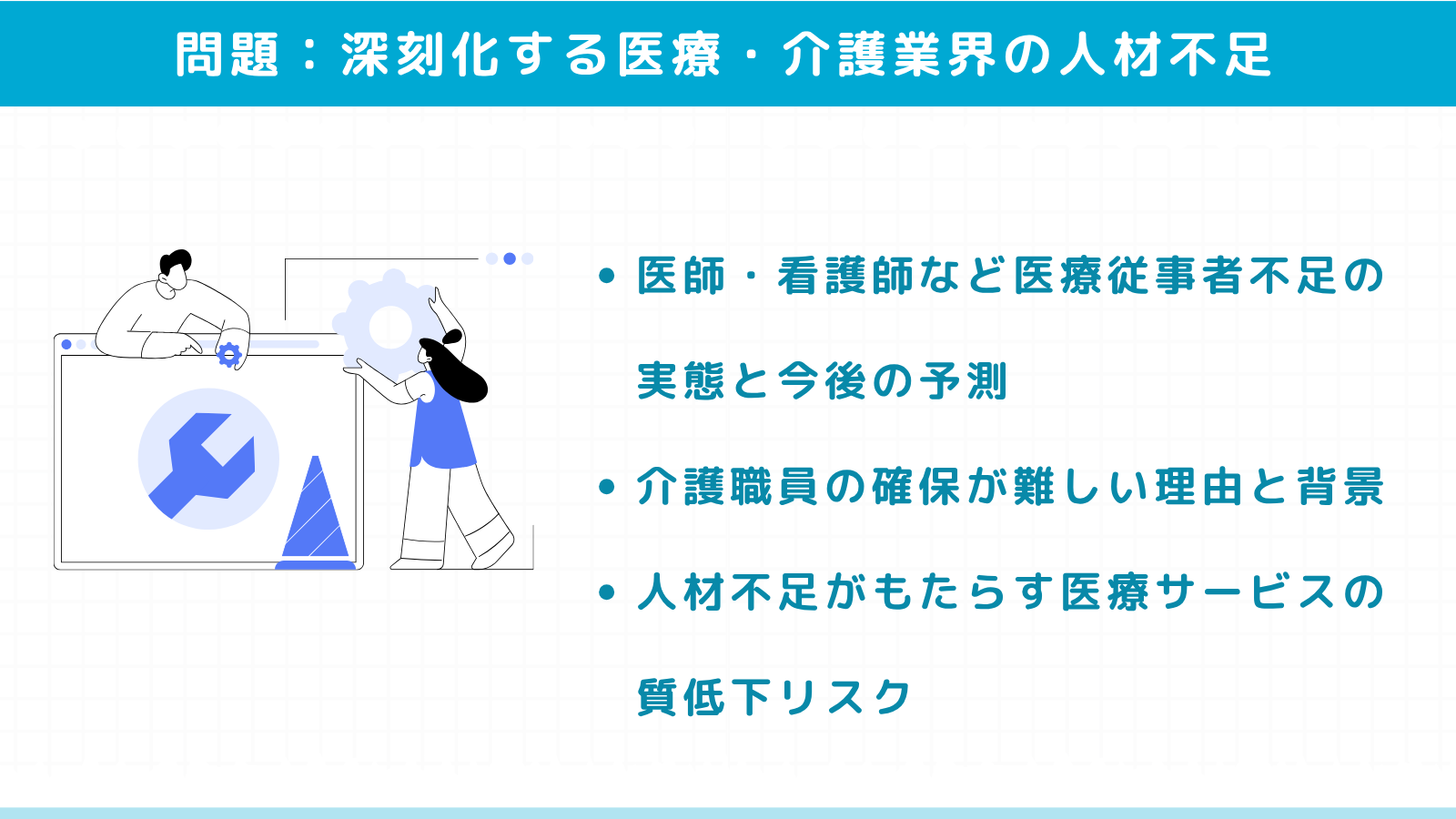
医師・看護師など医療従事者不足の実態と今後の予測
2030年問題において特に深刻なのが、医師や看護師など医療従事者の人材不足です。日本では、団塊の世代が後期高齢者になることで医療需要が急増しますが、それに見合った医療従事者の数は確保されていません。厚生労働省の推計では、2030年時点で医師や看護師の不足は数万人規模に上るとされています。
医師の場合、特に地方の病院や診療所での人材不足が深刻で、地域医療の崩壊を招きかねません。大学病院を含む大病院に医師が集中する一方、地方の医療機関では医師確保が難しく、医師一人当たりの負担が増加する状況が続いています。看護師に関しても同様に、病棟勤務や訪問看護などでの業務負担が増え、離職率が高止まりしているのが実情です。このような状況下で、人材採用がクリニック経営を成功に導くカギとなり、医療スタッフの質や人数を確保することが地域医療を守るための最重要課題となっています。医療従事者不足がこのまま進むと、患者への対応時間が短縮され、診療の質低下や医療事故リスクが高まる恐れがあります。さらに、医療スタッフの負担増加による心身の健康問題も深刻化するため、医療現場の崩壊を未然に防ぐための対策が急務となっています。
介護職員の確保が難しい理由と背景
介護職員の確保が難しい背景には、以下のような要因があります。
労働条件の厳しさ
・夜勤や長時間勤務など身体的・精神的な負担が重く、職員の離職率が高い。
低賃金の問題
・他産業と比較して給与水準が低く、人材が集まりにくい。
社会的評価の不足
・介護職に対する社会的な評価や認知度が低く、就業希望者が増えない。
慢性的な人手不足
・施設数が増加する一方、採用が追いつかず、現場の一人当たりの業務量が増加。
将来的なキャリアパスの不透明さ
・昇給や昇進の仕組みが明確でないことから、長期的に介護職を続ける意欲が維持されにくい。
こうした要因から、介護業界の人材不足は今後さらに深刻化することが予測されています。
人材不足がもたらす医療・介護サービスの質低下リスク
人材不足は、医療・介護サービスの質を著しく低下させるリスクをもたらします。特に医療現場では、医師や看護師の不足により診療やケアにかける時間が減少し、医療の安全性が脅かされる可能性があります。また、スタッフ一人あたりの負担が増えることで疲弊し、ケアの質が低下したり、医療事故やミスが起こりやすくなったりする危険性も高まります。
介護現場においても同様で、介護職員が不足すると、一人あたりのケアが行き届かず、介護サービスの質が落ちます。その結果、高齢者の健康状態が悪化したり、家族が介護離職を余儀なくされたりするなど、社会的にも経済的にも大きな影響を及ぼします。
さらに人材不足が続けば、現場スタッフの離職が加速し、さらなる人材不足という悪循環を生むことになりかねません。このため、医療・介護サービスの質を維持するためにも、人材確保や育成、定着を図る取り組みが不可欠となっています。
地域医療崩壊の危機とその影響
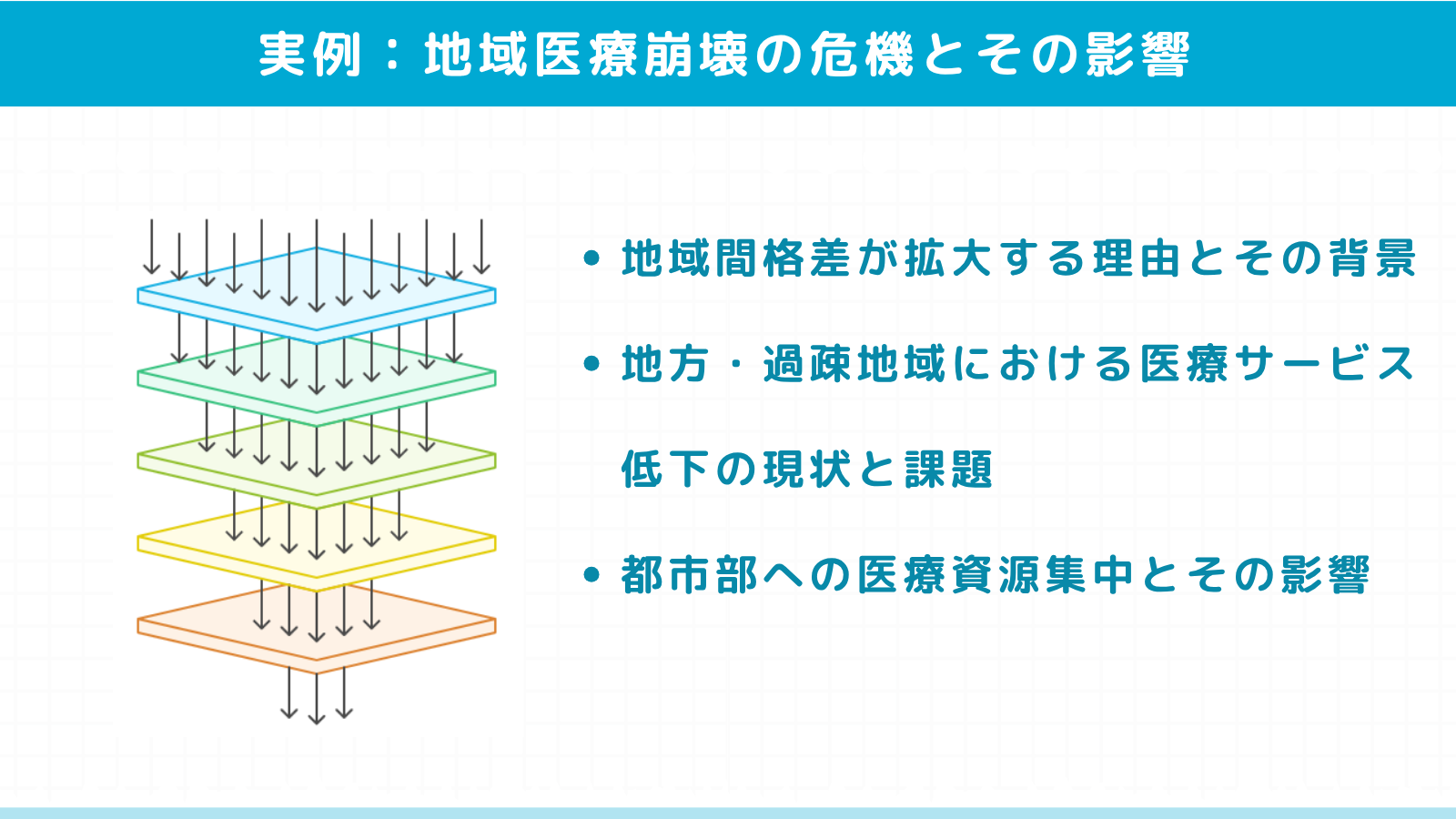
地域間格差が拡大する理由とその背景
2030年問題が深刻化すると、地域間の医療提供体制の格差がますます拡大すると予測されています。特に地方や過疎地域では、若年層の流出により人口が減少し、高齢者が占める割合が大幅に増えています。その結果、地域内の医療需要が高まる一方で、十分な医療人材や施設を確保できない状況が続いています。
さらに、都市部では医療資源が集中する傾向が強く、大規模病院や専門医療機関が都市に集約されることで、地方では医師や看護師の採用が難しくなり、施設の縮小や廃止が相次ぐようになっています。また、地域の医療機関が減少すれば、住民はより遠方まで通院する必要があり、医療アクセスの不便さが増加します。
こうした背景から、都市と地方の医療提供体制の格差が今後も広がり続ける可能性が高く、地域住民の健康維持が難しくなることが懸念されています。
地方・過疎地域における医療サービス低下の現状と課題
地方や過疎地域における医療サービスの低下には、以下のような現状と課題があります。
医師不足・医療従事者不足の慢性化
・医師や看護師が不足し、必要な医療提供が難しくなる。
診療所・病院の廃止や診療縮小
・採算が取れず施設が閉鎖され、地域の医療機関が減少している。
救急医療体制の弱体化
・緊急時に対応できる施設や人材が不足し、緊急搬送が困難になる。
在宅医療・訪問看護の担い手不足
・高齢者の在宅医療・介護を支える人材不足により、ケアが行き届かなくなる。
交通の不便さが医療アクセスを困難に
・医療機関までの移動手段が少なく、特に高齢者が医療機関に通うのが難しくなる。
こうした課題が放置されれば、地域医療が崩壊し、地域住民の健康を著しく損なうリスクが高まります。
都市部への医療資源集中とその影響
医療資源が都市部に集中すると、地方との間に深刻な医療格差が生まれます。特に大都市では大規模病院や専門医療機関が集積し、医療の選択肢が広がり質の高い医療を受けやすくなります。一方、地方や過疎地域では医療資源が限られ、慢性的な人材不足から医療の質やサービス内容が低下し、地域住民が適切な医療を受ける機会を失うケースが増えてしまいます。
また、都市部に医療資源が集中することで、地方から都市への医療目的の人口流入が進み、都市部の医療機関の混雑や過負荷を生じさせる可能性もあります。その結果、都市部でも待ち時間が長くなり、患者への対応が手薄になるリスクが生まれます。
こうした医療資源の偏在を解消し、全国どこでも安心して医療を受けられる体制を築くことが、今後の重要な課題となります。
医療費・介護費の急増がもたらす経済的課題
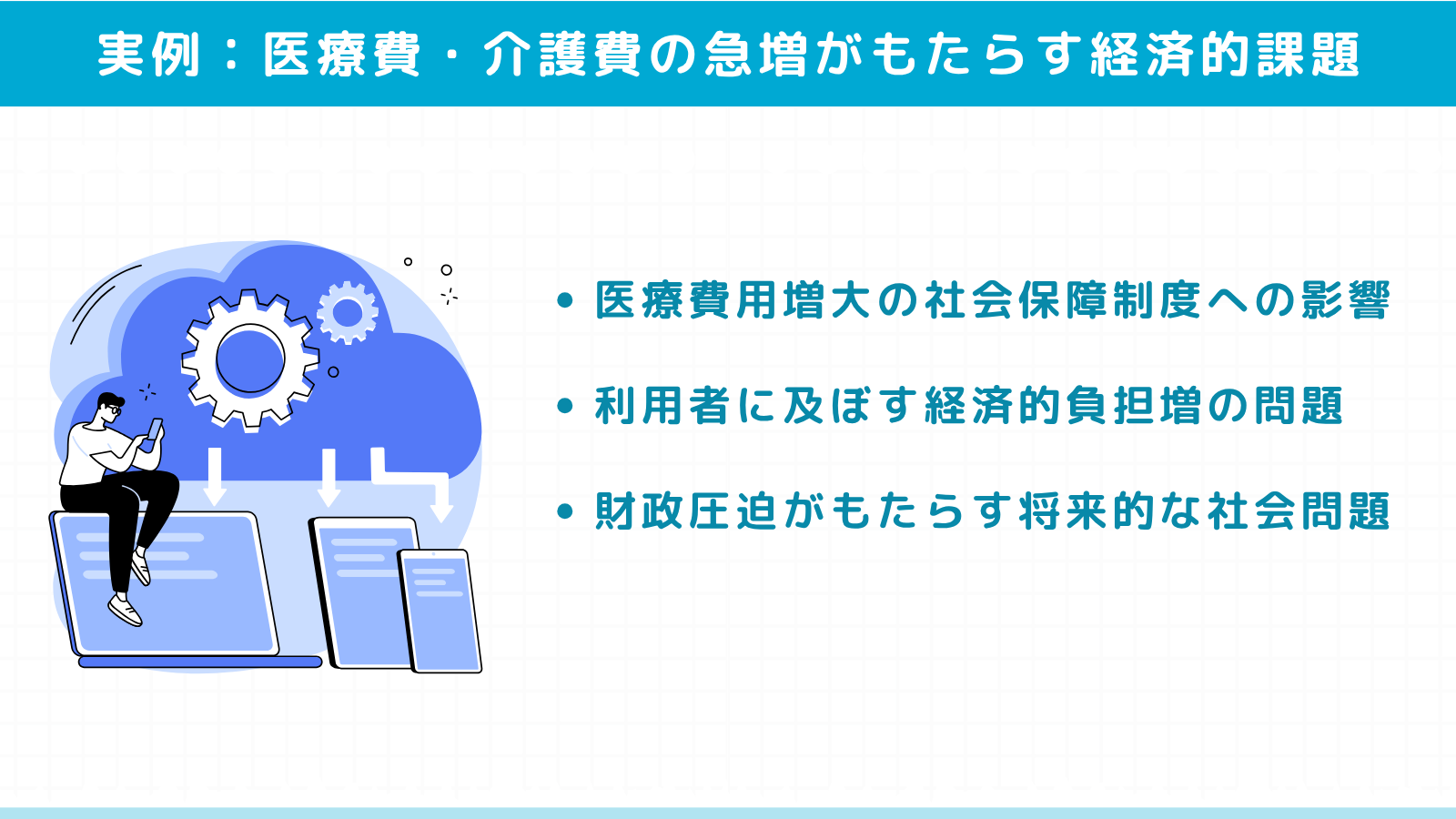
医療・介護費用増大の社会保障制度への影響
2030年問題により高齢者人口が急増すると、医療費や介護費の増加が避けられません。厚生労働省の試算によれば、2030年度には医療費は現在より数兆円規模で増加すると予測されています。高齢者ほど医療・介護の利用頻度が高く、慢性疾患や複数疾患を抱えるケースも増えるため、これまで以上に医療資源の消費が急増します。
こうした費用増は、財政面で社会保障制度に大きな負担をかけることになります。具体的には、保険料の引き上げや公費負担の増加を招くこととなり、現役世代の経済的負担増や社会保障制度の維持困難という問題が現実化します。社会保障制度の持続可能性が危ぶまれる状況になり、制度自体の大幅な改革や見直しが不可欠となってきます。
患者・利用者に及ぼす経済的負担増の問題
医療費・介護費が増大すると、患者や利用者個人にとっても深刻な経済的負担が生じます。具体的な問題点としては以下が挙げられます。
医療費・介護費の自己負担額増加
・自己負担割合の引き上げや、サービスの自己負担増が検討される可能性。
保険料の引き上げ
・現役世代だけでなく、高齢者自身の医療・介護保険料が高額化するリスク。
経済的理由での受診控えやサービス利用控え
・経済負担を理由に必要な医療や介護サービスを受けられず、健康悪化につながる。
家計への圧迫
・医療・介護費増が家計を圧迫し、他の生活費を削るなどの問題が起きる可能性。
こうした負担増により、社会的な格差拡大や健康格差の深刻化を招くことも懸念されます。
財政圧迫がもたらす将来的な社会問題
医療費や介護費の増大による財政圧迫が続くと、医療・介護以外の分野への予算配分が難しくなる可能性があります。特に教育や子育て支援、インフラ整備など、将来を支える重要な政策分野への財源確保が困難になり、社会全体の持続的発展が阻害されるリスクがあります。
また、財政の悪化により地方自治体の財政状況も逼迫し、地域医療や介護サービスの縮小や撤退を余儀なくされるケースが増え、地域格差が一層深刻になる恐れもあります。
長期的には社会保障制度を支える現役世代の負担が過重となり、労働意欲や消費活動にも悪影響を及ぼすなど、経済活動そのものが停滞する可能性も指摘されています。持続可能な社会システムを維持するためには、医療費・介護費増大に伴う財政圧迫を適切に管理し、バランスの取れた財政政策を展開することが重要となります。
「2030年問題」への政府・自治体による対策と政策動向
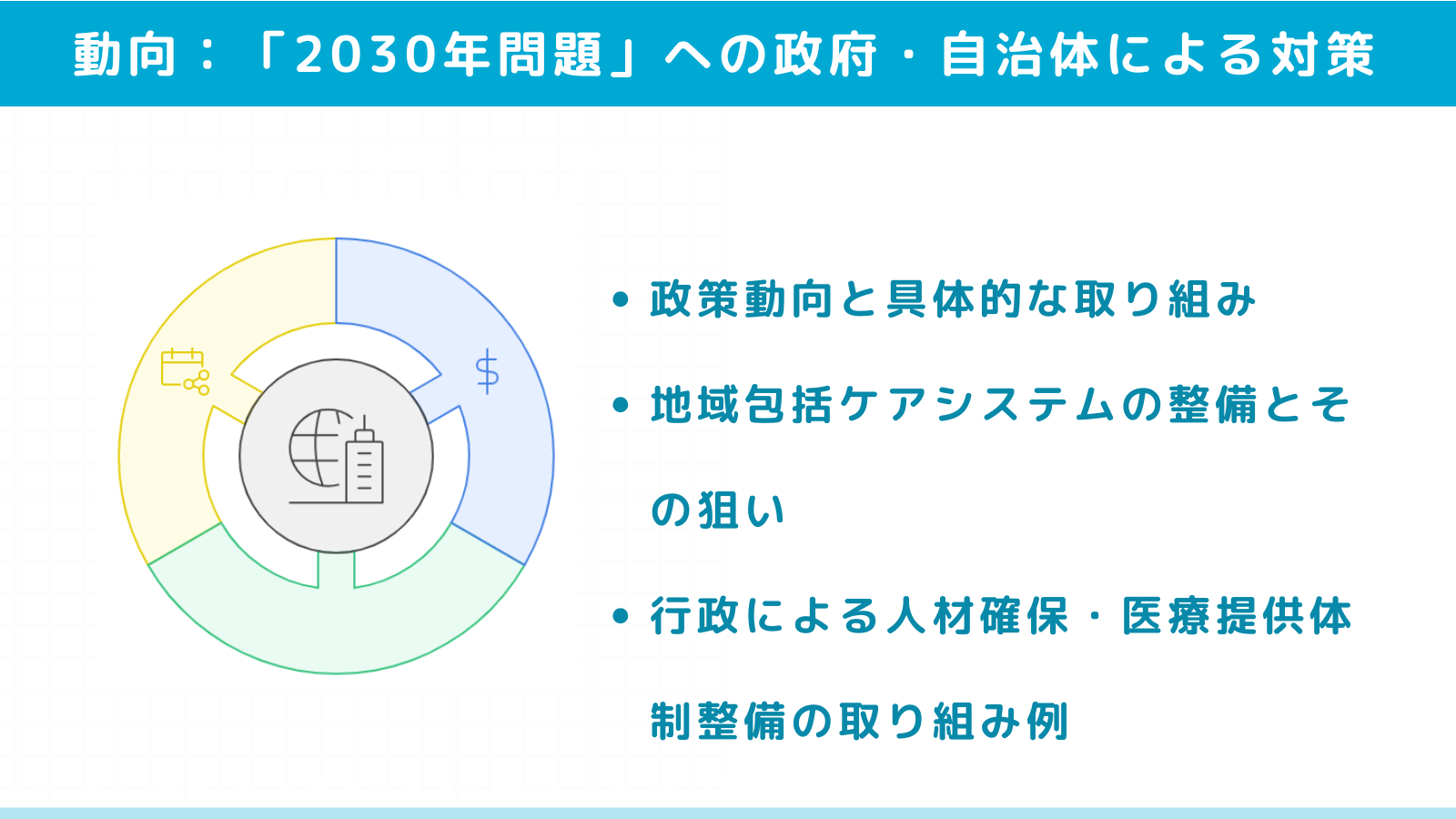
現在の政策動向と具体的な取り組み
「2030年問題」への対策として、政府や自治体はさまざまな施策を進めています。厚生労働省は、超高齢社会を見据え、地域包括ケアシステムの推進や、医療・介護の連携強化を政策の柱に据えています。また、地方自治体においても、地域医療・介護サービスの充実を図るために独自の取り組みを行う例が増えてきています。
具体的な取り組みとして、在宅医療・訪問看護サービスの充実、地域医療ネットワークの整備、ICTを活用した遠隔診療や遠隔介護支援の推進などが進められています。また、介護予防や健康増進事業を積極的に展開し、高齢者自身の健康維持・自立支援を強化することで、医療・介護需要の抑制を図っています。
こうした政策の推進により、将来的な医療・介護サービスの逼迫を緩和し、地域での安定したサービス提供を目指しています。
地域包括ケアシステムの整備とその狙い
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を継続できるよう、医療・介護・福祉の一体的な提供を目指す仕組みです。その整備による狙いは以下の通りです。
地域密着型サービスの充実
・在宅医療・介護サービスを地域内で完結させ、高齢者の生活を支える。
医療と介護の連携強化
・地域の病院やクリニック、介護施設、訪問看護・介護サービス事業者が情報共有し、シームレスなサービス提供を実現。
予防・健康増進への取り組み強化
・介護予防プログラムや健康教室を開催し、高齢者自身の健康維持を支援。
地域コミュニティとの連携促進
・地域住民やボランティアなども巻き込み、見守り・支援体制を構築。
財政負担の軽減
・医療・介護費用の抑制につながり、社会保障制度の持続可能性向上。
こうしたシステム整備を通じて、高齢者が安心して暮らせる地域社会を目指しています。
行政による人材確保・医療提供体制整備の取り組み例
医療・介護現場の人材不足は深刻化していますが、政府や自治体は人材確保と提供体制整備のため、具体的な取り組みを展開しています。例えば、医療従事者・介護職員の処遇改善策として、給与・待遇改善のための財政支援や、キャリアアップ支援を進めています。
また、医学部定員の地域枠設置を通じ、地域医療を担う医師の育成を推進しています。看護師や介護職の養成学校の支援や、資格取得支援、奨学金制度の拡充などを通じて、医療・介護分野への人材参入を促しています。
さらに自治体単位で、地域医療・介護拠点の整備や人材バンクの設置、移住・定住支援、子育て支援施設の拡充などを行い、医療・介護従事者が安心して働ける環境整備に努めています。こうした施策により、人材の確保と定着を図り、将来にわたって安定した医療提供体制を維持することを目指しています。
医療機関・介護事業者が今から取り組むべき対策
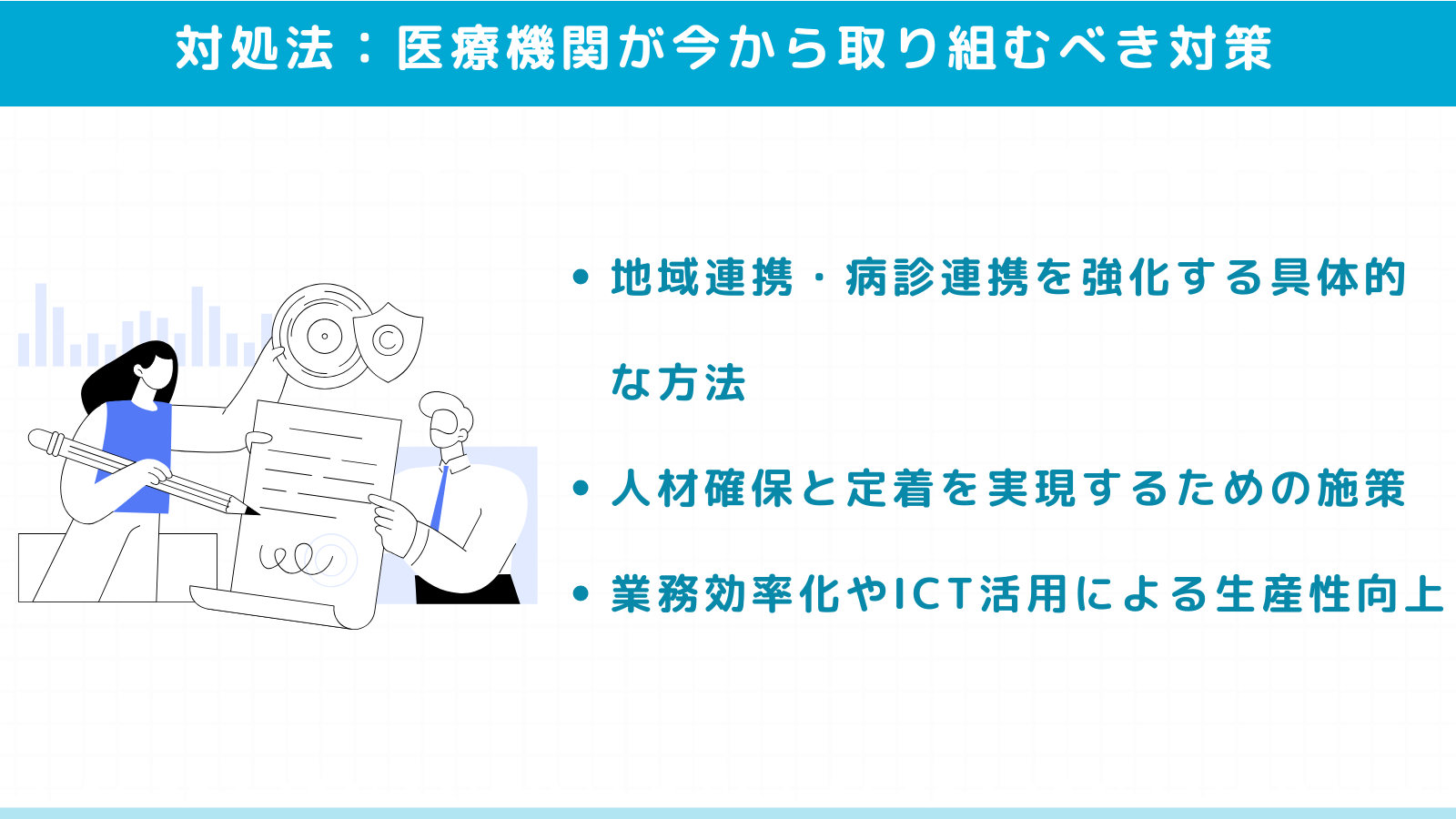
地域連携・病診連携を強化する具体的な方法
「2030年問題」に向けて、地域の医療機関や介護事業者が取り組むべき最も重要な対策の一つが、地域連携や病診連携の強化です。特に、団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護サービスの需要が急増するなかでは、個々の施設やクリニックが単独で対応することは難しく、地域全体で連携した対応が不可欠となります。
地域連携を強化するには、まず地域の医療機関同士や介護サービス事業者との日常的な情報共有の仕組みづくりが必要です。ICTを活用した地域医療ネットワークの構築を進め、診療情報や患者情報をスムーズに共有できる環境を整備します。また、定期的に地域内で医療・介護関係者の会合を開き、情報交換や連携課題の共有、解決策の検討を進めることも有効です。
病診連携では、地域の病院と診療所がそれぞれの役割を明確にし、急性期の治療を病院で行い、慢性期やリハビリを診療所や介護施設が担当するなど、役割分担を明確にすることが重要です。患者が医療機関間を円滑に移行できるような連携システムの構築を早期に行い、地域全体での医療提供体制の効率化を図ることが求められます。
人材確保と定着を実現するための施策
医療・介護現場で深刻化する人材不足問題を解消するためには、人材の確保と定着の両面から取り組みを進める必要があります。具体的な施策としては以下の通りです。
労働環境の改善
・勤務時間や休日の柔軟な設定、残業削減のための業務効率化を推進する。
給与・待遇改善
・地域相場に応じた給与体系の整備やキャリアアップによる給与増を実現する。
教育・研修の充実
・職員のキャリアアップやスキル向上を支援するため、定期的な教育・研修を行う。
子育て・介護支援制度の整備
・子育てや介護と仕事の両立を可能にするための支援制度を整える。
キャリアパスの明確化
・昇進や役職への道筋を明確にし、職員の意欲向上と定着を促す。
ICT・AI活用による業務負担軽減
・業務効率化ツールの導入により、業務負担を減らし働きやすい環境を提供する。
こうした施策を積極的に導入することで、人材が定着し、安定的な医療・介護サービス提供が可能になります。
業務効率化やICT活用による生産性向上
「2030年問題」に備えるためには、医療機関・介護事業者が業務効率化やICT活用を積極的に推進し、生産性を向上させることが不可欠です。現在、多くの現場ではスタッフの業務負担が大きく、煩雑な事務作業などによって本来業務に集中できない状況が課題となっています。
業務効率化を進めるためには、電子カルテやオンライン資格確認、医療情報連携システムなどを導入し、患者情報管理や事務処理を大幅に効率化することが求められます。例えば、診察記録のデジタル化により、事務作業の負担を減らすとともに、診療の質向上やミス削減にもつながります。
また、介護現場では、IoTを活用した見守りシステムや介護記録アプリの導入により、スタッフの業務負担を軽減し、介護サービスの質を高めることが可能になります。ICT活用は業務負担軽減にとどまらず、医療・介護サービスの質的向上や患者満足度向上にも直結します。
医療機関や介護事業者は、こうしたテクノロジー導入を積極的に進め、生産性の高い現場づくりを目指すことが求められています。
医療・介護業界におけるICT・DX活用による解決策
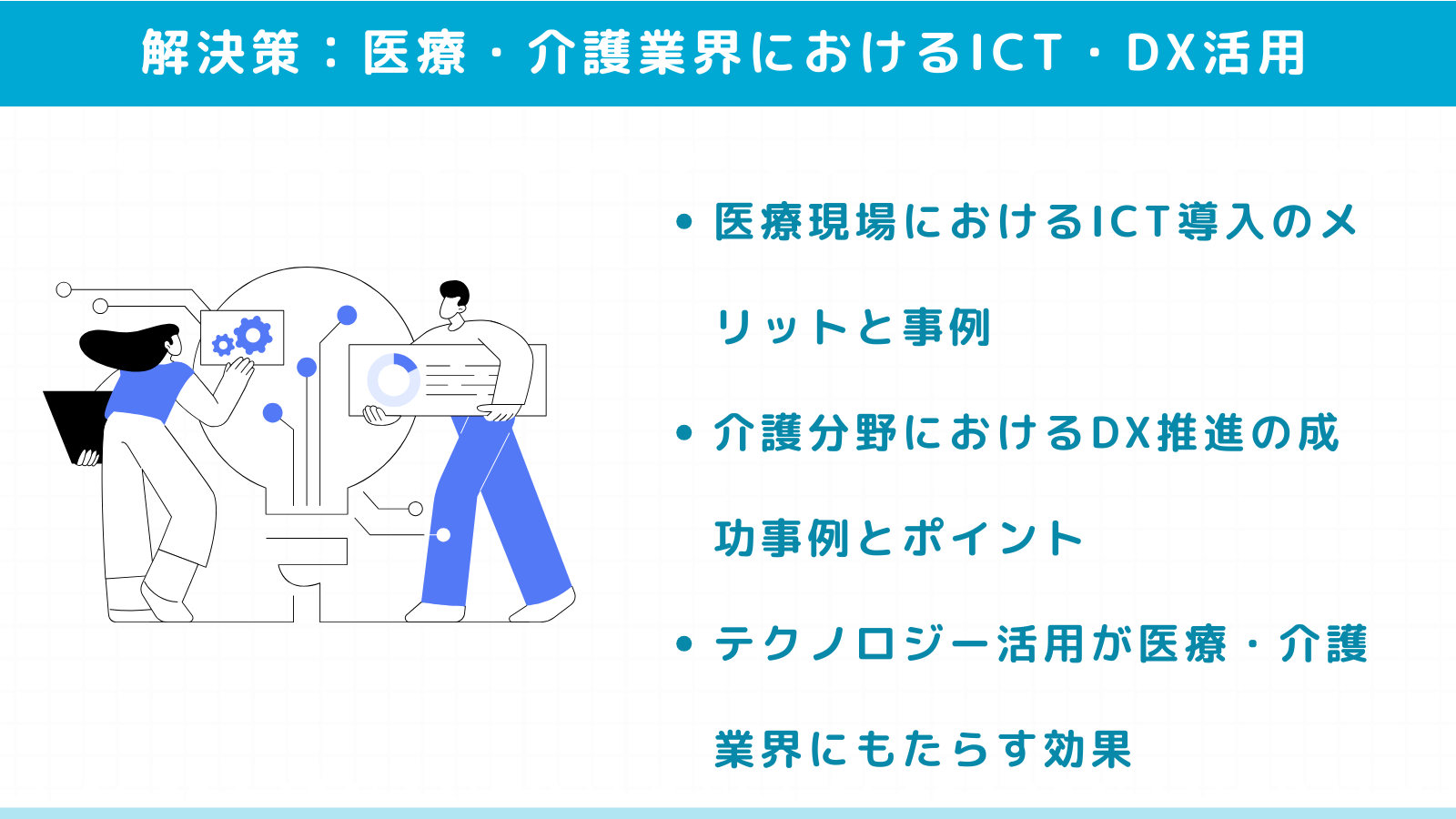
医療現場におけるICT導入のメリットと事例
医療現場では、2030年問題に対応するためICT(情報通信技術)の導入が急務となっています。ICTを導入することで、診療・治療の効率化、情報共有の迅速化、患者安全性の向上といった多くのメリットが期待できます。
例えば電子カルテの導入は、診療記録の管理や共有を迅速に行い、紙ベースの記録に比べて医療ミスのリスクを低減します。また、オンライン診療の普及によって患者が自宅から診察を受けることが可能になり、通院困難な高齢者や地方在住の患者への医療サービス提供が容易になります。
さらに、AIを活用した画像診断支援システムの導入によって、診断精度が向上し、医師の負担軽減にも繋がっています。実際の導入事例では、AI搭載の画像解析ソフトウェアにより、疾患の早期発見や正確な診断が可能となり、医療の質の向上に成功したケースも報告されています。
ICT導入は、患者だけでなく医療スタッフにとっても働きやすい環境を作り出し、業務効率化・医療安全性向上に大きく貢献しています。
介護分野におけるDX推進の成功事例とポイント
介護業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められており、多くの事業者がすでに成果を上げています。特に成功している取り組みには以下のようなものがあります。
見守りシステムの導入
・IoTを活用した高齢者見守りシステムでスタッフ負担軽減・安全管理を向上。
介護記録アプリの活用
・記録業務のデジタル化で書類作成時間を大幅短縮し、直接介護時間を増加。
AI搭載介護ロボットの導入
・移動支援や力仕事を軽減する介護ロボットでスタッフの身体的負担を削減。
ICTを用いたスタッフ間コミュニケーション強化
・チャットツールやオンライン会議で情報共有を迅速化、業務効率を改善。
VRを用いた介護スタッフ研修
・VR技術によるリアルな介護技術トレーニングで実践的スキルを向上。
これらの事例に共通する成功ポイントは、「現場のニーズに即した技術の選定」「導入後のフォロー体制の整備」「スタッフ教育・トレーニングの充実」です。
テクノロジー活用が医療・介護業界にもたらす効果
テクノロジーの活用は、医療・介護業界が直面する課題を克服するために非常に有効な手段です。ICTやAI、IoTなどの先進技術を取り入れることで、効率化だけでなくサービスの質向上や働きやすい環境づくりが可能となります。
例えば、医療・介護現場でのICT活用により業務の非効率性が改善され、職員の業務負担が軽減されます。その結果、直接的な医療・介護に注力できる時間が増加し、患者や利用者へのきめ細かいサービス提供が可能になります。また、テクノロジーを活用した遠隔診療や見守りシステムにより、地域格差の問題を解消し、どこに住んでいても質の高い医療・介護サービスを受けられるようになります。
さらにAI技術を活用した予測医療・介護も進んでおり、疾患や介護リスクの早期予測が可能になります。これは疾病予防や早期介入を促進し、結果的に医療費や介護費用の削減にもつながります。
テクノロジー導入によって医療・介護業界は、サービスの質向上、スタッフ負担の軽減、経済的な負担軽減という多面的な効果を享受することができるのです。
2030年以降も持続可能な医療・介護体制を築くために
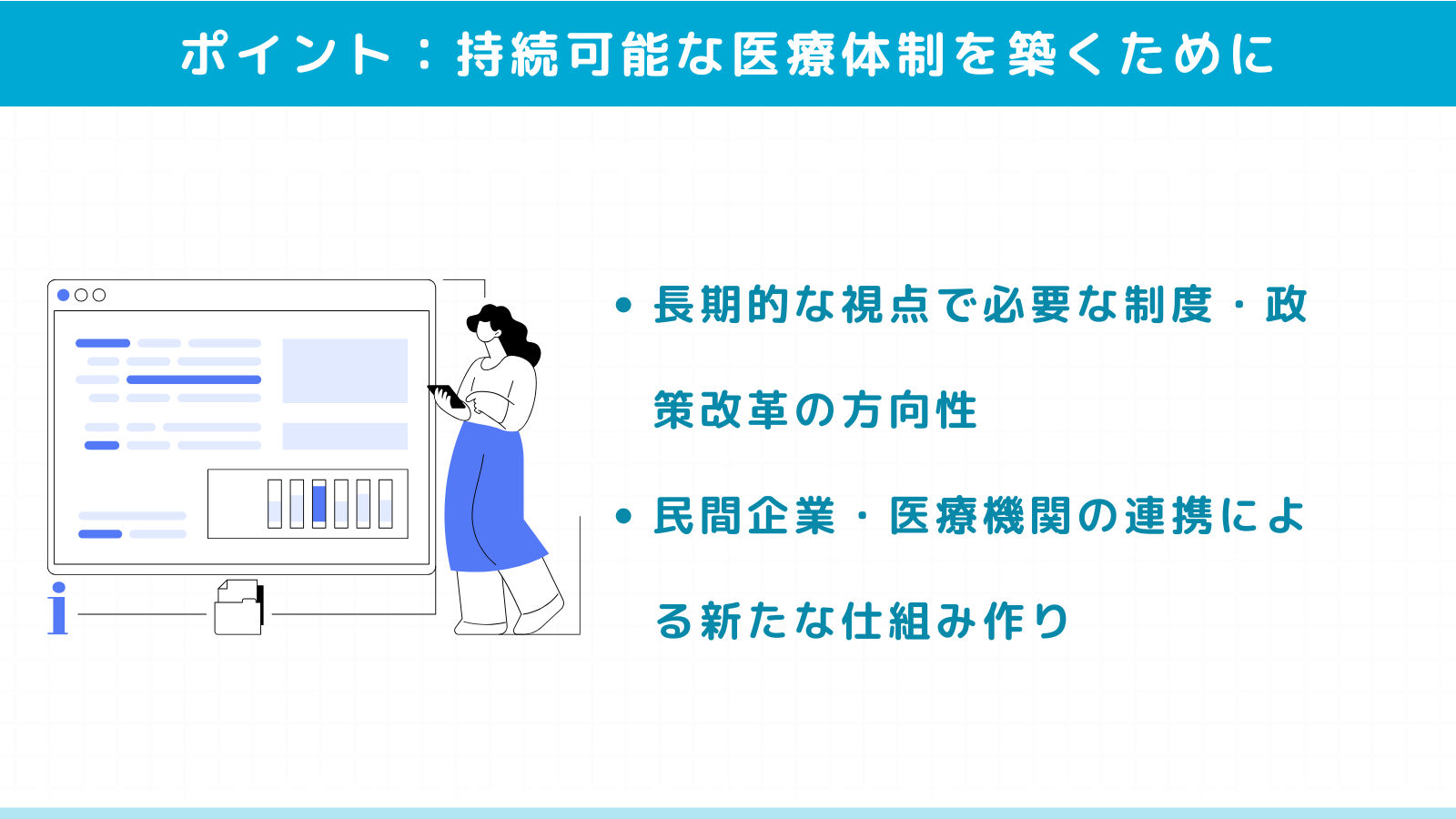
長期的な視点で必要な制度・政策改革の方向性
2030年問題を乗り越え、その先も持続可能な医療・介護体制を実現するには、長期的な視点での制度・政策改革が不可欠です。高齢化がピークを迎え、労働人口が減少する中、医療・介護資源を効率的かつ公平に配分する仕組みづくりが求められています。
制度改革の方向性としては、予防医療や健康寿命延伸を推進し、疾病の発生を未然に防ぐことが重要になります。例えば、健康診断や予防接種の義務化や拡充、生活習慣病予防のための具体的な政策を進めることが挙げられます。
また、医療・介護の連携をさらに強化し、地域包括ケアシステムの質を向上させることも重要です。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、在宅医療・訪問看護・訪問介護といったサービスを充実させるための政策支援が不可欠です。
さらに、医療費・介護費抑制のため、ICT・DX導入支援や保険制度の効率化、介護報酬の適正化など、多面的な政策改革を推進していく必要があります。持続可能な制度設計に向けて、現状の課題を正確に分析し、計画的な施策を段階的に展開することが求められます。
民間企業・医療機関の連携による新たな仕組み作り
医療・介護業界が持続可能な体制を構築するためには、行政だけでなく民間企業や医療機関との連携が鍵となります。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
民間企業の技術活用と連携
・IT企業やテクノロジー企業と協働し、電子カルテや遠隔医療、見守りシステムなどを開発・導入。
医療機関同士のネットワーク化
・地域の医療機関同士で病診連携を強化し、患者情報共有や連携医療体制の整備。
介護事業者と医療機関の協働
・地域包括ケアシステムの中核として医療・介護の連携を深め、円滑な在宅ケアサービスの提供。
産学官連携による人材育成
・医療・介護現場での人材不足解消に向け、学校や教育機関と連携し、即戦力人材を育成。
地域コミュニティやNPOとの協力
・地域資源を活用し、高齢者見守りや生活支援サービスを地域全体で支える仕組み作り。
これらの協力体制を構築することで、行政だけでは解決が難しい課題を補完し、持続可能な医療・介護の仕組みを地域全体で支える体制が整備されます。