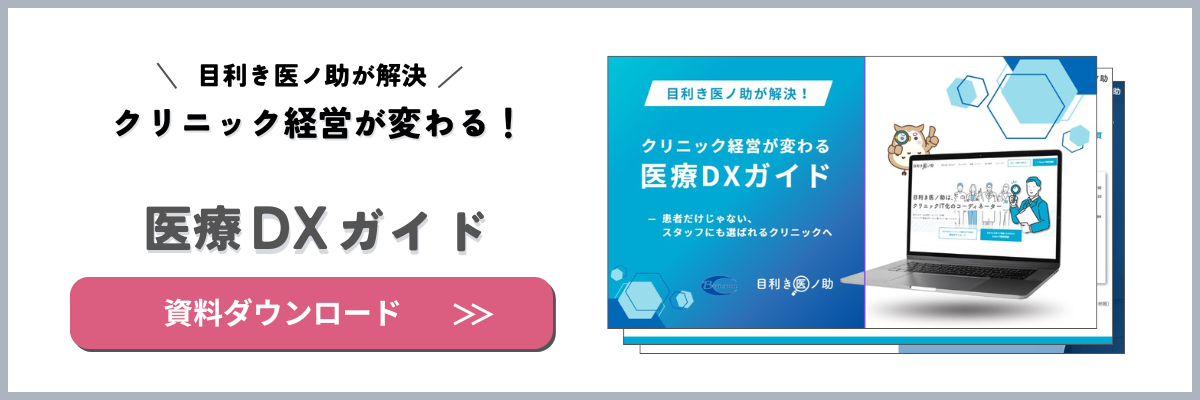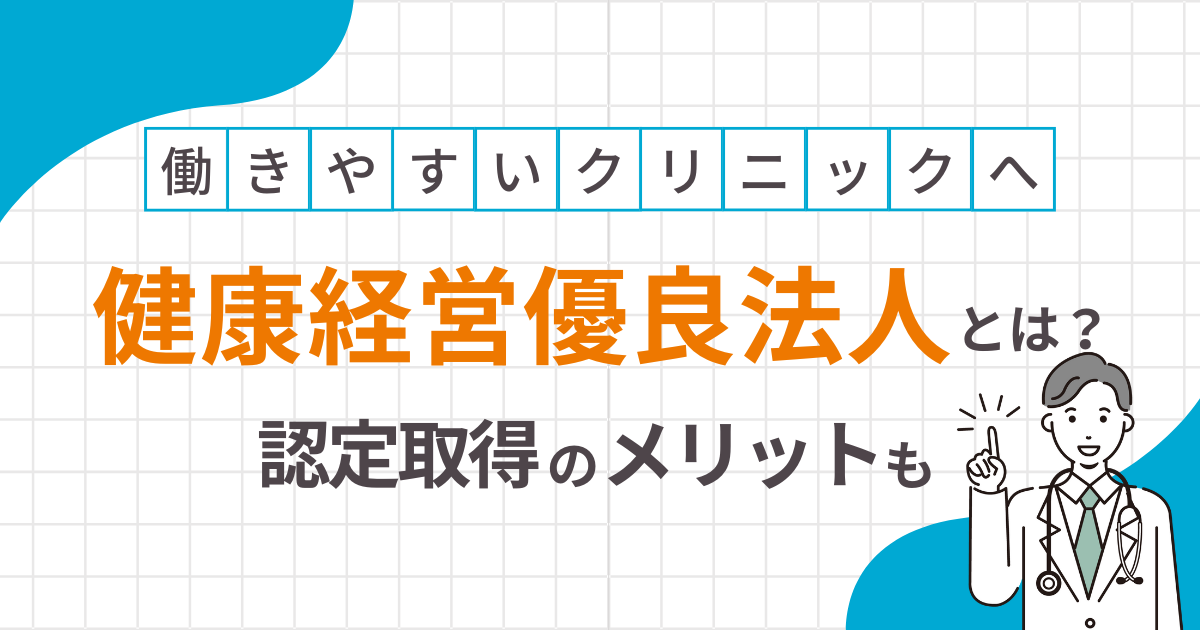
2025.11.21
健康経営優良法人とは?認定取得のメリットを解説【目利き医ノ助】
健康経営優良法人とは?制度の目的と基本概要
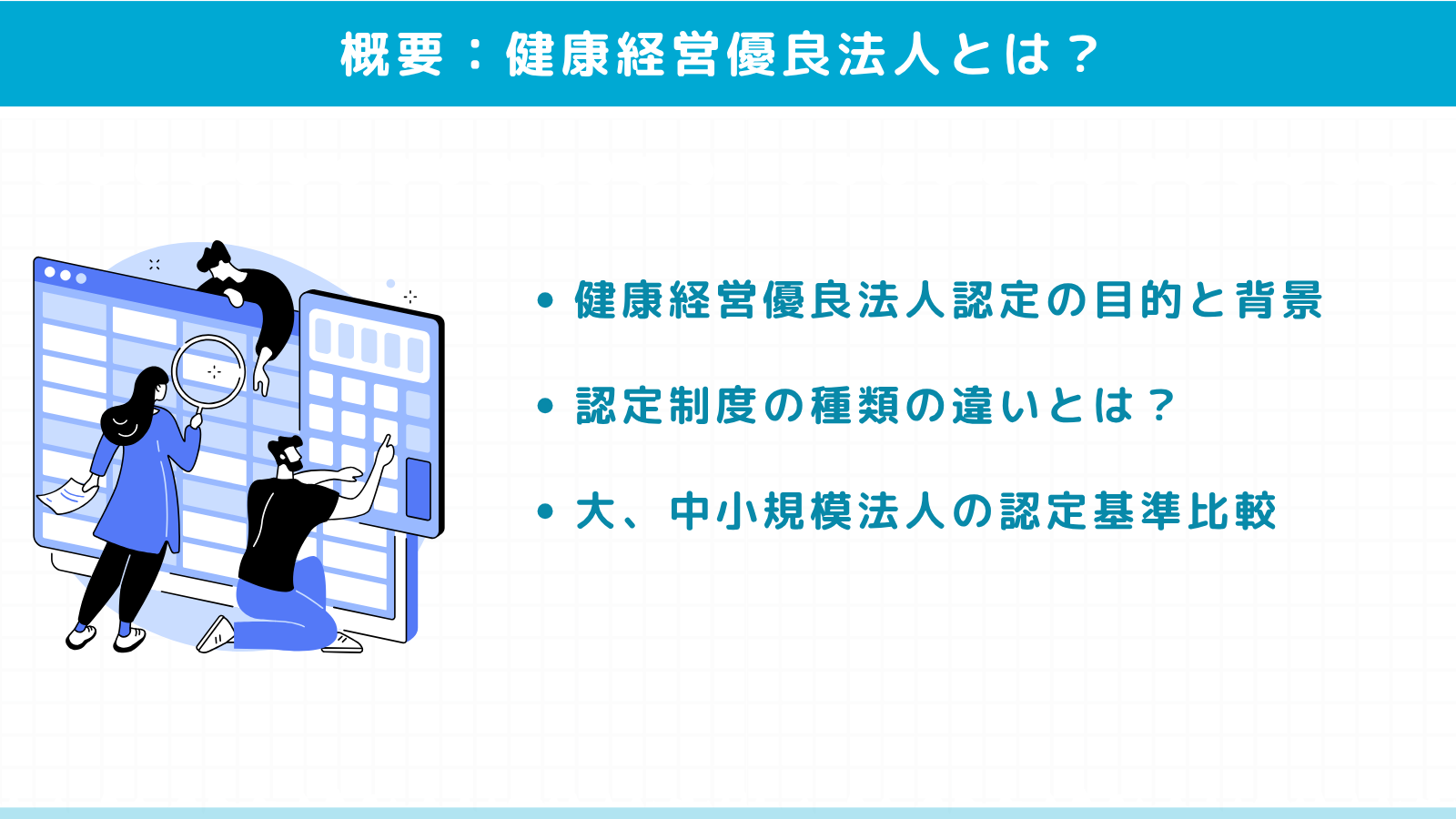
健康経営優良法人認定の目的と背景
健康経営優良法人とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している法人を顕彰する制度です。経済産業省が中心となって推進しているこの取り組みは、近年の日本社会が抱える労働人口の減少、働き方改革の推進、労働生産性の向上などの社会的課題に対応するために創設されました。
日本の労働人口は急激に減少しつつあり、その影響により企業は従業員一人ひとりの健康状態が生産性に直結することを強く意識せざるを得なくなっています。また、長時間労働の是正やメンタルヘルス不調者の増加、慢性疾患を抱える従業員の増加といった課題にも、経営として主体的に対応することが求められています。
こうした状況を背景に、健康経営の概念が広まり、健康経営優良法人の認定を取得することによって企業価値の向上や人材の確保・定着を図る企業が増えています。医療機関においても、健康経営優良法人として認定を受けることは、ブランドマーケティングでクリニックの集患力アップにつながる重要な戦略となっています。
この制度の目的は、企業が健康経営に取り組む意識を高めることで、従業員の健康を守りながら、企業の持続的な成長を促進することにあります。また、認定を取得した法人には、企業ブランドの向上や従業員満足度の向上、そして生産性の向上など多様なメリットがあり、近年では認定取得を目指す企業がますます増加傾向にあります。
認定制度の種類(大規模法人部門・中小規模法人部門)の違いとは?
健康経営優良法人認定制度には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つのカテゴリーがあります。これは、企業の規模や体力、実施可能な施策に差があるため、それぞれに適した評価基準を設定することで、規模に応じた健康経営の推進を促進することを目的としています。
【大規模法人部門の特徴】
大規模法人部門は、主に上場企業や大企業を対象としています。従業員数が多く、全国的・国際的な展開をしている企業が多いため、健康経営施策についても比較的大規模かつ体系的な取り組みが求められます。
具体的には、以下のような点が重視されます。
- 健康経営に関する明確な経営方針・戦略の策定
- 全社的に実施される健康促進施策や制度の整備
- 定期的な健康診断やストレスチェック等の制度化
- 健康経営施策の実績評価と改善を組織的に実施する体制の確立
【中小規模法人部門の特徴】
一方、中小規模法人部門は、地域密着型の中小企業や小規模事業者を対象としています。比較的規模の小さい企業であっても取り組める範囲での健康施策が求められ、従業員の健康意識の向上や働きやすい職場づくりが評価されます。
具体的には以下のような特徴があります。
- 身近で実践可能な健康づくり活動(運動推進、食生活改善など)
- 健康に関する社内教育や意識啓発活動の実施
- 経営者や管理職自らが健康づくりのリーダーシップを発揮しているか
- 従業員の健康維持・増進に向けた柔軟な取り組みや工夫
このように、企業規模に応じた評価基準を設けることで、大企業だけでなく中小企業においても健康経営の導入を促進することを狙っています。
大規模法人と中小規模法人の認定基準比較
健康経営優良法人の認定基準を大規模法人部門と中小規模法人部門で比較すると、主に以下のような違いがあります。
【大規模法人部門】
- 経営トップによる健康経営の明確なコミットメント(方針策定、社内外への発信)
- 全社的な組織体制整備(専任の担当部署・責任者の設置)
- 従業員の健康状態把握と分析(健康診断データ・ストレスチェック結果等の活用)
- 健康経営施策のPDCAサイクル運用(定期的な施策効果検証と改善)
- 対外的な情報開示(健康経営の取り組み成果や方針の公開)
【中小規模法人部門】
- 経営者が健康経営の推進に主体的に関与していること
- 従業員向けの健康づくり施策が具体的に実施されている(ウォーキング活動、健康講座開催等)
- 健康診断・ストレスチェックの実施率向上と結果を踏まえた具体的対応
- 健康に関する従業員の意識啓発活動の実施(ポスター掲示、社内広報等)
- 健康増進活動を評価し、報奨や表彰を行う制度の整備
以上のように、それぞれの企業規模や特性に応じた基準が設定されており、各法人は自身の規模に合った施策を推進し認定取得を目指すことが求められます。
健康経営優良法人の認定取得で得られる具体的なメリット
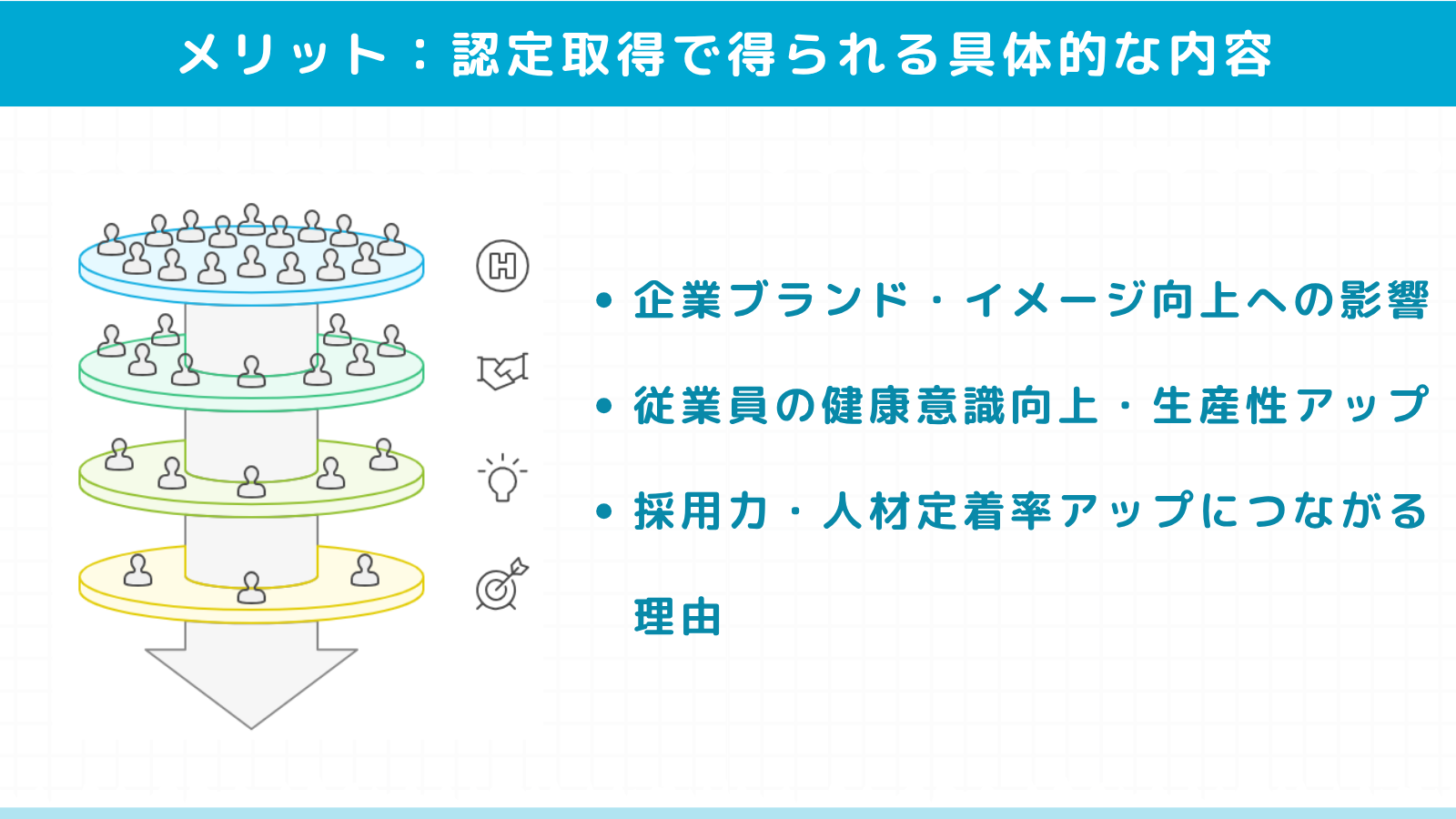
企業ブランド・イメージ向上への影響
健康経営優良法人の認定を取得すると、企業として従業員の健康に積極的に取り組んでいることが社会的に認知され、企業ブランドやイメージが大きく向上します。
特に昨今ではSDGs(持続可能な開発目標)やESG投資(環境・社会・ガバナンス)といった、社会的価値を重視する投資家や消費者が増えているため、健康経営の認定を受けることで社会的責任を果たしている企業としての信頼が高まります。
また、健康経営優良法人の認定は経済産業省が主導する公式なものであるため、その認定マークを広報活動や企業案内、求人広告などに活用することができます。これにより企業価値が可視化され、取引先企業や顧客からの評価も向上し、競争優位性が確保できます。
さらに、企業ブランドが強化されることで、企業の知名度や信頼性が向上し、新規顧客の獲得や取引先の拡大など、経営的なメリットも期待できるようになります。
従業員の健康意識向上・生産性アップ
健康経営優良法人の認定取得は、従業員一人ひとりの健康意識の向上にも直結します。企業が明確な健康施策を実施することによって、従業員自身も自らの健康管理の重要性を認識するようになります。例えば、健康診断や健康セミナー、運動推進イベントの実施などを通じて、従業員が健康に関する知識を深め、自発的に健康改善行動をとるよう促すことができます。
また、健康施策がしっかりと実施されることで、メンタルヘルス不調や生活習慣病などの予防につながります。その結果、病気やストレスによる欠勤・休職が減少し、従業員の心身が健康な状態を維持することで、生産性やモチベーションの向上が図られます。
実際、健康経営に取り組む企業では、従業員の健康改善とともに、職場の活力が向上し、組織全体の業務効率が改善されるケースが多く見られます。これは企業全体としての生産性向上につながり、経営的にも大きなメリットとなります。
採用力・人材定着率アップにつながる理由
健康経営優良法人の認定を取得することで、企業は人材採用・定着面での競争力が高まります。その理由を具体的に整理すると以下の通りです。
採用時の企業アピール力向上
就職活動を行う求職者は、働きやすさや健康への配慮を重視する傾向が強まっています。健康経営優良法人の認定を取得していることで、求職者に対して明確な健康経営への取り組みをアピールでき、他社との差別化が可能になります。
従業員の満足度向上による離職率低下
健康経営を推進する企業は、健康に配慮した働きやすい職場環境を整備しています。こうした環境により、従業員の働きがいが高まり、離職を防ぎ、優秀な人材が定着する傾向が強まります。
従業員紹介制度の活性化
従業員が自社の働きやすさを実感することで、従業員紹介制度(リファラル採用)が活発になります。認定取得により健康施策への取り組みが認知され、従業員自身が知人・友人を安心して紹介できる企業となります。
企業の社会的評価向上による人材確保の容易化
社会的な評価が高まることで、人材市場において信頼できる企業という評判が広がります。その結果、自発的に応募してくる優秀な人材が増加します。
このように、健康経営優良法人の認定取得は、企業ブランドや従業員の健康意識向上にとどまらず、採用力や人材定着率を向上させるための強力なツールとなります。
健康経営優良法人認定の具体的な申請方法と手順
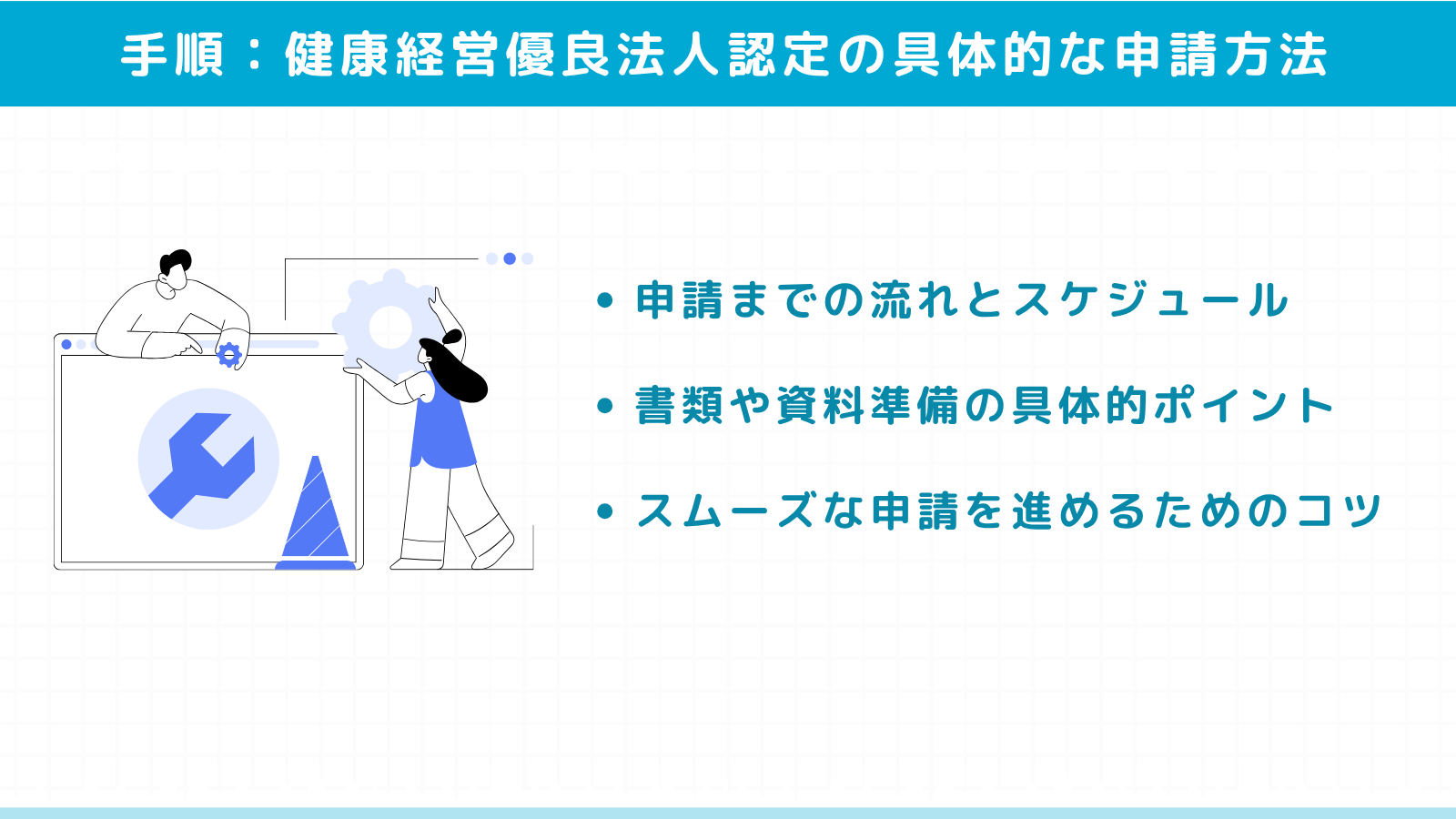
申請までの流れとスケジュール
健康経営優良法人の認定取得を目指す場合、まず制度の概要を理解し、自社が目指すべき方向性を明確にする必要があります。一般的な申請スケジュールとしては、次のような流れとなります。
【申請スケジュール例】
4月~6月(計画策定・情報収集)
申請に向けて企業内で健康経営推進プロジェクトチームを発足させ、現状の課題や具体的な施策を計画します。認定基準や評価項目の情報収集を行い、自社が取り組むべき施策の優先順位を決定します。
7月~9月(健康施策実施・実績収集)
計画した健康経営施策を実際に実施します。健康診断、健康イベント、メンタルヘルスケアなど、各種施策を行い、効果測定や従業員のアンケート結果などを収集します。
10月~11月(申請書類の作成)
認定基準に沿った申請書類の作成を進めます。各種実績資料や証明書類を整理し、評価基準を満たしているかを再確認します。
12月(申請書提出)
申請受付期間内に、健康経営優良法人認定事務局(日本健康会議)へ書類を提出します。提出方法は、電子申請もしくは書類送付のいずれかが指定されますので、申請要項をよく確認しましょう。
翌年2月~3月(認定結果発表)
認定の審査結果が発表されます。認定を受けた場合は、公式ウェブサイトなどで公表されます。
このスケジュールを念頭に置き、余裕をもって計画的に取り組むことが成功へのポイントです。
必要な書類や資料準備の具体的ポイント
健康経営優良法人認定の申請には、以下のような書類や資料の準備が必要です。
まず、制度が求める「経営理念に基づく健康経営への取り組み」を明確に記載した企業方針書が必要です。これは単に書面上の方針であるだけでなく、全社的な取り組みを示す重要な書類となります。
また、以下のような資料も準備が必要です。
- 健康診断受診率や健康指導実施率を証明する書類
- 社内健康セミナー・研修実施報告書
- メンタルヘルス対策(ストレスチェック実施記録)
- 労働安全衛生委員会などでの活動実績報告
- 職場環境改善活動の記録
- 健康づくりに関連する社内規定や福利厚生制度の書類
- 健康経営推進に関する従業員アンケート調査結果
これらは必ず保管し、後々の認定審査に備えておくことが重要です。特に従業員の健康診断受診率や、ストレスチェックの実施率など定量的なデータは評価項目として重視されるため、しっかりと準備しましょう。
スムーズな申請を進めるためのコツ
健康経営優良法人の認定申請をスムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえることが効果的です。
早期のプロジェクトチーム発足と担当者の明確化
・専任担当者を設け、社内体制を整えることが重要です。
経営層・管理職の理解と協力を得ること
・トップダウンでの推進を行うことで、全社的な取り組みがスムーズに進みます。
評価基準を事前にしっかりと理解すること
・公式資料や認定基準を詳細に確認し、不備のない申請書類を準備することが重要です。
実績資料を定期的に整理・収集する習慣をつける
・認定審査時に慌てないためにも、日頃から実績記録を取る習慣をつけましょう。
専門家・コンサルタントの活用を検討する
・初めての申請では専門的知識が不足しがちです。専門家の活用により、迅速かつ的確な申請が可能になります。
これらのポイントを念頭に置くことで、認定申請プロセスを円滑に進めることが可能となります。
認定審査の基準と評価ポイントを解説
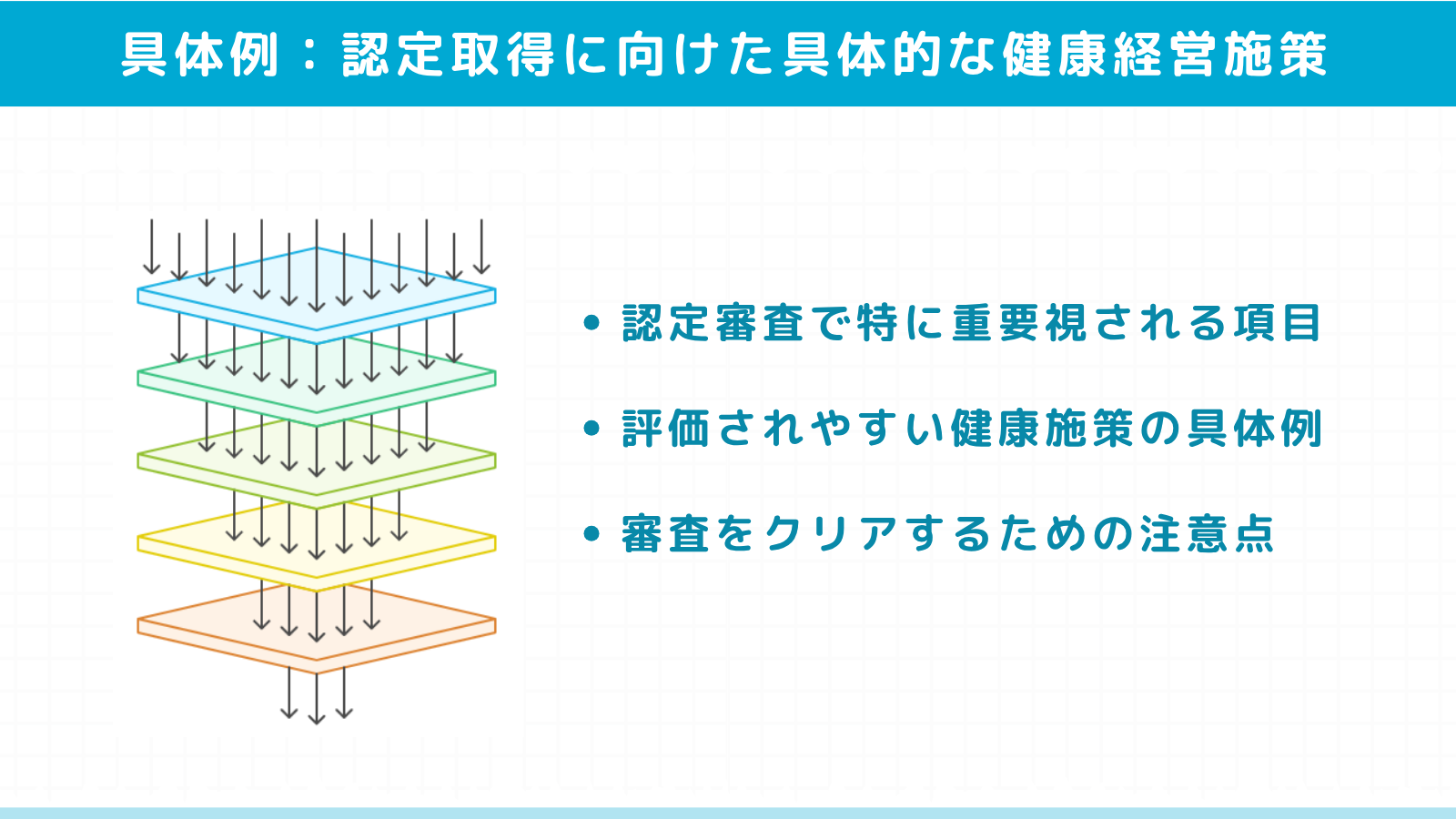
認定審査で特に重要視される項目とは?
健康経営優良法人の認定審査では、企業が従業員の健康を経営戦略として位置付け、組織的に取り組んでいるかどうかが厳密に評価されます。特に重要視されるのは以下のような項目です。
まず、「経営理念・経営方針との関連性」が最も重要です。経営層が健康経営の重要性を理解し、明確に示しているかが評価されます。次に、実際の健康施策が計画的に実施され、PDCAサイクルにより継続的に改善されていることも求められます。
さらに、具体的な数値指標として「健康診断受診率」「ストレスチェックの実施率とフォローアップ状況」「長時間労働の是正」「生活習慣病予防に関する施策」などが審査の中心となります。
加えて、施策の成果として「従業員の健康状態の改善」「生産性の向上」「離職率の低下」など、定量的・定性的な成果が評価対象となります。これらの指標を明確に示し、実績としてアピールできることが認定取得の大きなポイントとなります。
評価されやすい健康施策の具体例
健康経営優良法人の認定を受けるために、以下のような施策が特に評価されやすい傾向にあります。
健康診断受診率の向上と健康指導の徹底
- 健康診断受診率100%を目指す取り組み
- 健診結果に基づく具体的なフォローアップ施策
メンタルヘルス対策の充実
- ストレスチェックの実施と結果に基づく適切な対応
- 心理カウンセラーの配置やメンタル相談窓口の設置
生活習慣病予防対策
- ウォーキングイベントや健康セミナーなどの定期開催
- 喫煙率低下を目指した禁煙支援プログラムの導入
働き方改革・長時間労働削減施策
- 残業時間の抑制やフレックスタイム制度の導入
- 有給休暇取得促進のための啓発活動・制度整備
健康増進のための職場環境整備
- 健康的な食事を提供する社食の整備
- フィットネスルームの設置や運動推進キャンペーンの実施
これらの施策は、具体的な成果が数値として現れやすく、審査の際にも評価されやすいため、積極的な導入・推進を検討しましょう。
審査をクリアするための注意点と工夫
健康経営優良法人の認定審査をクリアするには、単に健康施策を実施しているだけでは不十分です。重要なのは、その施策が従業員一人ひとりに浸透し、効果が具体的な数値やデータとして示されていることです。
申請に際しては、特に以下の注意点を意識する必要があります。
まず、認定基準や評価項目をあらかじめしっかり理解しておくことが重要です。制度の基準は年度によって更新されることもあるため、最新の基準を随時確認しましょう。また、審査では施策の継続性や改善のプロセスが重視されるため、健康施策をPDCAサイクルで回し、改善点を明確にすることが求められます。
さらに、評価項目に関して客観的かつ具体的なデータや数値を示すこともポイントです。施策の実施だけではなく、その結果がどのような形で従業員の健康向上や生産性改善につながっているのかを明確に示す必要があります。
審査をクリアするためには、専門家の助言や過去の認定企業の成功事例を参考に、しっかりとした準備を行いましょう。
認定取得に向けた具体的な健康経営施策の取り組み例
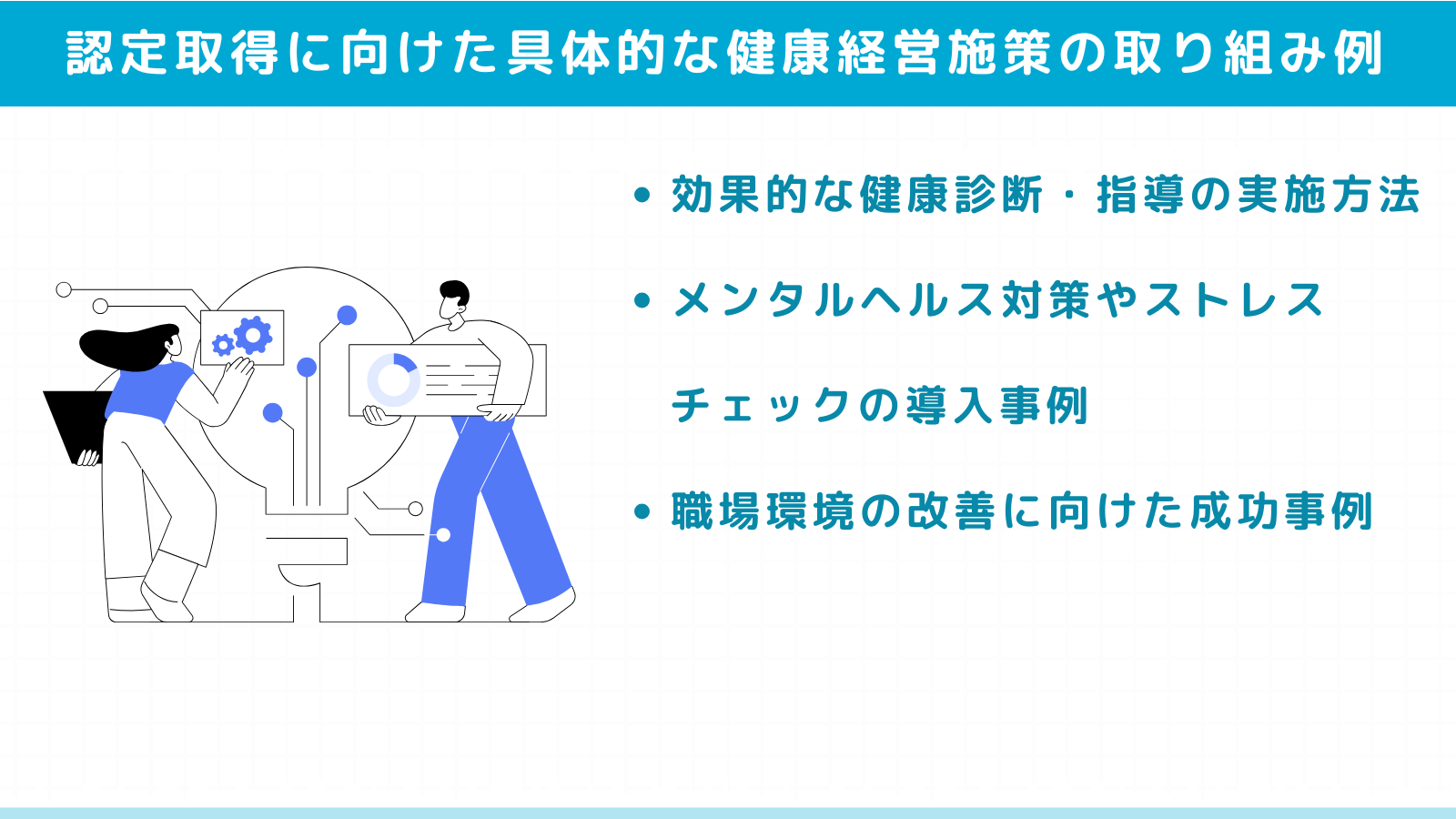
効果的な健康診断・健康指導の実施方法
健康経営の基礎となる施策として、健康診断の実施は非常に重要です。ただ単に実施するだけでなく、受診率を100%に近づけ、診断結果を活用した具体的な健康指導を徹底することが求められます。
受診率向上のためには、経営陣が率先して受診を推奨するメッセージを出す、診断を勤務時間内に受けられるよう制度を整える、受診しやすい医療機関との連携などが効果的です。また、診断後には保健師や産業医による個別面談を行い、健康リスクが高い従業員には定期的なフォローアップ指導を行うことが必要です。
これらを計画的に実施し、効果を数値で管理することにより、健康状態の改善が進み、生産性向上にもつながります。
メンタルヘルス対策やストレスチェックの導入事例
メンタルヘルス対策は健康経営の大きなポイントのひとつであり、従業員の精神的健康を守るために必須の取り組みです。以下の具体的な取り組み事例があります。
定期的なストレスチェックの実施
- 年に1回以上の全社員へのストレスチェック実施
- 高ストレス者への迅速な面談・ケア体制の確立
メンタルヘルス研修の実施
- 管理職向けメンタルヘルスケア研修の開催
- 全従業員向けのセルフケア研修や講習会の実施
相談窓口の設置と周知
- 社内に専門の相談窓口やオンライン相談サービスを設置
- 社外の専門家と連携したカウンセリングサービスの提供
職場環境改善の取り組み
- 長時間労働を抑制するための働き方改革の推進
- 有給休暇取得促進キャンペーンの実施
これらの取り組みにより、従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、職場環境改善に効果をもたらします。
職場環境の改善に向けた成功事例
職場環境の改善は従業員の心身の健康を維持するために不可欠です。実際に健康経営優良法人の認定を取得した企業では、さまざまな職場改善を行い、大きな成果を挙げています。
ある企業では、健康的な食生活を推進するために、社員食堂に栄養士を配置し、ヘルシーメニューを積極的に提供しました。その結果、社員の健康意識が高まり、生活習慣病のリスクが低下しました。
また別の企業では、職場に簡易的な運動スペースを設け、ストレッチや運動ができる環境を提供しています。休憩時間に運動を取り入れやすくすることで、腰痛や肩こりなどの身体的不調が軽減され、社員の集中力や生産性向上につながりました。
このように、職場環境の改善を具体的かつ継続的に実施することで、健康経営優良法人認定への近道となります。
認定後にさらに活用するためのポイント
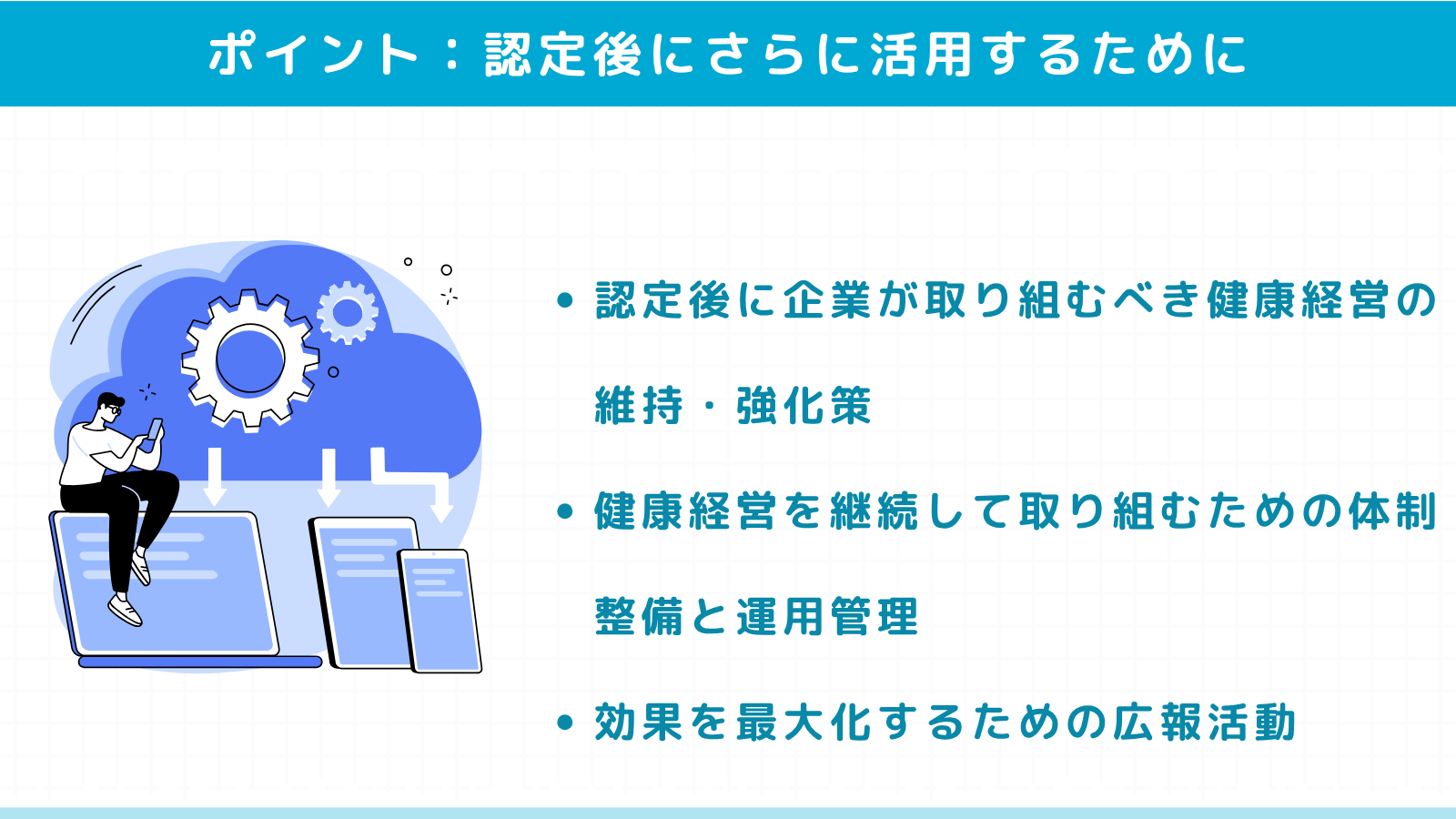
認定後に企業が取り組むべき健康経営の維持・強化策
健康経営優良法人認定はゴールではなく、あくまでも健康経営推進のスタートラインです。認定後にさらに企業が意識すべきポイントは、「継続性」と「改善・強化」です。
認定取得後は、健康経営の取り組みをPDCAサイクルで回し、継続的に見直しを行う必要があります。特に、従業員の健康状態やストレスチェックの結果、健康診断のデータなどを定期的に分析し、健康課題を明確化します。その課題に対して具体的な改善策を講じることで、健康経営の質を高め続けることができます。
また、健康経営を経営計画に組み込み、経営陣自らがコミットメントを示し続けることが重要です。トップの継続的な発信により、健康経営が社内文化として浸透し、従業員一人ひとりが健康維持・改善に積極的に取り組むようになります。
健康経営を継続して取り組むための体制整備と運用管理
健康経営を長期的に定着させるためには、社内の運用体制や仕組みづくりが不可欠です。具体的な体制整備のポイントは以下の通りです。
健康経営推進担当者の設置
- 専任または兼任で健康経営推進を担う責任者を明確化
- 定期的な推進チーム会議の開催と課題共有
経営陣・管理職の役割明確化
- 健康経営の重要性を理解するための研修を定期的に実施
- 管理職が部下の健康状態を把握できる仕組みを構築
評価・インセンティブ制度の整備
- 健康経営に積極的な部署・従業員を表彰する制度を設置
- 従業員が参加しやすい健康イベントや企画の継続開催
定期的なコミュニケーションの場の確保
- 従業員が健康に関する意見を気軽に出せる意見交換会やアンケートの実施
- 社内報やイントラネットを通じた健康情報の発信
このような体制整備を継続的に行うことで、健康経営が一時的な取り組みではなく、企業文化として根付いていきます。
認定取得後の効果を最大化するための広報活動
健康経営優良法人認定を取得したら、その効果を最大限活用するための広報活動が重要になります。まずは、自社のウェブサイトやSNS、採用パンフレットなどで認定取得を積極的に発信しましょう。これにより、外部への企業イメージの向上が期待できます。
また、取引先や顧客へのアピールとして、認定ロゴを名刺やパンフレットに記載することも効果的です。認定ロゴの使用により、自社の健康経営への取り組みを広く認知させることが可能となります。
さらに、地域や業界団体のセミナー・イベントなどでの事例紹介や講演を積極的に行うことで、認知度や信頼性をさらに高めることができます。こうした広報活動を戦略的に行うことで、認定取得の効果を最大限に活かすことが可能となります。
健康経営優良法人認定取得の成功事例から学ぶ
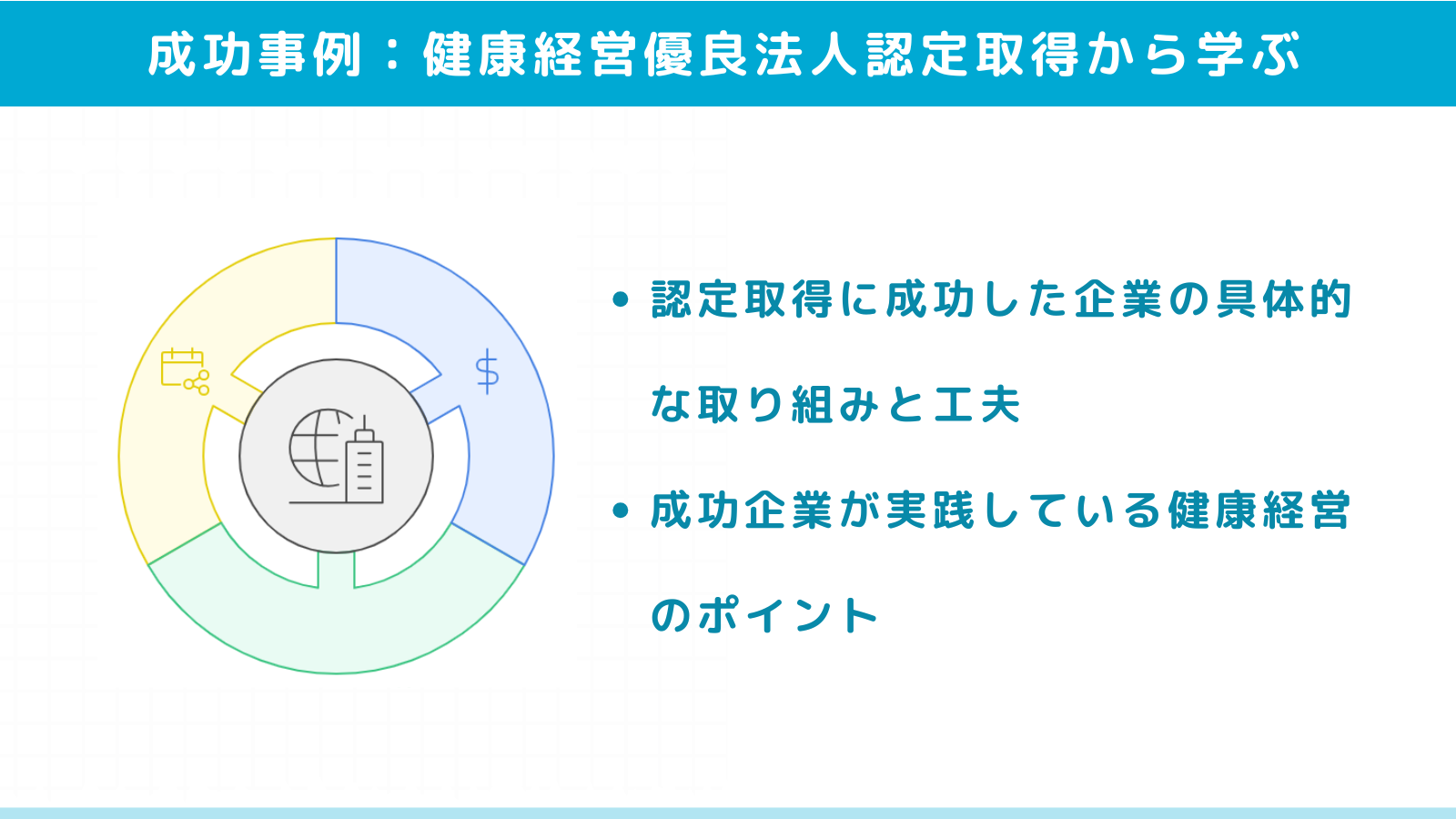
認定取得に成功した企業の具体的な取り組みと工夫
健康経営優良法人の認定を取得し、経営成果につなげている企業は、従業員の健康を単なる福利厚生ではなく、経営課題として明確に位置づけています。例えば、認定取得に成功したある企業では、経営トップ自らが率先して健康経営を推進し、社内の意識改革を行いました。
この企業は、まず従業員一人ひとりが自分自身の健康課題を正確に把握できるように、定期的な健康診断結果の分析とフィードバックを行い、その結果を元に個別具体的な健康指導を実施しました。また、健康課題に関する社内ワークショップや講演会を開催することで、従業員の健康意識を継続的に向上させています。
さらに、健康施策の一環として、運動習慣の定着化を目的とした健康ウォーキングイベントや、食生活改善を促すための社内食堂でのヘルシーメニュー導入など、具体的で実践的な施策を導入しました。その結果、従業員の健康状態改善だけでなく、生産性の向上や離職率の低下といった具体的な経営成果にもつながっています。
成功企業が実践している健康経営のポイント
健康経営優良法人認定の取得に成功している企業には、共通する成功のポイントがあります。以下にその代表的なポイントを挙げます。
トップの明確なコミットメント
- 経営トップが健康経営の重要性を社内外に明確に示し続けている
- 定期的なメッセージ発信や、健康経営方針の周知を徹底している
従業員参加型の施策展開
- 健康経営の施策をトップダウンだけでなく、従業員が自主的に参加できる形で展開している
- 健康改善のための意見や提案を取り入れる仕組みを構築している
継続的なPDCAサイクルの実施
- 健康経営の取り組み成果を定期的に評価し、改善点を見出している
- 継続的な見直しと改善を繰り返す体制を整えている
健康管理データの見える化と活用
- 健康診断やストレスチェック結果をデータ化し、従業員個人と会社全体の課題を明確化している
- 課題に対して具体的な改善策を導入し、定期的に効果測定を実施している
こうした具体的な取り組みを実践することで、健康経営を着実に根付かせ、認定取得後の経営成果にもつなげています。
事例から学べる認定取得・運用のヒント
健康経営優良法人の認定取得・運用で成功している企業の事例から学べる重要なヒントは、「経営トップのコミットメント」「従業員への浸透」「具体的で継続可能な施策展開」の3点です。
まず、健康経営の重要性を経営トップ自らが認識し、それを明確な方針として社内外に示すことが大切です。トップが示す明確な方向性により、社内の健康意識が高まり、従業員の自主的な健康管理を促すことができます。
また、従業員への浸透を図るためには、健康経営の施策を一方的に提供するのではなく、従業員が主体的に関わりやすいような企画・運営を工夫することがポイントです。例えば、運動会や健康イベントの開催、健康改善アイデア募集などを通じて、従業員が自ら積極的に参加できる環境づくりを行いましょう。
さらに、施策展開は一時的なイベントではなく、長期的に継続可能なものである必要があります。定期的な評価と見直しを繰り返しながら、徐々に施策をブラッシュアップしていくことが成功の秘訣です。こうした継続的な取り組みが、認定取得後も安定した健康経営の推進を可能にします。
健康経営優良法人認定取得時のよくある失敗と対策
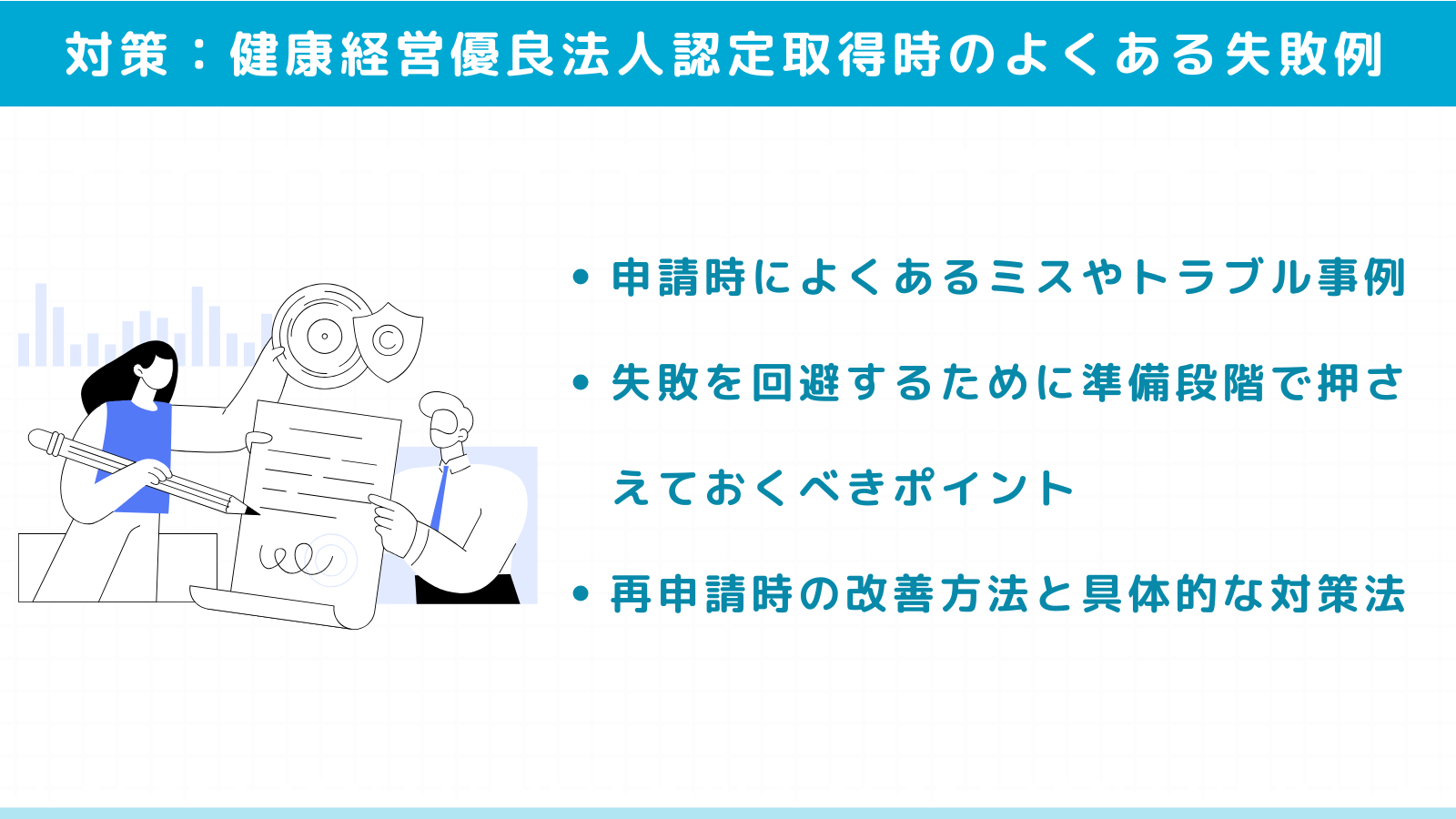
申請時によくあるミスやトラブル事例
健康経営優良法人認定を目指す企業にとって、申請時のミスやトラブルは決して珍しくありません。例えば、よくある失敗として、必要書類やデータの不備が挙げられます。健康経営施策を実施していても、それを証明する具体的な資料が不足していたり、記載方法が不明確であったりすると、審査時に評価されず認定取得が難しくなるケースがあります。
また、申請期限ギリギリになって慌てて書類作成を始めた結果、提出書類が不十分であったり、提出漏れが生じたりする事例も散見されます。さらに、社内での健康経営の取り組みが十分に浸透していない状態で申請を行った場合、実態との乖離が指摘され、認定が難しくなるケースも少なくありません。
このように、認定申請を行うにあたり、準備不足や社内体制の未整備が原因で起こるトラブルが非常に多いのです。
失敗を回避するために準備段階で押さえておくべきポイント
認定取得時のよくある失敗を避けるためには、以下のポイントを事前に押さえて準備を進めることが重要です。
認定基準と申請書類を正確に理解する
- 事前に経済産業省や日本健康会議の認定基準を詳細に確認する
- 必要な資料やエビデンスの収集を早い段階から進める
スケジュール管理を徹底する
- 認定申請期限から逆算して、余裕を持ったスケジュールを設定する
- 書類作成や資料収集の担当者を明確にし、進捗を定期的に確認する
社内への浸透と認識共有を図る
- 経営トップが健康経営の方針を明確に打ち出し、社内周知を徹底する
- 従業員が健康経営の意義を理解し、施策への参加意欲を高める取り組みを実施する
社内の実態との整合性を確認する
- 提出書類の内容と実際の社内取り組みに乖離がないか確認する
- 提出前に内部でのチェックや第三者によるレビューを実施する
こうした準備を進めることで、申請時に起こりがちなトラブルを未然に防ぎ、スムーズな認定取得を実現することができます。
再申請時の改善方法と具体的な対策法
一度健康経営優良法人の認定取得に失敗した場合でも、適切な改善を施すことで再申請時には取得が可能になります。再申請に向けてまず行うべきことは、前回の審査で指摘された事項や評価が低かったポイントを具体的に分析し、明確に把握することです。
次に、把握した課題を改善するための具体的なアクションプランを策定します。例えば、評価が低かった健康診断受診率やストレスチェック実施率を高めるために、より積極的な社内啓発活動や個別フォローを実施するなど、具体的な改善策を立て、実行する必要があります。
また、再申請に向けては、認定基準を再度詳しく見直し、必要とされるエビデンスを十分に揃えて準備を進めましょう。書類作成に関しても、専門的な視点から第三者による確認やアドバイスを受けることで、より精度の高い申請書類を作成できます。
再申請時は前回の失敗経験を活かし、早め早めの準備と明確な改善を意識することで、より確実に認定取得を達成できます。
認定取得をサポートする専門家活用のメリット
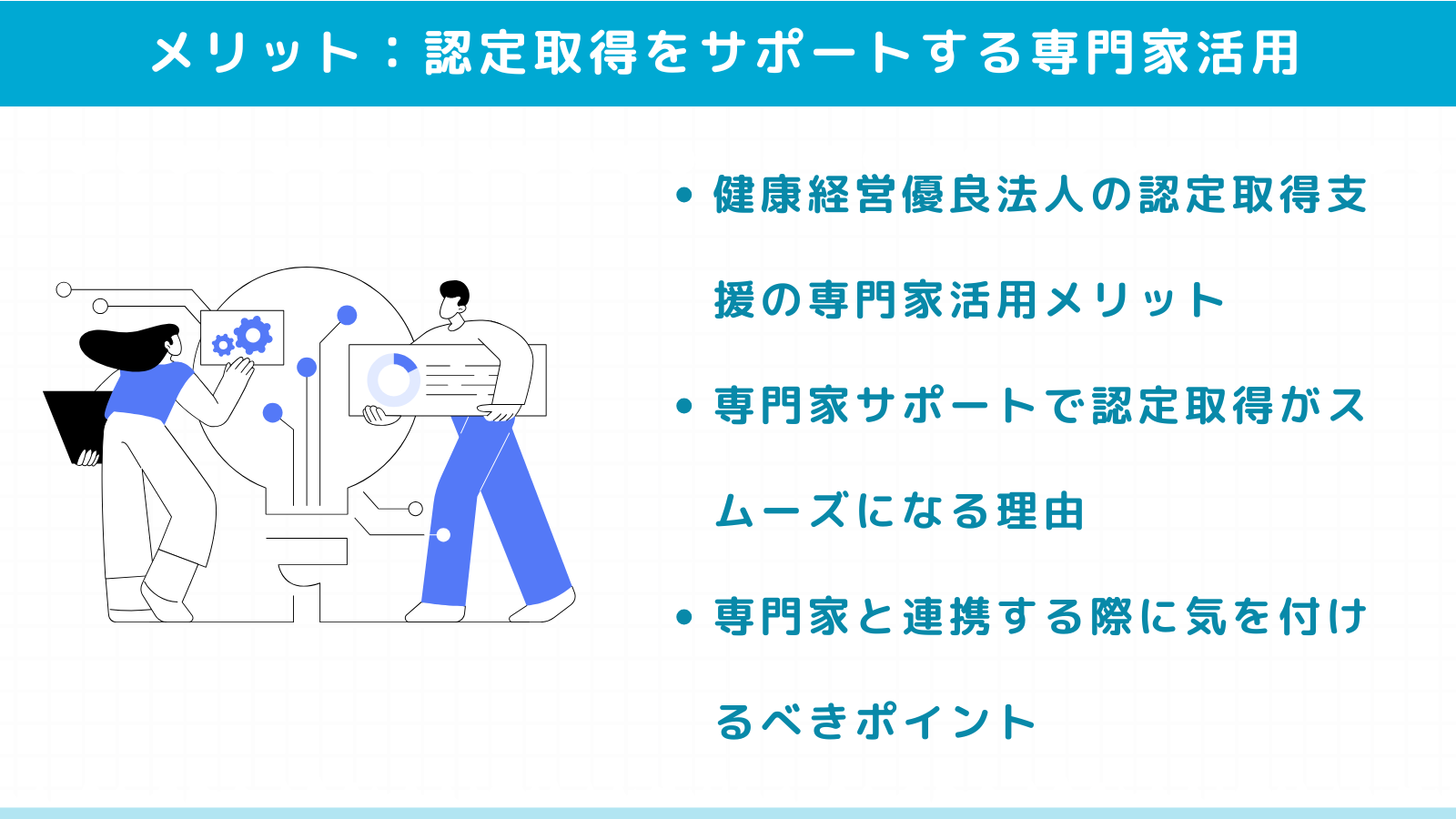
健康経営優良法人の認定取得支援の専門家活用メリット
健康経営優良法人の認定取得は、企業が独自に取り組むことも可能ですが、専門的なノウハウや経験を持つ外部の専門家のサポートを活用することで、より効率的かつ確実に認定取得を進めることができます。
専門家はこれまでの豊富な認定取得支援の実績をもとに、認定基準の最新動向や審査傾向を熟知しています。そのため、申請準備の段階からポイントを絞った的確なアドバイスを受けられます。企業単独では見落としがちな申請のポイントや、審査時に評価が高まる健康経営施策の実施方法についても具体的かつ実践的な助言を得られるのが最大のメリットです。
また、専門家が関与することで、社内担当者の負担を大幅に軽減できます。認定取得に必要な膨大な資料準備や書類作成においても、専門家の指導を受けながら進められるため、効率よく作業を進めることが可能です。
専門家サポートで認定取得がスムーズになる理由
専門家のサポートを受けることで認定取得がスムーズになる具体的な理由は以下の通りです。
認定基準や審査ポイントを熟知しているため、的確な準備が可能
- 最新の審査傾向を踏まえたアドバイスが得られる
- 無駄な作業や資料作成を省略できる
客観的かつ第三者の視点での改善点指摘
- 社内で見落としがちな問題点や課題を明確化
- 認定基準を確実にクリアするための改善提案を受けられる
企業側の負担軽減と効率的な進行が可能
- 資料作成・申請業務における手間を削減
- 社内スタッフが本来の業務に集中できる
認定取得後の運用・維持に関してもサポートを受けられる
- 認定維持のための取り組みを継続的に支援
- 長期的な健康経営の実践をバックアップ
こうした理由から、専門家の活用がスムーズな認定取得に大きく貢献します。
専門家と連携する際に気を付けるべきポイント
専門家と連携し健康経営優良法人認定を目指す場合には、いくつかの注意点があります。まず、専門家選定の段階で、自社の規模や業態に合った専門家を選ぶことが重要です。例えば、規模や業種に特化した支援実績を持つ専門家を選ぶことで、より具体的かつ有効なサポートを受けることができます。
次に、専門家との役割分担を明確にし、コミュニケーションを円滑に進める必要があります。自社の状況や実施可能な施策を明確に専門家へ伝え、専門家からのアドバイスや支援内容を明確に理解し、取り組みを進めていきましょう。
また、専門家に任せきりにするのではなく、企業側でも主体的に健康経営施策を推進する姿勢が求められます。専門家はあくまで支援・指導を行う立場であり、認定取得の主体は企業自身です。積極的に取り組み、課題や問題点を早めに相談・共有することで、認定取得を確実なものにすることができます。