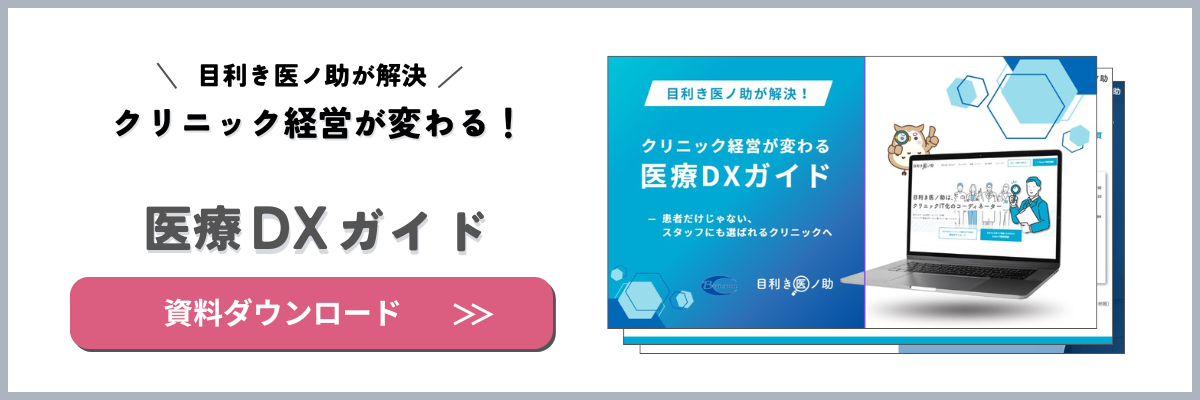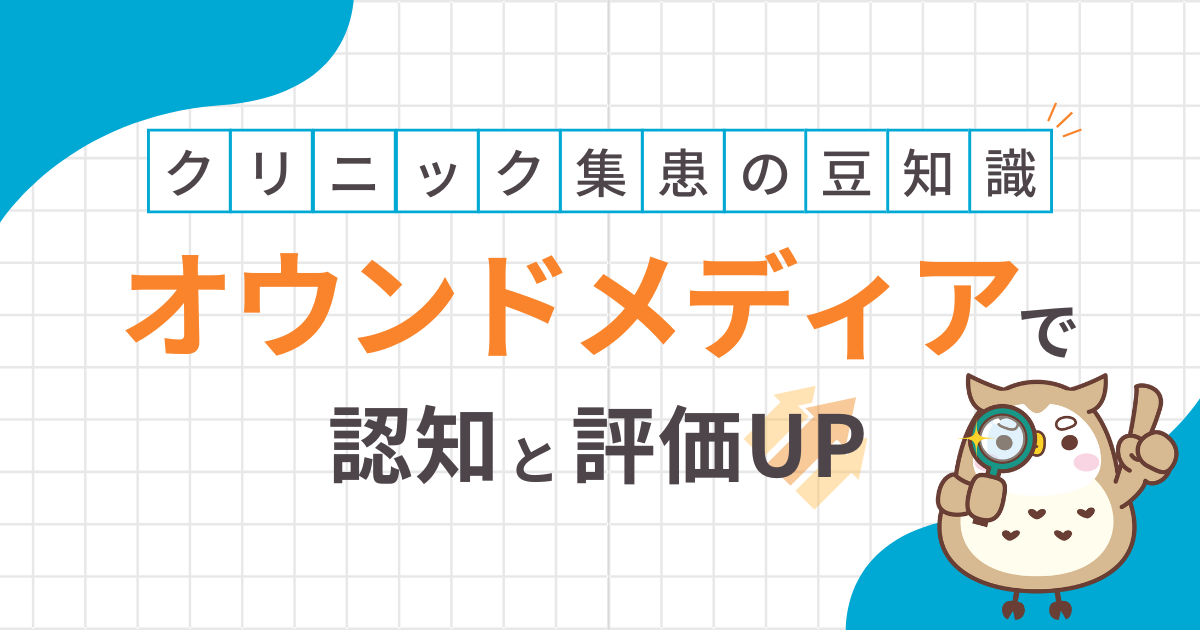
2026.01.05
オウンドメディアでクリニックの認知と評価をアップ【目利き医ノ助】
クリニックがオウンドメディアを活用すべき理由
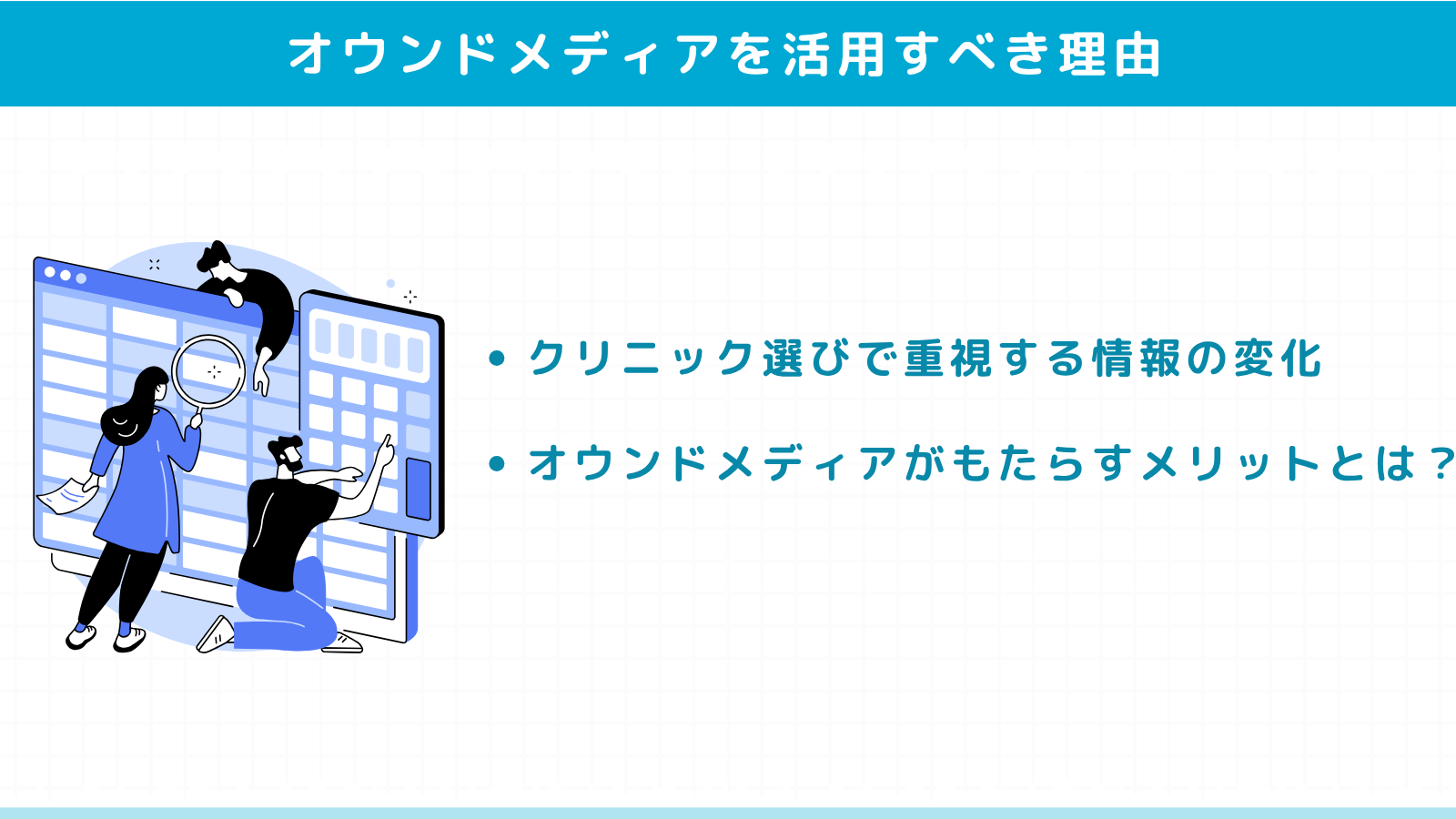
患者がクリニック選びで重視する情報の変化
近年、患者さんがクリニックを選ぶ基準は大きく変化しています。かつては立地条件や知人からの紹介が主な選択基準でしたが、現在ではインターネット上での情報収集が主流となっています。特にスマートフォンの普及により、患者さんは事前にウェブサイトやSNSを通じて医療機関の評判や情報を確認することが一般的となりました。患者さんが特に重視している情報は、『信頼性』と『専門性』です。ただクリニックの基本情報を提示するだけでは不十分であり、そのクリニックがどれほど専門的な知識を持っているか、患者の立場に寄り添った丁寧な情報提供をしているかが大切になっています。こうした背景から、クリニックが自ら情報を発信し、自院の専門性や診療に対する姿勢を患者さんに直接伝えることができる『オウンドメディア』が注目されるようになりました。オウンドメディアでクリニックの集患力アップを図ることは、患者さんが求める質の高い情報を継続的に提供し、自院の信頼性や専門性を伝えるための重要な手段となっています。これにより患者さんに選ばれやすくなり、競合クリニックとの差別化にも効果的に役立つのです。
オウンドメディアがクリニックにもたらすメリットとは?
クリニックがオウンドメディアを活用することで、以下のような具体的なメリットを得ることができます。
患者さんに直接信頼感を伝えられる
・診療内容や医師の専門性を詳細に伝えることで、患者さんが安心して来院できる環境を作れる。
SEO効果で地域での認知度を向上させられる
・地域の患者さんがよく検索するキーワードに関連したコンテンツを発信し、Google検索での露出を増やすことができる。
競合クリニックとの差別化が明確になる
・自院が得意とする専門分野や、患者さんへの対応姿勢を明確に打ち出すことで、他院との差別化を図れる。
継続的な情報発信でリピーターを増やせる
・定期的に患者さんにとって有益な情報を提供することで、患者さんがクリニックに対して親近感を持ちやすくなり、再来院を促進できる。
患者さんとのコミュニケーション強化
・コンテンツを通じて患者さんの悩みや疑問に答えることで、信頼関係を深め、口コミや紹介を自然に増やせる。
オウンドメディアの活用はクリニックにとって集患や信頼性向上、そして経営の安定化につながる非常に効果的な手法です。
オウンドメディアがクリニック集客に有効な3つの理由
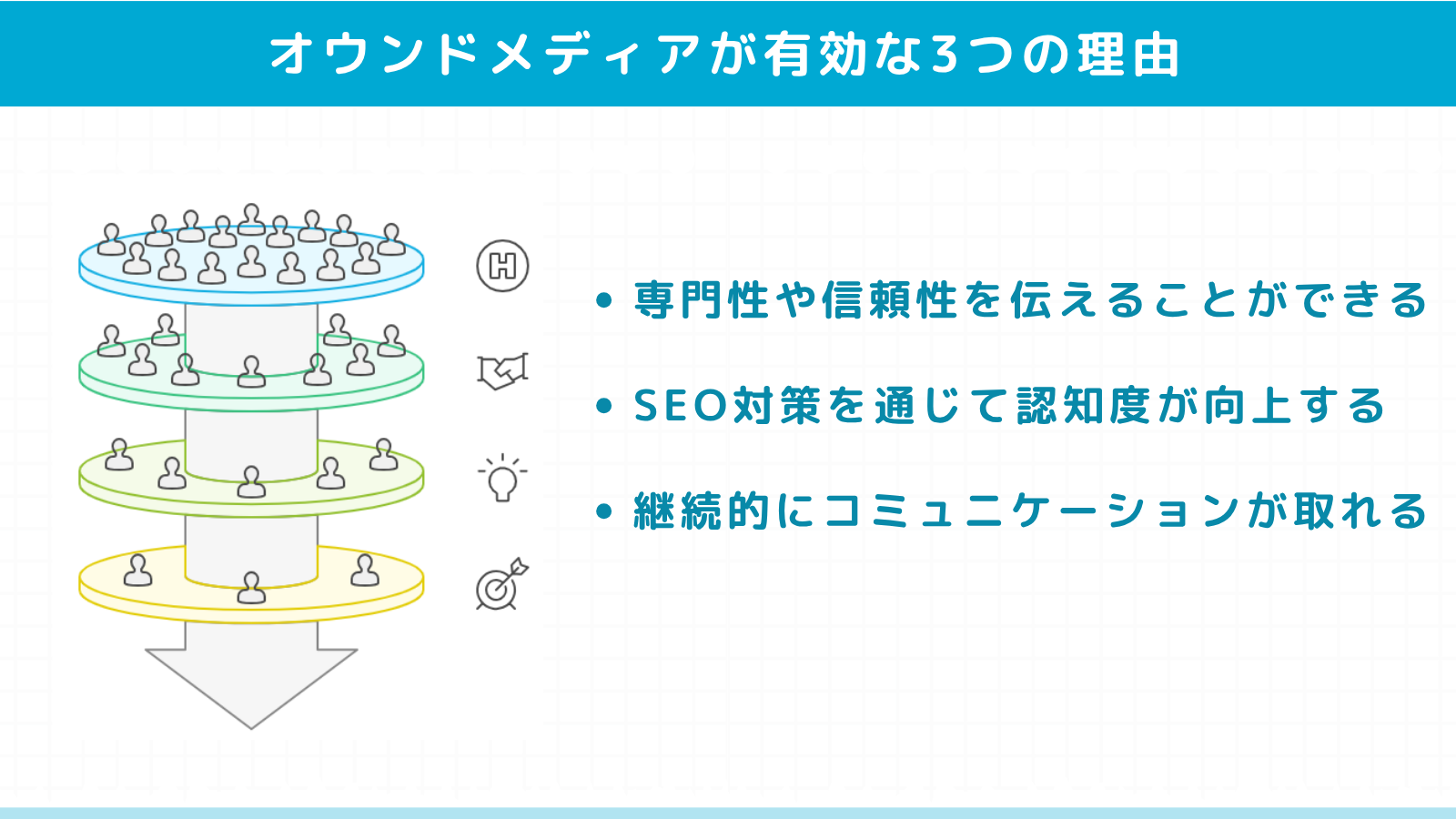
専門性や信頼性を患者に伝えることができる
オウンドメディアを活用する大きな利点の一つは、クリニックの専門性や信頼性を患者さんに直接伝えることができる点にあります。ホームページや診療案内だけでは伝えきれない専門的な知識や治療方針、診療理念を丁寧かつ具体的に表現できるのがオウンドメディアの強みです。
例えば、診療科ごとに症状や治療法について詳しく解説する記事を継続的に配信することで、患者さんがそのクリニックに対して持つイメージは「専門性が高い」「信頼できる」と自然に形成されます。また、医師の資格や実績、過去の治療事例をオウンドメディア内で公開することで、客観的な根拠に基づいた信頼感を提供できます。
オウンドメディアを通じて患者さんに「このクリニックなら安心して診察を受けられる」と感じてもらうことができれば、初診のハードルが低くなり、新規患者の来院が促進されるでしょう。
SEO対策を通じて地域での認知度が向上する
クリニックがオウンドメディアで記事を発信するときに、SEO(検索エンジン最適化)を意識することで、地域での認知度が大きく向上します。その具体的な理由は以下の通りです。
地域特化型キーワードでの検索流入が増加
・「地域名+診療科目」など、患者さんが検索するキーワードに合わせた記事を発信することで、Google検索からのアクセスを増やすことができる。
検索結果の上位表示が実現可能になる
・専門的で質の高い情報を継続的に公開することでGoogleからの評価が高まり、地域内での検索順位を上げることが可能になる。
長期的な集患効果が見込める
・広告のように費用を継続的にかけずとも、SEO効果によって安定した集患効果が得られる。
ブランディングとの相乗効果
・SEO対策で上位表示されることで、患者さんからの信頼性が高まり、自然とクリニックのブランド力が向上する。
SEO対策を取り入れたコンテンツ運営により、クリニックの知名度や地域での評価が高まり、効率的かつ安定的な集患につながります。
継続的に患者とコミュニケーションが取れる
オウンドメディアを通じて継続的に情報発信を行うことにより、患者さんとのコミュニケーションを強化できます。クリニックが定期的に発信する健康情報や診療に関する話題は、患者さんが抱える日常的な悩みや疑問に直接応えることになります。
例えば、季節ごとの流行する疾患や予防策を紹介したり、慢性的な症状に対する家庭でのケア方法を丁寧に解説したりすることで、患者さんは継続的にクリニックの情報をチェックするようになります。こうした取り組みを続けることで、患者さんとクリニックとの間に自然な関係性が生まれ、クリニックへの親近感や信頼感が醸成されます。
さらに、オウンドメディアのコメント欄や問い合わせフォームなどを活用すれば、患者さんからの質問や要望を収集し、それに丁寧に応えていくことも可能です。これにより、患者さんはクリニックとの直接的な交流を感じやすくなり、より長期的で強固な関係構築につながっていくでしょう。
患者が読みたくなるオウンドメディアコンテンツの作り方
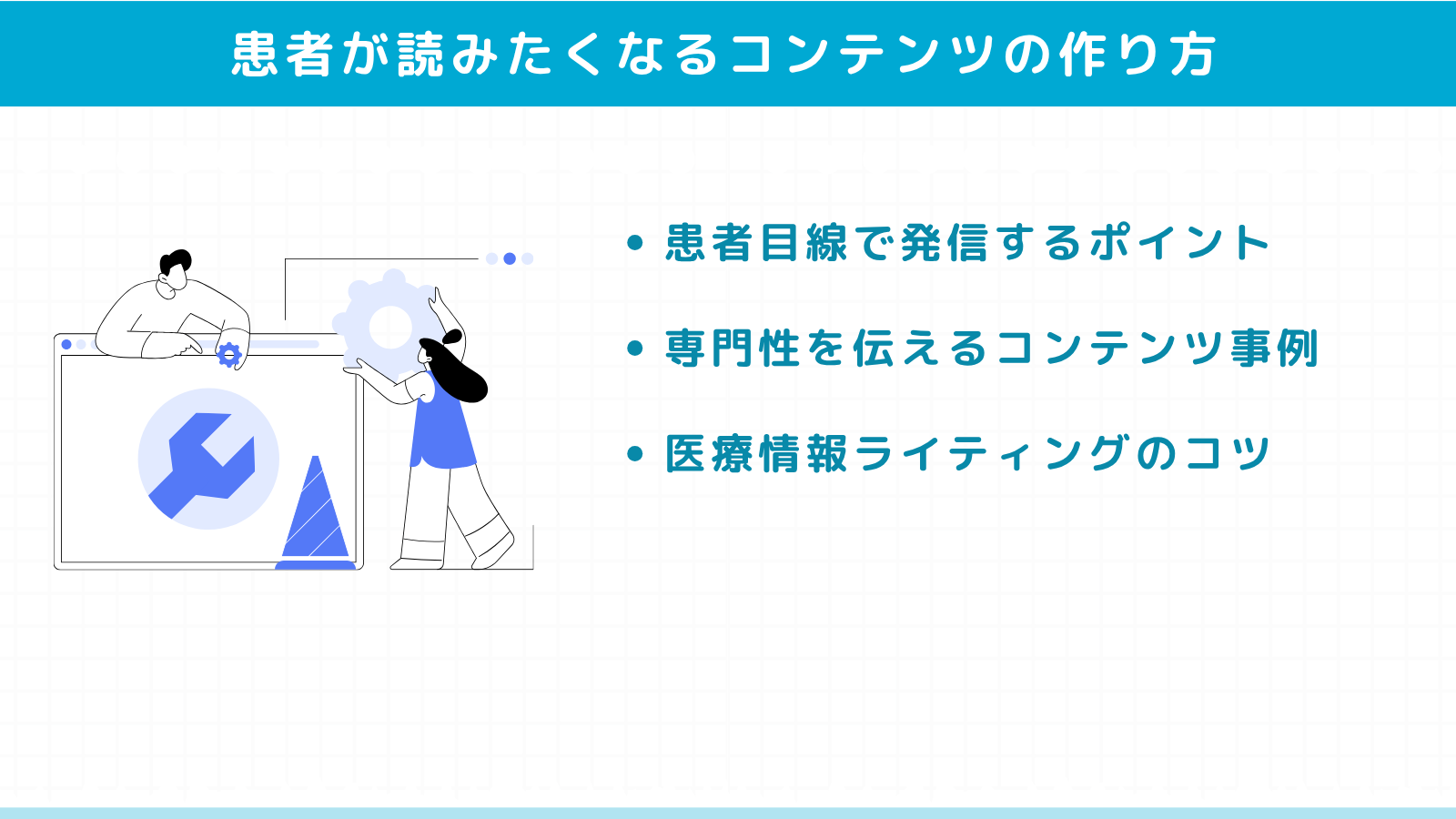
患者目線で役立つ情報を発信するポイント
オウンドメディアでコンテンツを作成する際に最も重要なことは、『患者目線』を常に意識することです。医療機関が発信する情報は、患者さんが日常的に抱えている悩みや不安を直接的に解消するものである必要があります。医師やスタッフの専門知識をただ羅列するのではなく、患者さんが「この情報を知りたかった」と感じるような具体的かつ実用的な内容であることが求められます。
例えば、「頭痛が起きた時の家庭でできる応急処置」や「花粉症の時期に取り入れたい生活習慣」など、患者さんの生活に密着した内容を具体的に取り上げることで、情報の有用性を高めることができます。また、患者さんの視点で理解しやすい言葉遣いや表現を選び、難解な専門用語を避けて情報を伝えることも大切です。
こうした患者目線を徹底することで、患者さんはそのクリニックのコンテンツを継続的に読み続け、自然とクリニックへの信頼感を高めることができます。
クリニックの専門性をわかりやすく伝えるコンテンツ事例
オウンドメディアを通じて専門性を患者さんに効果的に伝えるためには、以下のようなコンテンツの例が役立ちます。
医師が解説する疾患の詳しい情報
・特定の疾患について、症状や治療法、予防法などを患者目線で詳しく解説する記事。
患者さんからよく寄せられる質問への回答集
・患者さんが実際に診療の場でよく聞く質問を取りまとめ、分かりやすく丁寧に回答する記事。
最新の医療トピックや研究の紹介
・最新の医療ニュースや新しい治療法、医学的な発見などを患者向けに分かりやすく解説する記事。
自宅でできる健康管理やセルフケア方法
・自宅で簡単に実践できる健康管理のコツやセルフケアの方法を具体的に提案する記事。
これらのコンテンツにより、患者さんはクリニックの専門性を具体的に理解し、信頼感を深めやすくなります。
医療情報をわかりやすく解説するライティングのコツ
医療情報を患者さんにわかりやすく伝えるためには、専門的な内容を平易な言葉で表現する『ライティングスキル』が必要不可欠です。患者さんは専門用語や難しい医学的な表現に馴染みがないため、記事が難解であればすぐに離脱してしまいます。
医療情報をわかりやすく伝えるためには、以下のようなポイントを意識することが大切です。まず、難しい用語や専門的な言葉を使う場合は、必ず平易な言葉で補足説明を加えます。また、一文を短く区切り、箇条書きや図表なども積極的に使って視覚的に分かりやすく表現しましょう。
さらに、具体例や日常生活におけるシーンを積極的に取り入れることで、患者さんが記事を自分自身の状況に重ねやすくなり、内容への理解度が深まります。
こうしたライティングの工夫を継続的に行うことで、患者さんが読みやすく、理解しやすいコンテンツを提供できるようになり、オウンドメディアの継続的なファン化にもつながります。
オウンドメディア開設の基本手順とポイント
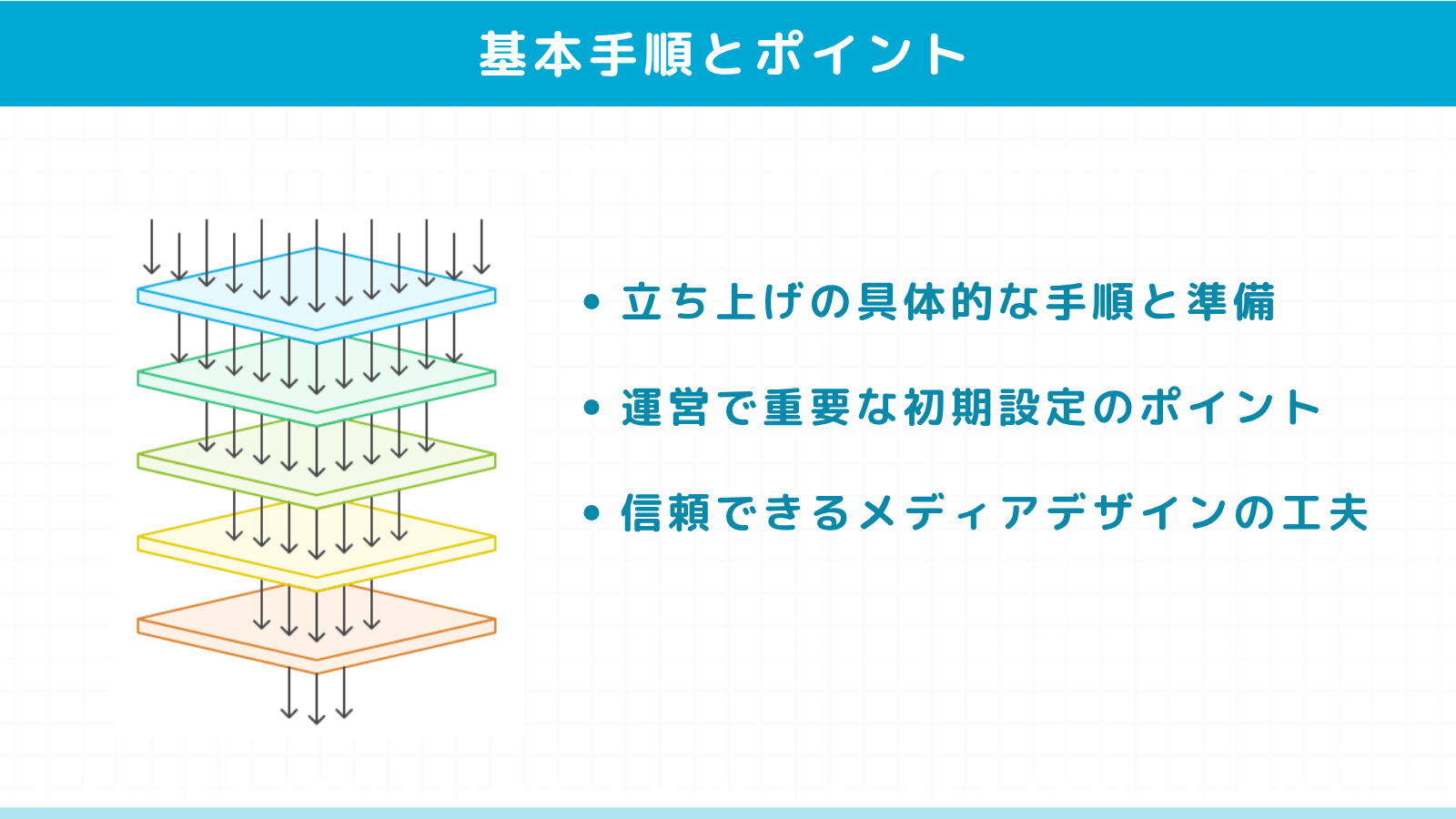
オウンドメディア立ち上げの具体的な手順と準備
クリニックがオウンドメディアを立ち上げるためには、手順と準備が必要です。
最初に行うべきことは、オウンドメディアを運営する目的やターゲットとなる患者さんの属性を明確に設定することです。目的が「新規患者の獲得」なのか、「既存患者とのコミュニケーション強化」なのかによって、発信するコンテンツや運営方針が大きく異なります。
次に、メディアを立ち上げるためのプラットフォーム選定を行います。自院のホームページ内にブログ形式で追加する方法や、WordPressを活用して独立したメディアサイトを構築する方法など、運営方法に応じて最適な方法を選びます。
また、コンテンツ作成のための体制整備も不可欠です。院内のスタッフだけで対応可能なのか、外部のライターを活用する必要があるのかを検討し、具体的な制作体制を整えましょう。記事の作成頻度や更新スケジュールをあらかじめ決めておくことも、運営開始後の円滑な運用につながります。
メディア運営で重要な初期設定のポイント
オウンドメディアの運営開始時には、以下のような初期設定を適切に行うことが重要です。
SEO対策の基本設定
・タイトルタグやメタディスクリプションなどをSEOの基本に沿って設定し、Googleなどの検索エンジンで適切に認識されるようにする。
ユーザー目線のカテゴリー設計
・記事が探しやすくなるよう、患者さん目線でカテゴリー分けを行い、情報を整理する。
サイトの使いやすさと見やすさ
・スマートフォンでも見やすいレスポンシブデザインを採用し、患者さんがストレスなく記事を閲覧できるようにする。
アクセス解析ツールの導入
・Google AnalyticsやSearch Consoleなどの解析ツールを導入し、記事のパフォーマンスやユーザー動向を把握できるようにする。
コンテンツ制作ルールの統一
・記事作成時の表記ルールや画像サイズなどを明確にし、コンテンツ品質に統一感を持たせる。
これらの初期設定を正しく行うことで、運営開始後のメディア運営が円滑かつ効果的になります。
患者が信頼できるメディアデザインの工夫
オウンドメディアは、ただ情報を発信するだけでなく、訪れた患者さんが信頼できるようなデザインを意識することも重要です。患者さんが「ここなら安心して情報を得られる」と感じられるサイトデザインを目指しましょう。
クリニックのメディアでは清潔感が非常に重要です。白や青系の色を基調としてシンプルで見やすいデザインにすることで、医療機関らしい誠実さと安心感を表現できます。また、院長やスタッフの顔写真や経歴を掲載することで、患者さんがクリニックに対する信頼感を感じやすくなります。
さらに、コンテンツの見出しや記事の冒頭部分に、記事内容が患者さんにどのようなメリットをもたらすのかを明確に示すことも効果的です。信頼性の高い情報源を示したり、医師監修マークを付けたりするなど、信頼感を視覚的に伝える工夫も欠かせません。
デザインの細かな工夫が、患者さんのオウンドメディアへの信頼感を高め、継続的な訪問を促すことにつながります。
SEOを意識したオウンドメディア運営方法
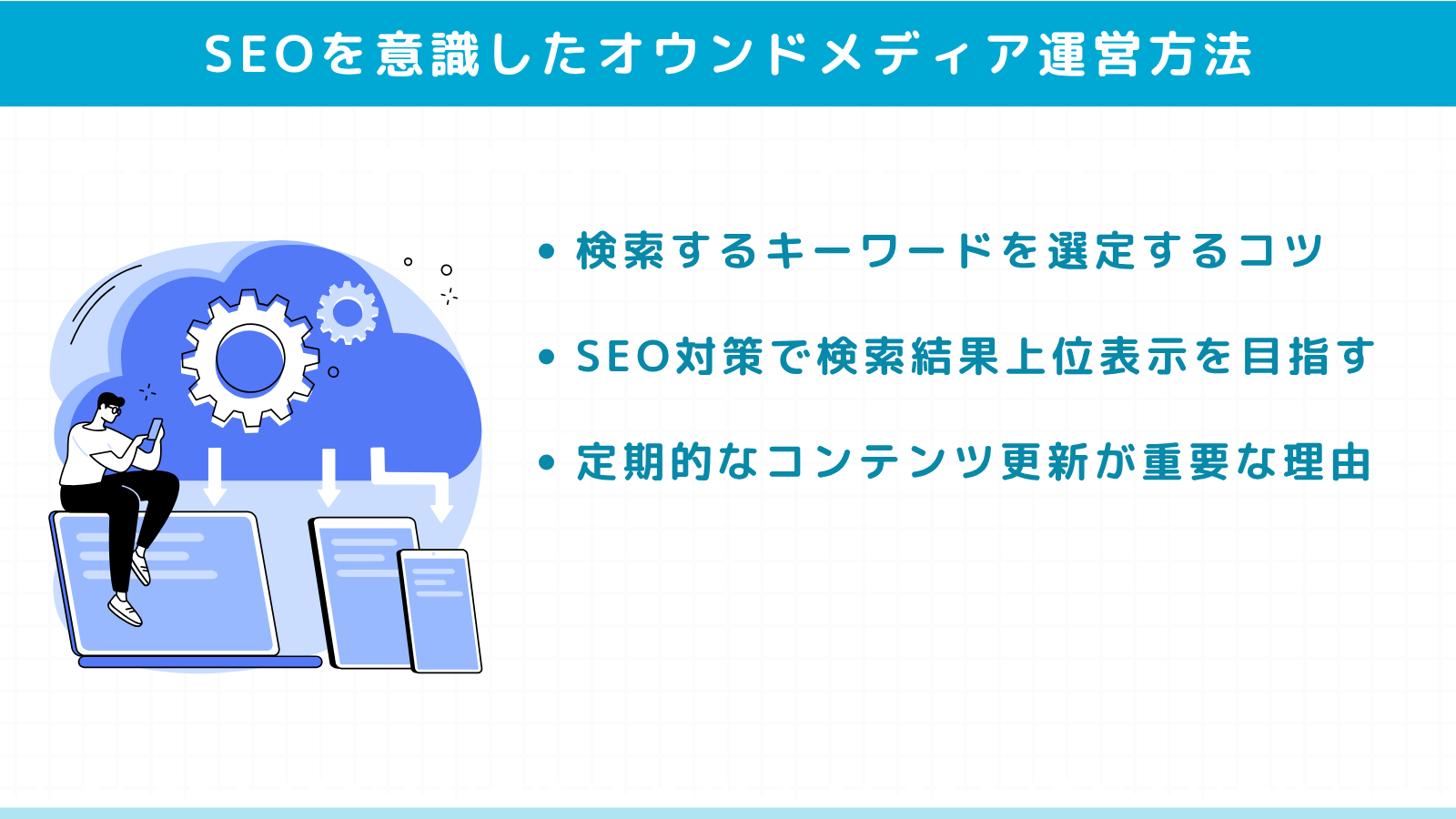
患者が検索するキーワードを選定するコツ
オウンドメディアで効果的に集患するためには、患者さんが実際にどのようなキーワードで検索しているかをしっかりと把握する必要があります。キーワード選定の際には、患者さんの視点に立って考えることが非常に重要です。
患者さんがよく検索するキーワードを選ぶためには、GoogleキーワードプランナーやGoogleサジェストなどのSEOツールを活用すると便利です。これらのツールを使って「地域名+診療科目」や「症状名+治療法」など、患者さんがよく使うであろう検索フレーズを特定します。
また、実際に患者さんから診療時によく質問される内容をピックアップし、それらのキーワードを記事に盛り込むことも有効です。具体的な症状や治療法についての質問、季節的な流行疾患に関するキーワードなど、患者さんが知りたいことをリアルに反映させることで、検索流入が増加します。
継続的にキーワードを見直し、実際のアクセス解析データをもとに記事の内容を改善していくことで、SEO効果を高めることができます。
効果的なSEO対策で検索結果上位表示を目指す
オウンドメディアを検索エンジンで上位表示させるためには、以下のSEO対策ポイントを継続的に実践することが重要です。
質の高いコンテンツ作成
・ユーザーの検索意図に沿った詳細かつ有益なコンテンツを作成し、Googleからの評価を高める。
キーワードを効果的に配置
・タイトルや見出し、本文に選定したキーワードを自然に配置し、検索エンジンに記事のテーマを明確に伝える。
内部リンクの最適化
・関連する記事同士を内部リンクで結び、サイト内で情報を網羅的に提供することでユーザー滞在時間を延ばす。
被リンクの獲得
・外部の信頼性の高いサイトからの被リンクを獲得し、SEO評価を高める。
ページの読み込み速度向上
・画像圧縮や不要なコード削減などによりページの読み込み速度を改善し、ユーザーのストレスを軽減する。
これらのSEO対策を地道に行うことで、オウンドメディアが検索エンジンの上位表示を達成しやすくなります。
定期的なコンテンツ更新が重要な理由
オウンドメディアを運営する上で、定期的なコンテンツ更新は欠かせない要素の一つです。検索エンジンであるGoogleは、情報が定期的に更新されているサイトを高く評価する傾向があります。新鮮で最新の情報を常に提供しているオウンドメディアは、検索結果で上位表示されやすくなります。
また、定期的に更新を行うことで、患者さんがオウンドメディアに何度も訪れる理由が生まれます。定期的な訪問者が増えることでサイトのアクセス数が安定し、SEO評価も向上します。
さらに、継続的に有益な情報を提供することで、クリニックに対する患者さんの信頼感や専門性の認識が深まります。一度訪れた患者さんが何度も戻ってくることにより、クリニックへの親近感や信頼感が強化され、集患効果を最大限に発揮できます。
SNSとオウンドメディアの効果的な連携
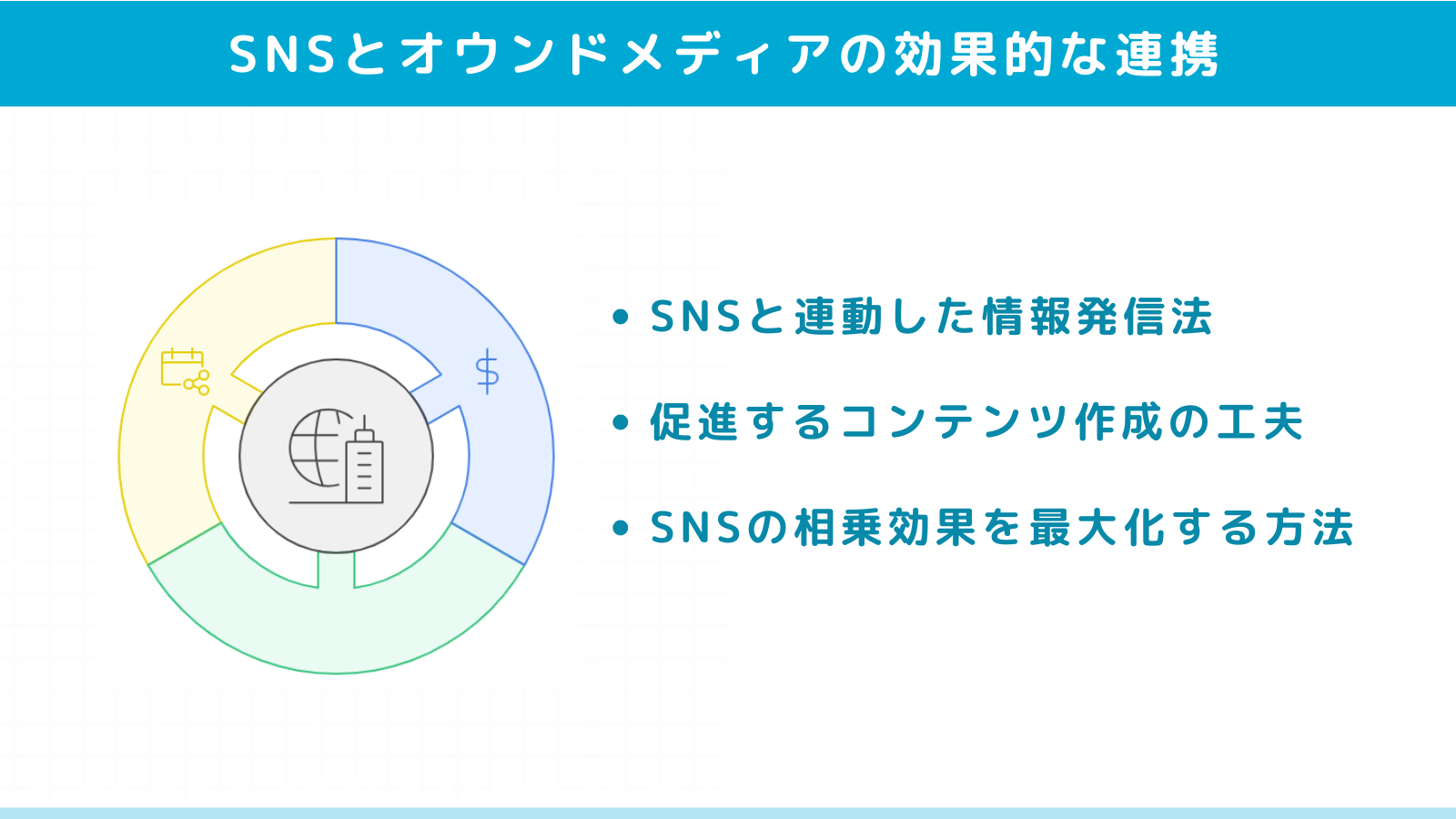
InstagramやFacebookと連動した情報発信法
オウンドメディア単独でも効果的ですが、InstagramやFacebookなどのSNSと組み合わせて運用することで、さらに集患効果や認知度を高めることができます。SNSをオウンドメディアと連携させることで、患者さんに対してより多面的で継続的な情報提供が可能になります。
SNSを活用した連携方法としては、オウンドメディアで記事を公開した際に、その記事の概要や魅力的なポイントをInstagramやFacebookで紹介し、詳細を読みたい患者さんをオウンドメディアに誘導することが基本です。また、SNSに投稿する際には、患者さんの興味を引くような魅力的な写真や短い動画を活用すると、視覚的に興味を惹きつけることができます。
こうした連動によって、SNSで初めてクリニックを知った患者さんをオウンドメディアへ誘導し、専門的で詳細な情報を提供する流れを作ることができます。結果として患者さんのクリニックへの信頼感が高まり、集患に繋がります。
SNSでの拡散を促進するコンテンツ作成の工夫
SNSを通じてオウンドメディアのコンテンツを効果的に拡散させるには、以下のポイントを工夫すると良いでしょう。
視覚的に訴える写真や動画の使用
・InstagramやFacebookの特性を活かして、視覚的に魅力的な画像や動画を用意し、注目を集めやすくする。
患者さんがシェアしたくなるテーマ設定
・健康や生活に役立つ具体的な情報や、「知っておきたい医療情報」など、患者さんが友人や家族に共有したくなるようなテーマを設定する。
ハッシュタグの積極活用
・適切なハッシュタグを用いて投稿することで、より多くの患者さんに情報を届けられる。
ストーリーズやライブ配信の活用
・InstagramやFacebookのストーリーズやライブ配信機能を活用してリアルタイム性のある情報を届け、患者さんの関心を高める。
定期的な投稿頻度の維持
・投稿頻度を一定に保つことで患者さんが継続的に訪問しやすくなり、拡散の可能性が高まる。
これらの工夫により、SNSからオウンドメディアへのアクセスを大幅に増やし、情報の拡散を効果的に促進できます。
オウンドメディアとSNSの相乗効果を最大化する方法
オウンドメディアとSNSを効果的に連携させることで、それぞれが持つ特性を活かした相乗効果を最大化できます。オウンドメディアはSEOを通じて安定的に情報を提供し、深い信頼を築きますが、SNSはリアルタイム性と拡散性が高く、即効性のある集客に適しています。
この二つを組み合わせることで、SNSが持つ「即時的な拡散力」と、オウンドメディアが持つ「専門的な情報提供」を融合させることができます。例えば、新しい記事をオウンドメディアで公開した際に、すぐにSNSで紹介を行い、多くの患者さんに即座に情報を届けることで、タイムリーな情報伝達を可能にします。
さらに、SNSを活用して患者さんからのフィードバックやコメントを積極的に集め、それを次のオウンドメディアの記事制作に反映することで、患者さんが本当に求める情報を継続的に発信できるようになります。
こうした連携を継続して行うことで、クリニックのブランディングが強化され、地域内での認知度や信頼性を大きく高めることが可能になります。
コンテンツマーケティングで患者ファン化
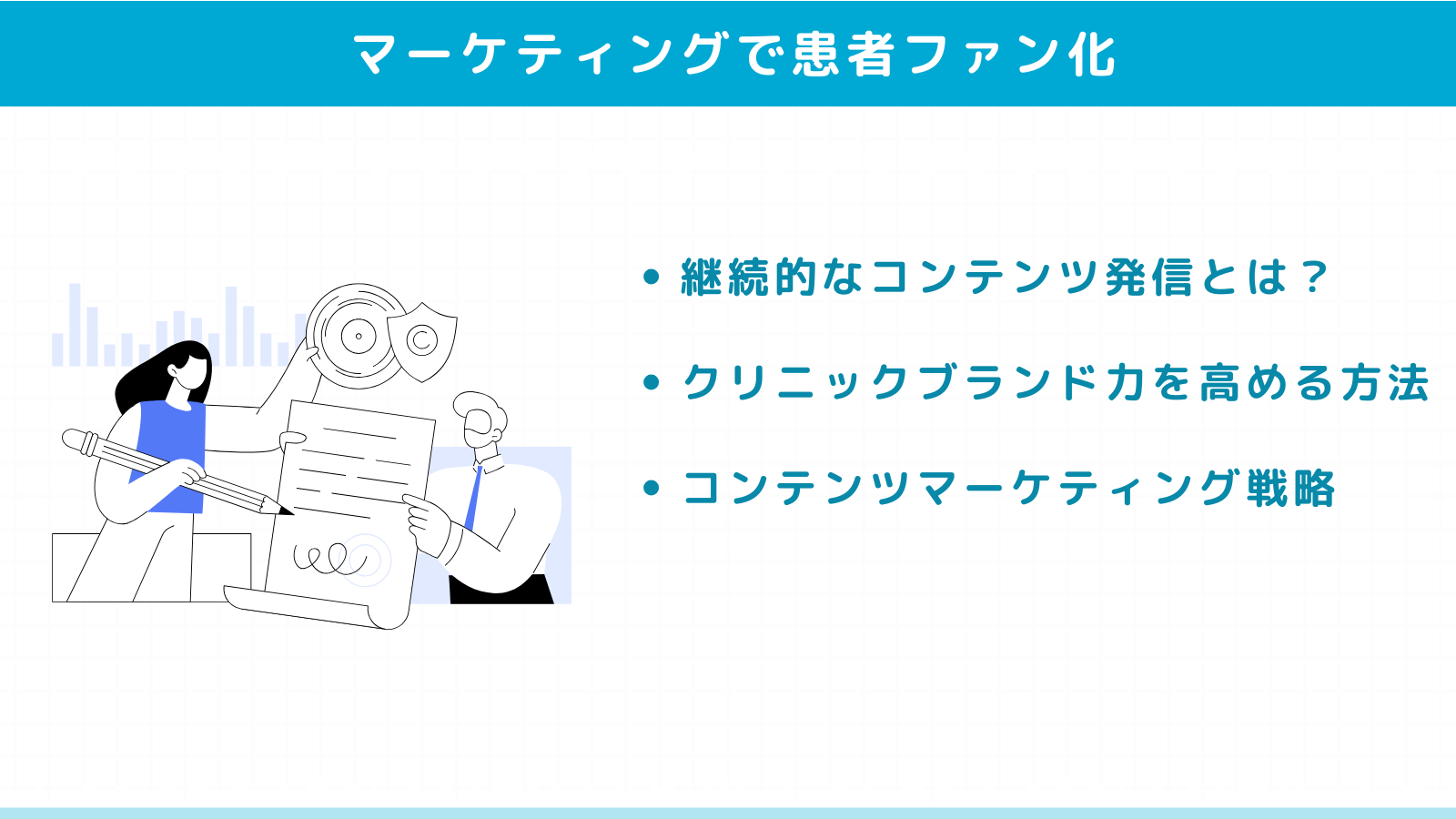
患者がファンになる継続的なコンテンツ発信とは?
クリニックがオウンドメディアで長期的な成果を得るためには、患者さんを一度限りの訪問者ではなく、継続的な『ファン』として育成していくことが重要です。そのためには、患者さんが何度でも読みたくなるような有益で魅力的なコンテンツを継続的に発信していくことが必要です。
ファン化を促すためには、患者さんの関心や日常生活に密着した情報を継続的に提供していくことがポイントです。例えば、季節や流行疾患に応じて定期的に更新する健康管理情報や、自宅で実践できる簡単なセルフケア方法をシリーズ化して連載するなどが効果的です。継続的に情報を提供することで患者さんは定期的にサイトを訪問し、クリニックに対して親近感を抱くようになります。
さらに、診療や日常生活に関するQ&A形式の記事を設け、患者さんから寄せられた質問に定期的に答えることで、読者参加型のコンテンツとしても展開可能です。このような継続性を持つコンテンツ運営により、患者さんは徐々にクリニックのファンへと変わり、自然と集患効果や口コミ効果が高まります。
コンテンツを通じてクリニックのブランド力を高める方法
コンテンツマーケティングを通じてブランド力を高めるには、以下の具体的な方法を実践することが効果的です。
専門性が明確な情報発信
・クリニックが得意とする専門分野を明確に伝え、患者さんが「このクリニックはこの分野で信頼できる」と認識できるようにする。
一貫性のあるブランドメッセージ
・すべての記事においてクリニックが大切にしているメッセージや理念を一貫して伝え続ける。
院長やスタッフの個性を活かした発信
・医師やスタッフの個性や人柄が伝わるコラムやインタビュー記事を掲載し、親しみやすさを高める。
地域密着型コンテンツの発信
・地域のイベントや健康に関連した情報を積極的に発信し、地域密着型のブランドイメージを高める。
これらの方法により、クリニックのブランド力が強化され、地域での評価や認知度が向上します。
患者のリピート率向上を実現するコンテンツマーケティング戦略
コンテンツマーケティングを活用することで、患者さんのリピート率を向上させることも可能です。そのためには、患者さんが一度クリニックを訪れた後も継続的に関心を持ち続けられるようなコンテンツ作りが求められます。
リピート率を向上させるには、患者さんが診療後のアフターケアとして活用できるような情報を提供することが効果的です。例えば、「診察後に気を付けるべき日常生活のポイント」「薬の正しい飲み方」や「定期的に受けるべき検診や予防接種の案内」など、診療と関連した継続的な情報を提供します。
また、季節ごとに起こりやすい健康トラブルや新たな健康情報を定期的に更新することで、患者さんが定期的にオウンドメディアを訪問するきっかけを作ります。さらに、ニュースレターやメールマガジンなどを活用して、新しい記事が更新されたことを患者さんに直接お知らせする仕組みを導入するのも効果的です。
このような戦略を取ることで、患者さんのクリニックへの継続的な関心を引き出し、リピート率の向上を実現できます。
オウンドメディア運営で失敗しやすいポイントと対策
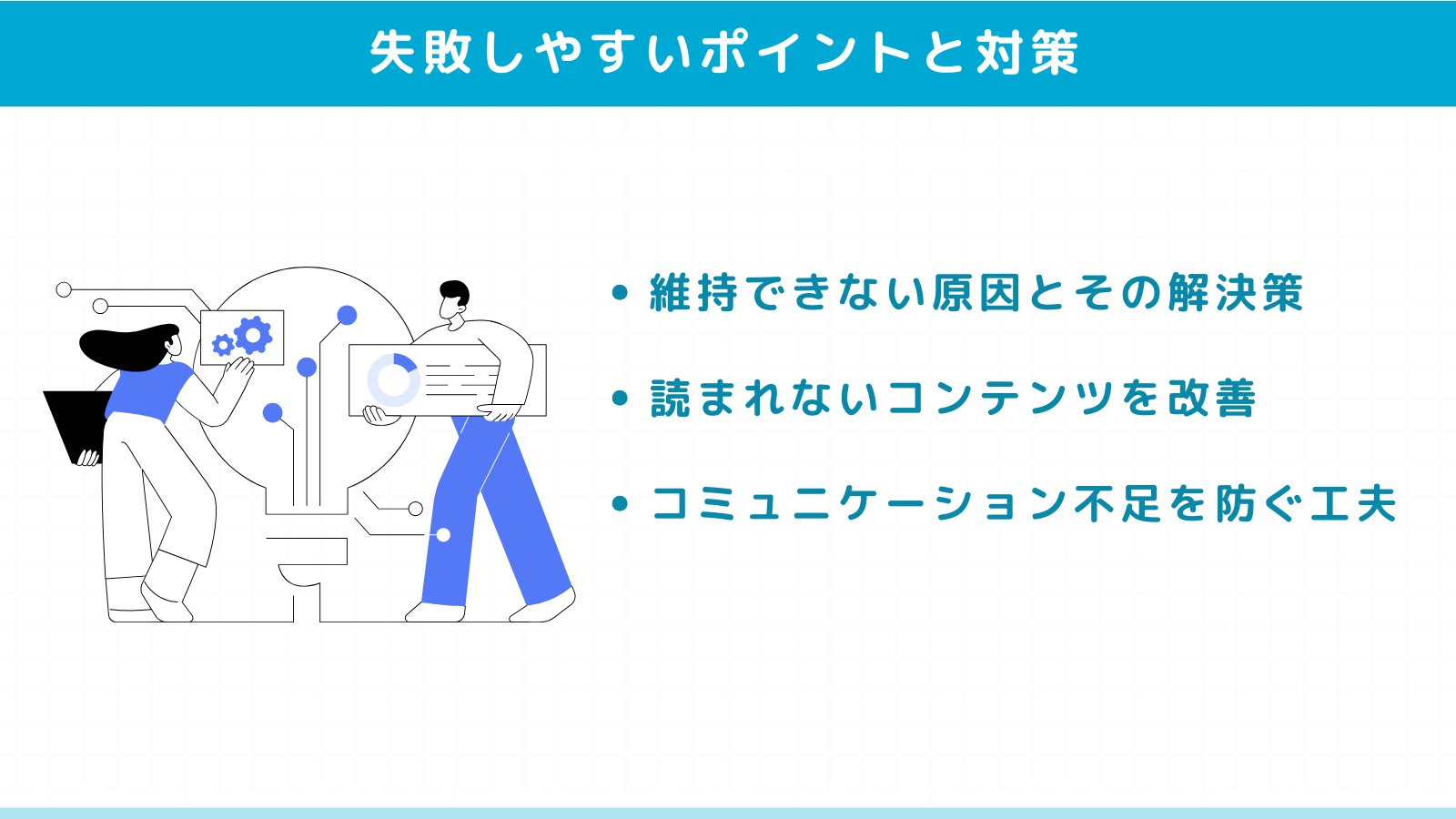
継続性を維持できない原因とその解決策
オウンドメディア運営でよくある失敗の一つが、『継続性が維持できないこと』です。クリニックがメディア運営を始めた当初は意欲的に更新を行っていても、日々の診療業務や運営の負担が大きくなると、徐々にコンテンツの更新頻度が落ちてしまいます。この結果、患者さんの関心が離れ、SEO評価も低下し、せっかくの効果が失われてしまいます。
継続性が維持できない原因の多くは、計画性の不足と運営体制の不備にあります。これを防ぐには、まず記事更新のスケジュールを具体的に立て、スタッフ間で共有することが大切です。記事作成に関する役割分担を明確にし、担当者を複数設けることで個人にかかる負担を軽減することも効果的です。
また、記事作成に十分な時間やリソースがない場合には、外部のライターや編集者に依頼することも検討しましょう。運営体制をきちんと整備することで、コンテンツ更新の継続性を保つことが可能になります。
読まれないコンテンツを改善する方法
作成したコンテンツが読まれない場合、以下のような改善策を試みることで読者の関心を引きやすくなります。
タイトルの見直し
・患者さんの関心を引くような具体的かつ魅力的なタイトルに変更し、クリック率を高める。
検索キーワードとのズレを修正
・実際の患者さんが検索しているキーワードに合致しているかを再検討し、内容を修正する。
視覚的な工夫を増やす
・画像や図表、箇条書きを増やして視覚的に理解しやすい記事に仕上げる。
内容の専門性と具体性を高める
・一般的な情報ではなく、より専門的かつ具体的で、患者さんが知りたい情報を深掘りする。
SNSでの再発信を行う
・記事内容の一部を抜粋してSNSで再発信し、読者を改めて誘導する。
これらの工夫を行うことで、患者さんの興味を引きやすくなり、コンテンツの閲覧数を改善することができます。
患者とのコミュニケーション不足を防ぐ工夫
オウンドメディアの運営において、ただ情報を一方的に発信するだけでは、患者さんとのコミュニケーション不足を招いてしまいます。患者さんが何を知りたいのか、どのような悩みを抱えているのかを理解し、それに応えることができなければ、オウンドメディアの価値は半減します。
患者さんとのコミュニケーション不足を防ぐためには、患者さんから直接フィードバックを得る仕組みを整えることが効果的です。記事の最後に質問フォームやコメント欄を設置し、患者さんが気軽に質問や意見を寄せられるようにします。寄せられた質問には丁寧に回答し、それをさらに新たな記事のテーマとして取り上げるなど、双方向のコミュニケーションを促進します。
また、SNSなどを活用して定期的に患者さんとの交流を図り、患者さんのリアルな声を積極的に取り入れましょう。こうしたコミュニケーションを通じて、患者さんが求めている情報を的確に発信し続けることができれば、オウンドメディアの価値と効果は一層高まります。
オウンドメディア活用で地域No.1のクリニックへ
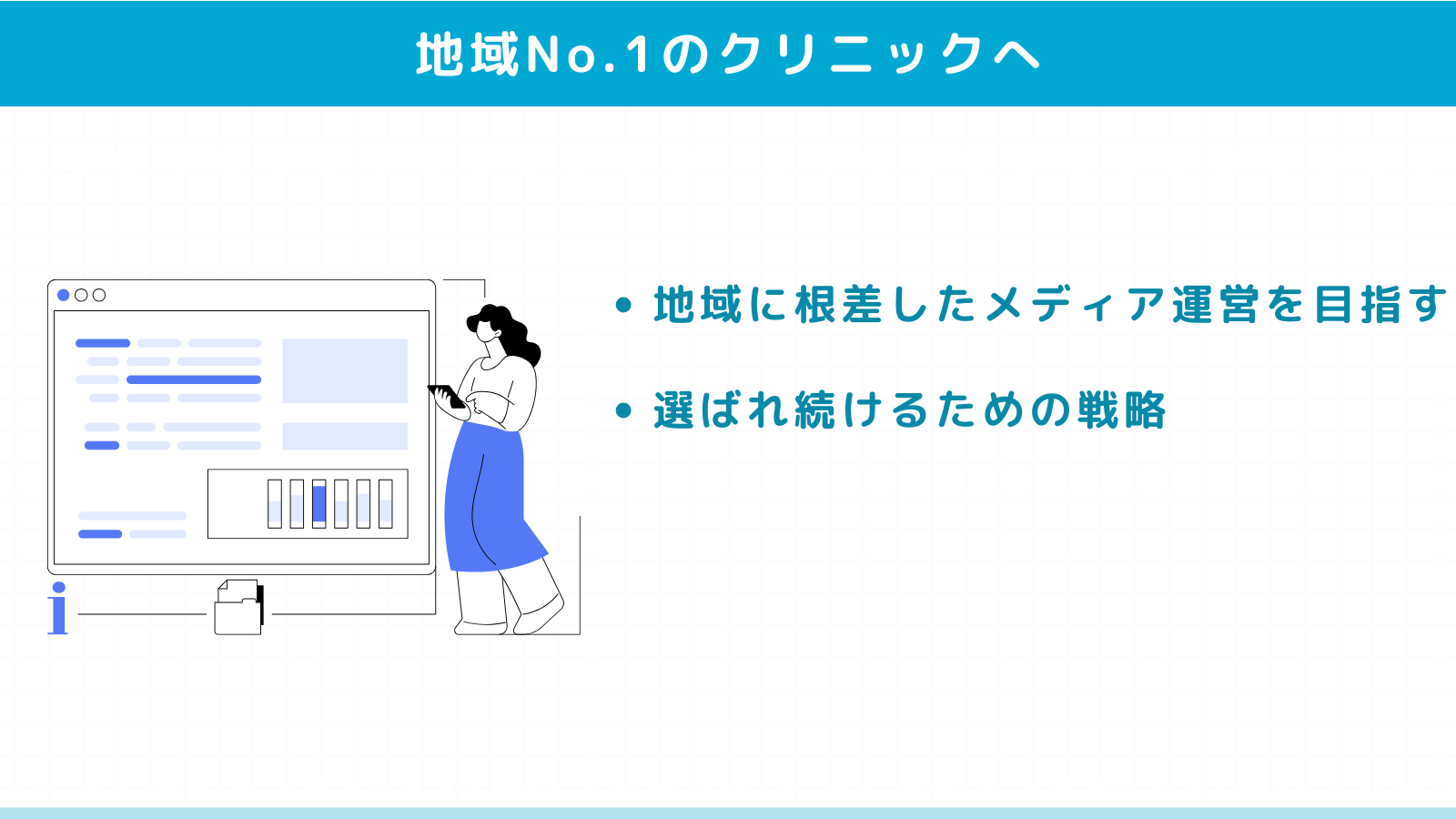
長期的な視点で地域に根差したメディア運営を目指す
オウンドメディアの運営を成功させ、地域No.1のクリニックとして認知されるためには、長期的な視点が不可欠です。一時的なアクセス増加や短期的な成果を目指すだけでは、本質的な集患効果や地域でのブランド構築にはつながりません。
地域に根差したメディア運営を行うためには、まず地域の患者さんが本当に求めている情報を継続的に発信し続けることが重要です。例えば、地域で流行する疾患や健康問題についてタイムリーに解説したり、地域のイベントや健康セミナー情報を定期的に掲載するなど、地域密着型のコンテンツを継続して提供します。
さらに、地域住民が抱える健康の悩みや不安をオウンドメディアを通じて丁寧に解消し、クリニックとしての信頼感を長期的に醸成することが必要です。地域の医療課題やニーズを的確に把握し、それに対して専門的かつ具体的な情報提供を続けることで、地域住民から長期的に信頼されるクリニックへと成長できます。
選ばれ続けるクリニックになるための戦略
地域で選ばれ続けるクリニックになるためには、以下のような具体的な戦略を継続的に実践しましょう。
地域住民との接点を増やす
・地域イベントや健康講座を主催・協賛し、その様子をオウンドメディアで積極的に発信する。
患者さんの声を活かしたコンテンツ作り
・診療や院内アンケートで得た患者さんの質問や要望を記事に反映させ、患者さん目線を徹底する。
定期的な情報提供で信頼を構築
・クリニックの専門性を活かした情報を継続的かつ定期的に発信し、地域での信頼性を高める。
他院との差別化を明確にする
・自院独自の専門性や強みを明確にし、それを繰り返し訴求することで地域内での差別化を図る。
地域特有の医療課題に対応する
・地域特有の健康課題や高齢化問題などに対する具体的な解決策や情報を発信し、地域の信頼を獲得する。
これらの戦略を実践することで、患者さんから継続的に選ばれるクリニックになることが可能です。
専門家にオウンドメディア運営を相談するメリット
オウンドメディアの運営はクリニックにとって大きなメリットがありますが、運営を成功
させるためには専門的な知識や運用ノウハウが必要になります。院内スタッフだけで運営を進めることは可能ですが、専門家の力を借りることで、より効率的かつ効果的に成果を出すことができます。
目利き医ノ助は、医療機関におけるICT活用を中心に、オウンドメディア制作やマーケティングサポートなど、適切な業者やサービスを厳選してご紹介します。医療現場での豊富な知識と経験をもとに、クリニックそれぞれの特徴や課題を丁寧に分析し、最適なサービスやパートナー企業を目利きいたします。
オウンドメディア活用をお考えの際には、ぜひお気軽に目利き医ノ助へご相談ください。