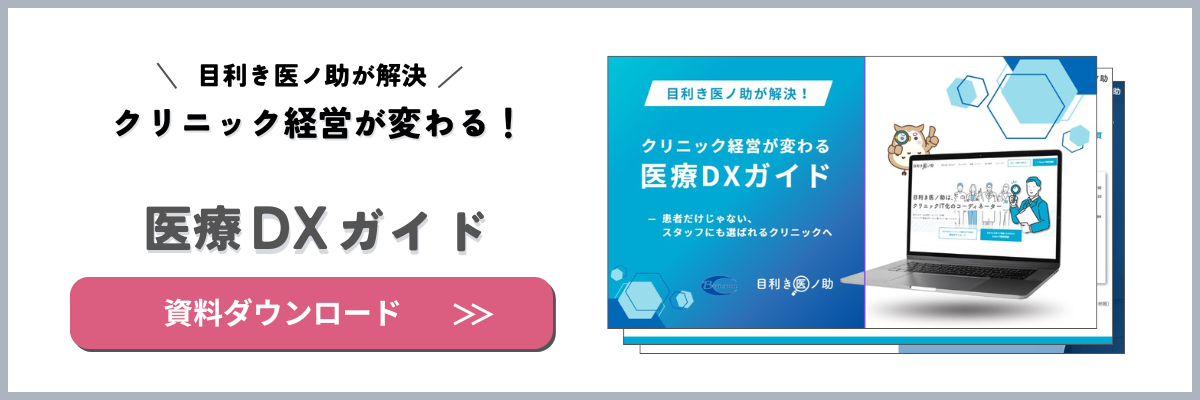2025.12.01
クリニックがYouTube運用を成功させる方法【目利き医ノ助】
クリニックが今すぐYouTubeを始めるべき理由
現在、多くの患者さんが健康情報や治療法をネット上で検索しています。特に動画を使った情報収集が急速に普及し、YouTubeが重要な情報源としての地位を確立しています。
ユーチューブは、趣味や娯楽のための動画視聴にとどまらず、信頼性が高く分かりやすい医療情報を発信できる場として、クリニックの新しい集患方法としても注目されています。
従来のホームページや口コミサイトだけでは伝わりにくかった医師の人柄や診療内容、クリニックの雰囲気などをリアルに発信することで、患者さんに安心感と信頼感を与えます。しかし、YouTube運用でクリニックの集患力アップするには、ただ写真や動画を投稿するだけではなく、フォロワーが本当に求めている情報を分析し、発信の頻度やタイミングを適切に調整すること、そしてクリニックの魅力が最大限に伝わるような視覚的な表現や統一感のあるブランディングを心掛けることが重要です。YouTubeを活用することで、「この先生に診てもらいたい」「ここなら安心して通える」と感じてもらえるクリニックへと成長できるのです。
1.YouTubeを使ったクリニック集患3つのメリット
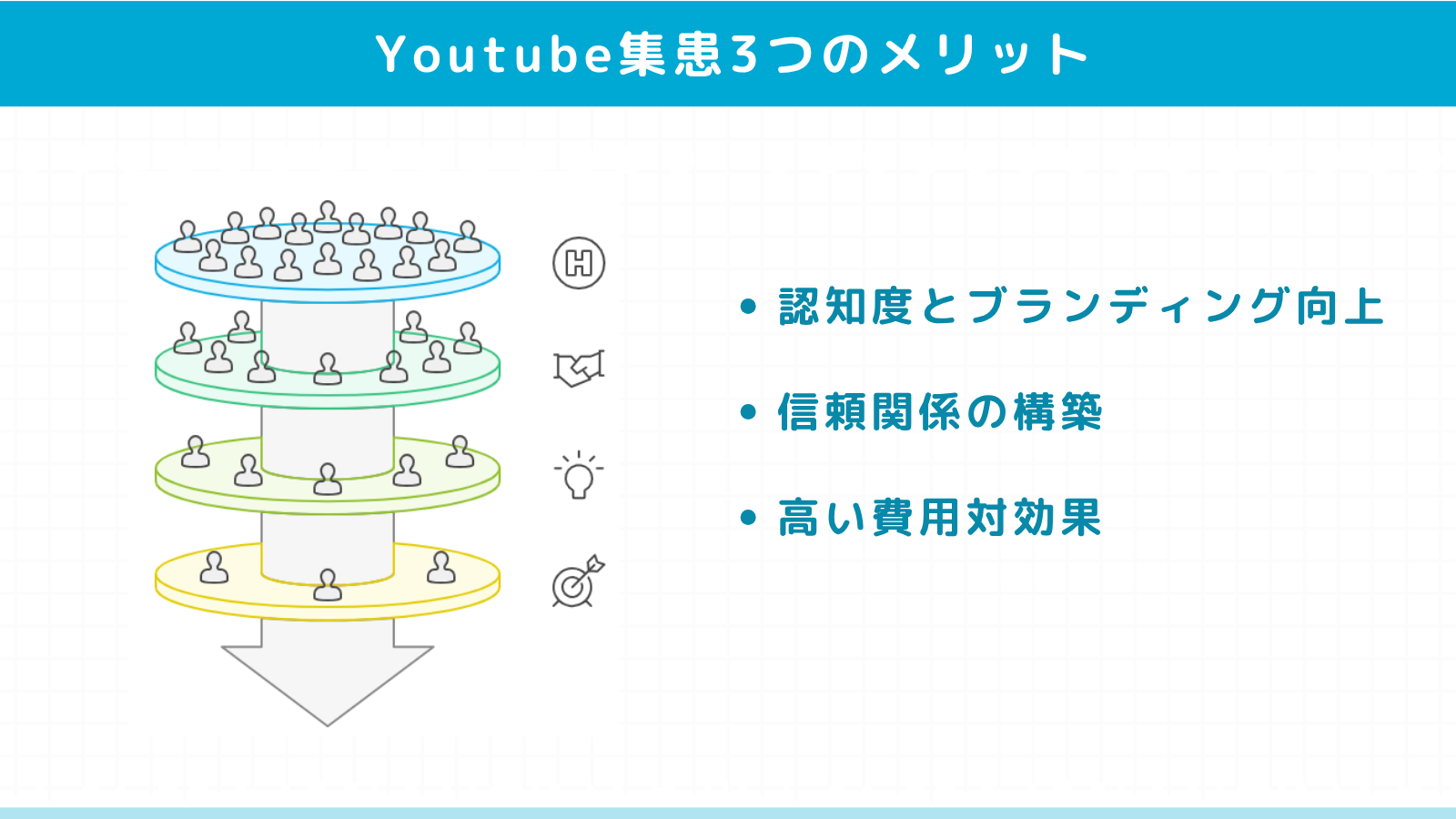
認知度向上と強力なブランディング効果
クリニックの経営において、地域での認知度向上や他院との差別化を図るためには、明確なブランディングが必要不可欠です。YouTubeは映像という特性を活かし、短期間で地域の認知度を高め、クリニック独自のブランディングを確立する強力なツールになります。
例えば、専門的な診療分野の動画を定期的に配信すれば、患者さんは「このクリニックは○○治療に強い」と認識します。また、医師が患者さんに寄り添って分かりやすく説明する姿を動画にすることで、信頼感が高まり、患者さんの心理的なハードルが下がります。
こうした動画を継続的に発信することで、地域におけるクリニックの存在感が増し、患者さんが自然に集まってくるようになるでしょう。
患者との信頼関係を強化できる
YouTubeを活用することで、診察以外の時間にも患者さんとの関係を築くことができます。具体的な信頼関係強化のポイントは以下の通りです。
医師の人柄が伝わる
・診察室では見えにくい医師の人柄やコミュニケーション能力をリアルに伝えられる。
診察内容の理解度向上
・動画で診療方針や治療方法を事前に伝えることで、診察時の理解度が向上し、患者さんの満足度が高まる。
安心感や親近感が増す
・スタッフや院内の様子を動画で紹介することで、クリニックへの親近感が高まり、患者さんが安心して来院できるようになる。
このように、YouTubeを活用すれば、より強固な患者さんとの信頼関係を築くことが可能になります。
費用対効果の高いマーケティング
YouTubeを利用したマーケティングは、従来の紙媒体やテレビ広告と比較して圧倒的に費用対効果が高い点も大きな魅力です。動画の制作は一度完成してしまえば、その後は継続的に多くの患者さんに届けることができます。
特に医療機関の場合、患者さんが気になる病気や症状について解説した動画を作成すれば、それが資産となり、検索を通じて継続的に視聴されることになります。また、YouTubeでは動画の視聴データや視聴者層が分析できるため、効果を数値化して把握しやすく、改善点も明確に分かります。
広告費をかけずとも質の高いコンテンツを作り続けることで自然と認知度が向上し、地域の患者さんに支持されるクリニックへと成長していきます。
2.クリニックの魅力を伝える動画コンテンツの具体例
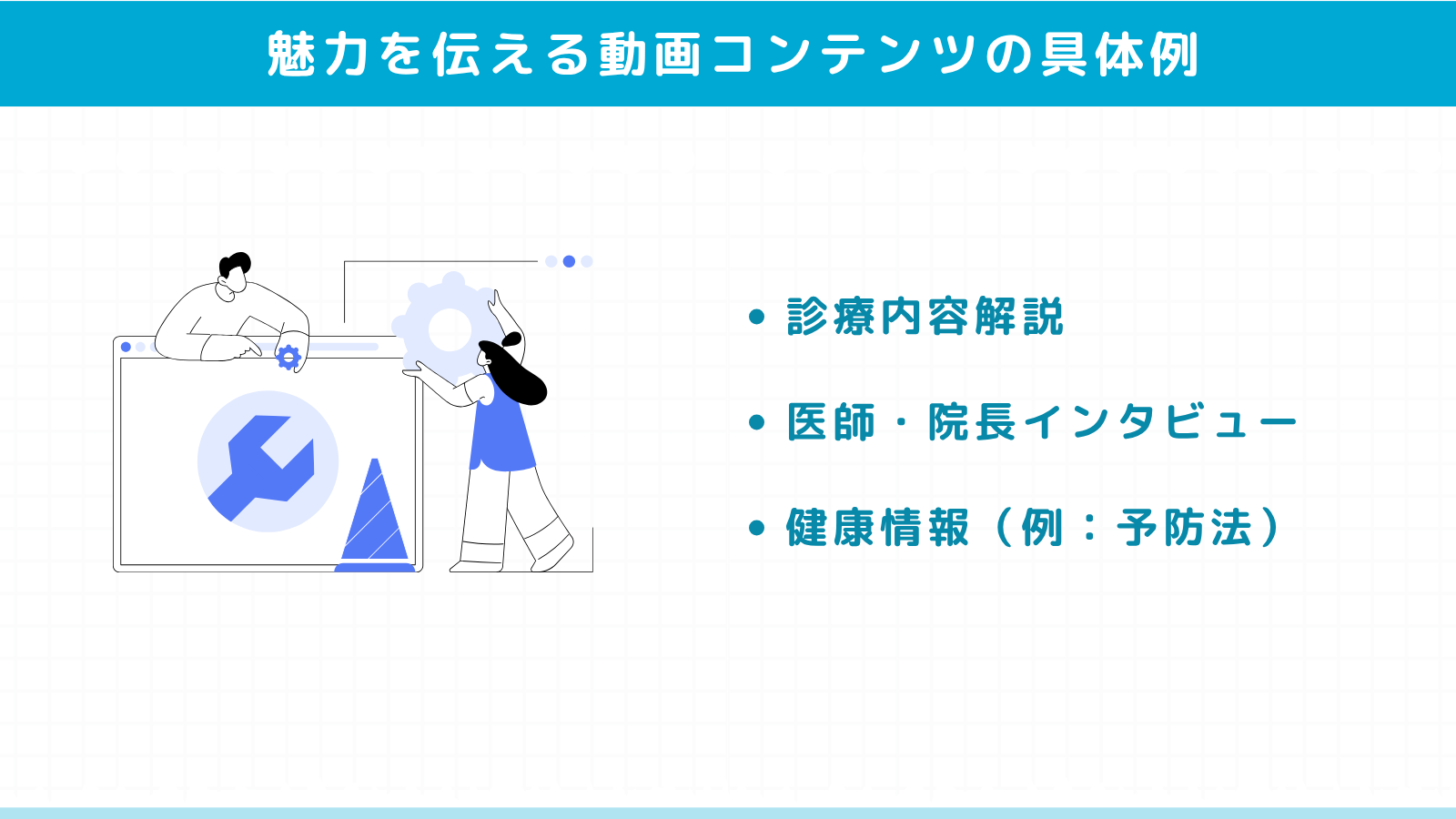
診療内容や専門性をわかりやすく伝える動画
クリニックがYouTubeを始める際、最も重要なのは、診療内容や専門分野を患者さんに分かりやすく伝えることです。なぜなら患者さんは、自分が抱えている悩みや症状に関する専門的な情報を、信頼できる医師・医療機関から得たいと考えているからです。
専門的な治療方法や疾患の説明を、医師自身が分かりやすく動画で解説することで、患者さんの不安を取り除き、クリニックの専門性を強く印象付けることができます。
動画を作るときには、医学用語を多用するのではなく、一般の方でも理解できる言葉で説明し、ポイントを絞って簡潔に伝えることが重要です。イラストや図表を併用すればさらに分かりやすくなり、患者さんから「信頼できる先生だ」「ここで診てもらいたい」と感じてもらえます。
医師やスタッフの人柄や院内の雰囲気を伝える動画
患者さんが安心して来院できるよう、医師やスタッフの人柄、院内の雰囲気を伝える動画を作ると、親近感や安心感がぐっと高まります。具体的な内容例は以下の通りです。
院長インタビュー動画
・治療方針や患者さんへの想い、普段の診療で心掛けていることを院長自身が話す。
スタッフ紹介動画
・スタッフが自己紹介をするだけでなく、診療中や休憩中の自然な笑顔やコミュニケーションを映す。
クリニックの院内ツアー動画
・待合室や診察室、処置室などの清潔で整った環境を紹介し、初診の患者さんの不安を和らげる。
これらの動画を通じて、患者さんにクリニックを身近に感じてもらうことができます。
患者が求める健康情報・セルフケア動画
患者さんは病気になったときだけでなく、日常的に健康維持や病気予防についての情報を求めています。そのため、YouTubeで日常的なセルフケア方法や健康情報を提供することは、非常に効果的です。
例えば、皮膚科であれば季節ごとの肌トラブル対策、整形外科であれば腰痛や肩こりの自宅でできるストレッチ方法、小児科であれば子どもの健康管理に役立つアドバイスなど、患者さんの日常に役立つ情報を定期的に提供します。
動画を見た患者さんが実際に役立つと感じることで、クリニックに対する信頼感や感謝の気持ちが高まり、定期的にチャンネルを訪れるようになります。また、身近で役立つ情報はSNSでシェアされやすいため、自然と新しい患者さんにも認知が広がりやすくなります。
3.YouTubeチャンネルの作成手順と初期設定
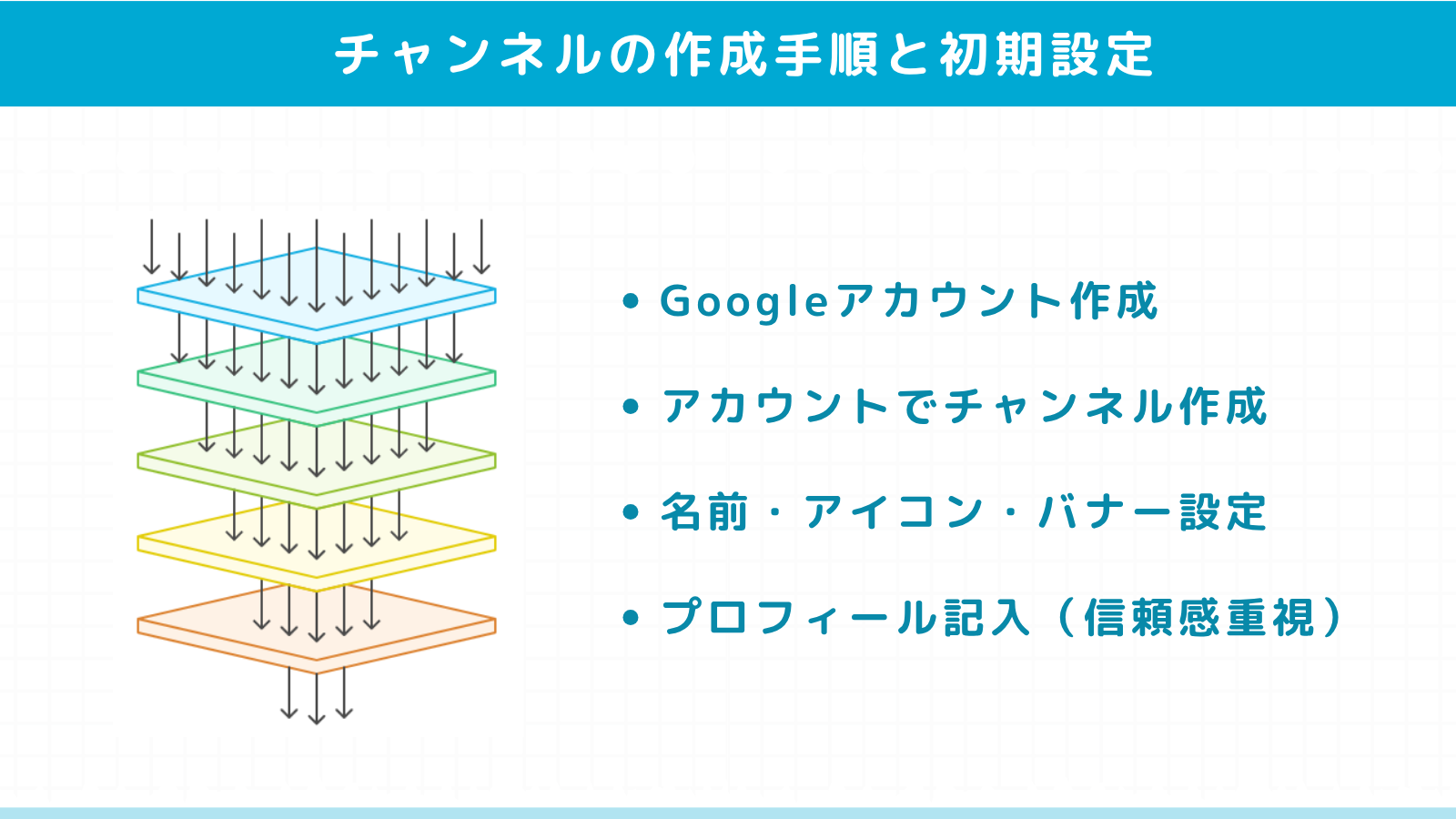
チャンネル開設の具体的な流れとポイント
クリニックがユーチューブを活用するためには、まずチャンネル開設が必要になります。手順自体は簡単ですが、最初の段階でしっかりと基礎を固めることが重要です。
まず、Googleアカウントを作成します。すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントを利用することも可能です。その後、YouTubeにログインし、画面右上のアイコンをクリックして「チャンネルを作成」を選択します。
チャンネルを作成する際には、「個人チャンネル」ではなく「ブランドアカウント」を選ぶのがクリニックにはおすすめです。ブランドアカウントを使うことで、複数のスタッフで管理が可能になり、運営を効率化できます。
また、初期の段階でチャンネルのテーマや目的を明確に設定することも重要です。「どのような患者さんに見てもらいたいのか」「どのような情報を提供するのか」をはっきりさせ、それに沿った動画制作を計画的に進めるようにしましょう。
チャンネル名やプロフィールの設定方法
チャンネル名やプロフィールは、視聴者が最初に目にする重要なポイントです。以下のようなポイントを意識して設定しましょう。
チャンネル名の決め方
- クリニック名をそのまま使うのが基本
- 専門性を強調したい場合は、「クリニック名+専門分野」などを入れる
- 検索されやすく覚えやすい名前を意識する
プロフィール画像
- クリニックのロゴ、もしくは院長や医師の信頼感ある写真を使用
- 視認性が高く、清潔感・安心感を与えるデザインを選ぶ
チャンネルのバナー画像
- クリニックの外観、スタッフの集合写真、専門分野を象徴するイメージ写真を使う
- 清潔感があり、クリニックのイメージに合ったデザインを選ぶ
こうしたポイントを意識することで、初めてチャンネルを訪れた視聴者に良い第一印象を与えられます。
患者が信頼するプロフィール設計のコツ
YouTubeチャンネルのプロフィールは、患者さんが信頼できる情報源だと認識するために重要な役割を果たします。プロフィール欄では、チャンネルの目的やクリニックの専門分野を明確に伝えることが大切です。
例えば、「当院では患者さんが気軽に健康情報を得られるよう、医療情報をわかりやすく発信しています」「患者さんが抱える不安や疑問に寄り添い、信頼できる医療情報を提供しています」といった明確なメッセージを記載しましょう。
また、公式ホームページや予約フォームへのリンクをプロフィールに設定することも大切です。動画を視聴した患者さんが簡単にクリニックへアクセスできるように導線を整えておくことで、実際の来院や予約の促進につながります。
患者さんが一目見て安心できるように、院長の経歴や専門資格、クリニックの特徴などを簡潔に記載することも信頼感向上のポイントとなります。
4.動画制作の基本と視聴者に響くポイント
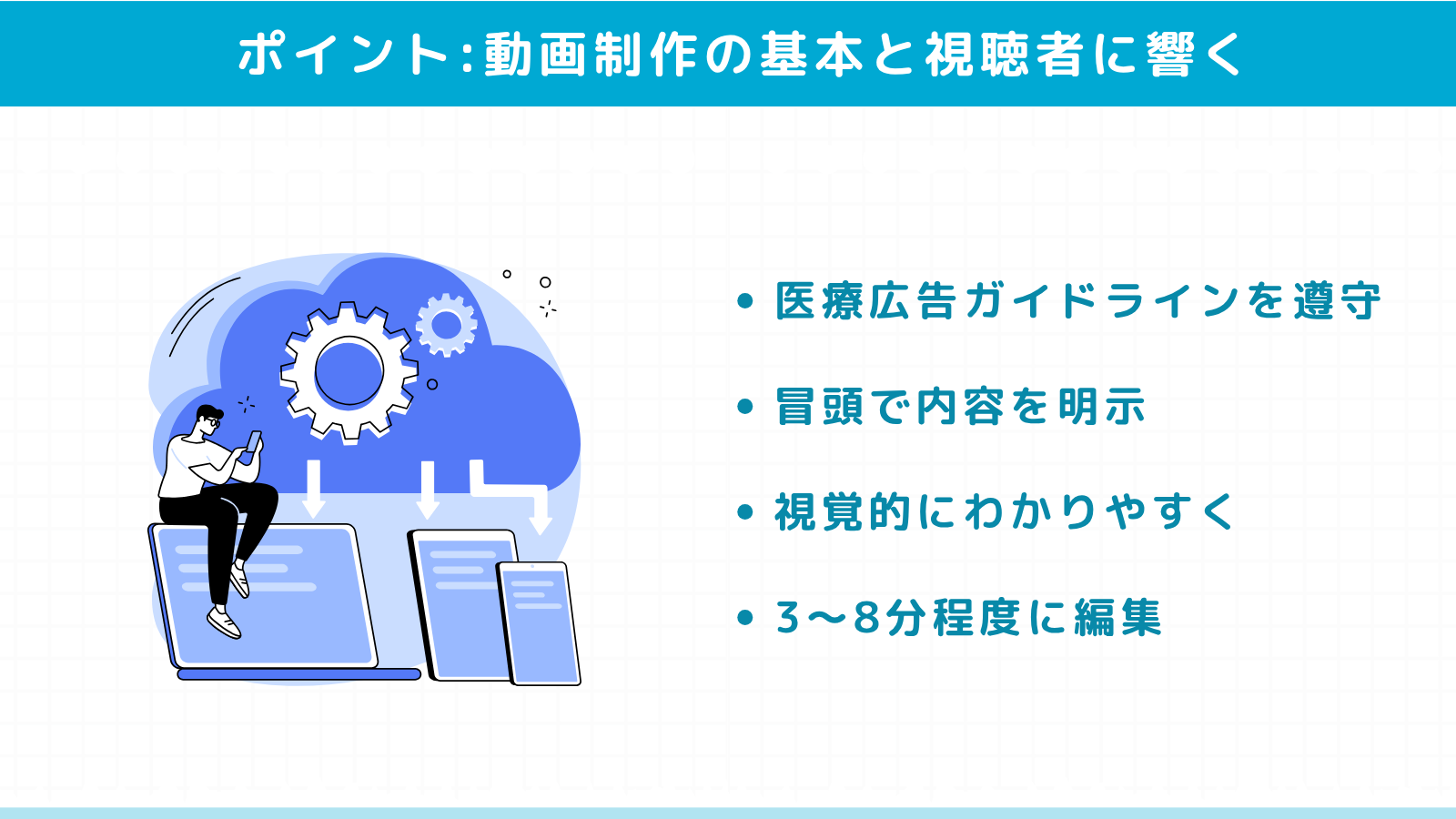
医療機関ならではの動画制作の注意点
医療機関が動画制作をする際には、一般企業とは異なる注意点があります。まず、最も気を付けなければならないのが「医療広告ガイドライン」の遵守です。動画内で患者さんの誤解を招く表現や、効果を過度に強調する表現は厳しく規制されています。
具体的には、治療効果の保証や、術前術後の比較を過剰にアピールする内容、患者さんの体験談を用いることは禁止されています。動画の制作前に必ず内容を確認し、客観的かつ正確な情報のみを発信するように心がけましょう。
また、プライバシーへの配慮も重要です。診療の様子を撮影する際には、患者さんの顔や個人情報が特定されないように注意し、撮影前に必ず許可を取ることが必須です。安心して患者さんが視聴できる動画づくりを徹底することで、信頼されるクリニックとしての評価が高まります。
視聴者が「見たい」と思う魅力的な動画作りのポイント
視聴者が「見たい」と感じ、最後まで視聴するような動画を作るには、以下のポイントを意識しましょう。
冒頭に動画内容を明確に伝える
- 動画の冒頭で「今回は○○について解説します」とテーマをはっきり示す
視聴者の関心に沿った内容を提供する
- 視聴者(患者さん)が日常的に抱えている疑問や不安をテーマとして選ぶ
- 「よくある腰痛の原因と対処法」や「正しいスキンケアの方法」など、身近で役立つテーマを選ぶ
視覚的に分かりやすくする
- イラストやテロップを使い、難しい医学用語を補足・解説する
- 図表やグラフを使って視覚的に分かりやすく情報をまとめる
これらを意識すると、患者さんが自然と視聴を続け、次回以降も動画を楽しみにするようになります。
短くても伝わる動画編集のテクニック
動画の長さは視聴維持に大きく関係します。特にYouTubeでは、視聴者は短時間で効率よく情報を得たいと思っています。そのため、情報は端的に伝える必要があります。理想的な動画の長さは、3〜8分程度が視聴者が最後まで見やすいとされています。
まず、動画編集の際は、本当に必要な部分だけを厳選して残すことが大切です。診療内容や説明は、最も伝えたいポイントに絞り込みましょう。話題が複数ある場合は、1つの動画にまとめるのではなく、テーマごとに短く分割する方が視聴者にとってわかりやすくなります。
また、不要な沈黙部分や「えー」「あのー」といった間をカットし、スピーディな展開を意識しましょう。重要なキーワードはテロップを用いて強調し、視聴者が直感的に理解できるよう工夫するとさらに効果的です。
こうした工夫をすることで、短時間でも情報がきちんと伝わり、視聴者の満足度が高まります。
5.再生数と登録者数を伸ばすための戦略
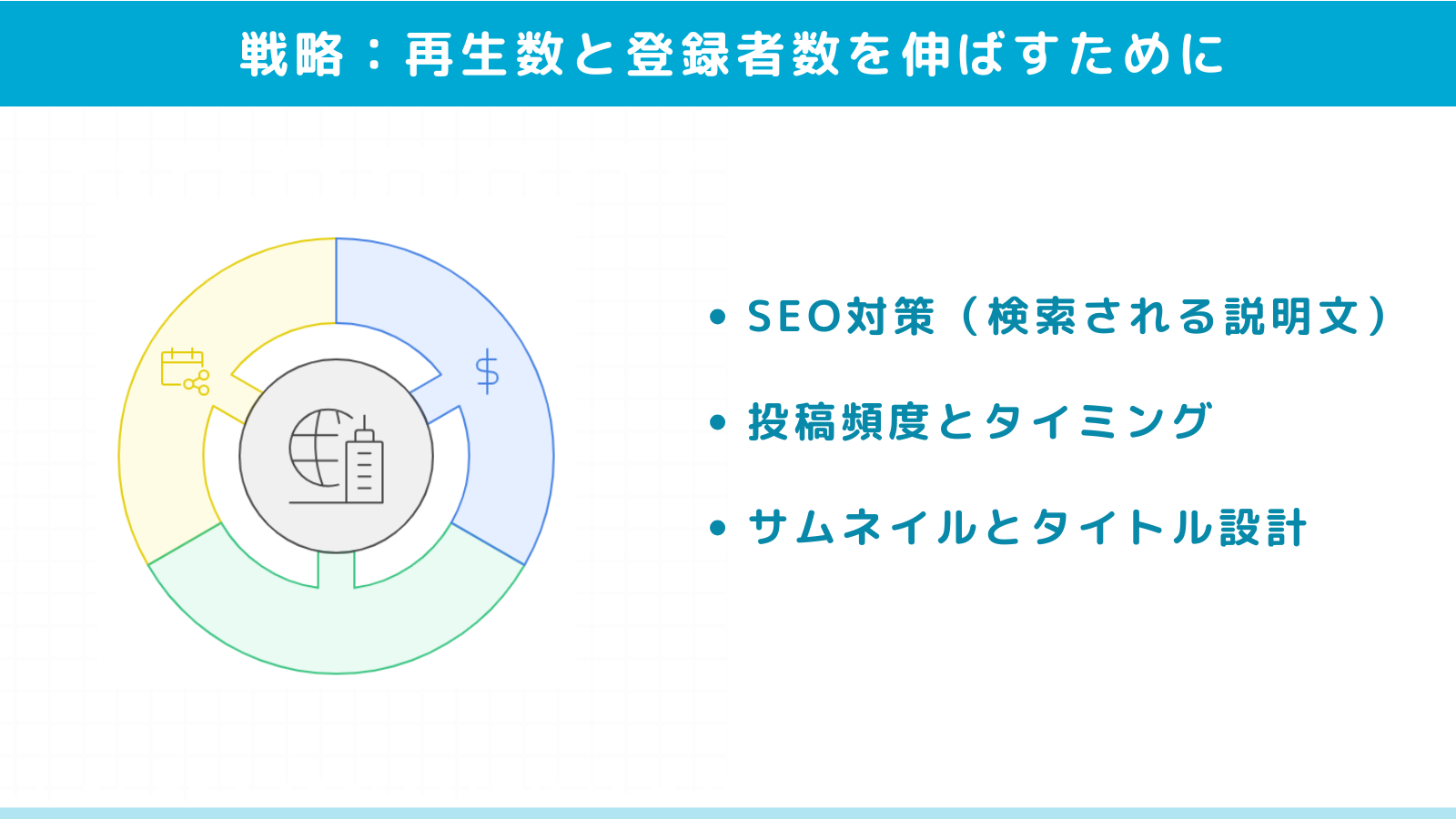
YouTube SEOの基礎とキーワード選定
YouTubeで動画を多くの人に見てもらうためには、「YouTube SEO」と呼ばれる検索エンジン最適化が非常に重要です。これはYouTubeの検索結果で動画が上位表示されるよう、タイトルや説明欄に適切なキーワードを配置し、検索に強い動画を作る方法です。
クリニックの場合、患者さんが検索する可能性のある症状や疾患名、日常的な健康管理のキーワードを中心に選びましょう。例えば、「肩こり改善」「ニキビ対策」「血糖値下げる方法」など、患者さんが日常的に悩むテーマが有効です。
また、キーワードを設定する際には「サジェストキーワード」(検索時に自動的に表示される関連語句)を活用し、具体的にニーズのあるキーワードを見つけましょう。そのキーワードを動画タイトルや説明欄に自然に盛り込むことで、検索結果に表示されやすくなり、再生回数とチャンネル登録者数を伸ばすことができます。
最適な動画投稿頻度とタイミング
投稿頻度やタイミングは動画の再生数や登録者数を伸ばすうえで非常に重要です。以下のポイントを意識して設定しましょう。
動画投稿頻度
- 週に1〜2本の投稿を継続的に行うことが理想的
- 一貫した頻度を維持することで視聴者が動画公開を期待し、チャンネル登録に繋がる
動画を投稿するおすすめの時間帯
- 平日の夜(19時〜22時):仕事や学校が終わり、ゆっくりと動画を見られる時間帯
- 休日の午前中(9時〜12時):休日にゆったり情報収集する人が多い時間帯
データに基づいた投稿タイミングの調整
- YouTubeアナリティクスを利用し、自チャンネルの視聴者が最もアクティブな時間帯を把握
- 視聴者が多いタイミングに合わせて投稿を予約すると再生数が増える
これらを実践することで、視聴回数が安定的に伸び、チャンネル登録者数の増加にも効果的です。
効果的なサムネイルとタイトルの作り方
ユーチューブの動画がクリックされるかどうかは、タイトルとサムネイルによって大きく左右されます。視聴者が動画を選ぶ際に最初に目にする部分だからです。
まず、サムネイルはシンプルでわかりやすく、視認性の高いデザインを心がけましょう。文字を入れる場合は、短いキーワードを大きく配置し、目立つ色を使ってメリハリをつけます。例えば、「5分でできる腰痛体操」など、簡潔かつ具体的に視聴者の興味を引くキーワードを用いると効果的です。
タイトルは、視聴者が動画を見たくなるように、分かりやすく魅力的に設定します。専門性をアピールするだけでなく、患者さんが具体的に解決したい悩みや問題を明示するのがポイントです。例えば、「プロ医師が解説!自宅でできる肩こり解消法」など、視聴者が具体的なメリットを感じられるタイトルにしましょう。
魅力的なタイトルとサムネイルを組み合わせることで、視聴者の関心を引きつけ、動画再生数とチャンネル登録者数の増加を実現します。
6.YouTube運用でよくある失敗事例と対策
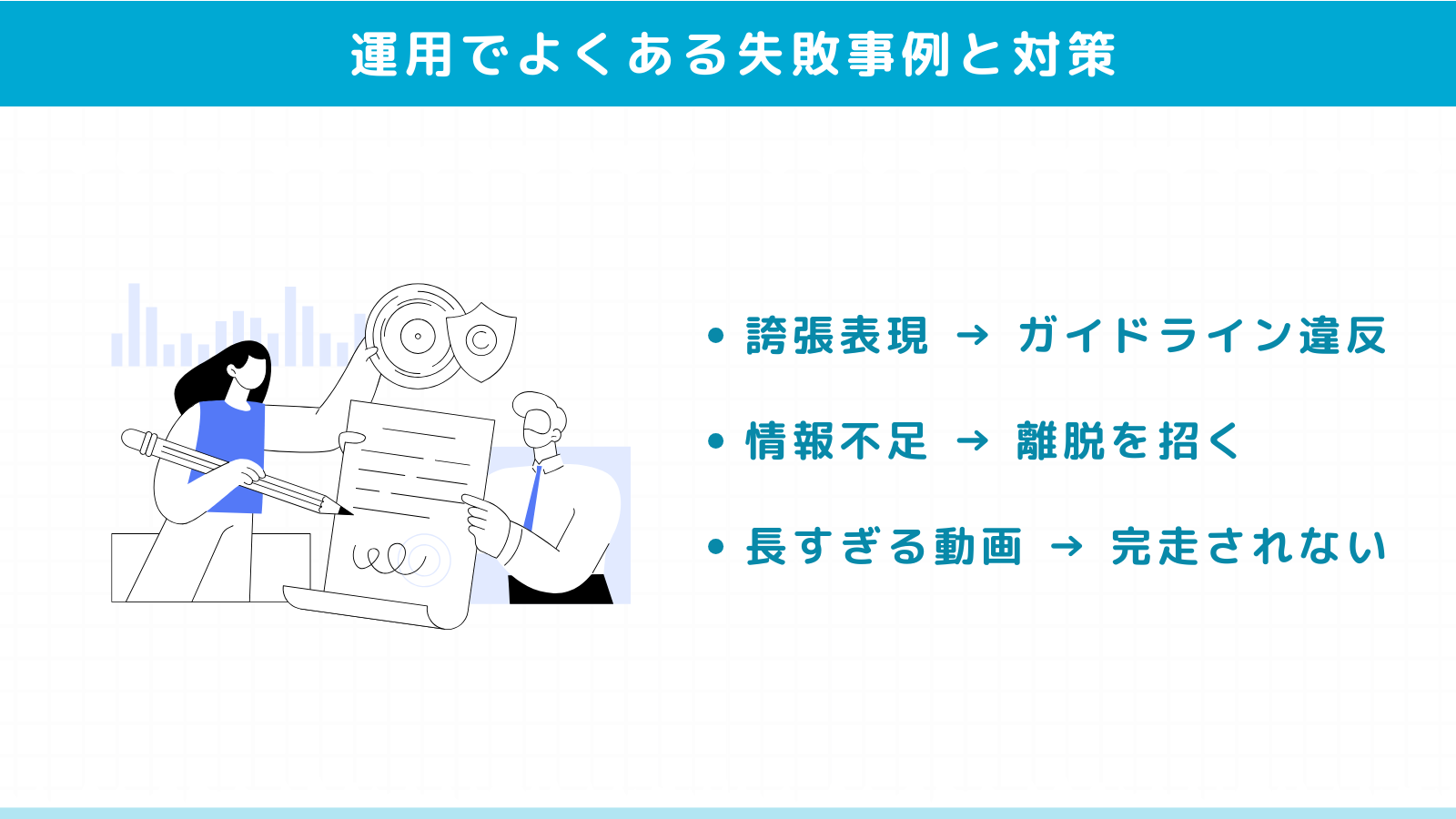
医療広告ガイドライン違反のリスクと注意点
医療機関がYouTube運用を始める際に、最も注意が必要なのが「医療広告ガイドライン違反」です。特に動画の場合、つい視聴者を惹きつけようとして表現が過剰になりやすいため、注意が必要です。
具体的には、患者のビフォーアフターを示すような動画、治療効果を保証するような表現、「この施術で必ず改善します」といった強調表現は、全てガイドライン違反となります。また、患者さんの個人的な体験談を使用する場合も、表現に細心の注意を払わなければなりません。
対策としては、動画を公開する前に複数人のスタッフで内容を確認し、客観的で過剰な表現がないかをしっかりチェックしましょう。また、定期的にガイドラインを確認し、最新の規定を遵守することが必要です。これにより、リスクを未然に防ぎ、安全にYouTube運用を継続できます。
視聴者離れを起こすNG動画コンテンツ例
視聴者が離脱してしまう動画にはいくつかの特徴があります。以下のようなNGコンテンツを避けることで視聴維持率を高めましょう。
専門用語が多すぎて理解しづらい動画
・視聴者がついていけないと、すぐに離脱してしまう。
情報が曖昧または内容が薄い動画
・具体的な情報がなく、「役に立った」と感じられない。
動画の尺が長すぎる
・必要以上に長い動画は途中離脱を誘発する。5〜10分以内を目安に。
画質や音質が悪く視聴しにくい動画
・見にくさや聞き取りづらさでストレスを与え、視聴を中断される。
これらを意識して、視聴者にストレスなく有益な情報を提供することが重要です。
登録者が伸び悩む原因とその改善策
チャンネル登録者が伸び悩む原因の多くは、視聴者が「次も見たい」と思う理由を感じていないことにあります。例えば、投稿頻度が不定期だったり、動画のテーマが一貫していないと視聴者は登録をためらいます。
これを改善するためには、まず明確なチャンネルコンセプトを設定し、それに沿った動画を継続的に投稿することが大切です。また、動画内で「チャンネル登録をお願いします」と視聴者に直接呼びかけたり、動画のエンディング画面で登録ボタンを表示するのも効果的です。
さらに、定期的に視聴者からのコメントを取り上げて動画内で回答したり、リクエスト動画を作成するなど、視聴者とのコミュニケーションを活性化させることも重要です。このような改善を行うことで、視聴者のチャンネルへの帰属意識が高まり、自然とチャンネル登録者数が増えていきます。
7.YouTubeと他のSNSやホームページの連携方法

ホームページへの誘導テクニック
YouTubeをクリニックの集患に活かすためには、ホームページへの誘導が非常に重要です。動画を視聴した患者さんが、すぐに予約やお問い合わせにつなげられる仕組みを整えておく必要があります。
まず、動画の概要欄には、必ずホームページへのリンクを設置しましょう。動画内でも「詳しい情報やご予約はホームページをご覧ください」と口頭で案内し、視聴者に次の行動を促します。また、ユーチューブのエンドカード機能を使い、動画終了時にホームページへの誘導リンクを表示させることも効果的です。
ホームページ側でも、YouTubeチャンネルの情報を掲載し、相互に誘導し合える環境を作ります。こうした連携を徹底することで、動画の再生からホームページ訪問、さらに来院へとスムーズにつなげることができます。
InstagramやLINEなど、SNSとの相乗効果を生む活用法
YouTube単独で運用するよりも、他のSNSと組み合わせることで相乗効果を生み、集患効果がさらに高まります。具体的な活用法は以下の通りです。
Instagramとの連携
- 動画のダイジェスト版をリールやストーリーで配信し、ユーチューブのフル動画へ誘導
- Instagramで患者さんの質問や意見を募集し、それをYouTubeの動画で回答する
LINE公式アカウントとの連携
- LINEで定期的に動画の更新通知を配信し、継続視聴を促す
- LINE限定でYouTube動画と連動した健康管理アドバイスや特別情報を配信
X(旧Twitter)との連携
- 動画のリンクと簡潔なポイントを短文で発信し、リアルタイムでの拡散を促進
- トレンドや話題性のあるテーマに関する動画を積極的にツイートし、関心を高める
こうした連携を効果的に活用することで、多くの患者さんにリーチし、継続的な関係性を構築できます。
一貫性ある情報発信で患者の信頼感を高める
ホームページやSNS、YouTubeをそれぞれ単独で運用するだけでは、本来の効果を十分に引き出せません。患者さんがクリニックの情報に触れる複数のメディア間で、一貫性ある情報発信をすることが重要です。
具体的には、ホームページに掲載する診療内容や方針、営業時間や休診情報などは、必ずYouTubeやSNSでの情報と一致させましょう。デザインや色合い、ロゴやバナー画像も統一することで、患者さんは一貫したブランドイメージを持ち、信頼感を強めます。
情報が矛盾していると、患者さんは不信感を抱き、せっかく築いた信頼関係が崩れる可能性もあります。情報更新時には全てのメディアで内容を確認・調整し、常に最新で正確な情報を提供するよう心がけましょう。これにより、患者さんからの信頼が高まり、安定した集患へとつながります。
8.YouTubeを活用してクリニック経営を一歩先へ
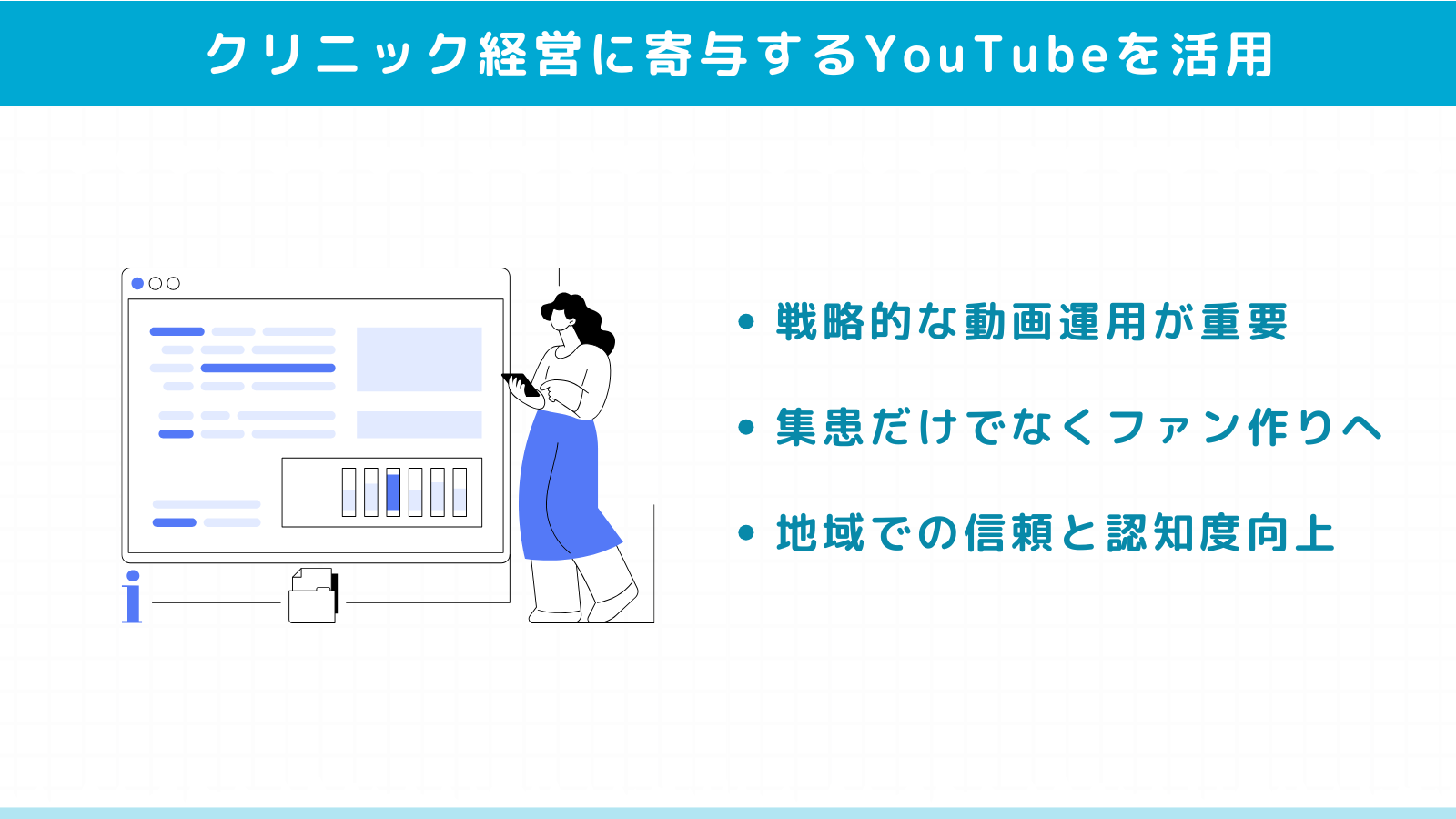
戦略的に動画を運用することの重要性
ただYouTubeに動画をアップするだけでは、十分な集患効果を得ることはできません。クリニックがユーチューブを最大限活用するためには、戦略的かつ計画的な運用が重要です。
まず、明確な目的を設定し、その目的を達成するためにどのような動画コンテンツを発信するかを綿密に計画します。ターゲット層や求められる情報を明確にし、それに基づいたテーマ設定を行いましょう。また、動画制作後も視聴データを定期的に分析し、視聴者が求めている情報や反応の良いコンテンツを把握することが必要です。
さらに、チャンネルの運用は長期的視野を持つことが重要です。即効性を求めすぎず、地道に動画投稿を継続し、視聴者との信頼関係を築くことで、徐々に集患効果や患者さんの定着を促進できます。長期的で一貫した取り組みこそが、クリニック経営の安定と発展につながります。
集患からファン作りへ、長期的なメリット
YouTube運用の価値は、患者さんを増やすことだけではありません。定期的な動画投稿によって、クリニックの理念や診療方針、医師やスタッフの人柄を伝えることで、患者さんとの深い信頼関係を築くことができます。
患者さんが継続的にクリニックの動画を視聴することで、医師やスタッフへの親しみや安心感が生まれます。結果として、診察室での限られた時間を超えたコミュニケーションが成立し、患者さんが「自分のかかりつけクリニック」として認識してくれるようになります。これにより、一度診療を受けた患者さんがリピーターとなり、定期検診や予防医療にも積極的に足を運ぶようになります。
さらに、地域の健康に役立つ質の高い情報を定期的に発信し続けることで、地域内でのクリニックの認知度やブランド価値が向上します。地域住民にとって「健康について信頼できる情報源」として位置付けられれば、長期的な患者さんとの関係構築に大きく貢献します。
このように、YouTubeを活用したファン作りは、目先の集患効果にとどまらず、クリニック経営の安定と持続的な成長を支える強力な土台になるのです。
YouTube活用のご相談は目利き医ノ助へ
これまでお伝えしてきたように、YouTubeをはじめとするSNSを戦略的に活用することは、クリニックの経営を安定させ、さらに成長させるために大きな役割を果たします。
ただ何となく投稿するだけでは、十分な効果は得られません。
SNS運用の成功の鍵は「計画的で戦略的な運営」にあります。自院の強みや診療分野に合った情報を継続的に発信し、フォロワーとのコミュニケーションを積極的に行うことで、患者さんとの信頼関係を構築できます。
しかし、運営には注意が必要です。特に開設・運用作業を誰がやっていくかによって得られる効果が変わります。インスタグラム運用に興味がある方や、導入を検討しているものの開設者がいないクリニックなどは専門家に相談するのもひとつの方法です。
目利き医ノ助はクリニック向けITシステムや集患施策などの目利きの相談窓口です。クリニックの状況やご希望に応じて最適な選定をサポートをさせていただきます。YouTube運用についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。