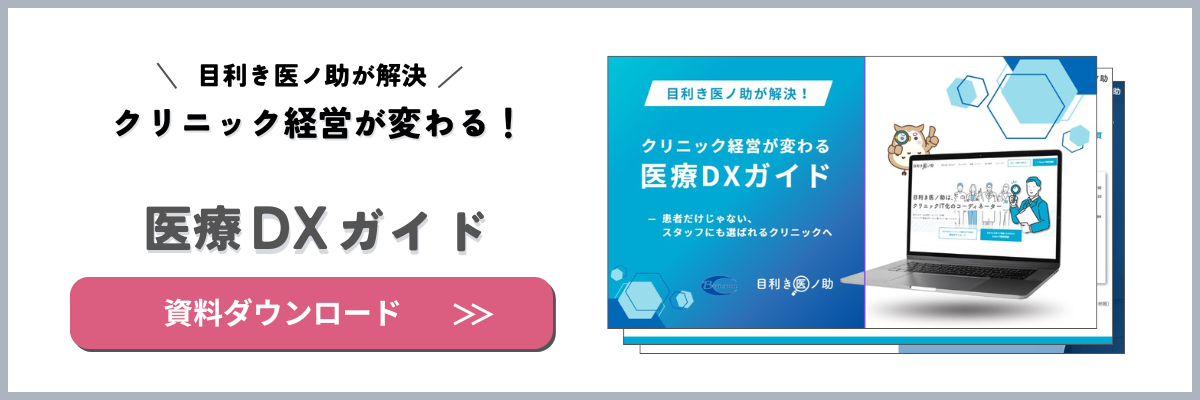2025.11.07
保険医療2035とは?医療制度改革の方向性を解説【目利き医ノ助】
「保険医療2035」とは?その目的と概要をわかりやすく解説
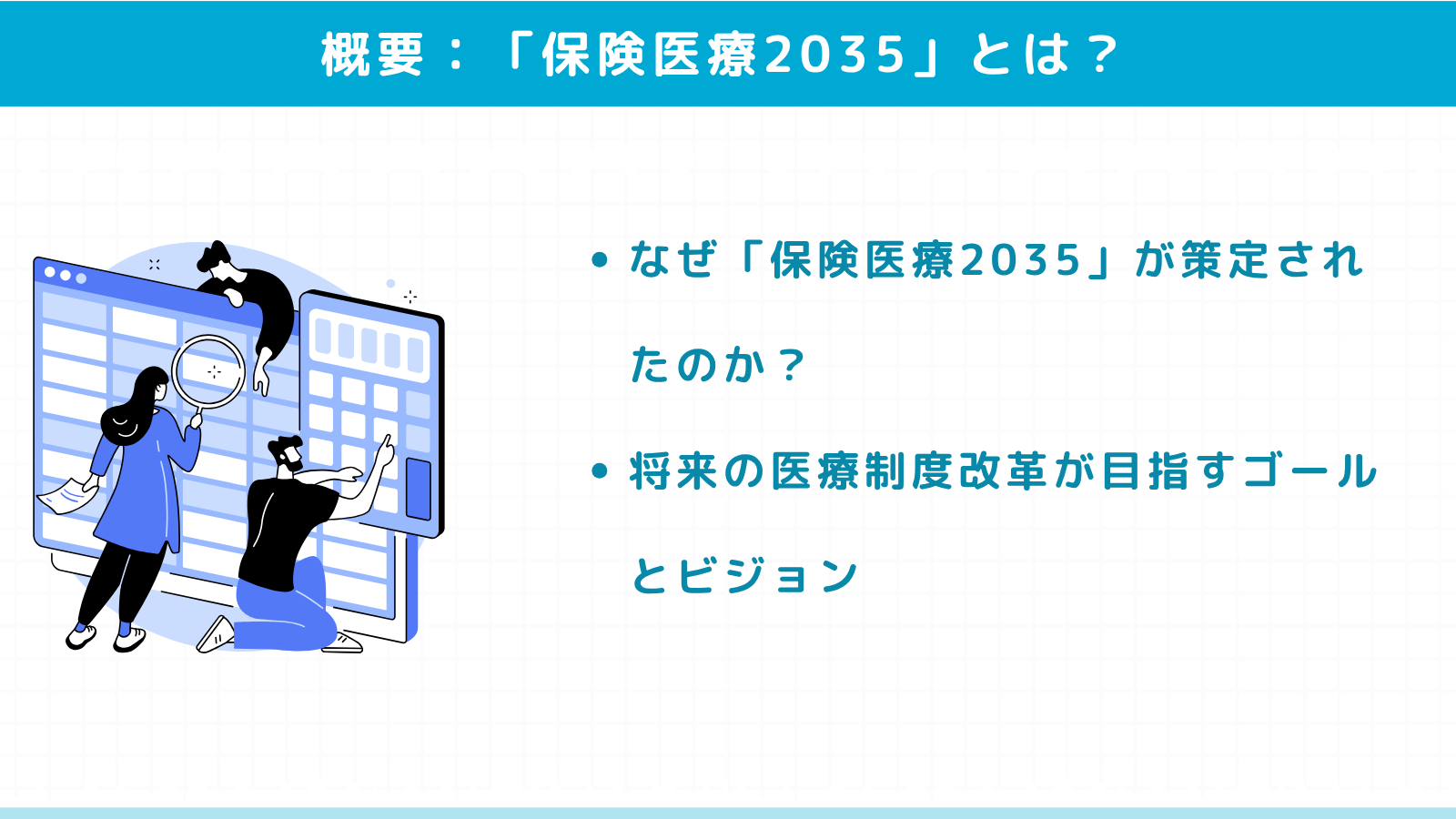
なぜ「保険医療2035」が策定されたのか?
「保険医療2035」とは、厚生労働省が中心となり、2035年の日本における望ましい医療の姿を示した提言書です。策定の背景には、日本が直面している急速な少子高齢化や人口減少、医療費の増大など、従来の医療制度では対応困難なさまざまな社会的課題があります。
特に日本では、2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護需要がピークに達します。その10年後の2035年には、高齢者人口がさらに増加する一方、現役世代の人口が大きく減少することで、医療・介護の提供体制や財政面で大きな課題に直面することが予測されています。
こうした社会構造の変化に伴い、従来型の医療提供体制や社会保障制度をそのまま維持することは困難です。持続可能な医療システムを確立するためには、抜本的な制度改革が不可欠との認識のもと、「保険医療2035」が策定されました。医療提供体制の再構築、効率的な医療資源の配分、患者本位のサービス提供などを軸として、医療の質を高めつつ経済的な持続可能性を担保することが目的となっています。
将来の医療制度改革が目指すゴールとビジョン
「保険医療2035」が目指す医療制度改革のゴールとビジョンは以下の通りです。
患者中心の医療体制の構築
・患者自身が主体的に医療を選択し、自らの健康管理に積極的に参加できる仕組みを整備。
効率的かつ持続可能な医療財政の確保
・医療費の適正化を推進し、医療保険制度の安定的運営を実現。
地域包括ケアシステムの深化
・医療と介護の連携を強化し、地域単位で包括的かつ効率的なケア体制を構築。
ICT・DXの全面的な推進
・電子カルテやオンライン診療の普及により、地域間格差を是正し、効率的な医療提供を促進。
かかりつけ医機能の強化
・身近な医師が患者の健康を包括的に管理することで、早期発見・早期治療を促進。
医療従事者の働き方改革
・医師や看護師などの働き方を改善し、人材の定着と医療の質向上を実現。
こうした具体的な改革を通じ、患者本位の質の高い医療を持続的に提供することが「保険医療2035」の最終的なビジョンとなっています。
保険医療2035が示す具体的な医療制度改革の方向性
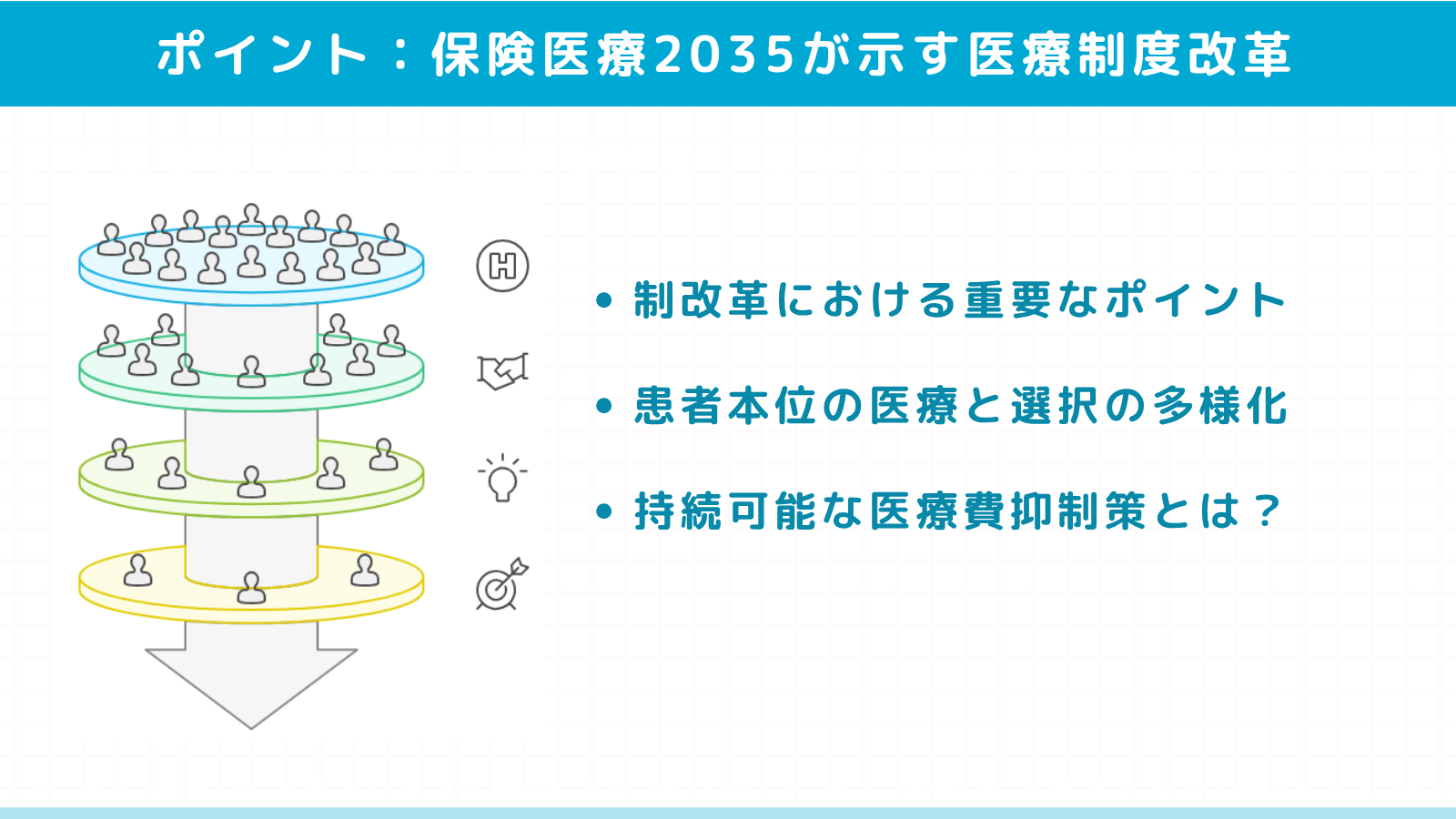
医療提供体制改革における重要なポイント
「保険医療2035」において、医療提供体制改革は特に重要なテーマです。その主な方向性として、まず医療機関の役割分担の明確化があります。これまでは病院が一般的な治療から高度な医療まで幅広く提供していましたが、今後は病院と診療所がそれぞれの強みを発揮し、連携する体制が求められます。
急性期医療は病院が担い、慢性期や予防医療、生活習慣病管理などは地域のクリニックや診療所が担当するなど、機能分化を明確にすることで、医療資源の効率的活用を図ります。
また、医療人材不足に対応するため、医師や看護師以外にも薬剤師や介護士、リハビリ専門職など多職種連携を強化し、医療スタッフが本来の専門業務に集中できる環境を整えることが重要です。役割分担と連携体制を強化することで、医療の質を向上させつつ、経済的負担を抑制する効果も期待されます。
さらに、医療ICTの推進による電子カルテやオンライン診療、AI診断支援などを導入することで、地域間格差を是正し、全国どこでも質の高い医療を受けられるような環境整備が目指されています。
患者本位の医療と選択の多様化に向けた方向性
「保険医療2035」では患者の選択肢を増やし、患者自身が主体的に医療を受けられることを重要視しています。従来の医療は、医師主導型で治療方針が決定されることが一般的でしたが、今後は患者が自分の価値観やライフスタイルに合った医療サービスを選択できるような仕組みづくりが必要です。
例えば、かかりつけ医制度の推進によって、患者が自分の健康状態や既往歴をよく知る医師と長期的な関係を築き、納得した上で治療法を選択できるようになります。また、オンライン診療や遠隔医療の活用により、時間や場所に制限されず、自分に最適な医療機関や医療従事者を選べる環境整備も求められます。
こうした患者本位の医療を提供する姿勢や仕組みづくりを積極的に進めることは、患者満足度を高めるだけでなく、口コミなどを通じて地域におけるクリニックの集客・集患対策としても有効に働きます。さらに、患者が医療に関する情報を適切に理解し判断できるよう、わかりやすく正確な医療情報提供を徹底する必要があります。これにより、患者自身が納得感を持って医療に参加でき、より良い治療結果や満足度の向上にもつながります。
効率的かつ持続可能な医療費抑制策とは?
「保険医療2035」では、増え続ける医療費を抑制し、持続可能な医療制度を実現するための具体的な取り組みとして以下のような施策を掲げています。
予防医療・健康管理の強化
・生活習慣病の予防や早期治療により医療費増大を抑制。
地域包括ケアシステムの深化
・在宅医療や介護と連携し、病院依存度を下げることで医療費を削減。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のさらなる普及促進
・ジェネリック薬品の使用拡大により薬剤費を抑える。
医療ICT・DX導入による診療効率化
・電子カルテや遠隔医療、AI活用による診療の効率化を促進。
医療資源の地域間・機能間の適正配分
・病院や診療所間の役割分担明確化、適切な施設基準設定による無駄の削減。
診療報酬改定による効率化誘導
・診療報酬制度を通じて適切な医療行動を促し、医療費抑制を実現。
こうした施策を総合的に推進することで、医療費の効率的活用と持続可能性を高める狙いがあります。
地域包括ケアシステムの重要性と今後の進展
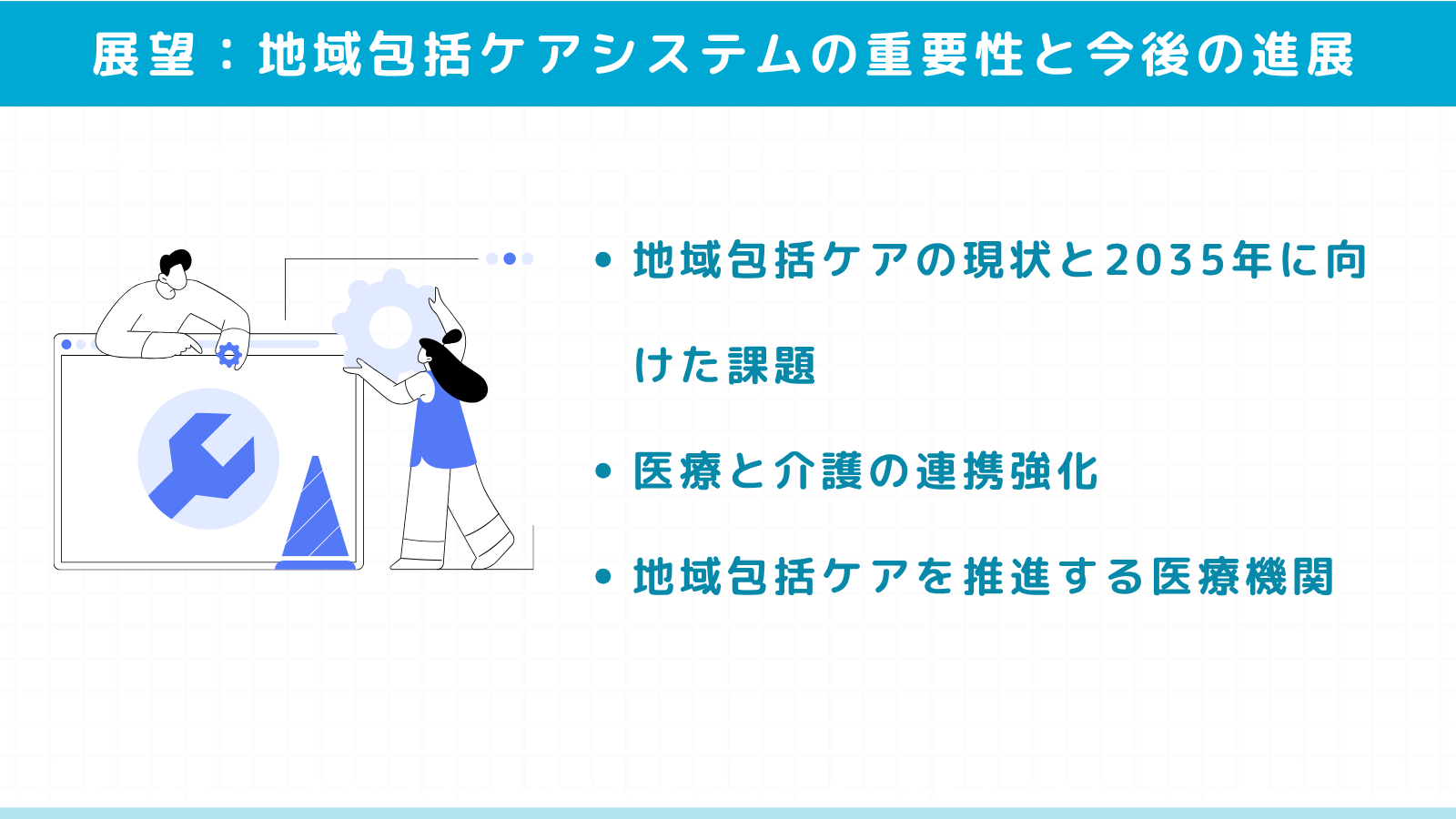
地域包括ケアの現状と2035年に向けた課題
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活を継続できるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される仕組みのことです。少子高齢化や医療費の増大、医療人材不足などの課題を背景に、高齢者が病院に過度に依存しない仕組みとして導入が進んでいます。
現在、多くの地域でこのシステムの構築が進んでいますが、現状では地域間での整備状況に大きな格差があります。都市部では医療・介護サービスが充実していますが、地方や過疎地域では十分な人材確保や施設整備が難しく、在宅医療・介護を提供する体制が整っていないケースが多く見られます。
2035年に向けては、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を経て、医療・介護需要がピークに達するため、地域包括ケアシステムの整備と深化が急務となっています。特に医療・介護の連携強化や、人材育成・確保、ICT活用などが具体的な課題として浮上しており、早期の対応が求められます。
医療と介護の連携強化に求められる具体的施策
地域包括ケアシステムが機能するためには、医療と介護の連携強化が不可欠です。そのためには、両分野の情報共有や人材交流の促進が重要となります。例えば、医療機関と介護施設間での診療情報共有システムを導入し、電子カルテや介護記録を一元管理することで、情報の途切れや重複を防ぎ、質の高い連携を実現できます。
また、医師や看護師など医療従事者が介護施設に定期的に訪問し、介護スタッフへの医療知識の共有や教育を行うことで、介護施設における医療ケアの質を高めることも可能です。逆に、介護スタッフが病院やクリニックで研修を受けることで、介護現場での医療的ケアの対応能力を向上させることも考えられます。
行政側も地域包括ケア会議を定期的に開催し、医療・介護関係者が一堂に会する場を設けることで、地域全体の連携強化や課題解決を促進する仕組みづくりを進めています。こうした具体的な施策により、より効果的な医療・介護連携を推進することが求められています。
地域包括ケアを推進する医療機関の役割
地域包括ケアを推進するためには、医療機関が果たすべき重要な役割があります。医療機関が地域包括ケアシステムに積極的に関与し、連携強化を促進するために取り組むべきポイントを以下に挙げます。
地域医療連携の窓口となる役割
・地域の医療機関・介護施設・行政との積極的な情報共有と連携促進。
かかりつけ医としての機能強化
・地域の患者の健康状態を把握し、適切な医療・介護サービスを提供。
在宅医療の提供と強化
・患者が自宅で安心して療養できるよう、訪問診療や訪問看護を充実。
医療ICT・DX推進による情報連携
・電子カルテやオンライン診療を活用し、地域全体で医療情報を共有。
医療スタッフの多職種連携促進
・医師・看護師・薬剤師・介護士・リハビリスタッフなどとの連携を強化。
地域住民への予防医療・健康増進活動の推進
・健康教室や予防接種の推進など、地域住民の健康維持を支援。
これらの役割を積極的に果たすことで、地域包括ケアシステムの構築と運営において医療機関が中核的な存在となり、地域の医療・介護の質の向上に大きく寄与することができます。
「かかりつけ医」機能の強化と医療機関の役割
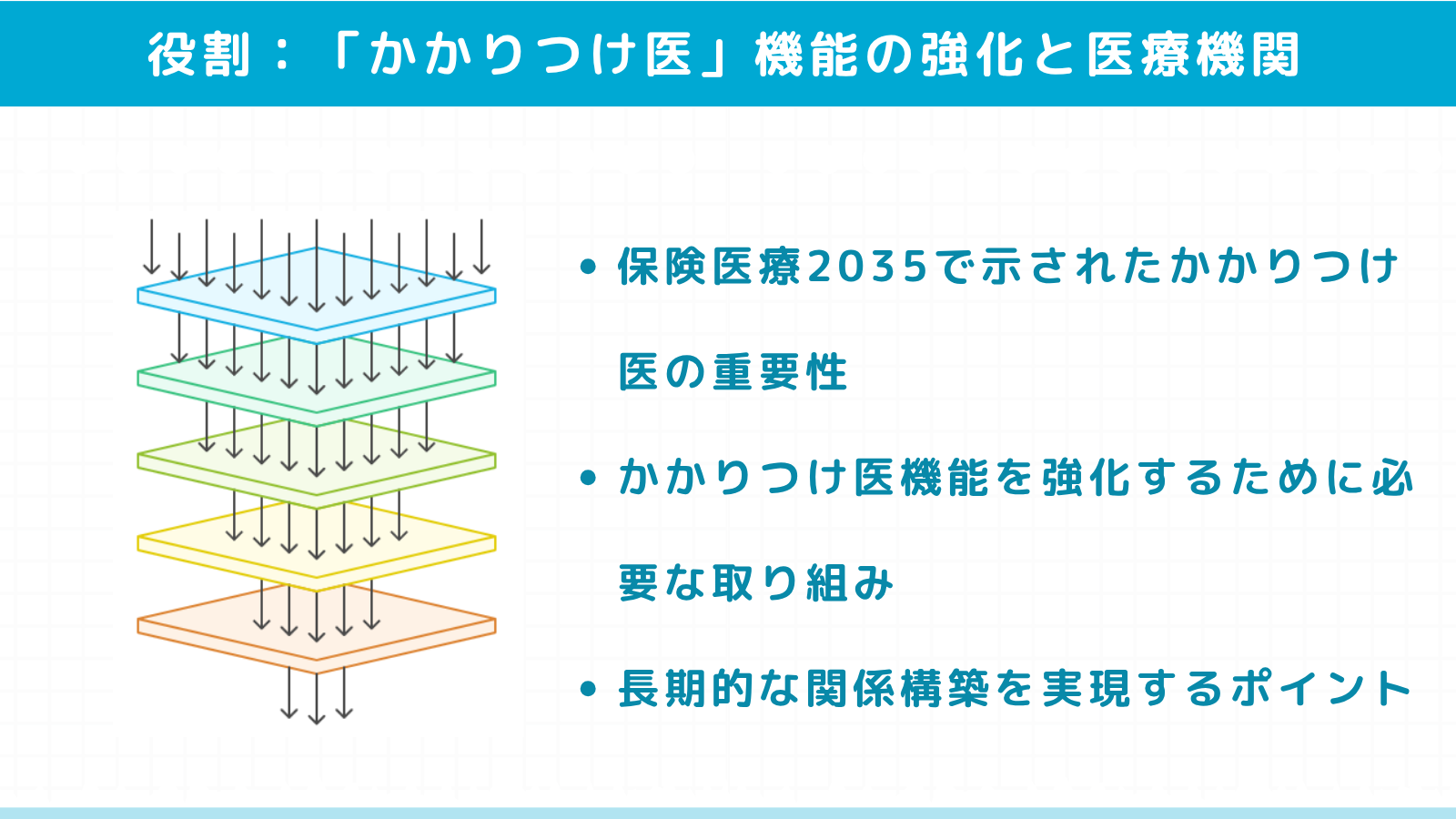
保険医療2035で示されたかかりつけ医の重要性
保険医療2035では、超高齢社会において効率的かつ質の高い医療提供体制を実現するために、「かかりつけ医」機能の強化が重要なポイントとして位置付けられています。かかりつけ医とは、患者さんが病気や健康上の悩みを何でも気軽に相談できる医師のことです。普段から患者の健康状態を把握し、病気の予防や早期発見、必要に応じて適切な専門医療機関への橋渡しを行う役割を担っています。
特に医療資源が限られる今後の社会では、患者一人ひとりに対する日常的な健康管理や生活習慣病予防、慢性疾患管理などを行うかかりつけ医の存在がますます重要になります。患者が病状の軽いうちにかかりつけ医に相談できれば、重症化を未然に防ぐことが可能となり、結果的に医療費の抑制や医療資源の適正配分にもつながります。
保険医療2035では、このように患者と長期的な関係を構築し、地域に密着した医療を提供するかかりつけ医の役割を明確化し、その体制整備や支援強化が進められる方向性が示されています。
かかりつけ医機能を強化するために必要な取り組み
かかりつけ医機能を強化するためには、まず医療機関自身がその役割を明確に意識し、日常診療の中で患者と継続的な関係を築く取り組みが必要です。その具体的な取り組みとしては、まず診療情報の一元管理と共有が重要です。電子カルテなどを活用して、患者の診療記録を一元的に管理し、地域の他の医療機関や介護施設との情報共有を図ることで、継続的で質の高いケアを提供できます。
また、地域住民の健康増進活動にも積極的に参加し、健康相談会や予防接種、健康講座などを定期的に開催することで、地域に密着した医療機関としての役割を果たすことが求められます。これにより、地域住民から信頼される存在となり、かかりつけ医としての機能強化につながります。
さらに、医療機関内において多職種連携を促進し、医師・看護師・薬剤師などが連携して患者に包括的な医療サービスを提供する体制を整えることも不可欠です。患者の多様なニーズに対応し、安心して頼れる医療機関としての存在感を高めるための取り組みが求められます。
患者との長期的な関係構築を実現するポイント
かかりつけ医として、患者と長期的で信頼に基づく関係を構築するためには、次のようなポイントを意識して取り組むことが重要です。
丁寧で分かりやすいコミュニケーション
・患者が話しやすい雰囲気を作り、症状や悩みを丁寧に聞く姿勢を持つ。
患者情報の継続的な記録と管理
・電子カルテなどを活用して患者の健康状態や治療履歴を継続的に管理し、適切なタイミングでフォローアップを行う。
予防医療や健康教育の積極的な推進
・地域住民向けの健康相談会や勉強会を定期的に開催し、日常的な健康管理や予防活動に積極的に関わる。
医療機関間の連携強化
・必要に応じて専門医療機関へのスムーズな紹介を行い、患者に適切な治療を迅速に提供できる体制を整える。
患者一人ひとりへのきめ細やかな対応
・患者のライフスタイルや家族状況を把握し、それぞれに最適な治療やケアを提供する。
これらのポイントを実践することで、患者が「困ったときはあの医師に相談したい」と感じられるような、信頼性の高いかかりつけ医としての役割を確立できます。
医療提供体制改革が医療機関経営にもたらす影響
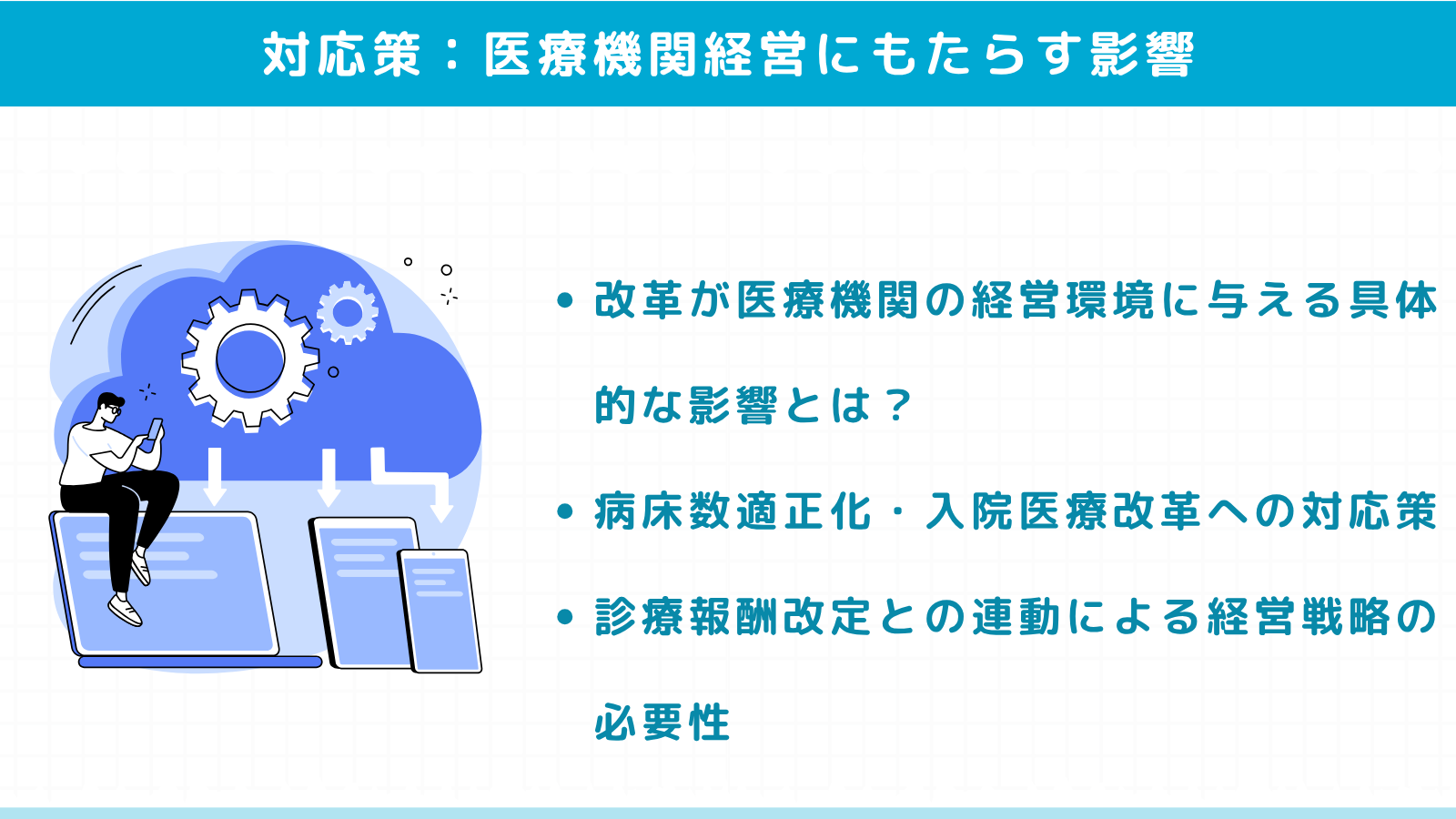
改革が医療機関の経営環境に与える具体的な影響とは?
保険医療2035に示された医療提供体制改革は、地域医療の効率化や医療費の抑制を目指すものであるため、医療機関の経営にも大きな影響を及ぼします。具体的には、入院から在宅医療への移行促進、病床数の適正化などにより、病院経営の収益構造が大きく変化すると予想されます。特に、これまで入院医療を主軸にしてきた病院においては、患者数の変動や診療報酬の見直しによって収益が低下するリスクがあります。
また、地域包括ケアシステムの推進に伴い、在宅医療や訪問診療を実施するクリニックや診療所が経営的に有利となる可能性があります。そのため、これまで入院を中心とした診療を行っていた医療機関も、在宅医療や地域医療との連携を視野に入れた経営戦略を構築する必要が生じます。
こうした環境変化に対応できない医療機関は経営難に陥る可能性もあり、長期的な視野を持った経営改革が必要不可欠となっています。
病床数適正化・入院医療改革への対応策
病床数適正化や入院医療改革に対応するためには、まず自院の入院診療の状況や収益構造を正確に把握し、病床の効率的な運用を図ることが重要です。具体的には、入院期間の短縮を推進するために急性期から回復期、在宅医療への移行をスムーズに進める仕組みづくりが求められます。
また、入院患者の早期退院・在宅復帰を支援するために、地域の介護施設や在宅医療機関との連携体制の強化も欠かせません。病診連携・多職種連携を強化し、患者さんが入院から退院後まで切れ目なくケアを受けられる環境を整えることで、病床の回転率を高めることができます。
さらに、病床機能の明確化や再編を検討し、自院が提供する入院医療の質と役割を明確に示すことが重要です。例えば、急性期病床を減らして地域包括ケア病床や回復期病床へ転換するなど、病院の特性に合わせた最適な病床再編計画を策定し、経営の安定化を図ることが求められます。
診療報酬改定との連動による経営戦略の必要性
医療提供体制改革は、診療報酬改定とも深く関連しています。そのため、医療機関は以下のポイントを意識した経営戦略を構築する必要があります。
診療報酬改定の動向を的確に把握
・最新の診療報酬改定の内容を随時確認し、算定可能な項目を漏れなく算定する体制を構築する。
施設基準の適合を早期に進める
・施設基準が変更・追加された場合、迅速に体制整備を進め、算定可能な報酬を確実に得る。
病院機能の明確化と差別化
・他院との差別化を図るため、病院の特徴や強みを明確化し、それに応じた診療報酬項目の活用を進める。
在宅医療や訪問診療の拡充
・診療報酬改定で在宅医療・訪問診療が評価される傾向にあるため、早期に対応できる体制を整える。
多職種連携の推進
・医師、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師など、多職種連携による診療報酬加算を積極的に算定できる体制を整備する。
これらの取り組みを診療報酬改定と連動させて進めることで、収益性を維持・向上させ、安定した経営を継続することが可能になります。
保険医療2035に向けて医療機関が今から備えるべきポイント
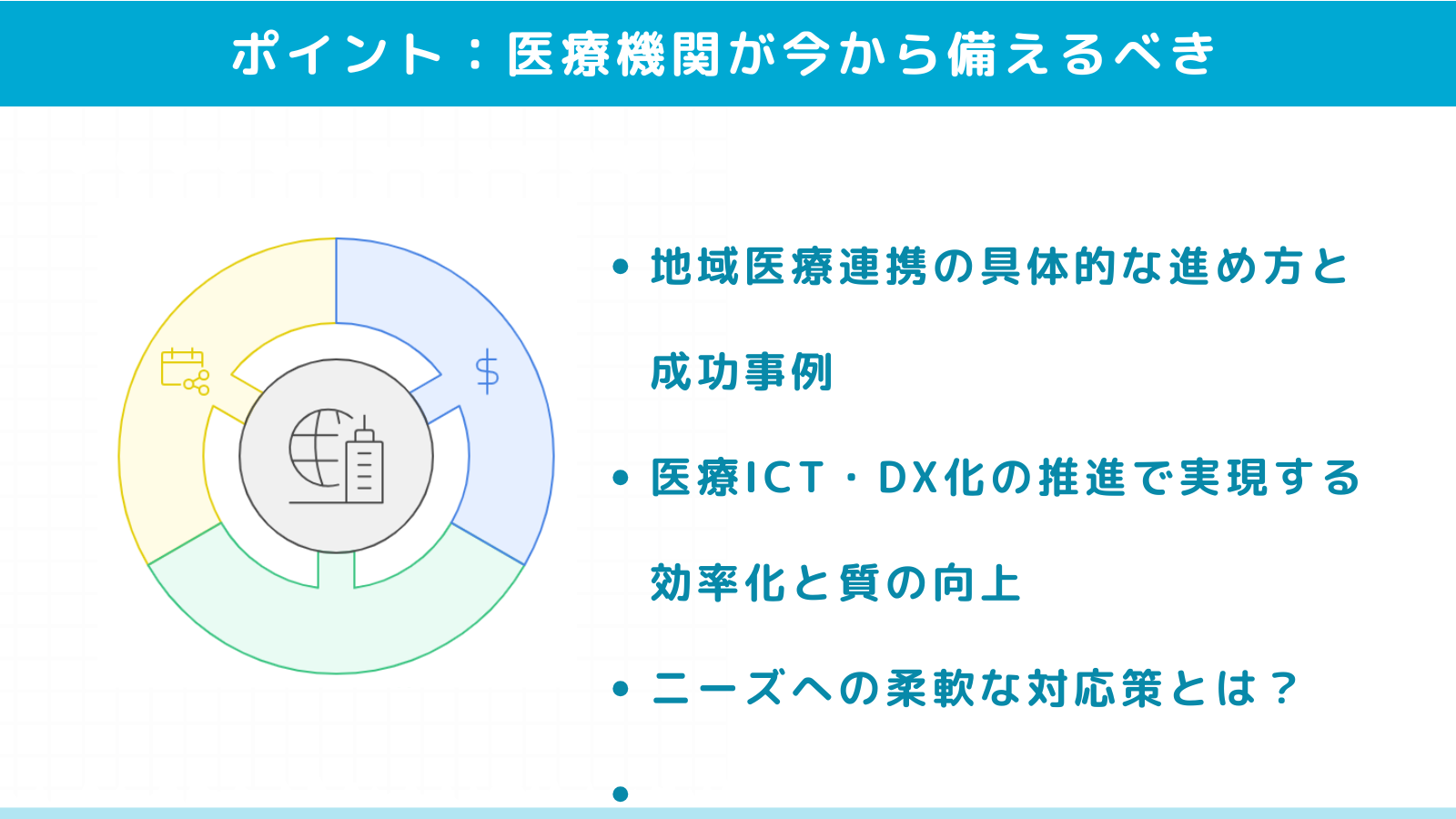
地域医療連携の具体的な進め方と成功事例
保険医療2035において重要なキーワードの一つが「地域医療連携」です。地域医療連携とは、病院やクリニック、介護施設、訪問看護ステーション、薬局など地域の医療・介護に関わる各施設が協力し、患者さんに継続的で包括的なケアを提供する仕組みを指します。
地域医療連携を具体的に進めるには、まず地域内の医療・介護関係者が定期的に情報交換を行う場を設けることが重要です。例えば、地域医療連携推進会議や症例検討会を定期開催し、患者情報を共有するとともに、地域での役割分担や課題解決に向けた議論を進めます。
成功事例としては、地域内の医療機関が共同で電子カルテや地域医療連携システムを導入したケースがあります。この仕組みによって、患者の診療情報をリアルタイムで共有できるようになり、患者さんがどの医療機関を訪れても適切かつ迅速な診療を受けられるようになりました。さらに、退院後の患者の在宅ケアも円滑に進むようになり、患者の満足度や医療の質が大幅に向上したという成果が報告されています。
医療ICT・DX化の推進で実現する効率化と質の向上
医療ICT(情報通信技術)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、保険医療2035が掲げる医療提供体制改革を実現するために欠かせない要素です。これらの取り組みを進めることで、医療機関の業務効率化や診療の質向上が期待できます。
具体的には、電子カルテやオンライン診療システム、AI(人工知能)を活用した診断支援ツールなどを導入することが挙げられます。電子カルテの活用によって情報共有が迅速に行えるようになり、医師や看護師の事務負担が大幅に軽減されます。また、オンライン診療の導入により、患者さんの通院負担が減るとともに、慢性疾患患者の治療継続率の向上にもつながります。
さらにAI技術を導入することで、診断精度の向上や早期発見が可能になり、患者の健康状態の悪化を未然に防ぐことも可能となります。こうしたICT・DXの積極的な導入により、医療機関の生産性や患者サービスの質を向上させ、持続可能な経営体制を整えることができます。
患者の多様なニーズへの柔軟な対応策とは?
保険医療2035では患者の多様なニーズに応えることが求められます。医療機関が患者のニーズに柔軟に対応するための具体的なポイントは以下の通りです。
オンライン診療・遠隔医療の導入
・通院困難な患者の診療アクセス向上や、時間的・地理的制約を軽減する。
訪問診療・在宅医療サービスの拡充
・慢性疾患患者や高齢患者に対して、住み慣れた地域・自宅で診療を受けられる環境を提供する。
予防医療や健康管理サービスの充実
・健診・健康相談・疾病予防サービスを強化し、患者の健康維持・増進に貢献する。
患者向け教育・啓発活動の強化
・医療知識や健康に関する情報を積極的に発信し、患者の自己管理能力や疾病予防意識を高める。
多職種チーム医療の推進
・医師・看護師・薬剤師・リハビリ専門職など、多職種が連携して患者の包括的ケアを提供する。
患者満足度調査や意見収集の仕組み導入
・定期的なアンケートやフィードバックを実施し、患者の声を診療改善に活かす。
こうした取り組みを実践することで、患者中心の医療サービスを提供でき、患者満足度や診療継続性を向上させることが可能になります。
医療人材確保と育成に求められる新たな視点
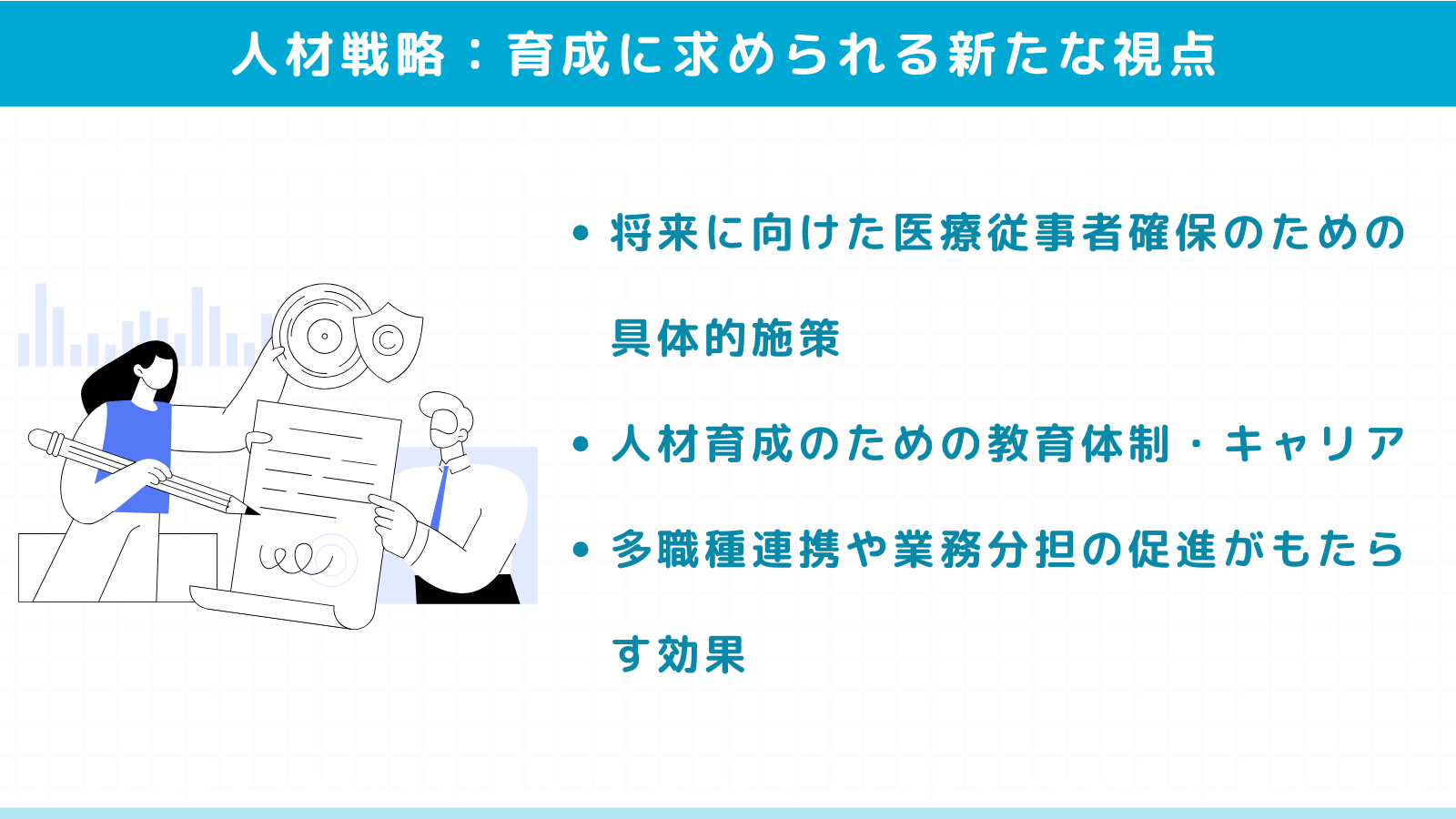
将来に向けた医療従事者確保のための具体的施策
「保険医療2035」の実現には、医療従事者の十分な確保が大前提となります。しかし、少子高齢化が進む日本では、医師や看護師をはじめとする医療人材不足が深刻化しています。このため、医療機関が安定的に人材を確保するための新たな施策が不可欠です。
具体的な取り組みとしては、まず働き方改革の推進があります。勤務時間の柔軟化や短時間勤務制度の導入など、働きやすい職場環境を整備することで離職を防ぎ、安定的な人材確保につなげます。また、子育てや介護との両立支援を充実させることも重要であり、例えば院内保育所の設置や介護休暇制度の整備が効果的です。
さらに、地域間・施設間の人材流動化を促進することも考えられます。地域内の医療機関同士が連携して人材をシェアリングしたり、定期的な研修・交流プログラムを設けることで、地域全体での人材の質向上と定着化を図ることが可能になります。
人材育成のための教育体制・キャリア支援
医療人材確保のためには、単に人数を増やすだけでなく、質の高い人材を育成することも極めて重要です。そのため、医療機関内の教育体制やキャリア支援制度の充実を図ることが求められます。
例えば、新人教育プログラムの導入や、指導医・指導看護師制度の強化を行い、経験の浅いスタッフでも安心して成長できる環境を提供します。また、専門的な技術や知識を体系的に学べる研修プログラムを整備し、スタッフ一人ひとりがスキルアップを図れる体制を構築します。
さらに、キャリア支援としては、個々の職員のキャリアプランに沿った働き方やスキルアップのサポートが重要です。専門医資格や認定看護師資格などの取得を支援する制度や、キャリアアップを促進するための定期的なキャリア面談の実施など、職員のモチベーションを高める工夫が求められます。
多職種連携や業務分担の促進がもたらす効果
医療従事者不足の中、多職種が連携し、適切な業務分担を進めることは不可欠です。その効果的な取り組み例は以下の通りです。
タスクシフト・タスクシェアの推進
・医師業務の一部を看護師・薬剤師・診療補助スタッフへ分担することで、医師の負担を軽減し、医療サービスの効率化を図る。
多職種によるチーム医療の導入
・医師・看護師・薬剤師・栄養士・リハビリスタッフなど、多職種による定期的なカンファレンスやカンファレンス参加を促進し、患者への総合的かつ包括的な医療提供を実現。
多職種合同研修の実施
・異なる職種間で合同研修を実施し、相互理解を深め、連携の質を向上させる。
ICTを活用した情報共有
・電子カルテやクラウド型の地域医療連携システムを導入し、多職種がリアルタイムで患者情報を共有できる環境を整備。
診療補助スタッフの拡充・育成
・医療クラークや医師事務作業補助者を配置し、医師が診療に集中できる環境を整える。
こうした多職種連携や業務分担の取り組みによって、医療機関の診療効率や質が向上し、患者満足度の向上にも大きく寄与します。
患者視点でみる保険医療2035による医療サービスの変化
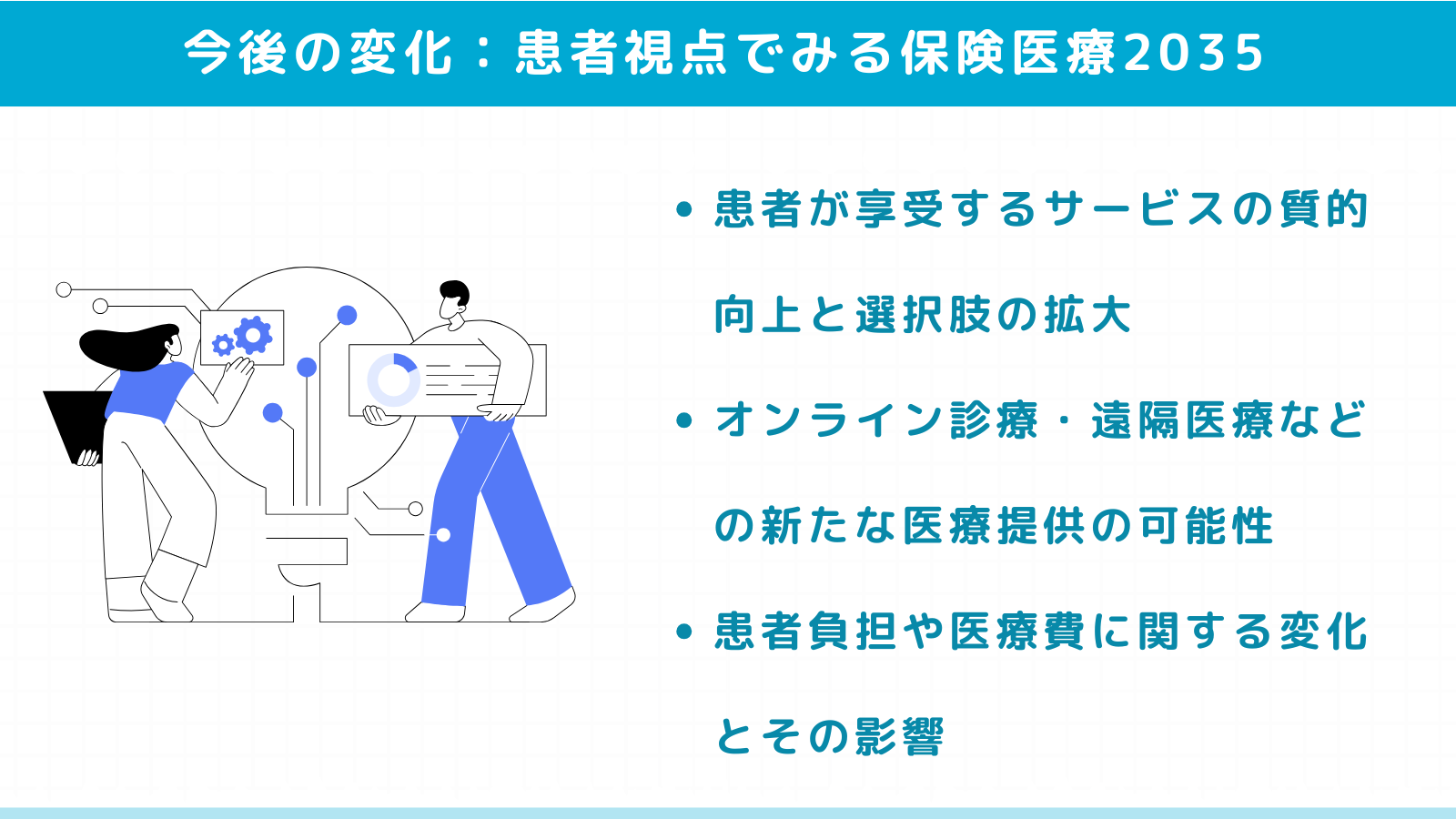
患者が享受するサービスの質的向上と選択肢の拡大
「保険医療2035」が目指す将来像は、患者が自らの意思で多様な医療サービスを選択し、質の高い医療を受けられる環境の実現です。患者中心の医療を進めることによって、患者自身が自分の健康に対して主体的に関わることができ、満足度の高い医療が提供されるようになります。
特に、患者の選択肢が大きく拡大することは重要です。かかりつけ医制度の強化により、自宅近くの信頼できる医療機関で日常的なケアを受けることが可能になるほか、高度な専門医療が必要な場合には、専門病院や専門医を選択しやすい環境が整います。また、自由診療を活用した先進的治療の導入や、予防医療・アンチエイジング医療など、個々のニーズに合わせた医療サービスもさらに充実していくでしょう。
このように、患者が望む医療サービスを主体的に選択できる仕組みが整備されることで、満足度向上だけでなく、医療提供側とのコミュニケーションも円滑化され、医療サービスの質が総合的に高まると期待されています。
オンライン診療・遠隔医療などの新たな医療提供の可能性
近年急速に進展しているオンライン診療や遠隔医療は、「保険医療2035」の重要な柱の一つです。ICTやデジタル技術を活用することで、場所や時間の制約なく診察・相談が可能になり、患者の通院負担軽減や医療アクセス改善につながります。
特に、高齢者や慢性疾患を抱える患者にとってオンライン診療は画期的な仕組みです。遠方に通院しなくても自宅で診察や薬の処方を受けることができ、体調管理や定期的な健康チェックが容易になります。また、都市部に集中しがちな医療資源を地方でも効率的に活用できるため、地方在住の患者が専門医の診察をオンラインで受けることも可能になります。
遠隔医療の活用により、患者一人ひとりがよりきめ細かく継続的な医療サービスを享受できるようになり、医療機関とのコミュニケーションも一層深まることが期待されます。
患者負担や医療費に関する変化とその影響
医療制度改革は、医療費負担や保険料の仕組みにも影響を及ぼします。患者が実際に感じるであろう負担の変化を以下のように整理できます。
予防医療や健康増進活動へのインセンティブの強化
- 健康診断や予防医療を積極的に利用することで保険料割引などのインセンティブが導入される可能性
- 患者自身が健康管理に取り組む動機付けが高まり、医療費の抑制につながる
自己負担額の見直し
- 高齢化や医療費増加を背景に、一定の診療やサービスで患者負担が増加する可能性
- 一方で、必要度の高い医療に対しては負担軽減措置が導入される可能性もあり、メリハリの効いた負担設定に変化
オンライン診療の普及による交通費や通院時間の節約
- 通院の負担が軽減され、間接的な医療費負担が減少する
自由診療・先進医療選択による負担増加の可能性
- 自由診療の選択肢が広がる一方、自己負担で利用する患者の費用負担が増加するケースも
医療費の透明化・可視化が進む
- 医療費の内訳やサービス内容がより明確に示されることで、患者自身が医療費を意識しやすくなり、賢い選択を行えるようになる
こうした負担変化に対しては、患者への十分な説明や情報提供が求められ、納得性の高い医療提供を進めていく必要があります。
医療機関が保険医療2035に対応するための専門家活用法
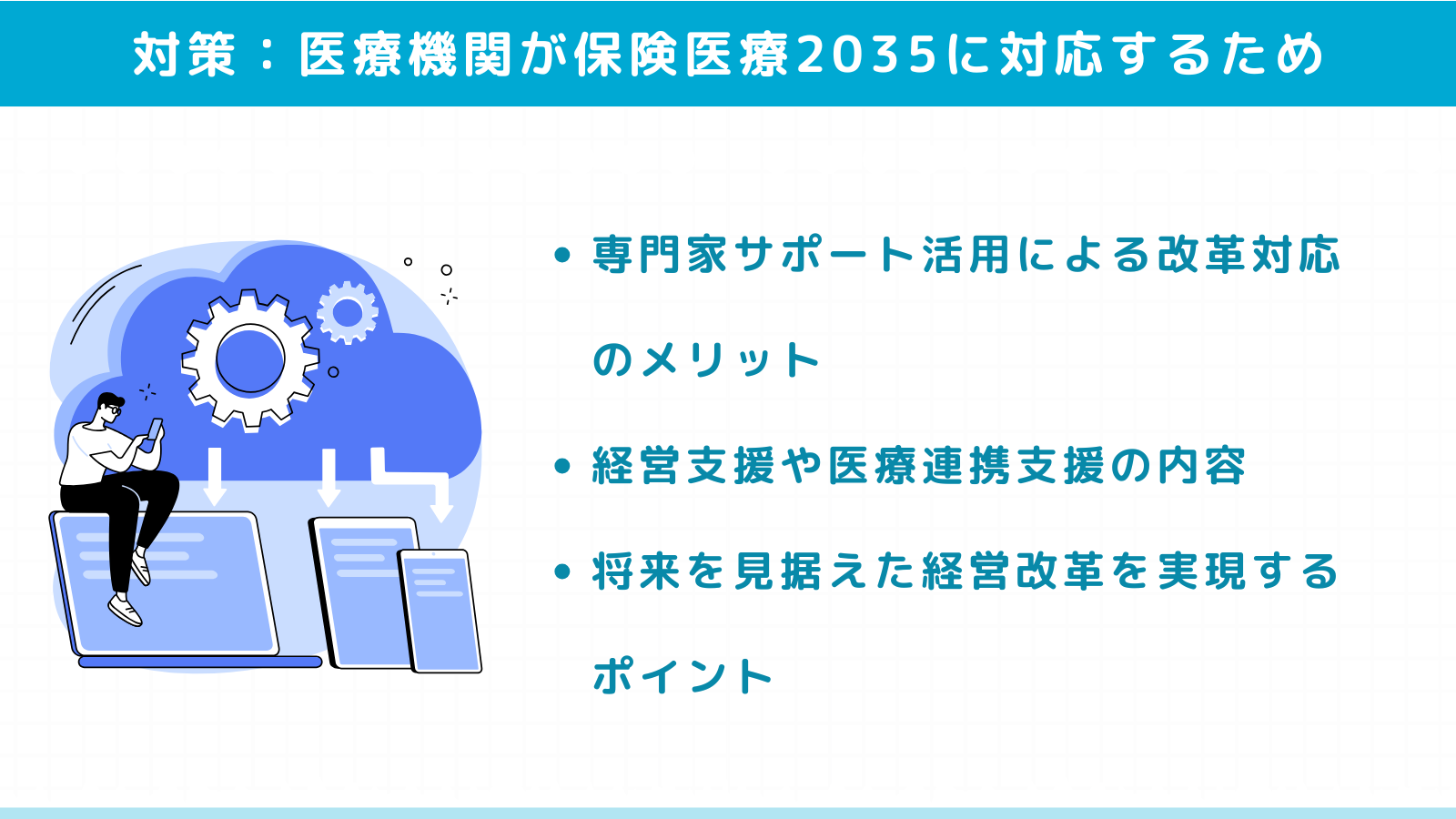
専門家サポート活用による改革対応のメリット
医療制度改革を実現する「保険医療2035」は、医療機関に大きな変革を求めています。しかし、制度改革への対応は複雑で多岐にわたり、自院だけで対処することは容易ではありません。ここで、専門家のサポートを活用することが非常に効果的になります。
専門家を活用する最大のメリットは、改革内容の詳細な理解と自院の具体的な対応策を迅速かつ的確に策定できる点です。医療機関は日々の診療業務で忙しいため、新たな制度や政策動向を継続的にキャッチアップし、それを具体的な行動計画に落とし込むのが難しいのが現実です。専門家の支援を得ることで、改革の最新情報を正しく把握し、自院に最適な方法で対応策を講じることができます。
また、専門家は全国各地の医療機関が抱える共通の課題や成功事例を熟知しています。この知見を活用することで、独自に試行錯誤を繰り返すことなく、より短期間で効率的に改革対応を進めることが可能となります。
さらに、外部の客観的な視点を取り入れることで、組織内の改革への意識を高め、医療スタッフ全員が同じ方向を向いて対応できるような環境整備にも役立ちます。
経営支援や医療連携支援の具体的な内容
専門家の支援を受けることによって、以下のような具体的な経営支援や医療連携支援を受けることができます。
経営戦略支援
- 医療制度改革に伴う経営戦略の策定支援(事業計画の作成、経営改善策の具体化)
- 診療報酬改定への迅速かつ適切な対応策提案
施設基準・届出支援
- 新制度に対応するための施設基準確認・届出支援
- 診療報酬上の新基準への対応策や届出プロセスの支援
ICT・DX推進支援
- 電子カルテ導入やオンライン診療などのICT導入・運用支援
- 医療DX化に向けたシステム整備の計画策定支援
地域医療連携支援
- 地域包括ケアシステム構築に向けた地域内医療機関との連携構築支援
- 病診連携の具体的な仕組みづくりや運用支援
人材育成・人事労務支援
- 医療従事者の人材確保戦略や人事制度設計支援
- スタッフの教育・研修プログラム策定支援
リスク管理・コンプライアンス支援
- 法制度改正に伴うリスク管理体制の構築支援
- 医療広告規制等の法令遵守支援
これらを専門家が伴走支援することで、医療機関は制度改革への対応を確実に進めることが可能となります。
将来を見据えた医療機関の経営改革を実現するポイント
医療機関が「保険医療2035」に対応するためには、目先の課題解決だけでなく、将来を見据えた経営改革を意識することが重要です。そのためのポイントとして、以下の点が挙げられます。
まず、重要なのは「患者中心の医療」を実践する組織文化の醸成です。医療従事者一人ひとりが改革の目的や意義を深く理解し、自発的に患者視点で行動できるような環境をつくる必要があります。
次に、組織内外でのコミュニケーション強化が挙げられます。地域連携・病診連携を推進するためにも、地域医療機関との連絡体制を整備し、情報共有を円滑に進める仕組みを確立することが不可欠です。
さらに、ICTやDX化を通じて、効率的な業務フローの再構築が重要となります。業務効率化によって医療従事者の負担軽減が図られ、本来業務である患者対応に集中できる環境が整います。
そして、専門家の知識や経験を活用することで、常に新しい情報や改革に迅速に対応できる柔軟な組織を構築することが求められます。将来的な医療環境の変化を常に意識し、迅速に対応できる組織体制を確立することが、医療機関の持続可能な発展を支えることになるでしょう。