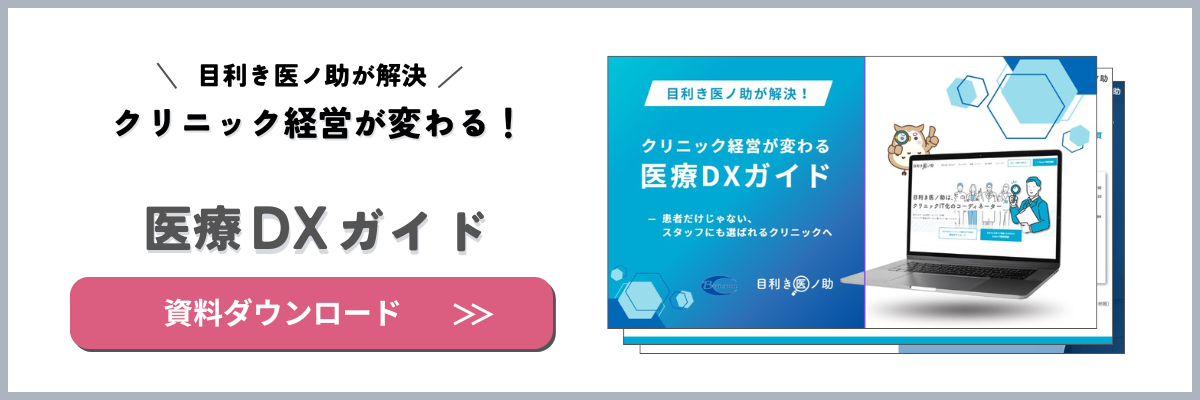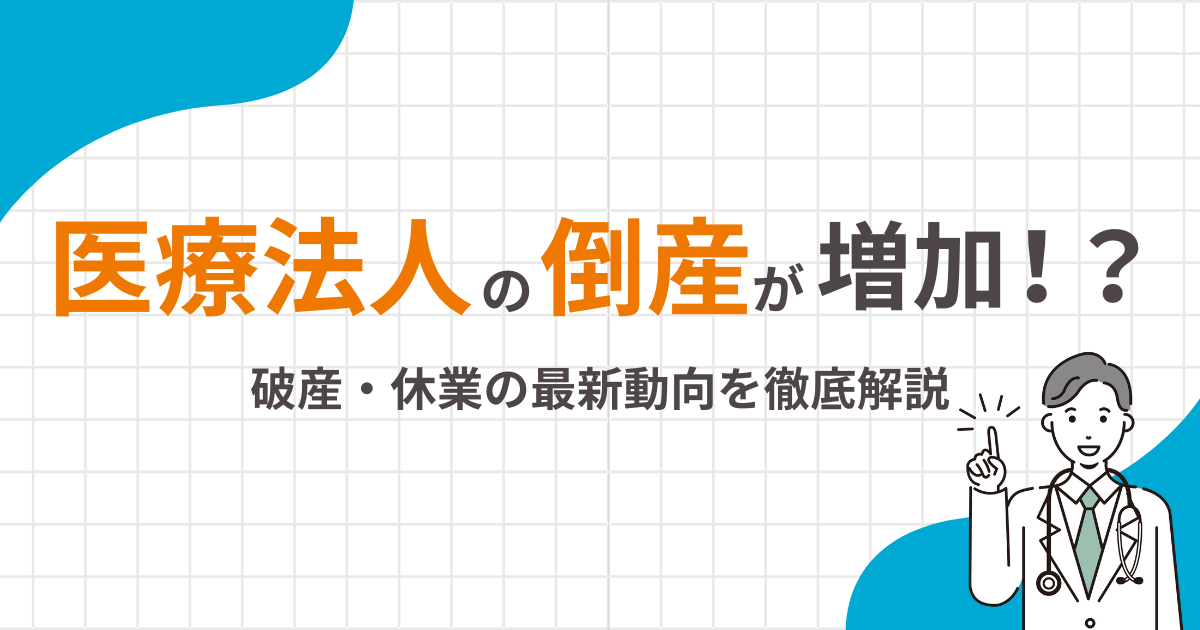
2025.09.26
医療法人倒産が増加?破産・休業の最新動向を徹底解説【目利き医ノ助】
増加傾向にある医療法人の倒産・破産の現状
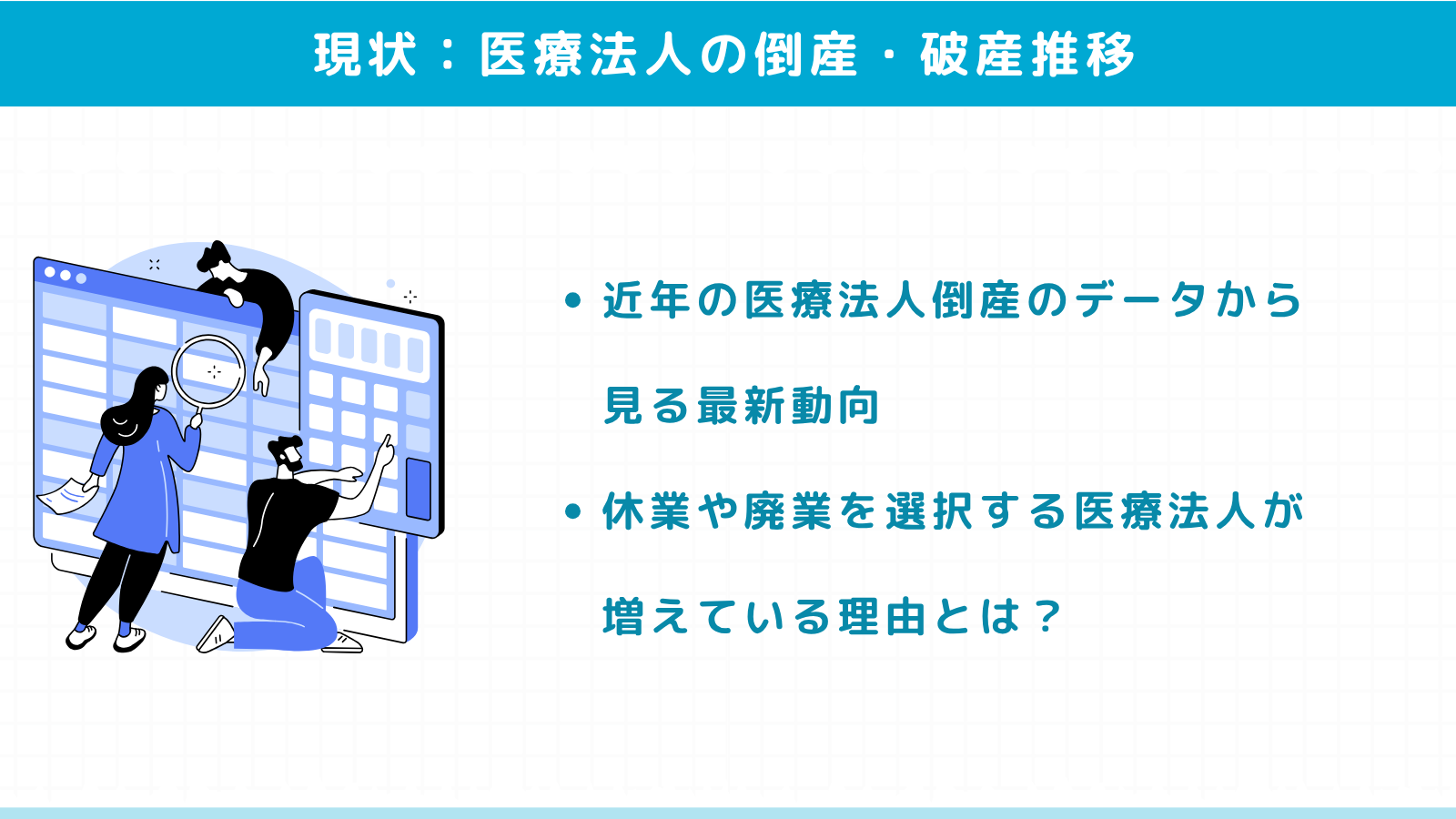
近年の医療法人倒産のデータから見る最新動向
医療法人の倒産・破産件数はここ数年、増加傾向にあります。特に2020年以降、新型コロナウイルスの流行や診療報酬の改定、物価上昇や人件費増加などが重なり、多くの医療法人が経営難に陥っています。帝国データバンクなどの信用調査会社によると、2023年には全国で約70件以上の医療法人が倒産し、過去10年間で最も多い水準となりました。倒産が最も多い診療科目は内科や歯科、整形外科などで、これらの分野では競争の激化に加えて、患者数の減少が顕著なケースが多いことが特徴です。こうした状況のなか、倒産リスクを回避するためには、日頃からクリニックの集客・集患対策にしっかり取り組み、地域や患者さんから支持を集める仕組みづくりが必要です。また、地域別に見ると、都市部における医療法人の倒産は激化した競争によるものが多く、地方では人口減少による患者不足や後継者難に起因する倒産が目立っています。このように、医療法人の倒産・破産の現状は複合的な要素が絡み合った結果として生じており、単一の要因に絞り込めないのが実情です。
休業や廃業を選択する医療法人が増えている理由とは?
近年、倒産に至る前に自主的に休業や廃業を選択する医療法人も増加しています。その主な理由は次の通りです。
経営環境の悪化と収益性の低下
- 診療報酬の引き下げや経費増加により収益が悪化。
- 採算ラインを維持することが困難になるケースが増加。
後継者不足や高齢化問題
- 理事長や院長の高齢化による後継者不在が深刻化。
- 事業承継が困難となり、廃業を余儀なくされる。
患者数減少による集患力低下
- 地域人口の減少や競合の出現によって患者数が減少。
- 新規患者獲得が難しくなり、経営継続を断念。
人材不足やスタッフの離職問題
- 医師や看護師などの専門職の採用難が継続。
- 人件費の高騰により十分なスタッフを確保できなくなる。
医療法人経営者の経営意欲低下
- 経営難が続くことで経営者の精神的・肉体的負担が増大。
- 経営継続への意欲を失い、自主的な廃業を選択する例が多発。
このように、経営継続が難しいと判断された場合には、経営悪化が進む前に自主的な廃業や休業を選ぶケースが増えており、倒産件数に加えて医療法人の休業・廃業も注視すべき動向となっています。
倒産(破産)・休業に至る医療法人の特徴と共通点
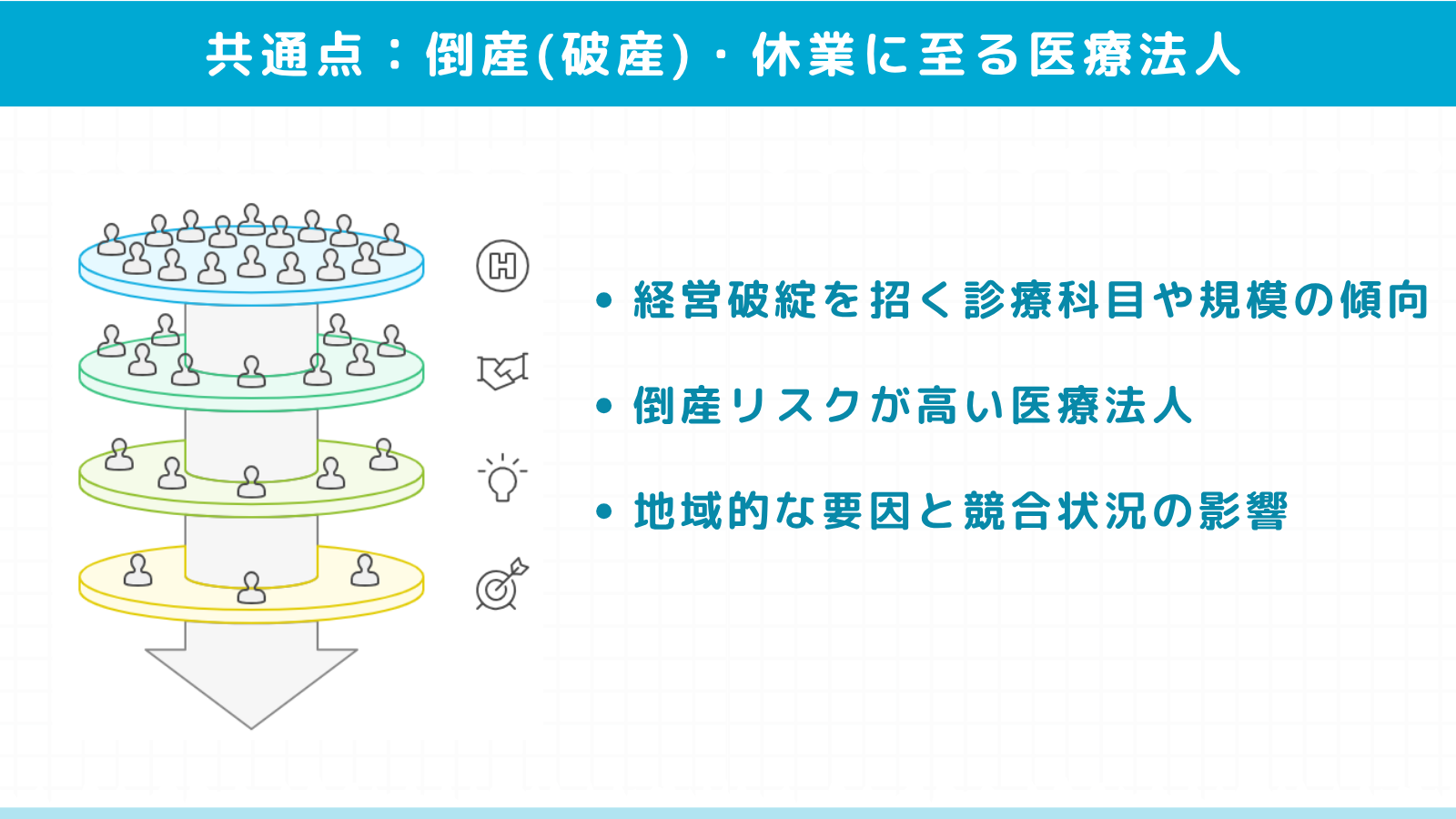
経営破綻を招く診療科目や規模の傾向
医療法人の倒産や休業が相次ぐ背景には、診療科目や法人の規模に一定の傾向があります。まず、特に倒産や休業が多く見られるのが「内科」「歯科」「整形外科」などの診療科目です。これらの科目は市場規模が大きい一方、競争が激しく、患者の獲得競争に負けると経営が急激に悪化しやすい傾向にあります。
特に歯科は新規参入が多く、過剰供給状態になりがちなため、小規模のクリニックが患者数減少による経営難に陥ることが頻繁にあります。また、内科や整形外科などでは、高齢化社会の進展に伴い一定の需要が見込まれるものの、診療報酬の引き下げや医療材料費、人件費の高騰により収益構造が圧迫され、経営が成り立たなくなるケースも目立ちます。
一方で、規模の小さな医療法人ほど経営破綻のリスクが高いことも特徴的です。小規模法人は資金力が乏しく、患者数の減少や突発的な資金繰り問題が発生した場合、短期間で経営破綻に至る可能性が高くなります。このため、小規模な医療法人は特に注意深い経営管理や財務管理が求められるのです。
倒産リスクが高い医療法人の経営パターン
倒産や休業に陥りやすい医療法人には、以下のような共通した経営パターンがあります。
患者獲得策の不足
- 集患施策がなく、地域内での認知度が低い。
- リピーター患者を定着させる施策が不十分。
収支管理の不徹底
- 財務状況の把握が曖昧で、赤字経営に気付くのが遅れる。
- 診療報酬請求のミスが多く、適正な収益を確保できていない。
経営者の独断専行型経営
- 経営者がスタッフの意見を聞かず、独断で意思決定を繰り返す。
- 経営方針が頻繁に変更され、スタッフが混乱し組織が安定しない。
過度な設備投資や借入金依存
- 経営基盤が脆弱にもかかわらず、多額の設備投資を行い負債が膨らむ。
- 借入金の返済負担が重く、資金繰りが破綻する。
人材管理の軽視
- 労働環境が悪化し、離職率が高い。
- 人材不足によるサービス品質の低下で患者離れが進む。
こうしたパターンが複合的に絡み合った結果、経営破綻のリスクが高まるため、日常的な経営改善への取り組みが不可欠です。
地域的な要因と競合状況の影響
医療法人の倒産リスクには、地域的な要因や競合状況も大きな影響を与えます。都市部では競合が多く、患者が医療機関を選ぶ選択肢も豊富であるため、特色のない医療法人は簡単に患者離れを起こします。また、都市部では家賃や人件費など固定費が高いため、経営難に陥った際の負担が一気に重くなりがちです。
一方、地方の医療法人は人口減少に伴う患者数の絶対的な減少が経営を直撃します。高齢化率が高い地域では一定の医療需要はありますが、若年層が減少すると、将来的に患者数が減り続ける懸念があります。特に人口流出が進む地域では、経営環境が急速に悪化するリスクが高く、適切な対策を講じなければ経営破綻の危険性が高まります。
また、地域内での競合医療機関の出現や大規模な病院の進出など、外部環境の急激な変化も経営リスクを高める要因となります。医療法人経営においては、自院の経営努力だけでなく、地域の医療環境や競合の状況を常に把握し、それらの変化に迅速かつ適切に対応できる体制が求められます。
医療法人が倒産・休業に陥る主な原因
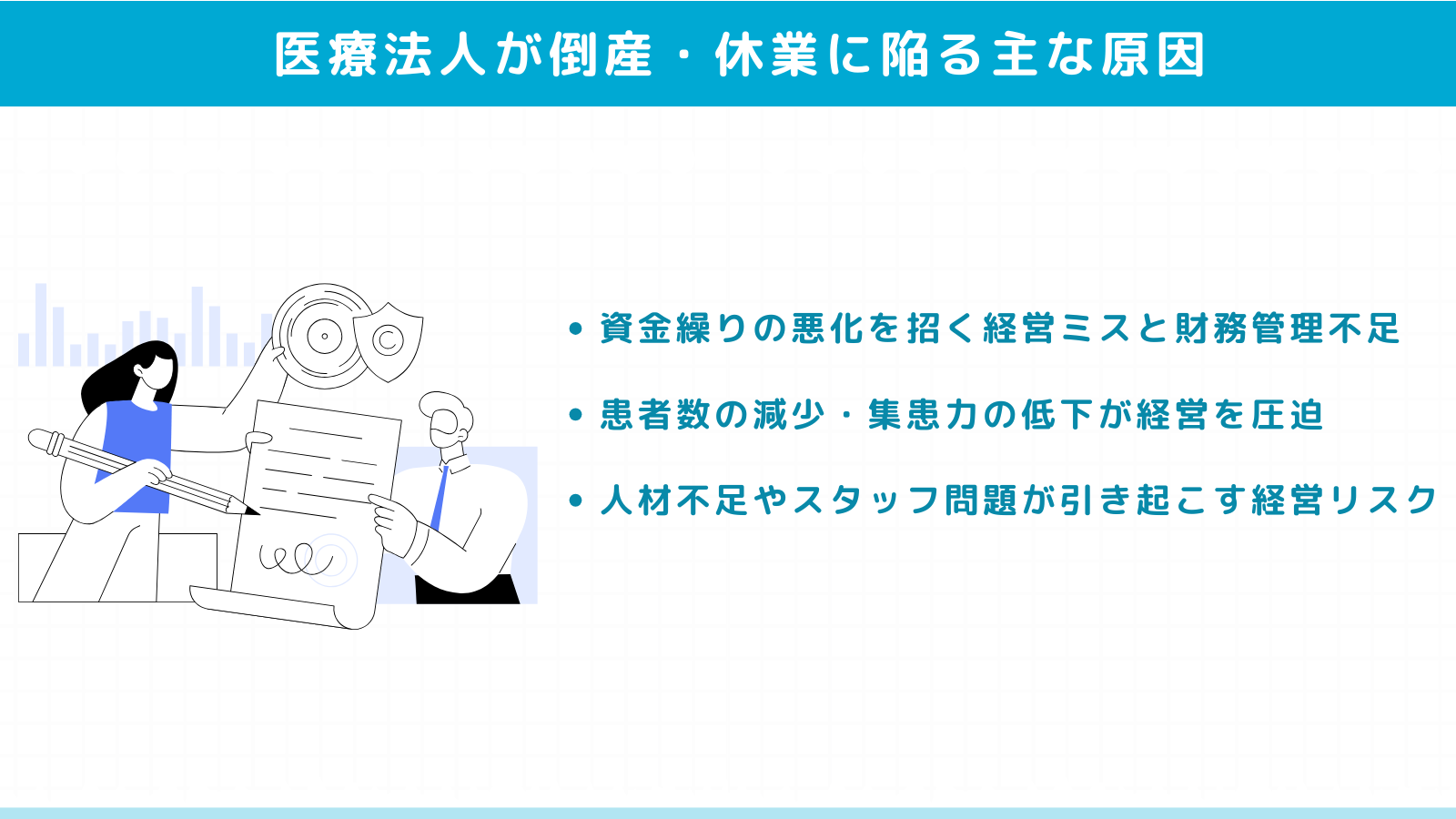
資金繰りの悪化を招く経営ミスと財務管理不足
医療法人が倒産・休業に追い込まれる原因として、まず挙げられるのが資金繰りの悪化で
す。特に資金繰りが悪化する原因の多くは、経営者の経営判断ミスや財務管理の不徹底にあります。
具体的には、過大な設備投資や不必要な医療機器購入によって負債が膨らんだり、日々の資金繰り状況を正確に把握していないために、突然の資金不足に陥るケースがあります。特に経営者が医療現場の運営に集中するあまり、財務状況の管理や資金計画が後回しになってしまい、気がついた時には財務状況が著しく悪化していることも少なくありません。
さらに、診療報酬の請求ミスや未収金管理の甘さから、本来得られるはずの収益が確保できず、経営が次第に圧迫されるケースも多いです。このように、経営上の小さなミスや管理不足が蓄積することで、資金繰りが悪化し、倒産リスクが高まります。
患者数の減少・集患力の低下が経営を圧迫
患者数の減少は、医療法人経営にとって致命的な要素の一つです。特に、近年は競争激化や少子高齢化、人口減少などの外部環境の変化により、安定的な患者数確保が難しくなっています。患者数の減少はそのまま収入減少につながり、固定費を賄うことが難しくなります。
患者が減少する主な理由としては、他院との差別化ができていない、サービスの質の低下、医師やスタッフの退職による診療体制の弱体化、院内環境の悪化などがあります。また、インターネットを通じた情報収集が当たり前になったことで、患者がクリニックを選ぶ基準が高まり、口コミ評価やWebサイトの完成度が集患力に大きく影響しています。
患者数が一定数を割り込むと、資金繰りも急激に悪化し、医療法人の経営を圧迫する原因となります。そのため、常に患者数の変動をモニタリングし、集患力維持のための施策を講じる必要があります。
人材不足やスタッフ問題が引き起こす経営リスク
人材不足やスタッフの問題も、経営を揺るがす要因です。
専門職の人材採用が困難
- 医師や看護師、技術スタッフなどの採用難で診療体制が崩れる。
- 経営悪化が進行し、診療サービスの質も低下する悪循環に陥る。
スタッフの離職率の高さ
- 労働環境が悪く、離職が頻繁に起こり、業務が回らなくなる。
- 新規採用コストや人材育成コストが膨らみ、経営を圧迫する。
人件費の増加
- 採用難の中で給与や待遇を引き上げざるを得なくなり、人件費負担が増加。
- 経営が悪化するとともにスタッフのモチベーション低下を引き起こす。
労務トラブルの発生
- 労働時間や残業代、休暇取得を巡って労務トラブルが発生。
- トラブル対応の負担が増え、本来の診療業務に支障をきたす。
このような人材やスタッフに関する問題は、組織の活力やサービス品質を低下させ、経営リスクを一気に高めます。したがって、人事労務管理を日常的に徹底し、職場環境を整えることが非常に重要です。
経営悪化の兆候を早期に見極める方法
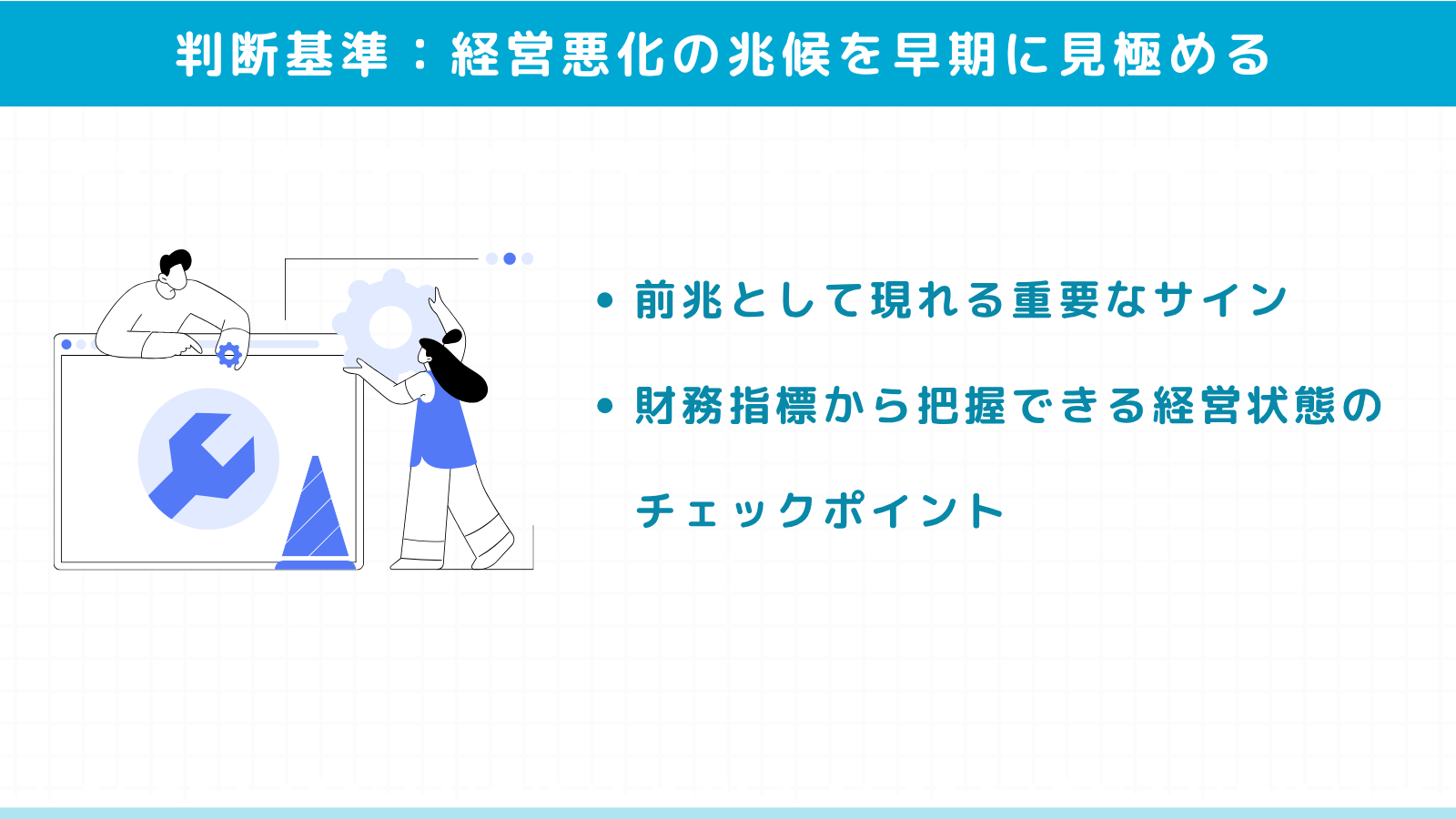
経営危機の前兆として現れる重要なサイン
医療法人が経営悪化を未然に防ぐためには、経営危機の前兆を早い段階で見抜くことが大切です。経営悪化は一気に起こるのではなく、小さな兆候が積み重なって徐々に進行します。そのため、経営者は日頃からそのサインを敏感に察知し、早期に対応策を取る必要があります。
代表的な経営危機のサインとしては、患者数の減少傾向や診療報酬請求の未収金の増加、月次収支の赤字化、スタッフの退職率の上昇、金融機関からの借入依頼の増加などがあります。また、設備投資や経費削減の延期、税金や社会保険料の納付遅延などの資金繰りの兆候も、経営状態が悪化している重要な指標となります。
これらのサインが現れた場合、経営者はすぐに対策を講じる必要があります。放置すると状況が悪化し、対処が難しくなるため、早期発見・早期対応が経営の健全化において非常に重要です。
財務指標から把握できる経営状態のチェックポイント
経営状況を正確に把握するためには、財務指標を日常的にモニタリングすることが不可欠です。特に以下の指標を定期的にチェックし、異常がないか確認しましょう。
収益性指標
- 月次売上高の推移や患者単価の変化。
- 粗利率・営業利益率の推移。
資金繰り指標
- 現金・預金残高の推移と資金余力の有無。
- 未収金や診療報酬請求の滞留状況。
流動性指標
- 流動比率(流動資産 ÷ 流動負債)の低下傾向。
- 当座比率(当座資産 ÷ 流動負債)の悪化。
借入依存度指標
- 負債比率(負債 ÷ 自己資本)の上昇。
- 金融機関からの借入残高の推移。
コスト管理指標
- 人件費比率の推移(人件費 ÷ 売上高)。
- 医療材料費や経費率の変動状況。
これらの財務指標を定期的にモニタリングすることで、経営悪化を未然に防ぎ、安定的な経営状態を維持できます。
患者やスタッフから得られる早期警戒シグナル
経営悪化の兆候は、患者さんやスタッフの日常的な言動や反応からも察知できます。患者さんからのクレームや不満が増加したり、患者のリピート率や紹介数が減少した場合、経営悪化の初期段階である可能性があります。特に患者満足度が下がると口コミ評価が低下し、新規患者の来院が鈍ることにつながります。
また、スタッフのモチベーション低下や離職率の上昇も重大な経営リスクの兆候です。日頃からスタッフとのコミュニケーションを密にとり、彼らの働き方や職場環境についての不満や懸念事項を把握することが重要です。スタッフが不満を感じている状態では、診療サービスの質や患者対応にも悪影響を及ぼし、患者離れを引き起こします。
経営者は、患者さんやスタッフの声に常に耳を傾け、些細な変化でも見逃さない姿勢を持つことで、経営悪化の兆候をいち早く察知し、適切な対策を講じることが可能となります。
倒産を防ぐために押さえるべきリスク管理策
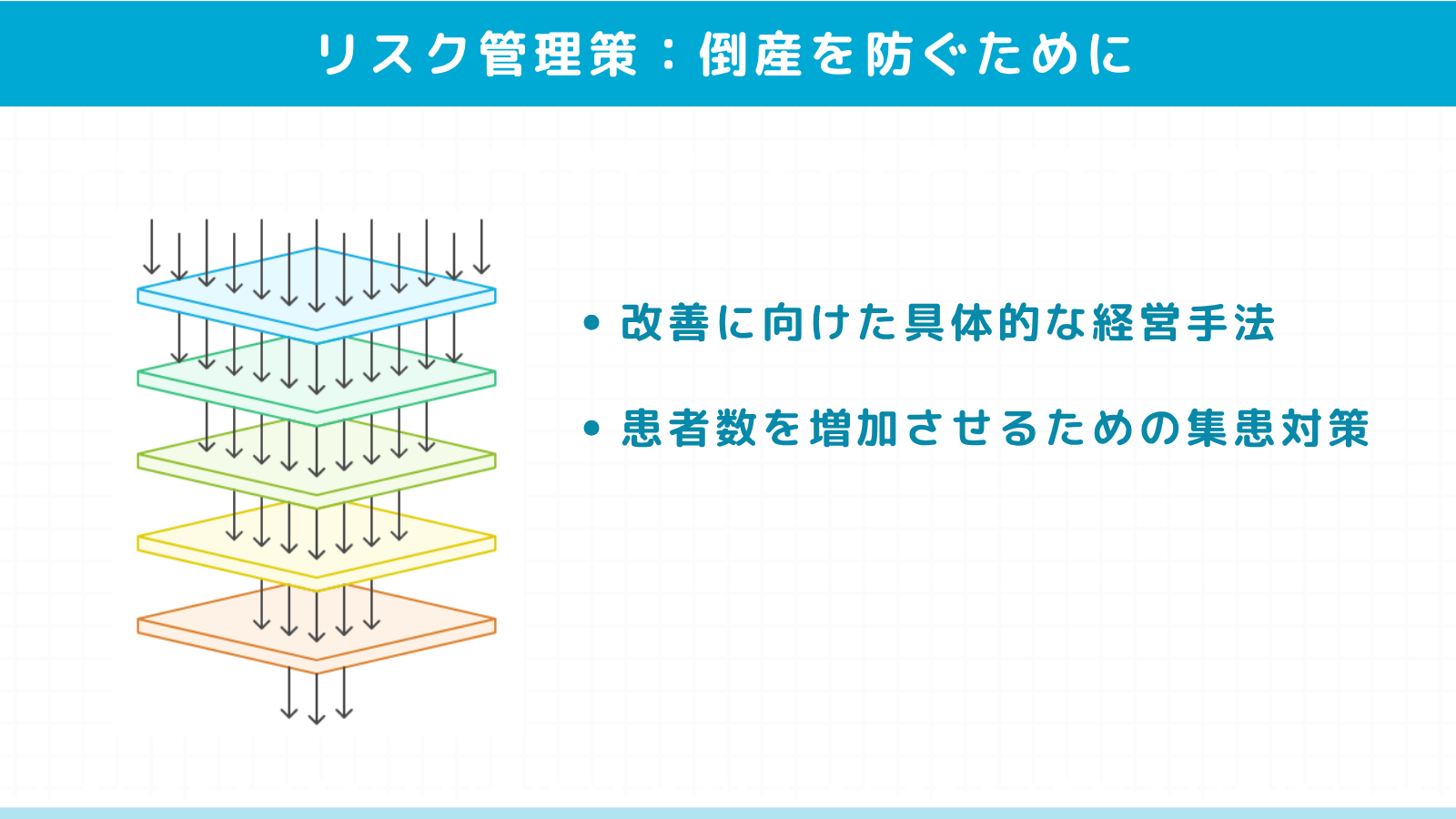
資金繰り改善に向けた具体的な経営手法
医療法人が倒産を防ぐためには、資金繰りを安定させることが最も重要です。具体的には、日々の資金の出入りを正確に把握し、綿密な資金計画を立てる必要があります。資金計画では、短期的・中期的なキャッシュフロー予測を行い、資金が不足しそうな時期を事前に予測して対策を講じることが不可欠です。
また、売上の安定化と診療報酬の未収金回収の徹底が資金繰り改善には大きな効果を発揮します。診療報酬の未収金が発生した場合には、速やかに回収業務を進め、未収金が滞留しないよう管理体制を強化することが求められます。さらに、資金繰りが苦しくなった際には、金融機関との良好な関係構築や緊急融資・リスケジュール交渉などの対応が取れるように、日頃から信頼関係を築いておくことも重要です。
患者数を維持・増加させるための集患対策
倒産を回避するためには、患者数を安定的に維持・増加させる集患対策が必要です。特に以下の施策が有効です。
インターネットを活用した集患
- SEO対策による地域特化型の集患強化。
- ホームページやSNSを利用した情報発信の強化。
患者満足度向上によるリピーター増加策
- 待ち時間の短縮や診療環境の快適化。
- 患者との丁寧なコミュニケーション強化。
地域連携の強化と認知度向上
- 地域のイベントや健康セミナーの開催。
- 地域住民との信頼関係構築。
口コミ促進策の実施
- 満足度が高い患者に口コミ投稿を促す工夫。
- Googleマップなどの口コミサイト活用。
診療サービスの質向上
- 定期的なスタッフ研修で診療レベル向上。
- 他院との差別化となる専門性や特色の確立。
これらを計画的かつ継続的に実施することで、安定的な患者数確保につながり、経営基盤の安定化を図れます。
スタッフの定着率を高める人事労務管理法
人材不足や離職率の高さは、医療法人の経営に深刻な打撃を与えます。スタッフの定着率を高めるためには、労働環境の改善と職場満足度の向上が不可欠です。
具体的な人事労務管理としては、労働時間の適正化、残業の削減、有給休暇取得促進、育児休暇や介護休暇などの柔軟な働き方の整備が挙げられます。また、給与や評価制度の透明性を確保し、スタッフが公正で納得できる評価を受けられるようにすることも重要です。
さらに、スタッフが働きやすい職場づくりを進めるために、定期的な面談や意見交換の機会を設け、スタッフの要望や不満を迅速に吸い上げて改善につなげる仕組みを整えることが効果的です。スタッフ一人ひとりが安心して長く勤務できる環境を提供することが、結果的にサービス品質の向上と患者満足度の向上にもつながり、医療法人の経営安定に寄与します。
経営基盤を安定させるための財務戦略
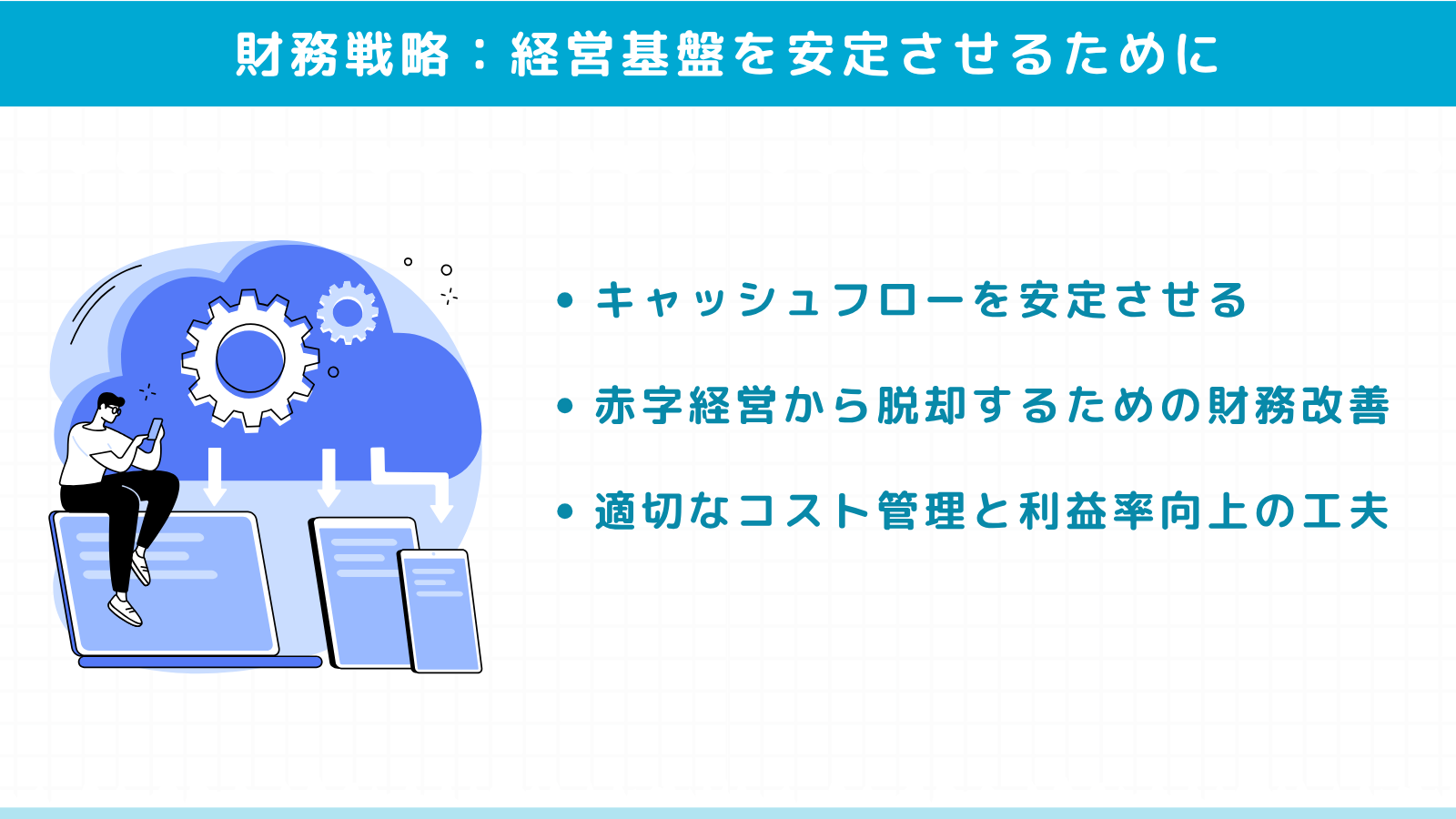
キャッシュフローを安定させるためのポイント
医療法人が経営を安定化させるためには、キャッシュフローを健全な状態に保つことが非常に重要です。特に医療法人の経営では、売上(診療報酬)が入金されるタイミングと、支払いが発生するタイミングがずれるケースが多いため、資金繰りの見通しを正確に立てる必要があります。
キャッシュフローを安定させるためのポイントは、まず現金収入と現金支出の管理を徹底し、資金不足が生じないよう先回りした対策を取ることです。具体的には、毎月のキャッシュフロー表を作成して資金の動きを常に把握し、診療報酬の入金時期や経費支払い時期を調整することで、一時的な資金不足を防ぐことが可能です。
また、急な資金需要に対応するために、一定の資金余裕を常に確保しておくことも重要です。金融機関との良好な関係を維持しておくことで、緊急時の融資対応や支払いリスケジュールなど柔軟な対応が可能となります。
赤字経営から脱却するための財務改善手法
赤字経営が継続すると資金繰りが悪化し、倒産リスクが高まります。赤字経営から脱却するための具体的な財務改善手法としては、以下の方法が挙げられます。
収益改善策
- 患者単価の見直し(自費診療・自由診療メニューの充実)。
- 診療報酬請求漏れの防止と未収金の早期回収。
固定費削減策
- 医療材料費の見直し(購買コストの低減)。
- リースや外注契約の再検討(コストパフォーマンスの改善)。
人件費管理の最適化
- 残業時間の管理徹底と適正な勤務シフト作成。
- 業務効率化や人員配置の見直し。
資金調達・返済計画の最適化
- 金融機関との交渉による借入金の返済条件の見直し。
- 長期的・安定的な資金調達の実施(資本性ローンや長期融資の活用)。
これらの施策を実行し、赤字体質を抜本的に改善することで、安定的な経営基盤を構築できます。
適切なコスト管理と利益率向上の工夫
経営基盤を安定させるためには、コスト管理の徹底と利益率向上への工夫が欠かせません。コスト管理を徹底するには、まず各部門の経費を見える化し、無駄や非効率な支出を明確に特定することが重要です。特に医療材料費や設備維持費などのコストを定期的に見直し、適正な範囲内に抑えることで収益構造を改善できます。
さらに、利益率を向上させるためには、診療報酬単価の高い診療メニューを積極的に展開することや、自院の専門性を高めて患者から選ばれる理由を明確にすることが効果的です。また、自費診療や予防医療、健康診断など、保険診療以外の収益源を拡充することも利益率改善に大きく寄与します。
こうしたコスト管理と利益率向上の施策を計画的に推進することで、持続可能な経営体制を整え、財務の安定化を実現することが可能です。
医療法人の倒産動向(2024年)
2024年、医療法人の倒産件数は64件にのぼり、前年(2023年)と比較して56.0%増加しました。これは、これまで最も多かった2009年の52件を超えて過去最多となっています。倒産の形態としては、破産が62件(96.9%)を占めており、民事再生法による倒産が2件という状況です。
業態別の倒産件数内訳
- 診療所:31件(過去最多)
- 歯科医院:27件(過去最多)
- 病院:6件
特に、小規模な診療所や歯科医院での倒産が目立っています。
主な倒産原因
倒産原因のうち最も多かったのは、収入減少(販売不振)であり、64.1%を占める41件に達しました。具体的には、以下のような原因が挙げられています。
- 新型コロナウイルス関連の補助金削減による収入の急激な減少
- 医療材料費や人件費など運営コストの増加
- コロナ禍での特別融資や補助金返済の開始に伴う資金繰りの悪化
主な医療法人破産事例(2024年)
- 医療法人社団 美実会(東京都)
- 全国展開していた医療脱毛クリニック「アリシアクリニック」を運営。
- 負債総額:72億9,500万円と大規模。
- 関連法人の一般社団法人八桜会も同時に破産、こちらの負債総額は51億7,500万円。
- 債権者数は約9万1,800人に上り、多数の患者が影響を受けた。
- 高橋デンタルオフィス(千葉県)
- インプラント治療や矯正治療を専門とした歯科医院。
- 負債総額:約19億円。
- 前払いの治療費返還訴訟や、患者を巻き込んだ投資・融資案件による訴訟が発生。患者トラブルが財務状況をさらに悪化させ破綻。
- 医療法人社団 アブラハムクラブ(宮崎県)
- 病院運営を主な業務とする医療法人。
- 負債総額:約13億1,200万円。
- 2024年8月に民事再生法の適用を申請。地域の医療供給にも影響が広がった。
- 医療法人 篤信会(長崎県)
- 病院を運営する法人で、2024年6月に破産申請。
- 負債総額:約11億7,000万円。
- 地域における患者数減少が経営悪化を招いた事例。
- 休廃業・解散の増加傾向
倒産以外にも、休廃業や解散を選択する医療法人が増加しています。2024年の休廃業・解散は722件に達し、前年より100件以上増えて過去最多となりました。
- 業態別の内訳
- 診療所:587件(全体の81.3%)
- 歯科医院:118件
- 病院:17件
- 主な要因
- 経営者の高齢化:診療所経営者の54.6%が70歳以上と高齢化が著しく進行している。
- 後継者不在問題:診療所の約50.8%が後継者がいないと回答しており、事業承継が困難な状況が続いている
今後の医療法人倒産動向の見通しと課題
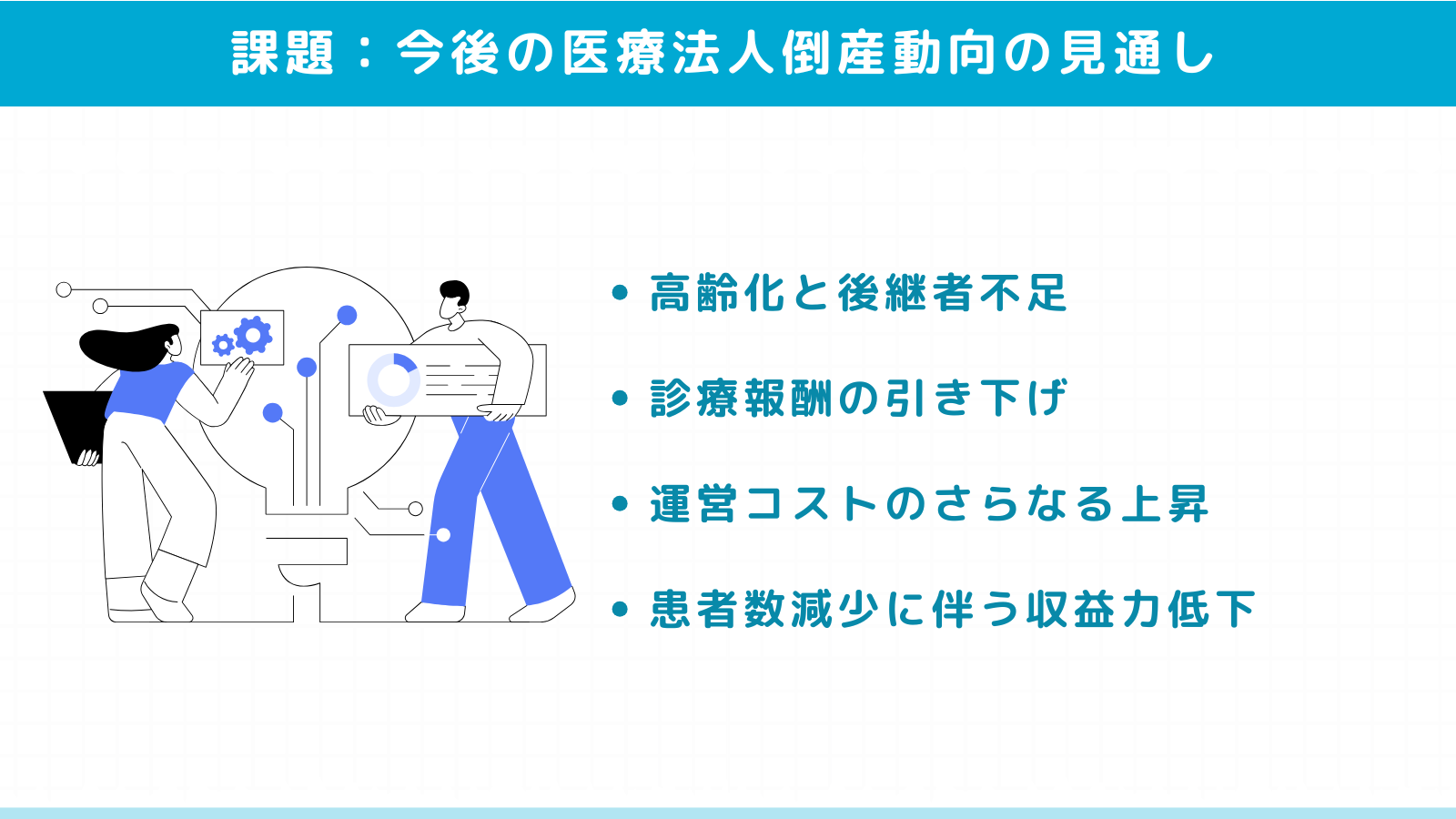
今後も医療法人の倒産や休廃業・解散は増加すると見込まれています。以下のような複合的要因が指摘されています。
- 経営者のさらなる高齢化と後継者不足
- 診療報酬の引き下げや補助金依存体質からの脱却の難しさ
- 医療材料費・人件費など運営コストのさらなる上昇
- 人材確保難や患者数減少に伴う収益力低下
これらの要因は、特に診療所や歯科医院などの小規模な医療機関において深刻であり、地域医療全体への影響も懸念されています。
医療法人が今後生き残り、地域医療を支えるためには、事業承継やM&A、経営効率化など経営の抜本的改革が求められます。また、専門家や外部機関との連携を積極的に行い、経営の見直しや安定化を進めていくことが重要です。
以上のデータや事例は、帝国データバンク、東京商工リサーチ、PR TIMESなどの調査結果を基にまとめられています。これらの動向については、引き続き注意深く見守る必要があります。
今後の医療法人経営に求められる対策と戦略
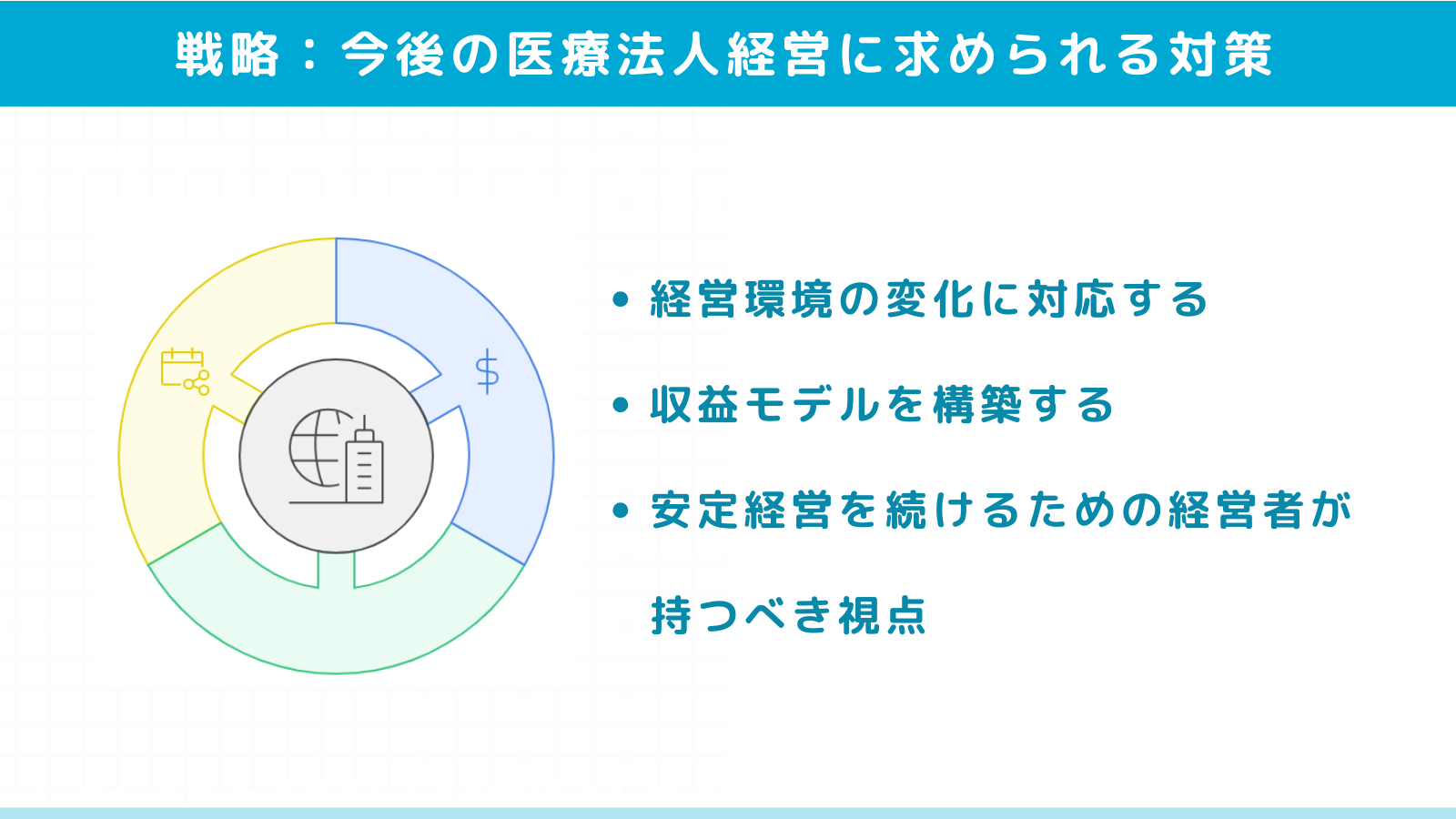
医療法人を取り巻く経営環境は、今後も大きな変化が予想されます。こうした状況下で持続的な経営を実現するためには、これまでの慣習にとらわれない新しい戦略や柔軟な体制づくりが求められます。
経営環境の変化に対応する柔軟な経営体制の構築
経営環境が急激に変化する現在、経営者は「柔軟性」をキーワードとした体制構築が不可欠です。新型コロナウイルスの感染拡大や、診療報酬の見直し、患者ニーズの多様化など、想定外の環境変化にも迅速に対応できる仕組みづくりが求められます。
オンライン診療や予約システムの導入など、ICT活用による業務効率化が挙げられます。また、医師やスタッフがフレキシブルに動けるような組織体制や、患者の需要に応じたサービス提供が可能な柔軟な運営方針を構築することが重要です。
今後の医療法人経営では、従来の固定観念を捨て、環境変化に即応できる組織へと進化することが必須です。
新たな収益モデルを構築するための具体的なアイデア
新たな収益モデルを構築し、収益源を多様化することは経営安定化の鍵となります。以下に具体的な収益モデルのアイデアを挙げます。
自由診療メニューの充実
・美容やアンチエイジング、予防医療分野への進出
オンライン診療の積極的な導入
・患者層を拡大し、診療機会を増加させる
ヘルスケア関連商品の販売
・栄養補助食品や健康管理機器などの取り扱い
企業・団体との提携による新規患者開拓
・健康診断や予防医療の法人契約拡充
サブスクリプション型の健康管理サービス提供
・定額制で継続的な患者囲い込みを実施
こうした新しい収益モデルを取り入れ、従来の診療報酬に依存しない収益体制を構築することが重要です。
安定経営を続けるための経営者が持つべき視点
医療法人経営者が持つべき視点は、「長期的視野」と「患者目線」です。短期的な収益追求だけでなく、5年後、10年後の医療市場の変化を予測し、持続可能な経営基盤を築く必要があります。
特に、患者目線を意識した経営を実践することが重要です。患者満足度の向上や地域社会への貢献を通じて、自然と患者が集まるクリニックづくりを目指しましょう。
また、経営者自身が常に最新の医療トレンドや経営手法を学び、経営判断の精度を高めることも重要です。定期的な専門家やコンサルタントとの意見交換、セミナーや勉強会への参加などを通じて、常に自己研鑽を続ける姿勢が求められます。
医療法人経営を安定させるための専門家サポート活用法
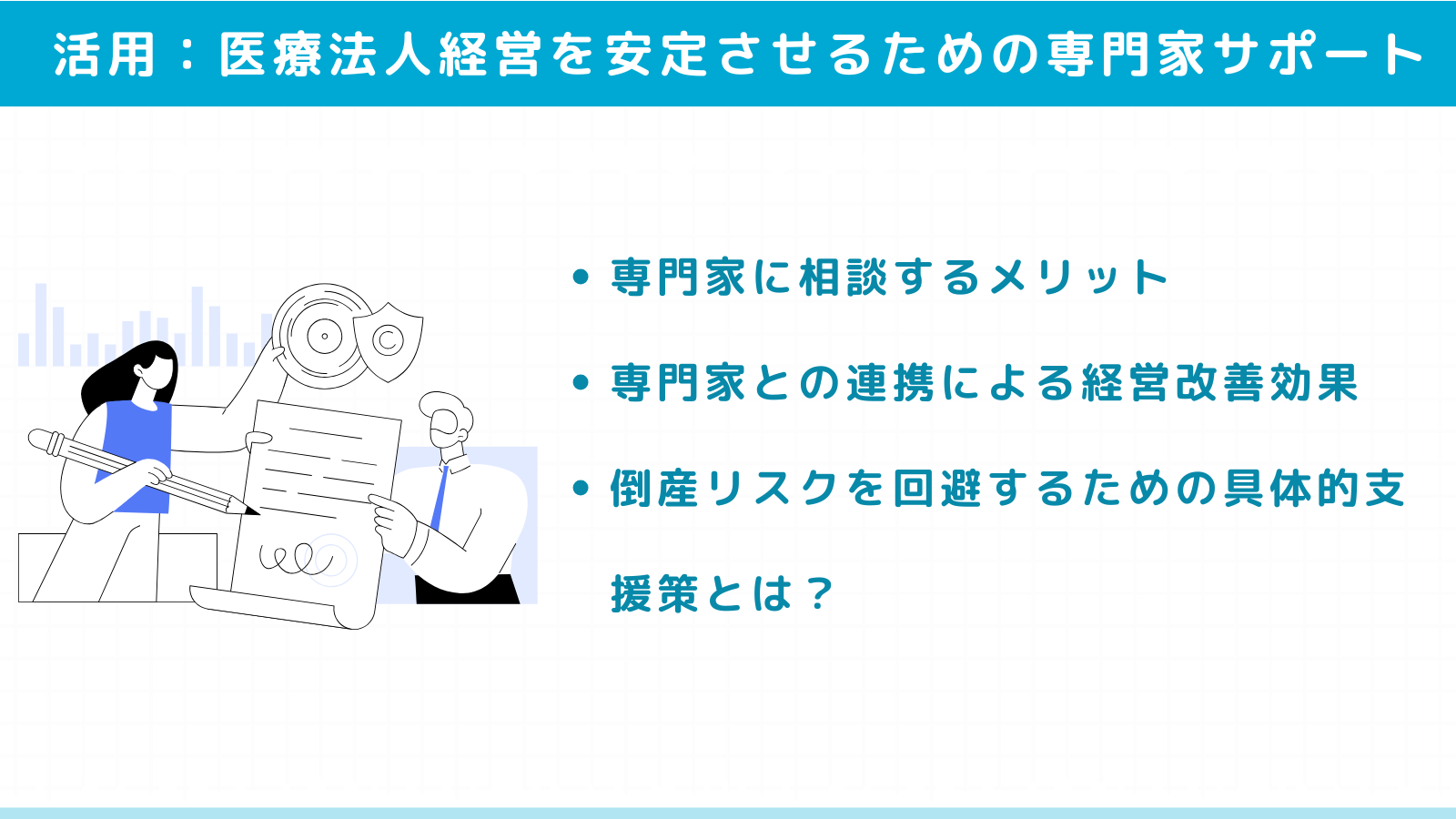
医療法人経営の安定化には、自力で対応するだけでなく、専門的なノウハウを持つ外部専門家を積極的に活用することが有効です。ここでは、専門家サポート活用法について具体的に解説します。
経営リスク管理を専門家に相談するメリット
医療法人経営において、リスク管理は非常に重要です。特に経営や財務の専門家に相談することで、自院では気づけない潜在的な経営リスクを早期に発見できます。専門家の第三者的視点を活用し、財務状況や経営体制を定期的にチェックすることで、経営悪化の兆候を見逃さずに対応が可能となります。
また、専門家の客観的かつデータに基づいた分析により、経営判断の精度が向上し、資金繰りの安定化や収益性の改善が実現できます。
専門家との連携による経営改善効果
専門家との連携による主な経営改善効果は以下の通りです。
財務分析と資金管理の改善
・適切な財務管理体制の構築による資金繰りの安定化
マーケティング・集患施策の最適化
・地域特性を踏まえた患者獲得戦略の策定・実行
スタッフ管理・人事労務問題の改善
・労務トラブルを未然に防ぎ、安定した職場環境を構築
リスク管理体制の強化
・経営リスクの把握と予防策の策定による経営安定化
事業承継やM&Aの円滑化
・事業承継や統廃合をスムーズに進め、持続的な経営を実現
倒産リスクを回避するための具体的支援策とは?
医療法人が倒産リスクを回避するためには、専門家による具体的な支援が効果的です。専門家は、財務状況の分析やキャッシュフローの改善、効率的な資金調達方法の提案を行います。また、具体的な経営改善プランを策定し、実行支援を行うことで、短期間での経営改善が可能になります。
さらに、事業承継やM&A支援を専門家が行うことで、後継者不足問題への対策や統廃合による経営基盤の強化も実現できます。専門家との連携によって倒産リスクを確実に回避し、安定した医療法人経営を継続できる体制を整えることが可能となります。