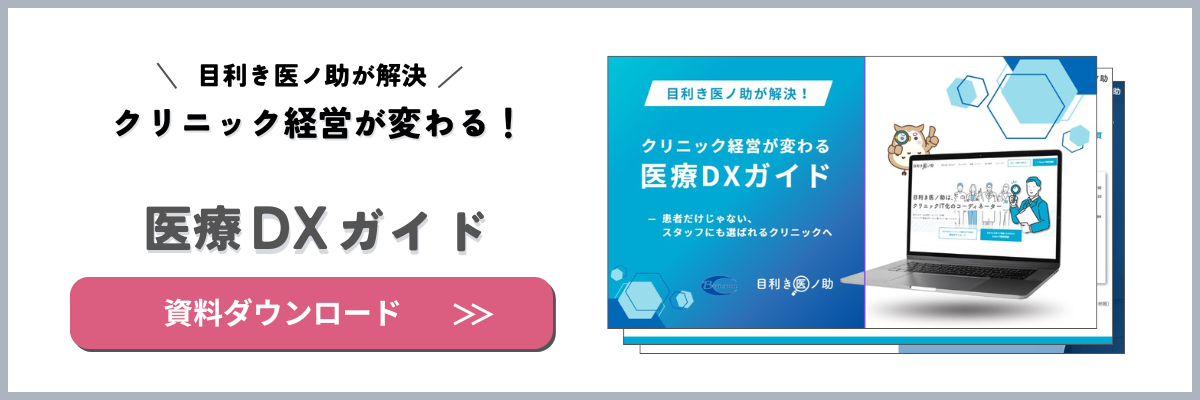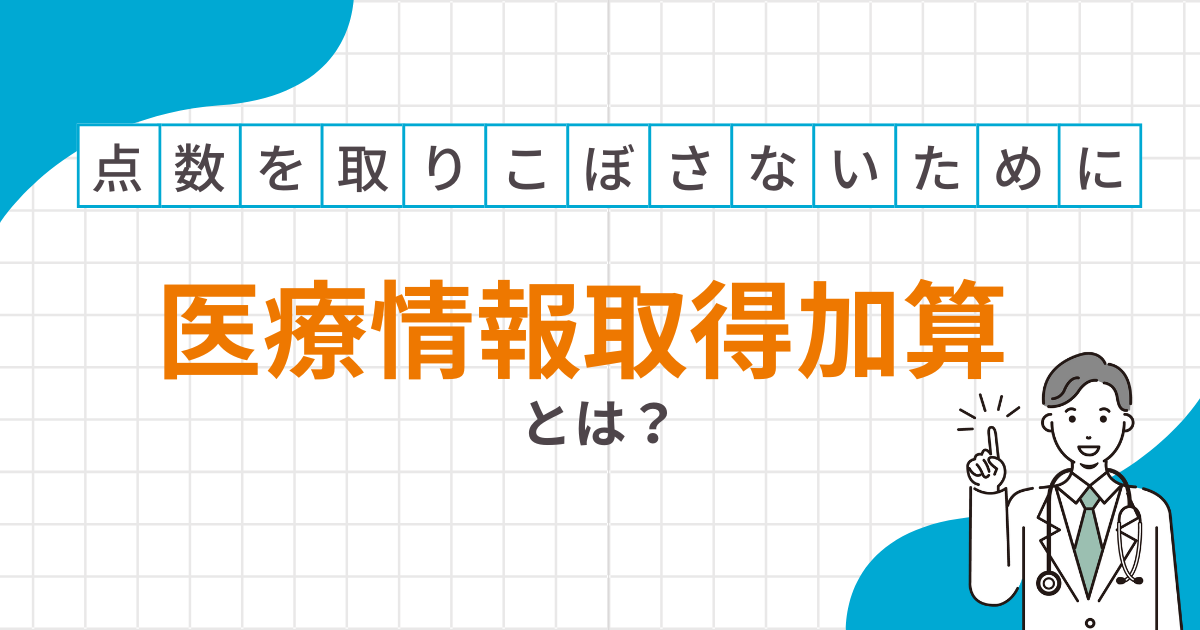
2025.10.17
医療情報取得加算とは?【目利き医ノ助】
医療情報取得加算とは?制度の概要と目的
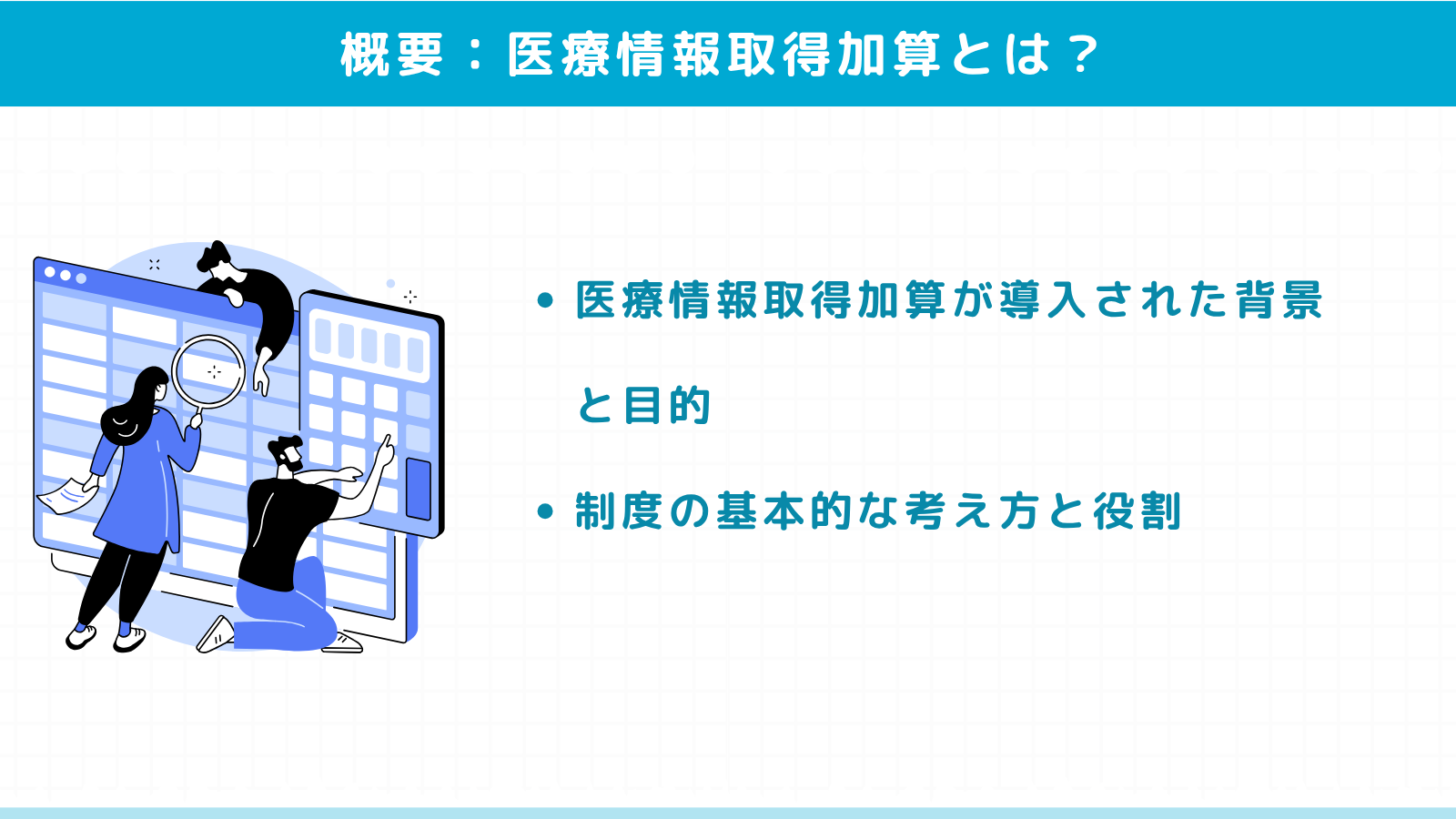
医療情報取得加算が導入された背景と目的
医療情報取得加算とは、患者の過去の診療情報を医療機関間で共有することにより、診療の質の向上を図ることを目的として導入された診療報酬制度の加算項目です。特に近年、医療の高度化や専門化が進む中で、患者が複数の医療機関を受診するケースが増えており、診療情報の共有が十分になされないことによる重複検査や治療の非効率性が問題視されていました。
この問題を解決するため、厚生労働省は医療機関間での診療情報共有を促進する目的で、2022年度の診療報酬改定において「医療情報取得加算」を新設しました。具体的には、患者が別の医療機関で受けた検査や治療内容を正確に把握し、より的確な診断・治療につなげることを目指しています。
また、この制度は患者の安心・安全にも寄与します。例えば、薬の重複投与や副作用のリスクを未然に防ぐことが可能になり、患者にとっても医療の質や安全性が向上するメリットがあります。さらに、情報共有を推進することで、地域医療全体の効率化や医療費の抑制にも貢献することが期待されています。
制度の基本的な考え方と役割
医療情報取得加算の基本的な考え方は、「診療情報の円滑な連携による診療の質向上」です。従来、医療機関間での診療情報の共有は紙ベースで行われることが多く、情報伝達が非効率かつ不十分な場合がありました。この課題を解消するため、電子的な情報共有を推進し、診療の連続性を確保する仕組みとして設けられました。
制度の役割としては、医療機関が他の施設から適切に情報を取得・活用することを促進し、以下のような効果をもたらすことが挙げられます。
患者の診療履歴を迅速かつ正確に把握
・患者が過去にどのような検査や治療を受けたかを迅速に把握できるため、二重検査や不要な処置を避けられ、効率的な診療を提供できます。
治療方針の精度向上
・過去の治療経過や薬剤情報を詳細に把握することで、患者に適した治療方針を立てることができます。特に慢性疾患患者や高齢者の治療管理において大きな役割を果たします。
医療安全の強化
・薬の重複や検査の見落としを防ぎ、医療安全を高めます。また、医療ミスやトラブルのリスクを軽減することにも繋がります。
地域医療連携の強化
・地域内の医療機関間の情報共有が進むことで、地域医療全体の質が向上し、患者にとって安心して医療を受けられる環境が整います。
医療情報取得加算は単なる診療報酬上の加算項目に留まらず、地域医療全体の連携強化と診療効率化を促進する重要な役割を担っています。
医療情報取得加算の算定条件と具体的な内容
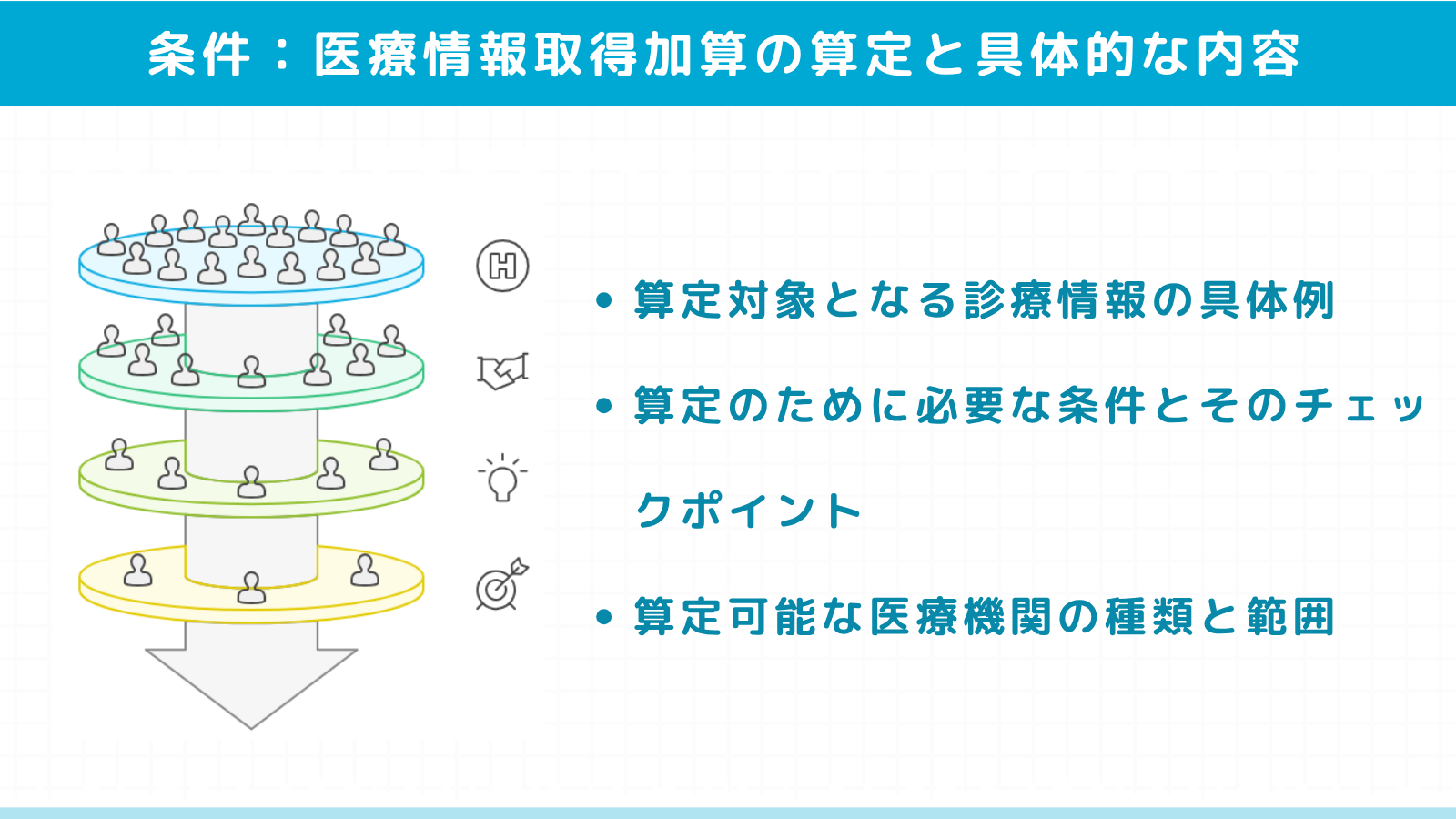
算定対象となる診療情報の具体例
医療情報取得加算を算定するためには、特定の診療情報を適切に他医療機関から取得し、診療に活用する必要があります。その対象となる情報の具体例としては、以下が挙げられます。
まず、最も基本的なのが検査結果や画像診断情報です。例えばCTやMRIなどの画像データや血液検査、生化学検査、病理検査などの検査結果を取得することが該当します。これらを共有することで重複検査を回避でき、迅速かつ正確な診断に役立てることができます。
次に、薬剤情報や処方歴も算定対象となります。患者が現在服用している薬の情報を把握することで、薬の重複や薬剤相互作用による副作用リスクを避けることができます。特に高齢者や慢性疾患を抱える患者の治療において、この情報は非常に重要となります。
さらに、過去の治療歴や入退院情報、手術歴などの診療経過情報も対象となります。例えば、過去の手術内容や入院時の治療経過を把握することで、治療方針を迅速に立てることが可能になり、患者の治療継続性が向上します。
また、アレルギー情報や感染症情報など、患者の安全管理に関わる重要情報についても積極的な取得と活用が求められます。
算定のために必要な条件とそのチェックポイント
医療情報取得加算を適切に算定するためには、次のような条件を満たす必要があります。
患者の同意を取得していること
- 診療情報を取得・活用することに関して、患者本人の同意を明確に得る必要があります。
- 同意は書面または電子的に記録として残しておくことが推奨されます。
他の医療機関からの情報を適切に取得・保管していること
- 情報取得の経路や方法を明確にし、適切な電子カルテなどで管理・保管します。
- 情報の授受の記録を残し、後日の確認や監査に備えることが重要です。
取得した情報を診療に実際に活用していること
- 取得した情報を診療プロセス内でどのように活用したかを明確に電子カルテ等に記録しておきます。
- 活用例として、検査省略、治療方針決定の根拠などが挙げられます。
施設基準を満たしていること
- 医療情報取得加算を算定するには、厚生労働省が定める施設基準を満たしていることが必要です。
こうした条件を正しく満たしているかを定期的にチェックし、算定漏れや誤りが起こらないような体制を整えておくことが大切です。
算定可能な医療機関の種類と範囲
医療情報取得加算は、全ての医療機関が一律に算定できるわけではなく、一定の基準を満たした医療機関が対象となります。
具体的には、主に電子カルテなどを導入して診療情報の電子的管理ができ、かつ地域医療連携を積極的に推進している医療機関が算定可能とされています。例えば、以下の医療機関が対象になることが多いです。
一般病院や大学病院
特に地域医療連携の中心となっている中核病院は、診療情報の取得と活用が重要な役割を担っています。こうした病院では、積極的な加算算定が推奨されています。
地域医療支援病院
地域の診療所やクリニックからの診療情報取得を積極的に進め、地域全体の医療質向上を支援しています。そのため、この加算を効果的に活用できます。
診療所やクリニック
地域密着型の診療所や専門クリニックにおいても、他医療機関との連携強化や患者の継続的な診療管理に医療情報取得加算が役立ちます。ただし、施設基準を満たす必要があります。
なお、算定する医療機関は患者からの診療情報取得を推進し、地域医療全体での情報共有に積極的に取り組む姿勢を明確にすることが求められます。そのため、算定可能な医療機関であっても、施設基準や運用条件をしっかりと満たす努力が必要です。
医療情報取得加算の施設基準とは?
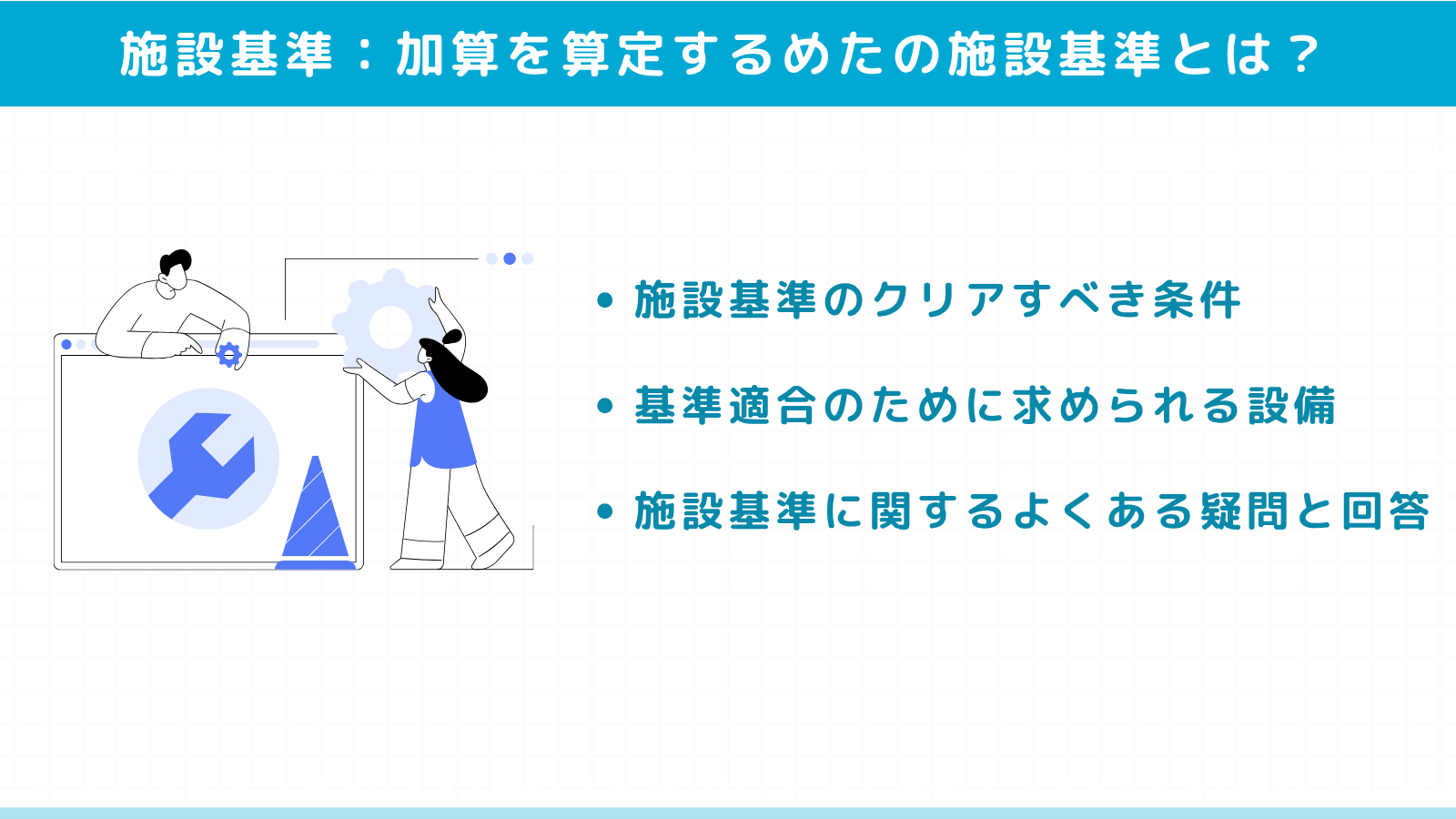
施設基準の具体的内容とクリアすべき条件
医療情報取得加算を算定するためには、厚生労働省が定める特定の「施設基準」を満たす必要があります。施設基準とは、加算を適切に運用し、診療情報を適切に管理・共有できる体制が整っているかを判断する基準です。
施設基準の具体的な内容として、まず挙げられるのが「電子カルテの導入と診療情報の電子的な管理体制」です。電子カルテを導入し、他の医療機関から取得した診療情報を電子的に適切に記録・管理できることが求められます。
また、「地域医療連携ネットワークへの参加」も重要な基準の一つです。地域内の医療機関間で情報をスムーズに共有できる仕組みに参加していること、またその仕組みを活用し情報を定期的に取得していることが求められます。
さらに、「個人情報の適切な管理と保護体制の整備」も必須条件です。個人情報保護法やガイドラインに基づき、患者の診療情報を安全かつ適切に管理・運用できるセキュリティ体制が整備されていることが必要です。
こうした施設基準を満たすことで、患者の診療情報を適切に取得・活用でき、診療の質の向上や地域医療連携の強化につながります。
基準適合のために求められる設備や体制
施設基準をクリアし、医療情報取得加算を算定するには、以下のような具体的な設備や体制を整備することが重要です。
電子カルテシステムの導入と運用体制
- 他医療機関から取得した診療情報を安全に保管・管理できる電子カルテシステムの導入。
- 電子カルテを操作できるスタッフの教育と運用体制の確立。
地域医療連携システム(ネットワーク)への参加
- 地域の医療機関間で情報交換を行えるオンラインシステムへの参加。
- 情報連携ネットワークを常に適切に使用できる環境整備と運用支援。
情報セキュリティ対策と個人情報保護体制の確立
- 患者情報を適切に保護するためのセキュリティ対策(アクセス制限、パスワード管理、バックアップ体制)。
- スタッフへの個人情報保護教育の定期的な実施。
診療情報取得・活用マニュアルの整備
- 情報取得から診療活用までの流れを記載した具体的な運用マニュアルの作成と運用徹底。
- 運用マニュアルに基づく定期的なモニタリングと改善体制。
こうした設備や体制を具体的かつ確実に整備することで、施設基準の適合性が高まり、加算の算定が可能になります。
施設基準に関するよくある疑問と回答例
施設基準に関しては医療機関からの質問が多く寄せられます。代表的な疑問と回答例を以下に紹介します。
【Q1】電子カルテを導入していれば、施設基準はクリアできますか?
【A1】電子カルテ導入だけでなく、地域医療連携ネットワークへの参加や個人情報管理体制の整備など、複数の基準を総合的に満たす必要があります。単なる電子カルテ導入だけでは不足する場合が多いです。
【Q2】地域医療連携ネットワークがない地域では算定は不可能でしょうか?
【A2】地域連携ネットワークが未整備の場合でも、個別の医療機関同士で情報交換の取り決めを作り、電子的に診療情報をやり取りしている場合は、施設基準を満たすことがあります。厚生労働省や自治体の指針を確認することが重要です。
【Q3】施設基準の適合性は定期的に審査されますか?
【A3】施設基準は定期的な届出・報告が求められる場合があります。また、診療報酬改定時や監査時に適合性が確認されることもあるため、常に適合基準を維持する体制を整えることが求められます。
施設基準に関する理解を深め、継続的に管理・整備を行うことで、医療情報取得加算の適正な算定が可能になります。
医療情報取得加算導入による医療機関側のメリット
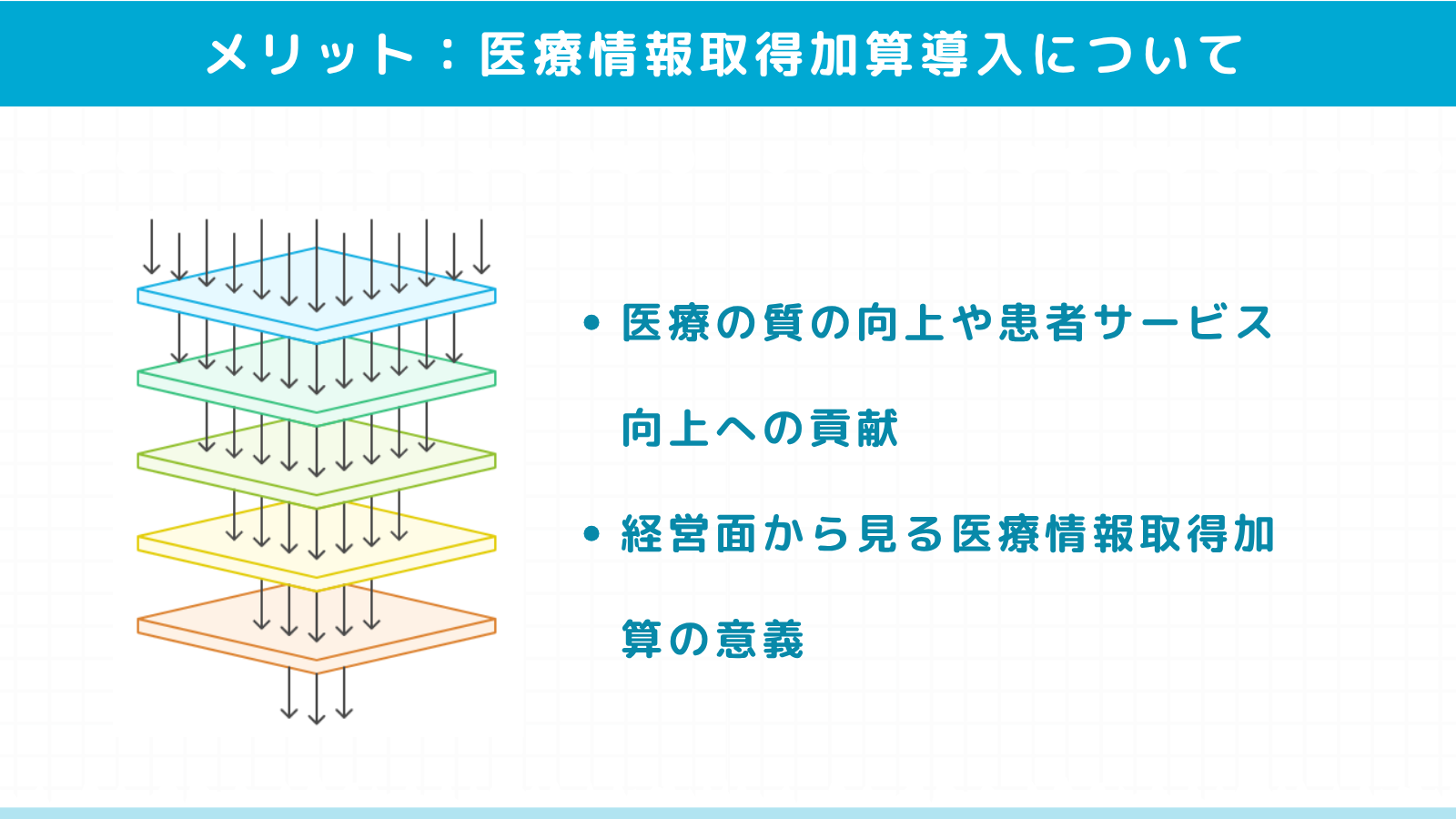
医療の質の向上や患者サービス向上への貢献
医療情報取得加算の導入は、診療報酬の向上にとどまらず、医療機関全体の医療の質や患者サービスの改善にも大きく寄与します。具体的には、患者が他院で受けた治療履歴や薬剤情報を的確に把握できるため、重複処方や不要な検査の防止、適切な治療方針の立案につながります。
例えば、患者が複数の医療機関を受診している場合、それぞれの病院の診療情報を一元的に管理・参照できれば、患者の治療歴をより正確に把握できます。その結果、患者ごとに最適化された診療計画を立てることができ、患者満足度や診療の効果も大きく向上します。
また、情報が電子的に共有されるため、診療時の情報伝達ミスや紙カルテの管理負担が軽減され、医師やスタッフの業務効率も改善します。さらに、こうした質の高い診療やスムーズな情報管理体制は、患者からの信頼感や評判の向上にもつながりクリニックの集客・集患対策にも貢献します。このように医療情報取得加算の導入は、単に報酬加算を目的とするのではなく、患者サービスの質を高め、診療全体の品質向上を図る上で重要な役割を果たします。
経営面から見る医療情報取得加算の意義
経営的な観点から見ても、医療情報取得加算の導入は非常に重要です。算定要件を満たすことにより、診療報酬収入が安定的に増加し、経営の安定化につながります。
また、地域医療連携が強化されることにより、自院が地域の中で信頼される医療機関としての地位を確立しやすくなります。他院とのスムーズな情報連携が可能になると、地域の医療ネットワークの中でより積極的な役割を果たすことができ、患者の紹介や連携案件も増えることが期待されます。
さらに、電子カルテや情報連携システムの活用は業務効率化にも直結します。結果として人件費や時間的コストの削減が実現し、経営リソースを有効活用できるようになります。
業務効率化や診療の質向上の具体的効果
医療情報取得加算の導入によって、医療機関における業務効率化や診療の質向上が具体的にどのように実現するのか、以下のような効果が挙げられます。
情報共有の迅速化と効率化
- 電子的な情報連携により、患者情報の取得にかかる時間や手間を大幅に削減できる。
- 患者来院前に情報を把握でき、診察の準備が円滑になる。
不要な検査や投薬の削減
- 他医療機関での検査や処方情報を把握できるため、重複処方や不要な検査が避けられる。
- 医療費の削減にもつながり、患者満足度も向上する。
診療の精度向上
- 過去の診療情報を活用して、より精度の高い診療計画や治療方針を立案できる。
- 医療ミスの予防や診断精度の向上につながる。
患者満足度の向上
- 他院との情報共有により、患者が同じ説明や検査を繰り返さなくて済む。
- 医療提供のスピードアップと質的向上で患者満足度が高まる。
このように医療情報取得加算は、日々の診療活動の中で明確で具体的な業務効率化や診療品質向上の効果をもたらします。
医療情報取得加算を活用する際の注意点とリスク
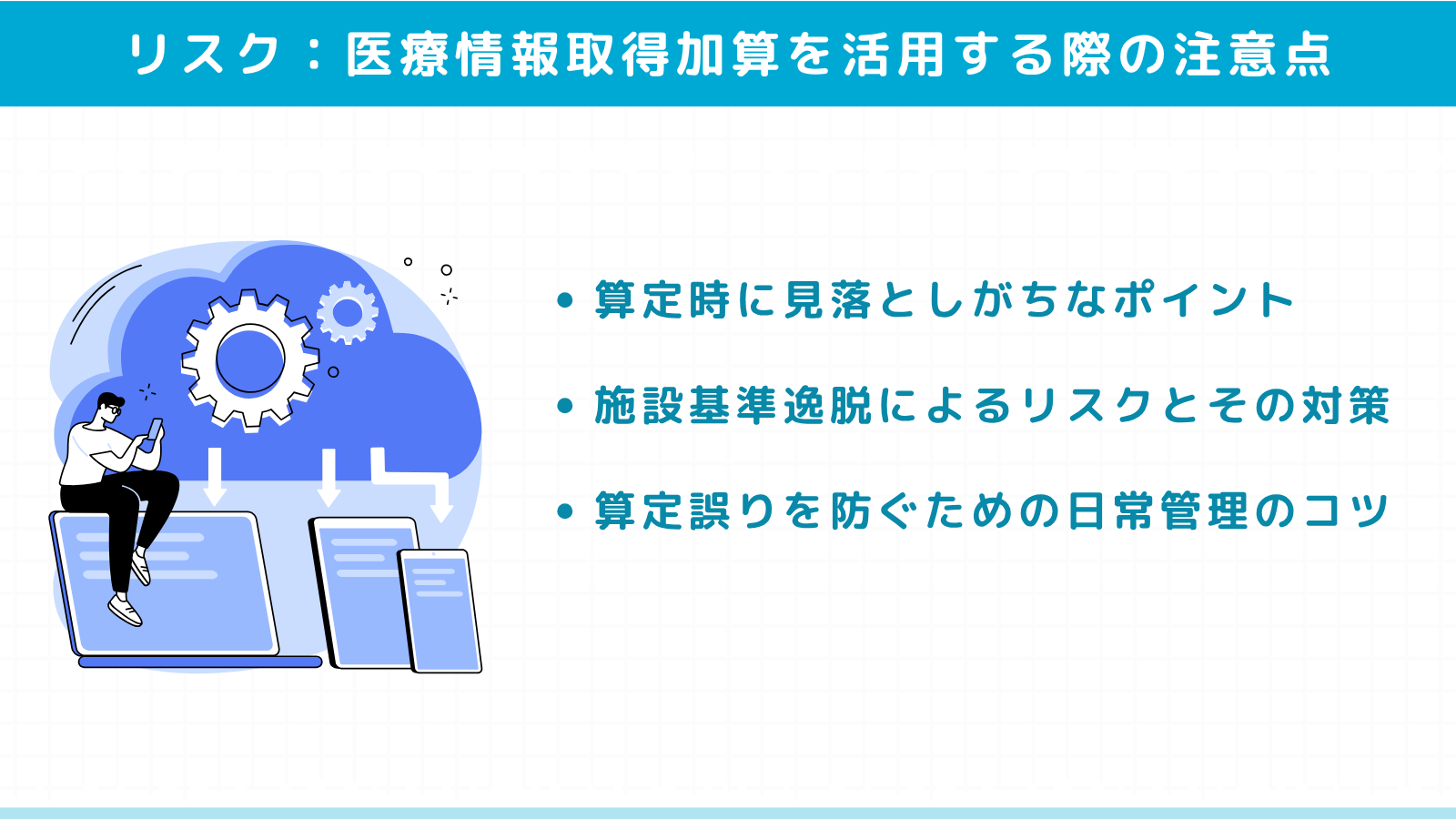
算定時に見落としがちなポイント
医療情報取得加算を導入して算定を始める際に、特に注意すべきポイントは、「算定対象となる診療情報がきちんと取得・記録されているか」「施設基準を満たし続けているか」の2点です。
まず、診療情報を取得したとしても、それが電子カルテなどに適切に記録されていなければ算定対象とは認められません。実際に診療情報を入手した証明となる記録がないと、保険審査時に返戻や査定の対象となってしまいます。
また、取得した情報が算定対象外のケースもあるため、診療情報が本当に算定可能かどうか事前に確認しておくことも重要です。具体的には、取得元の医療機関の情報が明確であるか、取得した診療情報が患者の治療方針に影響を与える重要な内容であるか、などの基準を満たす必要があります。
施設基準逸脱によるリスクとその対策
施設基準を逸脱した状態で算定を続けてしまうと、後に保険審査などで大きな問題になることがあります。特に医療情報取得加算の場合、施設基準が非常に具体的に設定されているため、一つでも条件を満たしていないことが後から発覚すると、返戻や査定、場合によっては施設基準の取り消しという重大なリスクが発生します。
これを回避するためには、施設基準を定期的にチェックし、基準を満たしているかどうかを確認する体制を整えることが重要です。医療機関内部で担当者を明確に決め、日常的な施設基準の管理を徹底する仕組みを作りましょう。また、定期的に施設基準を満たしているかの内部監査を行い、逸脱や基準外の状態がないかを検証することも効果的です。
算定誤りを防ぐための日常管理のコツ
算定誤りを防ぎ、適切に医療情報取得加算を運用していくためには、日常的な管理体制の構築が欠かせません。以下のような具体的な管理方法を実践しましょう。
専任担当者を置く
・算定ルールや施設基準の管理を専門とする担当者を明確にし、責任の所在を明らかにする。
定期的なスタッフ研修
・スタッフに算定条件やルールを定期的に説明・確認し、最新の情報を共有する。
電子カルテの活用とチェック機能強化
・電子カルテシステムを活用し、算定時に必要な情報が漏れなく記載されているか、自動的にアラートを出す機能を活用する。
月次の算定状況チェック
・毎月の算定状況を定期的に監査し、不正確な算定や漏れがないかを確認する。
マニュアルの整備と活用
・算定業務のマニュアルを作成し、算定時のポイントをいつでもスタッフが確認できる状態にする。
こうした日常的な管理を継続的に行うことで、算定誤りやリスクを回避でき、安定した医療情報取得加算の運用が実現します。
電子カルテと医療情報取得加算を効果的に連携する方法
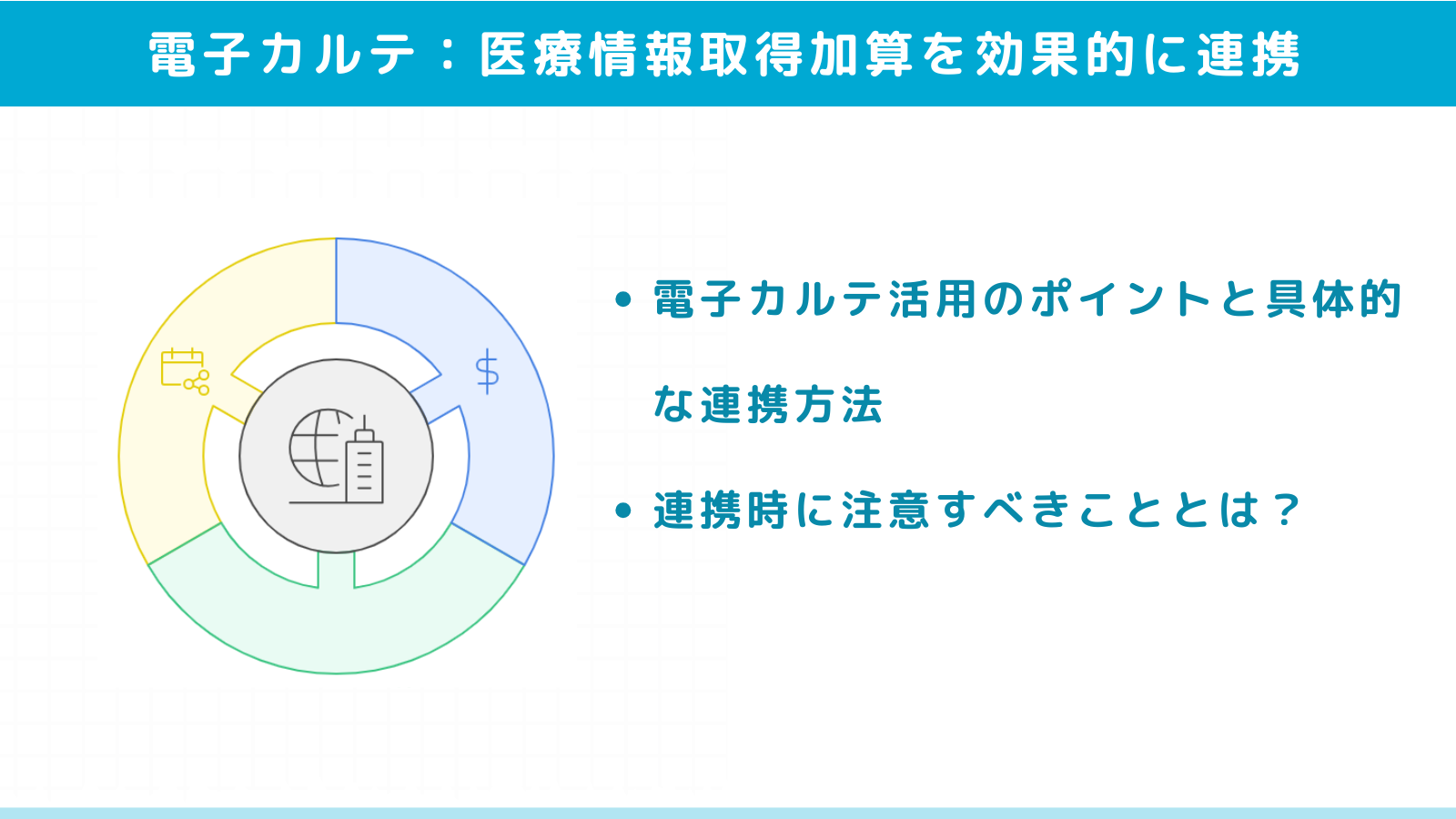
電子カルテ活用のポイントと具体的な連携方法
医療情報取得加算の効果的な運用には、電子カルテの導入・活用が不可欠です。電子カルテは情報を迅速かつ正確に取得・管理し、他医療機関との連携を円滑化させます。
電子カルテを効果的に活用するためには、患者の診療情報が取得されたらすぐに電子カルテに記録する習慣を徹底する必要があります。また、情報入力のフォーマットを統一することで、スタッフ間での情報共有がスムーズになり、記録漏れを防ぐことができます。
さらに、電子カルテの運用においては、取得した診療情報を患者ごとに整理・分類し、他院との情報連携に利用できるようにしておくことが重要です。この仕組みを導入することで、患者診療の質が高まり、医療情報取得加算の算定要件を常に満たしやすい環境が整います。
データ連携時に注意すべきこととは?
電子カルテでデータ連携を行う際に特に注意が必要なのは、患者のプライバシー保護と情報セキュリティです。他医療機関との情報連携は患者の個人情報を扱うため、情報漏洩や不正アクセスといったリスクが常に伴います。
そのため、連携するデータには適切なセキュリティ対策を施し、情報の取り扱いに関して患者本人からの同意を明確に取得しておく必要があります。電子カルテシステムには厳密なアクセス管理を行い、許可されたスタッフのみが情報にアクセスできる体制を作ることも重要です。
また、医療情報取得加算を算定する上では、取得した情報が正確かつ最新であることが求められます。連携情報が古い、もしくは不正確な場合は、患者診療に悪影響を及ぼすリスクもあるため、データの最新性・正確性を日々確認するプロセスを設けることが大切です。
情報取得とカルテ記録の一元化がもたらすメリット
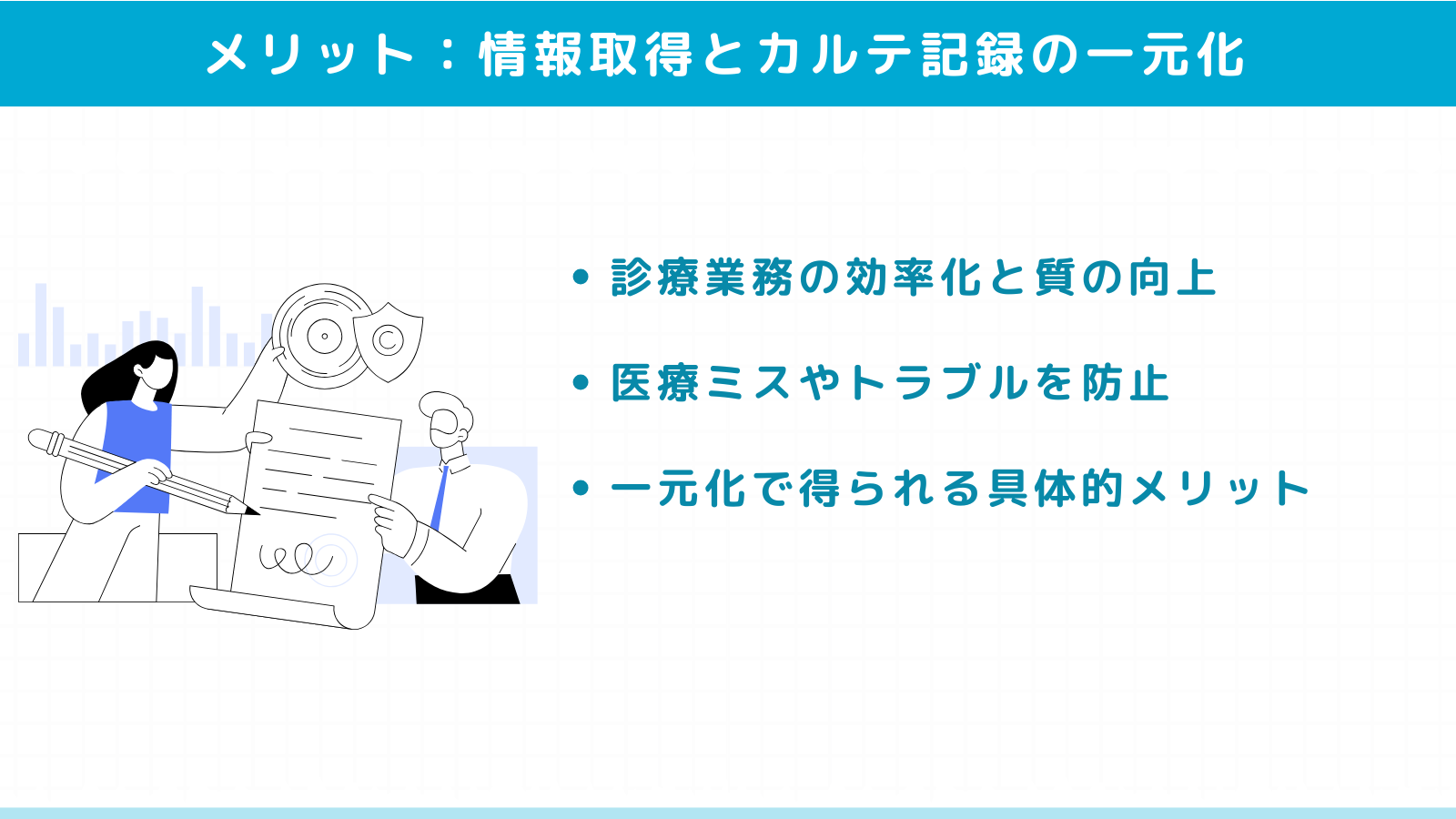
診療業務の効率化と質の向上
医療情報取得加算を円滑に運用するには、取得した情報とカルテ記録を一元化することが非常に効果的です。一元化によって、医師やスタッフが患者情報を検索・確認する手間が大幅に軽減され、診療業務のスピードが向上します。また、診療情報が一箇所に整理されることで、複数の医療スタッフ間での情報共有が容易になり、チーム医療の質が高まります。
さらに、一元化された情報をリアルタイムで更新・確認できる体制が整えば、他院からの情報取得時にもスムーズな連携が可能となり、治療の継続性や整合性が保たれます。結果として、診療の質が向上し、患者満足度の向上にもつながります。
医療ミスやトラブルを防止
情報取得とカルテ記録の一元化は、医療現場でのミスやトラブル防止にも大きな効果を発揮します。複数箇所に情報が散在すると、重要な情報が漏れたり、最新の状態が反映されないなどのリスクが高まりますが、一元化することで、常に最新かつ正確な情報にアクセスできるため、投薬ミスや重複検査などの医療事故を未然に防ぐことができます。
また、万一トラブルが発生した場合でも、情報が一元管理されているため、原因特定や早期対応が迅速に行える点もメリットです。患者からの信頼を維持するためにも、こうした情報管理の徹底は欠かせません。
情報の一元化で得られる具体的メリット
診療情報の一元化により医療機関が得られる主なメリットを以下にまとめます。
情報管理の効率化
・情報の検索・確認が迅速になり、業務効率が大幅に向上する。
スタッフ間のコミュニケーション促進
・情報共有が円滑になり、チーム医療の質が向上する。
治療の継続性の確保
・他院からの情報取得時に迅速に反映できるため、治療の継続性や整合性が向上する。
医療安全性の向上
・情報漏れやミスが減少し、患者安全の確保が徹底される。
患者満足度の向上
・医療の質が向上し、患者への対応が迅速化・正確化されることで満足度が上がる。
情報の一元化は、医療機関の経営面にも直接的なメリットをもたらし、長期的に安定した医療サービスを提供できる基盤となります。
医療情報取得加算を上手に運用している医療機関の成功事例
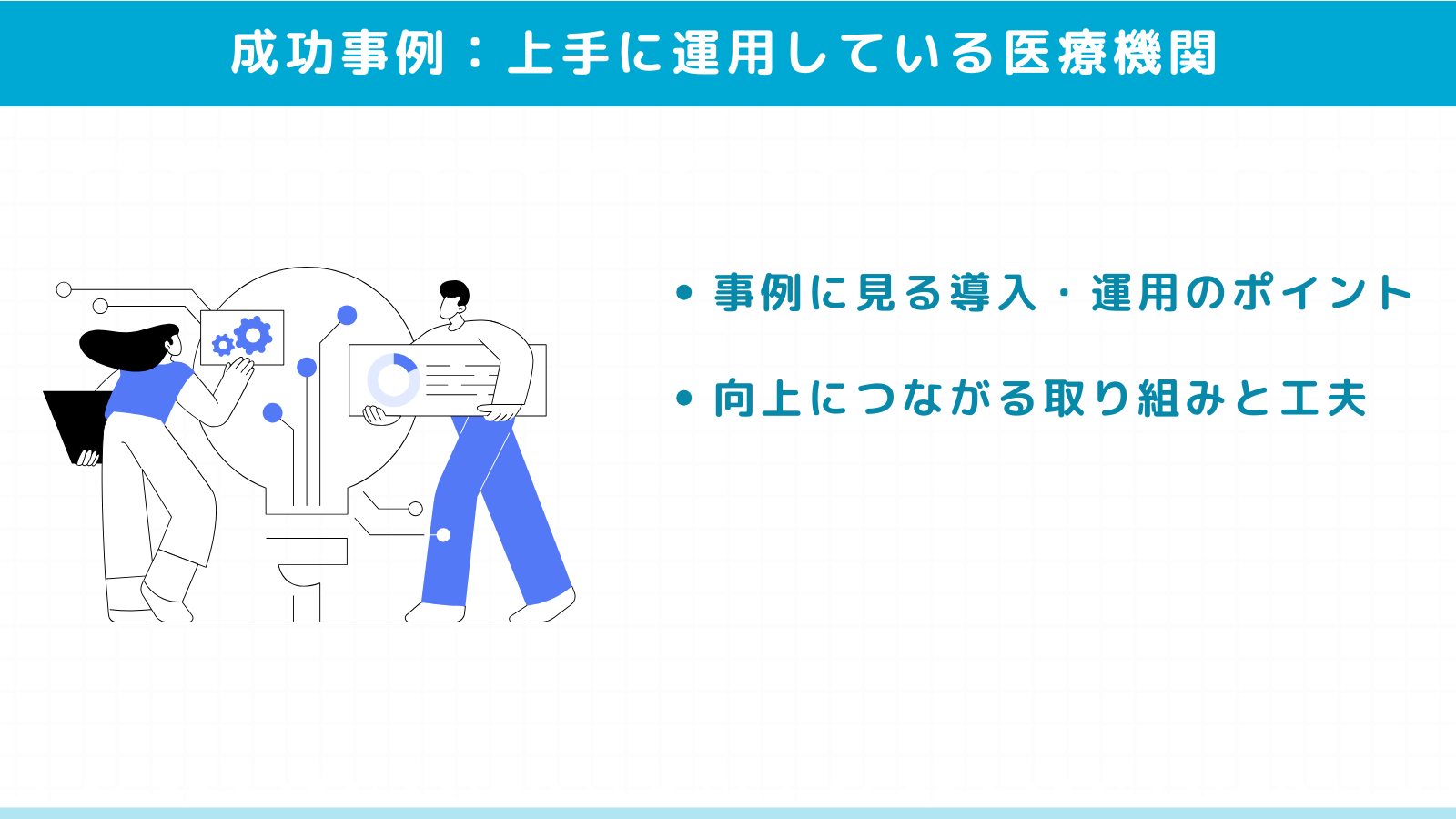
成功事例に見る導入・運用のポイント
医療情報取得加算を導入し、円滑に運用している医療機関には共通した特徴があります。例えば、成功している病院では、導入時にスタッフへの説明会を丁寧に行い、算定条件や業務フローについて徹底的に周知徹底しています。また、専任担当者を設置し、情報取得のプロセスからカルテ記録までの流れを管理することで、制度運用の定着を図っています。
ある医療機関では、導入時に電子カルテを大幅に改良し、情報取得と記録のプロセスを自動化する仕組みを構築しました。その結果、診療の質向上だけでなく、算定漏れやミスが減少し、収益性の改善にもつながっています。
算定率向上につながる取り組みと工夫
算定率を高めている医療機関が実践している主な工夫としては、スタッフへの定期的な教育・トレーニングが挙げられます。算定ルールを分かりやすくマニュアル化し、定期的に研修を行うことで、スタッフの理解度を常に高く維持しています。また、算定状況を定期的にチェックし、改善すべき課題を迅速にフィードバックすることで、算定率の維持・向上を実現しています。
さらに、医療機関全体で定期的に運用状況を評価し、問題点を早期に発見・改善するPDCAサイクルを確立することも、算定率を安定的に向上させるポイントです。