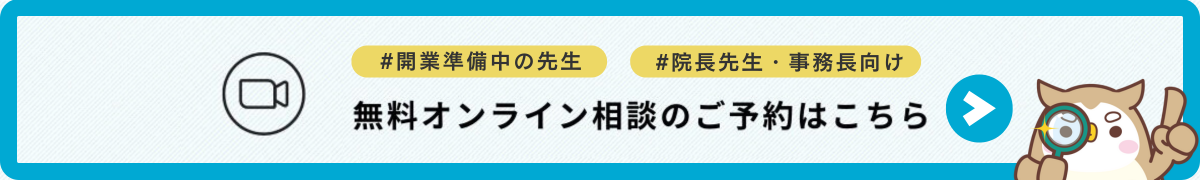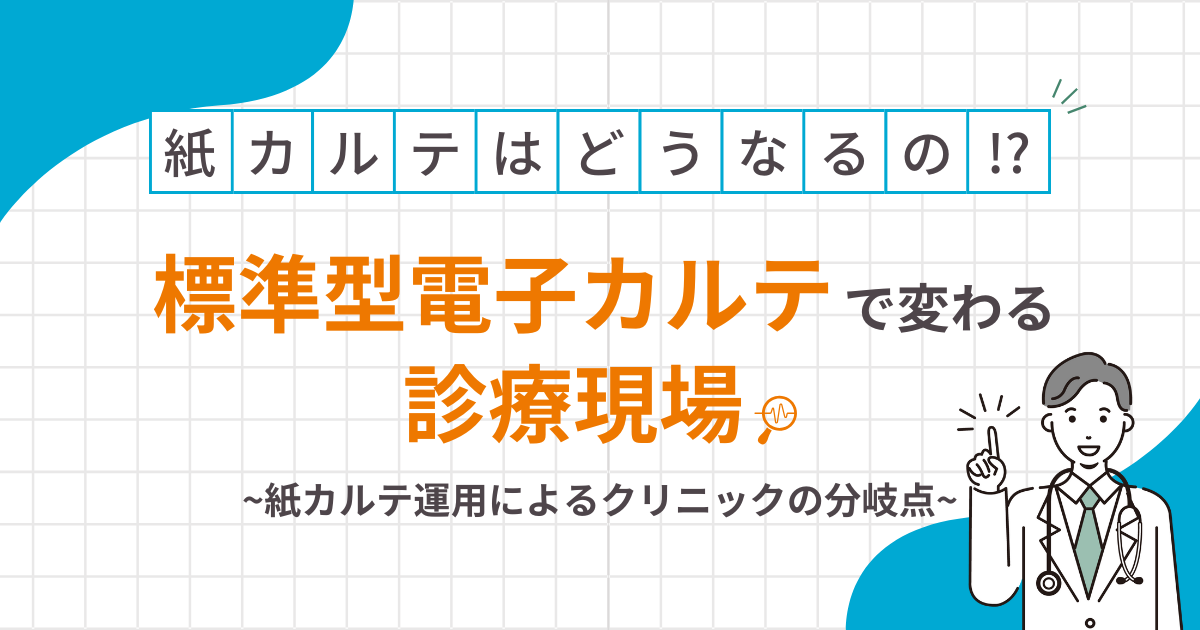
2025.10.29
標準型電子カルテで変わる診療現場|紙カルテ運用クリニックの分岐点【目利き医ノ助】
政府が進める医療DXの一環として、診療情報のデジタル化や医療機関同士の情報連携が進んでいます。現在も紙カルテを使用しているクリニックにとっては、まさに分岐点を迎えている状況です。
「いつまで紙カルテを使い続けてよいのか」「電子カルテに切り替えるべきか」を悩んでいる医療機関も多いのではないでしょうか。そんな中、国が開発を進めている「標準型電子カルテ」の登場により、選択肢がさらに広がり、かえって判断が難しくなっている側面もあります。
この記事では、電子カルテ未導入のクリニックに向けて、標準型電子カルテの概要、導入の背景、検討時の注意点、準備の進め方までをわかりやすく解説します。紙カルテからの移行を検討しているクリニックはぜひ参考にしてください。
そもそも標準型電子カルテとは?紙カルテはどうなるか

「標準型電子カルテ」は、従来の電子カルテメーカーが開発している電子カルテとはまったく異なるアプローチで開発されています。こちらは、厚生労働省とデジタル庁で一緒に開発を進めています。
「全国医療情報プラットフォーム」構想を進めていく中で、紙カルテを使用しているクリニックにもクラウド型電子カルテを利用してもらう必要がありました。そこで導入のハードルを下げるためにできたのが、紙カルテと併用する新しい仕組みです。
政府のスケジュールでは、2025年度にモデル事業を開始し、2026年度以降の本格稼働が予定されています。2025年の段階では、山形県や千葉県など全国10ヶ所の限られた地域で先行導入が始まっています。
厚生労働省の調査によると、令和5年度時点で電子カルテを導入しているクリニックは約55%です。この標準型電子カルテは、主に電子カルテ未導入の診療所をターゲットにしており、現行の紙カルテとの併用や段階的な移行が前提とされています。
また、診療報酬請求に使用するレセプトコンピュータ(レセコン)に関しては、現時点ではwebORCAと連携が必要です。別のシステムを使用している場合は、システムの入れ替えが必要になる可能性があります。
なお、「電子カルテの標準化」と「標準型電子カルテ」は別の概念である点にも注意が必要です。電子カルテの標準化は民間電子カルテも含めた「仕様の共通化」を目指すものであり、標準型電子カルテは1つのシステムにすぎません。
標準型電子カルテに注目が集まる背景とは?
今「標準型電子カルテ」が注目されている背景には、以下のような医療現場の課題と、それを解決しようとする国の構想があります。
- 電子カルテ情報共有サービスと連動できる
- 紙カルテと電子カルテの併用で業務を効率化できる
それぞれくわしく解説していくので参考にしてください。
1. 電子カルテ情報共有サービスとの連携
国が整備を進めている医療DXのひとつである「電子カルテ情報共有サービス」とのAPI連携が可能になることで、他院や地域連携がよりスムーズになります。また、 紹介状や外注検査結果の共有が自動化されるため、患者さんの情報連携が格段に進むと期待されています。
このシステムは当然ですが、紙カルテを使用しているクリニックでは連携ができません。そのため、政府はスムーズな情報連携を実現するために、紙カルテと併用できる標準型電子カルテを開発しました。
2. 紙カルテと電子カルテの併用が可能
従来の電子カルテメーカーが開発した電子カルテの導入には「一気に全てを切り替える必要がある」という印象がありました。しかし、標準型電子カルテでは紙カルテとの併用が前提とされています。
これは「医者が高齢のため電子カルテの導入は困難」や「すぐに完全移行は難しい」という現場の声に応えたものです。このようなクリニックでも、スムーズに移行できるように最低限の機能を搭載したものになっています。
標準型電子カルテの導入を検討するときに気をつけること
標準型電子カルテを導入するときは、以下のような点に注意しなければいけません。
- スタッフのITリテラシーアップ
- システム費用と運用負担
- 紙と電子カルテ併用による入力の手間
それぞれの項目についてくわしく解説していきます。
スタッフのITリテラシーへの対応
新しいシステムを導入すると、操作方法に慣れるまでの間、業務負担が一時的に増えることがあります。
電子カルテ未経験のスタッフが多い場合は、事前の研修やサポート体制の整備が必要です。とくに院長が年配で紙カルテを使用している場合は、スムーズに導入ができない可能性もあるため、事前に十分な準備をしておきましょう。
システムの運用負担と費用感
標準型電子カルテだからといって、無料や格安ではない点も理解しておく必要があります。現時点で価格情報は未公表となっています。国主導のシステムであるため、比較的低価格で提供される可能性はあるものの、運用費やサポートの詳細は不明です。
システム導入には、一定の初期費用がかかることを想定しておく必要があります。また、スムーズな運用には、導入後のサポート体制も重要です。導入前に費用面やサポート面は十分に確認しておくと安心です。
紙と電子カルテ併用による入力の手間
標準型電子カルテは紙カルテとの併用ができる一方で、「紙+電子」双方に記載する二度手間の運用がネックです。
電子カルテのみの場合、記録やオーダー入力を一括で行えます。しかし、標準型電子カルテでは紙カルテと電子カルテの双方に記載が必要になるため、二重入力の手間が発生するかもしれません。
しかし、標準型電子カルテの場合は紙カルテに記載する必要があり、それとは別に電子カルテでも入力する必要があります。慣れてくれば難しい作業ではないかもしれませんが、二重に記録しなければいけないため、最初は作業が煩雑になる可能性があるでしょう。
電子カルテ導入のための準備
電子カルテを導入する際は、事前に準備や情報収集が必要です。
電子カルテ導入の事前準備

電子カルテを導入する際に、何から始めればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。まず、導入の流れを確認する必要があります。基本的な流れは以下のような3ステップです。
- 情報収集
- ベンダー選定
- 自院に合った準備
現在、国が開発を進めている「標準型電子カルテ」は、比較的安価な選択肢になる可能性があります。
そのため、標準型電子カルテの費用面でのメリットが期待されており、「まずは様子を見よう」という声も聞かれます。しかし、2025年時点では価格や仕様がまだ明らかになっていないため、クリニックにとって最適なタイミングを見極めることが大切です。また、標準型電子カルテは幅広い施設での利用を前提としており、現状では最低限の機能のみの汎用設計となっています。そのため、診療科やワークフローによっては使い方によっては慣れが必要な場面もある可能性もあります。
そのため「国が開発した標準型だから安心」という思い込みにとらわれず、各社が提供する民間製の電子カルテと比較することが大切です。 それぞれのシステムが持つ特徴や強みに注目し、クリニックにとって最適な選択を導き出しましょう。
電子カルテ導入の評価基準
電子カルテの導入を検討する際は、以下のような観点から評価することをおすすめします。
|
初期費用・ランニングコスト |
コストのバランスを確認 |
|
保守・サポート体制 |
トラブル時の対応スピード、サポート品質 |
|
操作性・スタッフ教育のしやすさ |
現場での負担軽減につながるポイント |
|
他システムとの連携可否 |
レセコン、予約、健診システムなど |
|
カスタマイズ性や拡張性 |
将来の診療内容変更や成長に対応可能か |
これらの基準をもとに、資料請求をして選ぶだけではなく、クリニック独自の導入基準を明確にしておくことが重要になります。
「何を基準に選べばいいのかわからない」「比較検討が難しい」と感じる方は、目利き医ノ助にご相談ください。電子カルテの導入を検討している医療機関に合うシステムを的確にアドバイスが可能です。
まとめ:標準型電子カルテに注目が集まる今、クリニックに本当に合う選択肢を見極めましょう
医療のデジタル化が進む中、紙カルテを使い続けていると流れに取り残されてしまいます。しかし、どのシステムを導入して、どのように運用していくかは、それぞれのクリニックにとって重要なポイントです。
患者さんやスタッフにとっても、安心して通える・働ける環境をつくることが、これからの医療経営に求められます。そのため、単に「話題になっているから標準型を選ぶ」のではなく、本当に自院に合った選択肢を見極める必要があります。
標準型電子カルテは、2026年度以降に本格運用が予定されており、今から準備を始めれば、十分に間に合うタイミングです。慌てて選ぶのではなく、必要な情報を整理しながら、じっくり判断していきましょう。
そして、「比較のポイントが分からない」「何が良いのか判断しきれない」という方は、医療ITの専門家である目利き医ノ助に相談するのがおすすめです。中立的な目線でアドバイスをしてくれる支援窓口があると、判断の軸が明確になり、導入の不安も軽減できます。