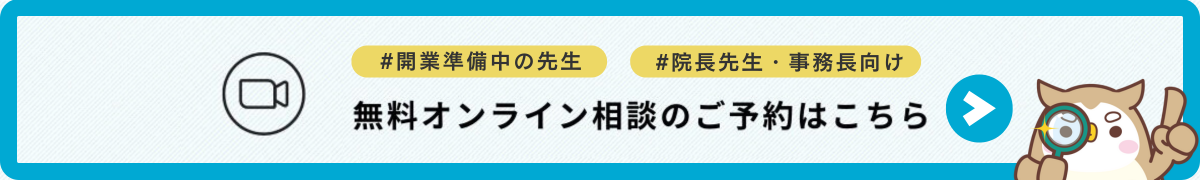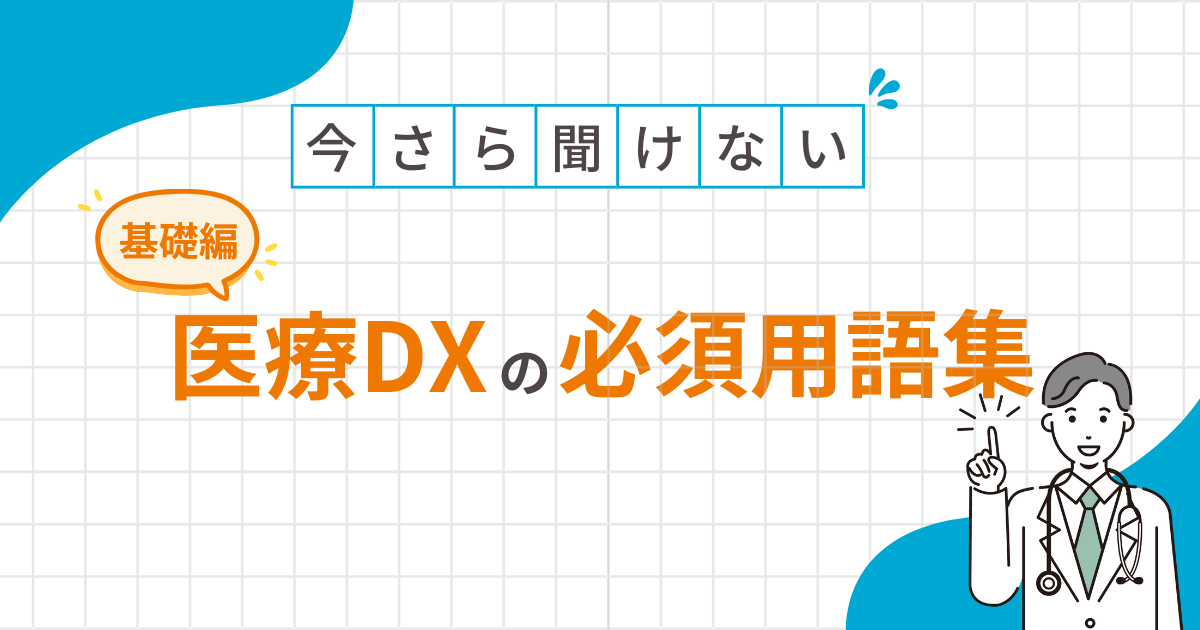
2025.11.10
【基礎編】今さら聞けない!医療DXの必須用語集
国が主導する「医療DX令和ビジョン2030」のもと、電子カルテの標準化、オンライン資格確認の導入、電子処方箋など、変革の波はクリニックや診療所といった地域医療にも急速に浸透しています。
しかし、変化のスピードがあまりにも速く、関連する専門用語も多岐に渡るため、以下の悩みを抱えているクリニックの院長や事務長も多いのではないでしょうか?
- 診察の合間に用語を整理・理解する時間がない
- 情報が多すぎてどれが重要な用語なのかわからない
本記事では、こうした不安を解消するために、医療DX関連の基礎用語を4つのジャンルにわけて内容もわかりやすく解説します。
診療の精度を高める最先端技術、セキュリティに関する応用用語は以下の記事で解説しています!より理解を深めたい方はあわせてチェックしてみてください。
>>関連記事:【応用編】セキュリティ・データ連携など最先端技術の医療DX用語集
DXの基本用語
医療DXは、一般的なDXの概念を医療分野に応用したものです。
ここでは、医療DXを理解するための知識として、各業界で共通して使われる基本的な用語とその意味をまとめています。
この用語を理解しておけば、ベンダーとの会話に戸惑うことがなくなります。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| DX(ディーエックス) | デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや業務手順を変革すること。 |
| IoT(アイオーティー) | 「Internet of Things」の略で、家電や機器など「モノのインターネット」を意味します。モノをインターネットに接続し、情報のやり取りを可能にすることで遠隔操作やデータ収集などができます。 |
| AI(エーアイ) | 「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」を意味します。人間の思考、学習、予測などの活動をコンピューターで再現します。 |
| クラウド | 簡単にいうと「データをインターネット上で保管する」ことです。クラウドサービスは、主にデータの共有や保存に活用されています。 |
| ビッグデータ | 人間で把握することが難しい膨大な量のデータを指します。収集・分析により深い洞察や新たな価値創出につながる可能性があります。 |
| デジタイゼーション | アナログ情報をデジタル形式に変換すること(例:紙の書類をPDFにする)。 |
| デジタライゼーション | デジタル技術を活用し、既存の業務プロセスや仕組みを効率化・改善すること。 |
| API(エーピーアイ) | 「Application Programming Interface」の略で、ソフトウェア間で情報や機能を連携させるための仕組みのこと。 |
| セキュリティ | 情報の機密性、完全性、可用性を維持し、不正アクセスや漏洩から守ること。 |
| ブロックチェーン | 取引履歴を1つの鎖(チェーン)のようにつなぎ、関係者間で分散して管理する技術のことです。データは暗号技術で保護されるため、改ざんが非常に困難です。 |
「国の制度・推進体制」に関する用語一覧
医療DXは、厚生労働省を中心に行政が強く推進している国家戦略です。
最も代表的な政策が「医療DX令和ビジョン2030」がありますが、国が実施する制度や推進体制を理解しておくことは重要です。
ここでは、国の制度・推進体制に関する用語を解説します。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 医療DX令和ビジョン2030 | 日本の医療分野のデジタル化を推進するために提言された戦略ビジョンです。人材不足、急速な高齢化などの課題から、デジタル技術を活用して効率化を目指しています。 |
| 医療扶助(オンライン資格確認に付随する) | 生活保護受給者などに対する医療費の公費負担制度。オンライン資格確認では公費負担情報も確認できるように整備。 |
| 医療情報システム整備事業 | 国が医療機関のシステム導入などを支援する事業。 |
| データヘルス改革 | 医療・介護データを情の利活用を推進し、国民の健康増進や医療の質の向上を目指す改革。 |
| 保健医療情報システム | 医療機関内で患者の情報を管理・共有するシステム全般のことを指します。 |
| GVP(ジーブイピー) | 「Good Vigilance Practice」の略。医薬品や化粧品などが市場に出荷されたあとの安全性を管理するための基準。 |
| GCP(ジーシーピー) | 「Good Clinical Practice」の略。医薬品の臨床試験の実施に関する基準。 |
| 再生医療 | 損傷した組織や臓器を細胞や組織を用いて再生させる医療。 |
| 特定行為研修 | 護師が医師の判断を待たずに、手順書に基づいて特定の診療補助を行うために必要な知識・技能などを向上させるための研修制度。 |
| 医療安全 | 取医療に伴う危険を予防し、事故の発生を防止・低減すること。 |
| 個人情報保護法 | 個人の権利利益を保護するための、個人情報の適切な取り扱いを定めた法律。 |
| 医療情報ガイドライン | 医療情報の取り扱いに関する、厚生労働省などが定める指針。 |
| DFFT(ディーエフエフティー) | 「Data Free Flow with Trust」の略。信頼性を確保しながら国境を意識することなく自由なデータ流通を目指すこと。 |
| 規制改革 | 時代に合わなくなった規制を見直し、イノベーションを促進すること。 |
ほかにも”医療DX令和ビジョン2030”の施策のひとつで「診療報酬改定DX」があります。診療報酬改定は2年に1度実施されるため、現状や内容について理解しておくと良いでしょう。
>>【関連記事】3分でわかる!診療報酬改定DXのメリットと注意点
「医療情報システム」に関する用語一覧
医療DXの根源となるものは情報管理システムです。
今まで紙ベースで保存していた情報をデジタル化することで、情報の共有・活用・管理が可能となり、診療の安全性や効率が向上します。
電子カルテやレセプトコンピューターなどが皆さんに馴染み深いと思います。ここでは、医療情報システムの用語と意味を解説します。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 全国医療情報プラットフォーム | マイナ保険証を基盤に、医療機関・薬局などの診療情報を集約・連携し、全国で共有・活用できるようにする国のIT基盤。 |
| 電子カルテ情報共有サービス | 全国医療情報プラットフォーム上で、過去の診療情報やPMH、検査結果などを医療機関や患者が共有・閲覧できる機能。 |
| 電子カルテ | 患者の診療情報を記録したカルテをデータ化し、システム上で管理するシステム。 |
| 標準型電子カルテ | 全国の医療機関での患者情報を円滑に共有するためのクラウドベースのシステム。 |
| レセプト | 「診療報酬明細書」のこと。医療機関が審査支払機関に提出するための請求書。 |
| レセコン | レセプトコンピューターの略。診療報酬を請求するために必要な「診療報酬明細書」を作成するためのシステム。 |
| EHR(イーエイチアール) | 「Electronic Health Record」の略。患者の医療情報をデジタル化し、複数の医療機関で共有・管理するシステム。 |
| PHR(ピーエイチアール) | 「Personal Health Record」の略。個人の健康や医療データを一元化し、患者自身が管理・活用する仕組みのこと。 |
| PACS(パックス) | 「Picture Archiving and Communication System」の略。医用画像管理システムのこと。 |
| RIS(リス) | 「Radiology Information System」の略。放射線科の検査予約・受付・結果管理システム。 |
| LIMS(リムス) | 「Laboratory Information Management System」の略。日本語では「ラボ情報管理システム」と訳され、臨床検査部門の情報を管理・効率化するためのシステム。 |
| オーダリングシステム | 医師が検査や投薬などの指示を入力し、迅速かつ正確に伝達するためのシステム。 |
| 相互運用性 | 異なるシステムやアプリケーション間で情報を連携・利用できる能力のこと。 |
| 共通プラットフォーム | 医療機関や行政などで共通して利用できる情報連携基盤。 |
| EMR(エーエムアール) | 「Electronic Medical Record」の略。電子化された医療記録のこと。 |
>>【関連記事】レセコンと電子カルテの違いとは?導入時に知っておきたいメリット・デメリットを解説
患者様の利便性を高める「サービス関連」の用語一覧
「電子処方箋」や「オンライン診療」「マイナンバーカードによる情報連携」など、患者様の待ち時間を減らし、診察を効率化するための仕組みに関する用語をまとめています。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 電子処方箋 | 医師が発行する処方箋情報をデジタルデータ化し、医療機関と薬局で薬の情報を連携する仕組みのこと。 |
| オンライン資格確認 | マイナンバーカード等を使って、患者の保険資格をリアルタイムで確認する仕組み。 |
| 地域医療連携 | 地域の病院、診療所、薬局などが連携して患者を継続敵にサポートする仕組みのこと。 |
| オンライン診療 | 情報通信機器(PC、スマホなど)を用いて診療すること。 |
| 遠隔医療 | 情報通信技術を活用し、遠隔地にいる患者様や医療従事者間で医療を連携するサービスのこと。 |
| D to P with D | 「Doctor to Patient with Doctor」の略。患者のそばにいる医師と、遠隔地の専門医をオンラインでつないで診療する形態のこと。 |
| 電子版お薬手帳 | アプリで薬剤情報や健康状態を記録・管理するサービスのこと。 |
| マイナンバーカード | 医療DXにおいては、保険証機能や医療情報閲覧に活用されています。 |
| 予防医療 | 病気になる前に健康を維持・増進するための医療活動。 |
| 個別化医療 | 患者個人の体質や病状に合わせた最適な治療法を選択すること。 |
| PRO(ピーアールオー) | 「Patient Reported Outcome」の略。患者自身が報告する治療効果や生活の質の情報。 |
| QOL(キューオーエル) | 「Quality of Life」の略。生活の質を指し、医療の評価指標の一つ。 |
| インフォームド・コンセント | 医師からの十分な説明に基づき、患者が治療に合意すること。 |
| セカンドオピニオン | 主治医以外の医師に、病状や治療法について意見を求めること。 |
>>【関連記事】電子処方箋の導入で差がつく!医師が開業で知るべき医療DX加算のポイント
まとめ:基礎用語を理解して医療DXの推進を!
医療DXに関する基本用語を4つのジャンルにわけて解説しました。用語の理解を深めることで、院内のDX化(システム化)を進める基盤となります。
とはいえ、用語の意味を理解しても「うちのクリニックに最適なシステムはどれか」「院内の課題にどう対応すべきか」といった課題解決に頭を抱える先生は多いと思います。
「目利き医ノ助」は、特定のメーカーにとらわれず、院内の課題をもとに中立な立場でクリニックにマッチしたメーカーをご提案します。
相談は無料ですので、「DX化に向けて何をすれば良いかわからない」という方もお気軽にご相談ください。